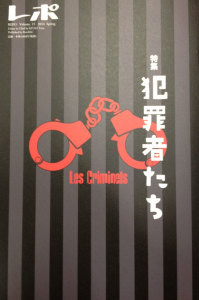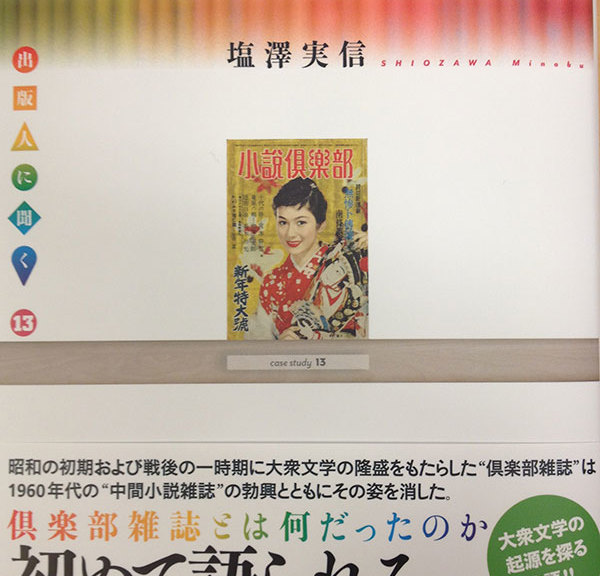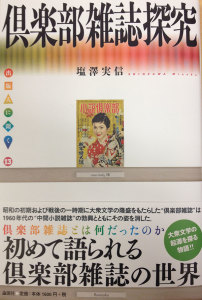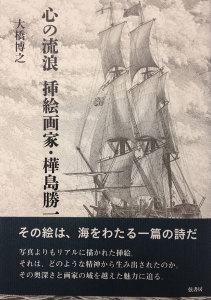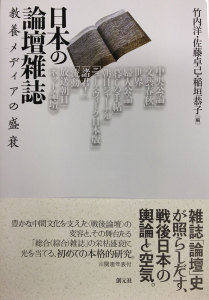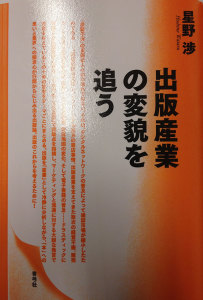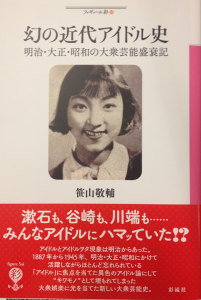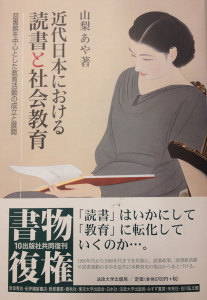小さな雑誌だから何でもできる
北尾トロ
|
| ぼくが編集人となって2010年の秋に創刊したノンフィクション専門誌『季刊レポ』は、ジャーナリズム系の堅い雑誌ではなく、体験ベースで肩の凝らない原稿を毎号80ページ満載している雑誌です。雑誌が売れ行き不振の今、自分が好んで書いてきた「読んでも役に立たないけどおもしろい」ノンフィクション記事を掲載する媒体はめっきり少なくなりました。ただでさえ経費持ちだしがあたり前なのに、発表の場までなくなったらノンフィクションライターをやろうなんて人間はいなくなる。だったら自分で雑誌を作り、「読んでも役に立たないけどおもしろい」原稿を集めて載せよう。創刊の動機は単純なものでした。
インディーズ雑誌の壁は流通です。ぼくが考えたのは、書店は置きたい店だけに扱っていただき、通販メインで年間購読者を募るというものでした。読者の手元に直接届く、手紙のような雑誌にしたかったのです。年4回の発行なので、年間購読者の特典として、雑誌が発行されない月には「ちびレポ」という手書きコピーの手紙を実際に送っています。直販で売ってくれる書店や単号販売を合わせ、発行部数は1000~1200部。もう存在そのものがレアな雑誌なんです。
でも、やってみたらおもしろいことが起きました。書く場を求める若手ライターだけではなく、えのきどいちろう、本橋信宏、平松洋子など、第一線の書き手が参加してくれる。月に一度の発送作業を手伝ってくれる執筆者がたくさんきて、プロアマ問わず勝手に交流。まるで部室にように編集部が使われ始めたんです雑誌の宣伝のために始めた週一のユーストリーム番組「レポTV」は全員ノーギャラなのに4年目に突入しました。番組放送中に突如話題になり、それがきっかけで雑誌で組んだ特集が河出書房新社の目にとまり、「愛の山田うどん」「みんなの山田うどん」という本まで誕生。特集や連載の書籍化計画も進んでいます。、そうこうしているうちにスポンサーまでつき、赤字だった財政面にも目処がつきました。
ぼくはこれ、小さなメディアだからこそ起きた現象だと思います。あいつは放っておくと何やらかすかわからないけど、おもしろいから付き合ってやろう。そんな気持ちで支えてくれる読者のおかげで、のびのびと活動できている気がします。
最新号の15号の特集は「犯罪者たち」。犯罪者、冤罪被害者、傍聴マニに執筆依頼し、熱度のある誌面ができました。こんな雑誌は他にないし、ぼくはこういうのが作りたかったんです。皆さん、ぜひご一読ください。
(購読申込先)季刊レポ公式サイト
http://www.repo-zine.com/
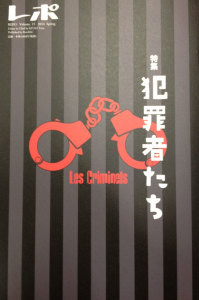
『季刊レポ』15号 特集犯罪者たち
定価:1050円(税込) 好評発売中
http://www.repo-zine.com/archives/10704
|
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|
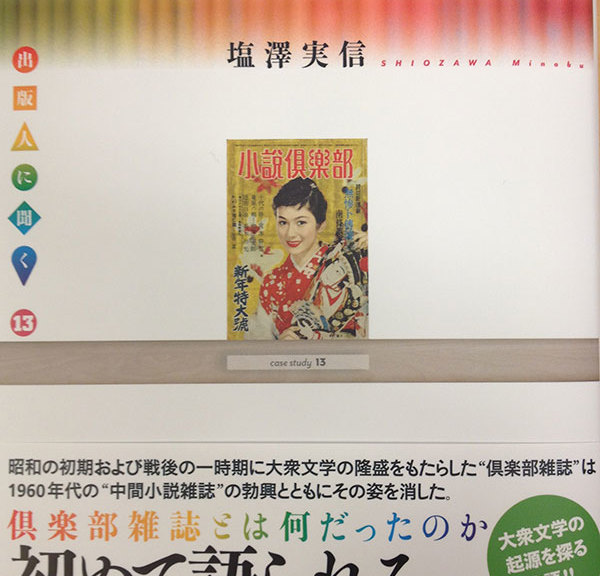
倶楽部雑誌探求
塩澤実信
|
| 「倶楽部雑誌」という言葉は、いまや死語に近いが、明治末期から大正時代を経て、昭和三十年代までの数十年間は、倶楽部雑誌時代であった。 講談社から創刊された「雑誌倶楽部」に端を発していて、講談は低俗ながら広い愛好者がいるのに着眼し、それに新しい魂を吹き込んで、大衆文学に衣替えさせたのである。
同社は、この誌を核に、婦人・少年・少女などの読者ターゲットに、倶楽部を結びつけた。面白くてためになる雑誌を次々に創刊。戦前に九大雑誌を擁して”雑誌王国”を豪語するまでになった。 弱小出版社は、この講談社に習い柳の下の二匹目のドジョウを狙って、倶楽部系雑誌を続々と発行し、そのトータル部数で定期刊行物の過半を占める時代を現出させた。
しかし、量より質を建前とする出版界は、倶楽部雑誌をはじめ、赤本・立川文庫・マンガ雑誌などのマイナーな分野は、疎んじて顧みようとはしなかった。 これでは、出版界を語るには片手落ちである。この間隙を埋めるには、倶楽部雑誌をはじめ、マイナーな出版にかかわった各位の証言を集めるほかはない。 だが、その類の定期刊行物は半世紀前にあらかた消滅し、かかわりのあった老兵は消え去って久しかった。 その現実を前に、ひとり犀利な出版評論家小田光雄氏が、日本出版史の欠落した部分を埋めるべく、探査、博捜、関係者に登場願って、論創社から画期的な「出版人に聞く」シリーズを始めていた。
小田氏は、また戦後出版界をつづった拙著を素材に、大部の『戦後出版史』を編纂していて、その因縁から私が『倶楽部雑誌探求』の語り部を務めるめぐり合わせになった。 私は、戦前・講談社で糧を食んだ面々が、敗戦直後に立ち上げ、一時は飛ぶ鳥を落とす勢いだったロマンス社を振り出しに、中小出版社を転々とし、辿り着いたのが倶楽部雑誌を十余誌も発行していた双葉社だった。
同社では、週刊誌編集が主で、後に編集部門を総括する立場にあったことから、倶楽部雑誌を一瞥していた。小田氏は、私のキャリアに着眼し、固辞したものの語り部に引っぱり出されたのである。そして、私の曖昧模糊した話に、整然とした裏付けと、条理だった筋道をつけ、一読できる体裁を整えてくれた。一読いただければ有難い。
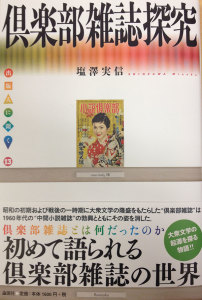
『倶楽部雑誌探究』塩澤実信著
論創社刊 定価1600円+税 好評発売中
http://www.ronso.co.jp/ |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

「松村書店の松村さんの思い出」
森岡督行
|
| 「日本の古本屋」のメールマガジンを読まれる方は、古本と古本屋に関心のある方ばかりなので、いまはもうなくなった、神保町の松村書店の松村さんをご存じの方も多いのではないでしょうか。神保町交差点付近の靖国通り沿いにあった松村書店は、洋書の美術書の専門店でした。
ご主人の松村さんは、とにかく毎日笑顔で、愛犬のハナをいつもそばによせていました。社屋は3階建てだったでしょうか。一階のお店の玄関は、靖国通りよりも若干低い位置にあるため、雨の日はよく、早じまいをしていました。植草甚一さんが、本に書いてある価格を消しゴムで消して、勝手に独自の価格を記入していたという逸話も残されています。松村さんの笑顔は、いま思い出しても、そんなお店のゆるさ加減をよく表して います。
この度、晶文社から出させていただいた「荒野の古本屋」でも、松村さんのことも、ほんの少しですが書かせていただきました。本書は、「就職しないで生きるには」というシリーズの一冊ですが、決して、仕事をしないで生きていこう、というわけではありません。むしろ、生きるためにどう仕事を生み出していくか、その仕事をどう楽しむか、という観点から企画された本だと思っています。
私はいま、松村書店の松村さんこそが、「就職しないで生きるには」を体現した人物だったのではないかと考えています。何度思い出しても、あの笑顔からは、神保町の古本屋稼業を楽しむ愛くるしさが伝わってくるからです。自分も松村さんみたいに笑っていたいのですが、この文章を書いているいまも支払いに追われているのが現実です。(事実です)
本書の内容は、松村書店の隣の一誠堂書店に入社した私が、独立して森岡書店を開業し、現在に至るおよそ16年間に身のまわりで起こったことです。他愛のない自伝のようなものですが、装幀を矢萩多聞さん、装画をミロコマチコさんが担当してくださったので、古本屋に持ち込んでも、いくらかの価値がつくのではないかと考えております。願わくは、松村さんにも読んでほしかったです。「古本屋が自分のとこなど書くな、バカ」と言われそうですが。

森岡書店 http://moriokashoten.com/
『荒野の古本屋』 森岡督行著
晶文社刊 定価:1575円(税込) 好評発売中
http://www.shobunsha.co.jp/?p=3025 |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

『心の流浪 挿絵画家・樺島勝一』について
大橋博之
|
『心の流浪 挿絵画家・樺島勝一』(弦書房)を上梓させて頂いた。
「日本の古本屋」を利用されている古書マニアな方々には樺島勝一(椛島勝一)の説明は不要かもしれない。まぁ一応、書いておくと、樺島は1888年(明治21年)、長崎県諫早市の生まれ。大正から昭和初期にかけて活躍した挿絵画家だ。〈少年倶楽部〉に描いた挿絵が絶大なる人気を博した。なんといっても独学で修得したというペン画が卓越しており、写真と見間違うような出来栄えに当時、誰もが舌を巻いた。特に船を描かせれば右に出る者はいないと言わしめた。船はロープ一本おろそかにせず描き込む。さらに圧巻なのは白波うめく波の描写だ。兎に角その描き込みには戦慄が走る。そんなことから〝船の樺島〟と評された。代表作に『正チャンの冒険』、山中峯太郎の『敵中横断三百里』『亜細亜の曙』、南洋一郎の『吼える密林』、海野十三の『浮かぶ飛行島』などの挿絵がある。
樺島勝一をリアルタイムで知る人は今ではそれなりのご高齢の方だ。樺島が最も活躍した〈少年倶楽部〉を読んだという読者は70歳以上だと思う。版元の弦書房は『心の流浪 挿絵画家・樺島勝一』を読んでくれたという方からの、感想をしたためた手紙などをわざわざ転送してくれる。樺島のファンは、やはり今も心に樺島が残っているのだなと感じることが出来て嬉しい。
2014年5月4日の〈朝日新聞〉「読書」蘭で、やはり樺島の熱烈的ファンである横尾忠則さんが書評を書いてくれた。その書評を読んで買ったよ、とイラストレーターの水野良太郎さん(http://ryot-mizno-web-magazine.webnode.jp/)が手紙を私に送ってくれた。
水野さんは「スケッチやデッサンは独学だとしても、実は『スケッチ・デッサンの独学』くらい大変な作業はありません。ましてリアルなデッサンをモノにするのは売れっ子の画家でさえ厄介で面倒な作業。特別に勉強をしなくても画家になれるのは、最初から成熟した画才の持ち主だったとしか思えないです」とプロのイラストレーターの立場から感想を書いてくれている。水野さんのように絵を描く立場からの意見というのはとても興味深い。
水野さんは1936年(昭和11年)三重県四日市生まれ。昭和20年の終戦の時は小学校三年生。最後の樺島世代にあたる。戦火を逃れた家庭には大正や昭和初期の児童書籍や雑誌が大切に残されており、そんなところで〈少年倶楽部〉などもむさぼり読むことが出来たという。そして樺島の絵にも触れ、感銘を受けた。水野さんは樺島の描く絵の「『一瞬停止状態の描写』は当時のハイスピード・カメラで撮った写真のように見えて、リアリズム表現の先端をイラストに取り込んだ感覚を新鮮に思いました」と評する。なるほどと感心。なんとも上手い表現だ。
樺島のファンとなった水野さんは中学二年生の頃に講談社に樺島の所在を訊ね、教えてもらった住所にファンレターと共に自身が描いた絵を送った。すると直筆の返事が届いた。その葉書のコピーも送ってくださったのだが、それがとても貴重な資料なのだ。一通を折角なので紹介しておきたい。
「あなたの力作を拝見しました。大体あなたの研究方法で好いと思ひました。率直に申せばあなたの描かれた海の感じが少し不充分かと思ひました。今少し研究される必要があります。あなたが感じられた通り海は何画で描いてもむずかしいです。殊にペン画の場合には波を描いて山に見へる恐れが多分にありますから、実際に海を見て研究するのが最も好い方法です。波の場合には共沸と反対の側にも相当に反射の光があることを知って置かれる必要があります」
波を描くと山に見える恐れがある、波は波らしく描く。そのためには実際に海を見て研究する必要がある。そして、波のうねりに光と影がある。〝船の樺島〟と言わしめる真髄のひと言だ。
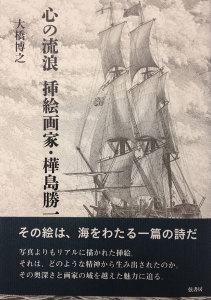
『心の流浪 挿絵画家・樺島勝一』 大橋博之 著
弦書房 定価 2200円 (+税) 好評発売中
http://genshobo.com/?p=5871 |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

『日本の論壇雑誌』について
竹内洋
|
| 敗戦を3歳で迎えた私のような世代には、戦後史は自分史と重なってくる。そんなことから自分史を重ねながら2011年に『革新幻想の戦後史』(中央公論新社)をまとめた。この著でも『世界』や『中央公論』『諸君!』などを取り上げたが、戦後の思潮を考えるには、論壇雑誌つまり総合雑誌の総合的研究がなくてはならないと思うようになった。
たしかに「総合雑誌の研究」(『流動』1979年7月号)のような明治以後の総合雑誌をすべて網羅した論文はある。しかし、これは総合雑誌の通史である。一方、各論的研究、つまり個別の総合雑誌についての評論、あるいは単著もあるが、これだけでは単体の綜合雑誌研究である。そこで、一冊の本にできるだけ多くの総合雑誌を取り上げ、読者が雑誌相互を横断・接続(connectivity)することで、戦後の思潮の場の攻防が俯瞰できるような本をつくってみたいとおもった。
しかし、このような本はひとりの力では生まれない。手間暇の問題もあるが、それ以上にテイストが合う雑誌と合わない雑誌、得手雑誌と不得手雑誌があり、一人では後者系の雑誌の扱いがぞんざいになってしまう懸念がある。そうおもい、京都大学の佐藤卓己さん、稲垣恭子さんに相談し、研究会を立ち上げた。メンバーには、上記3人を中心に、8名の参加を得て計11人でスタートした。こうして本書は出来上がったが、取り上げた雑誌は『中央公論』『文藝春秋』『世界』など10種類で、これに「ネット論壇」を加え、巻末には日本の「論壇雑誌年表」をつけている。
もちろん戦後の総合雑誌を網羅することはできなかったが、論壇の「中心」雑誌、「周辺」雑誌、中心への「対抗」雑誌群をカバーしたとおもう。本書によって読者が老舗総合雑誌の衰退やあらたな総合雑誌の勃興をつうじて戦後の論壇史を追体験し、それをつうじて戦後日本のインテリ界=中間文化界の輿論と空気を読み取り、戦後思潮の攻防と変遷史を考えるための一助にすることができれば、執筆者一同これに過ぎる喜びはない。ご一読、ご高配のほどよろしくお願いいたします。
執筆者を代表して 竹内 洋
以下のように、本書をめぐるシンポジュームを開催します。ご参加ください。
時間・プログラムなど詳細は、6月下旬以後の関西大学東京センターのホーム ページでご覧ください。
日時:8月22日(金)午後
会場:関西大学東京センター(東京駅日本橋駅すぐ、サピアタワー9階)
http://www.kansai-u.ac.jp/tokyo/map.html
テーマ「教養メディアの輿論と世論―『日本の論壇雑誌』から考える」(仮)
竹内洋
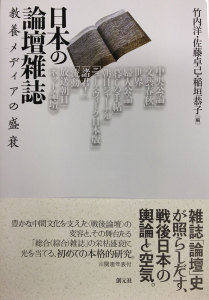
『日本の論壇雑誌』 竹内洋、佐藤卓己、稲垣恭子編
創元社 定価(税込):3,780円 好評発売中
http://www.sogensha.co.jp/booklist.php?act=details&ISBN_5=30048
|
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

「神田古本まつり俳句大会」について
神田古書店連盟会長 佐古田亮介
|
| なぜ古本まつりに俳句大会なのか。それはそもそも今年で第55回を迎える「東京名物 神田古本まつり」に何か新企画はないか。という話から始まり俳句を始めて五年目の私が俳句大会をやろうと言い出して決りました。単なる思いつきで言った訳ではなく、俳句大会をやるに当たって絶対必要となる条件には心当りが有りました。
私は四年前に創刊した俳誌「月の匣」の会員として俳句を始めると同時に、神保町に在る「銀漢亭」という知る人ぞ知る俳人酒場で行われている超結社句会「湯島句会」にも参加しましたので、俳人に知り合いが出来ました。そして俳句大会準備に欠かせないのが投句されて来た俳句の選者です。選者が決まらなければ大会に成りません。その選者に心当たりが有った事がやろうと言い出した一番の理由でした。しかも二人いました。一人は私が所属する「月の匣」主宰の水内慶太(みのうちけいた)先生。もう一人は「銀漢亭」主人にして俳誌「銀漢」主宰の伊藤伊那男(いとういなお)先生でした。俳句をやらない人には聞き覚えの無い名前かも知れませんが、お二人とも常時俳句総合誌に掲載されている一流の俳人です。
まずは慶太先生に下相談すると「それは良い是非おやりなさい。古本と俳句は相性が良い。何で今までなかったんだろう。」と大賛成を受けました。つぎに伊那男先生に相談するとこれも大賛成。お二人とも快く選者をお引き受け下さり俳句大会実現に一気に拍車が掛かりました。そして心強い味方がもう一人。これも神保町に在る俳句出版社「本阿弥書店」の編集長が「月の匣」同人で何でも相談に乗ってくれました。応募用紙の作成や宣伝方法など大変助かりました。
社長にごあいさつすると神保町に古くからある俳人喫茶「きゃんどる」の話や「一誠堂書店」の大番頭で俳句を作っていた小梛精以知(私の上司で「句集寸楮」がある。古書会館8階のGケースに入ってます。)の話も出て意気投合。俳句大会の後援も申し出てくれました。地域と俳人を結び付けて古本まつりが益々盛り上るよう、読者の皆様も是非投句して下さいね。どうぞよろしくお願い申し上げます。 応募用紙は「BOOKTOWNじんぼう」イベント情報にアクセスすればダウンロード 出来ます。
俳句大会にご応募をして頂いた方、10名様に掲載誌をプレゼントいたします。
『神保町公式ガイド Vol5』 10月初旬発行予定
発表は発送をもって代えさせて頂きます。
東京名物・神田古本まつり55回開催記念 俳句大会
本にまつわる俳句募集中!
http://jimbou.info/news/140415.html |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

「本の雑誌39年間の本屋ネタが満載!408ページの『本屋の雑誌』」
浜本 茂
|
| 5月末に出した別冊本の雑誌『本屋の雑誌』は雑誌という書名からイメージされる厚さをはるかに凌駕するボリュームと緑色のシンプルなカバーがウリ。あまりの厚さに書店の店頭でそれと気づかずスルーしてしまう人がいるとか、当社らしからぬおしゃれな(と自分たちでは思っている)装丁が輪をかけて見逃しに力を貸しているという噂も耳にするが、なにを隠そう書店カバーを模しているのである。そして本文はなんとなんとの400ページ! おまけに京都の三月書房と千駄木の往来堂書店の棚が読めるカラーグラビアが8ページつくという圧倒的な分量なのである。
どうしてこんなに厚くなったのか。実は『本屋の雑誌』は『SF本の雑誌』(09年)、『古本の雑誌』(12年)に続くダジャレ書名別冊シリーズ(?)の第3弾で、前2作と同様、本の雑誌に掲載した新刊書店関係記事の再録と新原稿の2本立てで構成している。ようするに新旧ごったまぜのバトルロイヤル本なのだが、前2作が過去の記事4割、新原稿6割の割合なのに対し、第三弾は過去記事が全体の7割強を占めることになってしまったのである。
なんだい、再録ばっかりかい、と思う人もいるかもしれないが、ちょっと待っていただきたい。『SF本の雑誌』は176ページ、『古本の雑誌』は192ページ。対して『本屋の雑誌』は408ページで、新原稿だけで108ページ分あるのである。『SF』『古本』と比べて新原稿の分量は決して見劣りしない、ということはおわかりいただけるだろう。
それでもバカみたいな厚さになってしまったのは、過去の記事があまりにも面白く、割愛するにしのびなかったからである。たとえば書店に行くと便意を催すという「青木まりこ現象」の謎と真実を1985年と2013年の2度にわたって探ってみたり、立ち読みの研究をしてみたり、ジュンク堂書店に単独登攀してみたり、本屋プロレスをレポートしてみたり、いや、どうしてこんなに面白いことを思いつくんだと自画自賛したくなるものばかり。困ってしまうのだ。
かくして再録記事だけで300ページにのぼったわけだが、これでも泣く泣く落とした記事は山のようにある。それほどに本の雑誌は新刊書店関連の記事を掲載し続けてきたという証でもあり、この再録記事の数々は本の雑誌創刊からの39年間に書店がどう変わったのか、あるいはどこが変わらなかったのを知るよすがになると自負している。108ページの新原稿がすぐれものであることは言うまでもないが、今回の別冊に関しては39年間の書店状況を俯瞰できる再録部分にこそ『本屋の雑誌』と名乗れるキモがあるとあえて言っておきたい。古本屋さんもいいけど、新刊書店もいいですよ。『本屋の雑誌』を読んで、新刊書店にますます足を運んでいただけるとうれしい。

『本屋の雑誌』(別冊本の雑誌17)
本の雑誌社発行 好評発売中 1980円+税
http://www.webdoku.jp/kanko/page/9784860112561.html |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

『出版産業の変貌を追う』
文化通信編集長 星野 渉
|
| 出版物の販売金額がマイナスに転じた1997年から17年が経過したが、いまの出版業界は、電子出版の拡大、中堅取次の経営危機など、当時では想像できなかった様相を呈している。
私が文化通信社で出版業界を取材する仕事について25年になるが、入社した当初の出版界は、市場拡大期の最終段階にあり、まだバブル的な雰囲気が色濃く残っていた。その後、市場の縮小、様々なレベルでの電子化の進展という、大きな時代の転換期に突入した。その変化を一言で表すとすれば、「電子化という環境変化が振興する中での、取次システムの行き詰まり」と表現することができる。
それは、世界で日本にしかなく、戦後の出版産業拡大の原動力ともなってきた「取次システム」が、デジタルネットワークの普及の影響によって、一部が機能不全に陥ろうとしているということであり、米国など諸外国の出版業界における電子書籍化の影響とは全く異なるものである。 本書は、ちょうどこの時期に出版業界の動向について、これまでにいくつかの媒体で発表してきた文章をまとめたものである。業界専門紙という、産業動向をウオッチすることを主な生業としてきたため、どちらかというと流通や経営的な側面への視線が強く出ていると思われるが、この間の変化は、まさに出版業界に係わるほぼすべての企業の経営を根幹から覆しかねないものである。
そういう視点から、改めて各論考を読み直してみると、現在も進行している出版産業の大きな流れが、どのあたりで曲がり角を迎え、どちらの方向に向かっているのかを、改めて確認できるように思う。
また、私はこの間、アメリカやヨーロッパ、韓国などの諸外国を何度か訪問する機会を得てきた。そうした海外の出版業界をみることで、日本と海外とのつながりや、ビジネスとしての可能性を実感するとともに、日本の出版業界が持つ独特の仕組みを相対化し、客観的に眺めることができるようになったとも思う。
2014年は、業界第三位取次の大阪屋が、経営再生に向けた一歩を踏み出す年であり、前年から本格化してきた電子書籍の市場が拡大し始めている時期でもある。 こうした変化が顕在する時期に、本書を刊行できたことは偶然ではあるが、出版業界の人々、そして本や出版に興味のある人々が、出版業界の今後を考える一助になればと考えている。
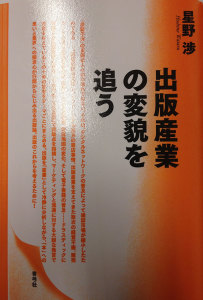
『出版産業の変貌を追う』 文化通信編集長 星野 渉 著
青弓社 定価:2000円+税 好評発売中
http://www.seikyusha.co.jp/wp/books/isbn978-4-7872-3377-6

文化通信(毎週月曜日発行)
文化通信社 https://www.bunkanews.jp/ |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

AKB48の論じ方
笹山敬輔
|
| 最近のアイドルブームから、書店には「アイドル」を様々に論じた本が並んでいる。現在のトップアイドルグループであるAKB48を論じた本も多い。それらを読んで感じることは、論者が社会学者であったり、社会学の用語を使って論述したりしていることが多い、ということである。これは、アイドルに限ったことではない。流行のドラマ・マンガやSNS等、現代に登場してきた最新の現象に対して、その論評を社会学者が担うことが多い。
一方で、文芸評論家を始めとした文学畑で育った論者は少ない。私の認識では、戦後のある時期まで、文芸評論家と呼ばれる人々が、様々な文化現象を解釈してきた歴史があると思う。現在は、その領域を社会学が担い、若い読者層の支持を得ているようだ。このことは、大学における文学部の退潮傾向とも無関係ではないだろう。文学部の教養を持つ論者が行う議論が、説得力を獲得しにくくなっている。
私自身は文学部の出身だが、社会学者が論じるものを読んで、面白いと感じることは多い。しかし、その一方で、歴史的な視点が少ないと感じることがある。我々が新しいと感じるものであっても、それは当然過去の様々な蓄積から生まれてきている。その系譜を丁寧に辿ることによって、現代の事象の位置付けはより明確になるはずである。
拙著『幻の近代アイドル史』では、従来1970年代に始まったとされるアイドル史を明治期にまで遡り、現在のアイドルブームに似た現象がその頃から見られることを書いている。明治から昭和前期において、「アイドル」という言葉はもちろん存在しなかったが、「アイドル的存在」は容易に見出すことができる。「総選挙」のようなファン投票もあったし、ファンたちが観客席から自分の好きな「推しメン」の名前を絶叫することもあった。かの川端康成も「推しメン」目当てに劇場通いをしていたのである。
このような歴史を踏まえた上で、現代のアイドル現象を過去に連なるものと見るか、全く新しいムーブメントとして見るかは、それぞれの論者が議論を展開すればよいと思う。ただ、何事も歴史を踏まえた方が、より説得的な議論が展開できるのではないだろうか。 拙著が現在のアイドル論に対して、何らかの貢献ができればうれしい。
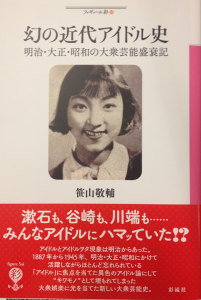
『幻の近代アイドル史』 笹山 敬輔
彩流社 定価 1800円 + 税 好評発売中
http://www.sairyusha.co.jp/bd/isbn978-4-7791-7014-0.html |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

「読み」・解釈とどう向き合うか
山梨 あや
|
| 拙著について語る機会をいただき、気恥ずかしさと、これをきっかけに新たな「読み」に触れることができるのではないか、という期待感とがないまぜになっている。本書は、なぜ読書という行為が教育の問題として取りあげられるようになったのか、そして読書という知的営為への参入は、誰に、どのような意味をもたらしたのか、という二つの問題を近代日本教育史の文脈において検討している。
筆者がこの問題に取り組み始めたのは、折しも永嶺重敏氏が一連の論稿・著作を刊行し、読書の問題が読書史や出版史にとどまらず、日本史、教育史、教育社会学など様々な領域において問われるようになった頃であった。書籍や新聞雑誌が誰に、どのように普及し、読まれていたのかという実態の解明にとどまらず、読者の意識や教養形成とどのように関わるのか、というより深化したレベルの研究が豊かになり、読書行為になじみのない人々がこの知的営みに参入する過程とその意味について検討していた筆者自身も大いに触発された。
とはいえ、読書に関する研究、著作はともすれば「都市・男性・中間層以上の人々」を中心に検討する傾向があった。これは必ずしも書き手の問題ではなく、読書行為を歴史的に論じる際に必ず突き当たる資料的制約に因るところが大きい。別の表現をすれば、読書に関する資料的制約のあり方に、近代日本の知的営為に関する様々な偏差が反映されているのである。読書行為が内包する「知の偏差」にいち早く注目し、これを「社会教育」という枠組みの中で教育的に組織化しようとしたのが内務官僚、次いで文部官僚であった。本書において、読み書きを取得させ、さらに教科書を含む本を「読む」という経験を多くの人々にもたらす上で大きな役割を果たしたと考えられる小学校教育ではなく、学校外教育を担う社会教育に焦点化して読書の問題を論じたのもこの理由による。
本書を執筆する過程で明らかにされたのは、「教化」か自発的な学習活動かという単純な二項対立では読書運動や読書指導を捉えきれず、読書により生み出される豊かな「読み」・解釈の歴史的意味を捨象してしまうということである。戦前・戦後を問わず、教育者や指導者、さらには書き手の意図を超えた「読み」は存在したのであり、この「読み」は様々な制約を伴いつつも、時として既存のものの考え方やあり方に揺さぶりをかける密やかな「力」となったのである。
研究者の一人として求められているのは、知的営みの所産をいたずらにラベリングしたりカテゴライズしたりするにとどまらず、一つ一つの営みと真摯に向き合い、その意味を紡いでいくことではないか、と考えている。本書の執筆後に見えてきた課題は多いが、筆者にとって最も大きな比重を占めているのが、読書運動や指導に携わった人々が、どのように学習者の「読み」や解釈と向き合い、彼ら・彼女らの知的要求に働きかけようとしていたのか、という問題である。恐らくこの問題に直面したのは、地域社会の知識人とも言うべき存在であった教員層であったろう。
本書でも事例として検討した長野県下伊那地方では、戦前から戦後にかけて図書館活動や読書運動が盛んに展開されており、戦後の読書運動に参加した古老からは、戦前の小学校時代の読書経験を重視する声が多く聞かれた。小学校教員は学校教育という枠組みを超え、家庭や地域社会に対する教育にも深く携わっていたことを踏まえ、このような状況下で読書をはじめとする知的営みはどのように育まれていたのか、そしてその知的営みの意味を明らかにすることが目下の目論見である。
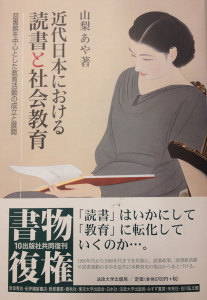
『近代日本における読書と社会教育』 山梨 あや
法政大学出版局 定価:5,700円 + 税 好評発売中
http://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-68605-4.html
|
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|
Just another WordPress site