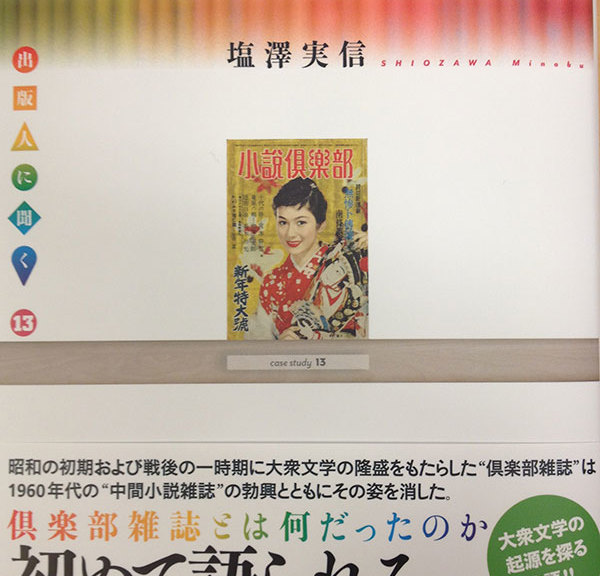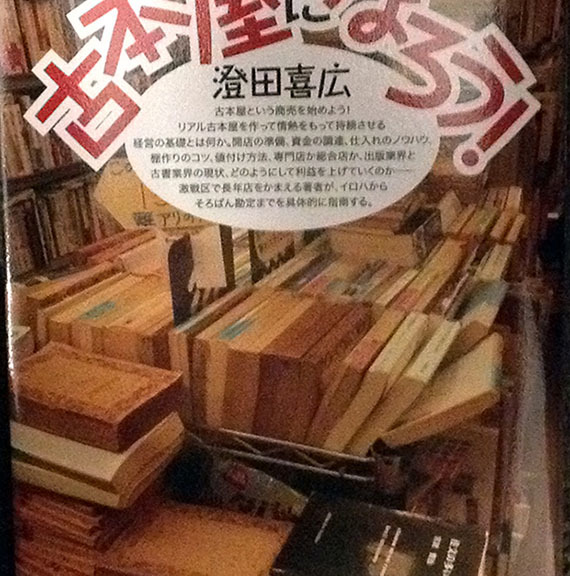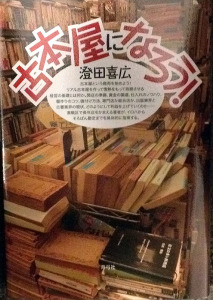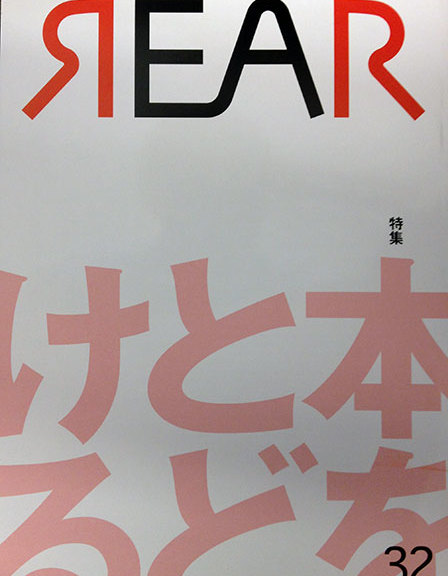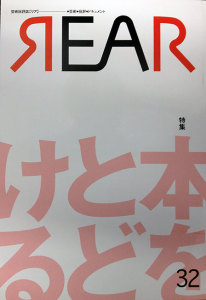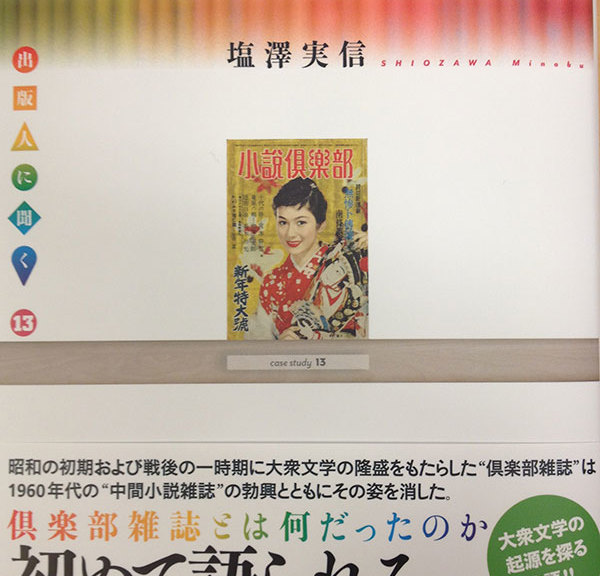
作家と歩んだ出版人生
原田 裕
|
| わたしが大日本雄弁会講談社へ入社したのは昭和21年のことです。それから半世紀以上経った今も現役で出版業界の片隅に生きており、われながら、長い編集者人生だと思っています。
本書『戦後の講談社と東都書房』は90歳にしての処女出版となりましたが、大勢の作家の本を数多く出版してきた者が、まさか自分自身で本を書くことになるというのも不思議なものです。 長らく出版業界に身を置いていると、往々にして信じられないことに出くわしますが、今回の自著出版はわたしにとって一番の驚きでした。
わたしが『キング』や『日本』の編集長となった頃、一般の大衆小説(現代もの、時代ものと呼ばれた)や推理小説(当時は探偵小説)は純文学と比べて一段も二段も低く見られ、軽蔑すべき通俗読物とされていました。現在のように面白ければどんなジャンルの小説でも読まれる時代ではありませんでした。
このように小説や作家を型にはまったレッテルで割り切って甲乙をつける日本独自の出版風潮に大反対であったわたしは新書サイズの「ミリオン・ブックス」や「ロマン・ブックス」を創刊し、いわゆる純文学の作家も大衆作家と同じ土俵に並んでもらいました。
戦後初となる全作書下ろしの新作からなる「書下ろし長篇推理小説」や新作長編が軽装で読めることをウリにした「東都ミステリー」を企画したのも狙いの一つで、いずれも読者からは好評を以て迎えられたようです。
現在、「書下ろし長篇推理小説」や「東都ミステリー」は古書でしか流通しておらず、なかには相応の高値がつくものもあると聞きます。 これらの叢書には、親しく付き合っていた高木彬光さんや山田風太郎さん、横溝正史さんの名前も含まれていますが、そういった著名作家以外にも、今では新刊書店に著書が並ぶ事もなく、知る人ぞ知るといった作家も少なくありません。
せっかくの機会ですので、本書では、そうした「忘れられた作家」の横顔についても可能な限りふれてみました。
わたしは推理小説の専門家ではなく、あくまで編集者の立場から見た作家の横顔しか紹介できませんでしたが、記憶の限り、知っていることを書いたつもりです。
本書には書きませんでしたが、川口松太郎や舟橋聖一とは苦い思い出があり、田無在住だった香山滋さんからは若い男が興奮するような写真を見せてもらいましたし、高木彬光さんの豪快な武勇伝も数多く見てきました。 その他、ご夫婦揃って好人物だった日影丈吉さん、将棋への傾向ぶりに泣かされた角田喜久雄さん、「霧の会」立ち上げに協力してくれた夏樹(当時は結婚前で五十嵐姓でした)静子さん……。思い出を語り出したら止まらなくなりそうなほど、60年近い出版人生では多くの方に巡りあえました。
時に楽しく、時に辛かった編集業を今も続けられるのは、かけがえのない出会いがあるからだとも言えます。 90歳を超えたわたしが初の著書を出す僥倖に恵まれたのも、数えきれないくらい大勢の作家と二人三脚で歩んだ出版人生があったからでしょう。
『戦後の講談社と東都書房』には、長い編集者生活で体験した「個人的出版史」をできる限り詰め込みました。 舌足らずな点や記憶違いもあると思いますが、最古参の編集者による昔語りを読者の皆様にお楽しみいただければ、こんなに嬉しいことはありません。

『戦後の講談社と東都書房』原田 裕 著
論創社刊 定価:1600円+税 好評発売中
http://www.ronso.co.jp/ |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|
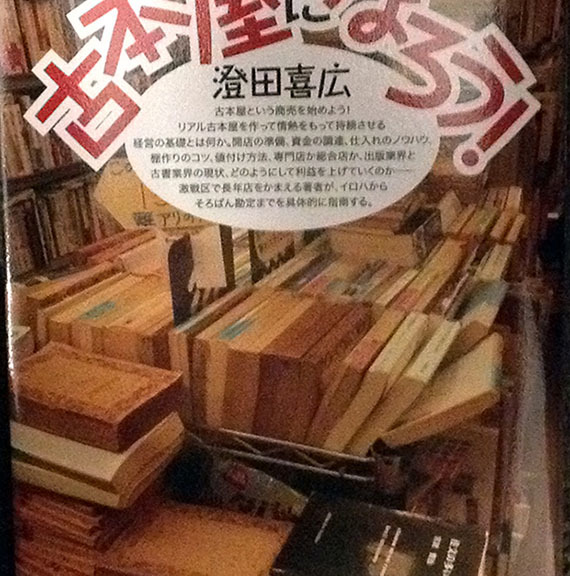
ちょっと本気で古本屋になるための本
澄田 喜広
|
| 古本屋の仕事の多くがお客さんの見えないところで行われることもあるけれど、値付けのノウハウや古書流通の仕組みについて、当事者たちが語らなかったという理由も大きい。古本屋は、やり方を知ってしまえば誰でもできる商売だ。簡単な秘密だからこそ、誰も語らなかったのだ。
古本屋をやるには特別な修行はいらない。そこがそば屋や洗濯屋との違いだ。独立するのに、大口の顧客や仕入ルートを確保しておく必要もない。
ただし、古本屋は本を愛していさえすれば始められるが、長く続けるにはそれなりのコツがある。数年も続けていれば自然に身につく事柄だが、そのまえに力尽きてしまう人も多い。ベテランの古本屋は、それぞれ自分なりの方法で商売をしている。一般的なセオリーを開業時に知っていれば、自分なりのスタイルを身につけるまでもたせることができるだろう。
レストランの経営は料理がうまいだけでは成り立たないということは、すぐに想像がつくだろう。繁盛している店には、おいしい料理を「商売」にするためのノウハウがあるはずだ。たいていの仕事では仕入れ先や問屋が多少なりとも指導してくれるだろう。居酒屋なら、ビールを納入するメーカーがメニューや看板の相談に乗ってくれるし、ヘアサロンなら薬剤や設備を卸す美容商社が開店資金の提供までしてくれることがあるという。
古本屋は一般客から仕入れた本を一般客に売る仕事なので、大手の取引先というものがない。せいぜい古書組合がある程度だが、同業者同士の集まりで営利団体でもないので、細かく面倒を見てくれることはない。そこで、伝統的なノウハウを知りたいなら、既存の古書店に勤めて実地の仕事をしながら身につけるのが、ほとんど唯一の方法だ。
しかし、古本屋を取り巻く環境はここ10年で大きく変わってしまった。既存の古書店のやり方を学んでも、その方法でこれから開業できるとは限らない。老舗古書店で経験を積んだとしても、これからの時代にも通用する経営の技法は自分で見つけるほかない。
本書では、古本屋のビジネスモデルを専門店型、自給自足型、新古書店型、セレクトショップ型、発見型総合古書店、検索型総合古書店(買取専門店)の6種にわけて解説した。とくに、専門店型とセレクトショップ型は似ていて、これから古書店を始めようとしている人も混同している場合がある。しかし経営の方法が全く異なるので、自分がやりたいのはどちらなのかしっかりと見極めておくことが必要だ。
あわせて、古書店を取り巻く環境の変化を、主に出版業界における大量出版時代の終焉と、流通業界におけるネットの影響を中心に考察した。
この『古本屋になろう!』は、ほとんど私の店「よみた屋」での経験がもとになっている。一般的な調査を経たものではないので、一面的独断的な部分もあるだろう。しかし、古書店を実際に経営している店主の生きた秘訣がつまっている。
古書店の経営は、多くの方の協力がなければ成り立たない。いままでよみた屋を支えてくれたお客様、地域の方、同業者、そして自営業だから家族、くわえて従業員のみなさまに感謝します。
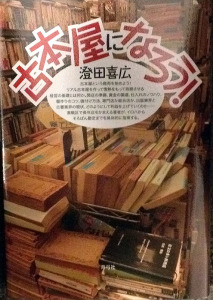
『古本屋になろう!』 澄田 喜広 著
青弓社刊 定価:1600円+税 好評発売中
http://www.seikyusha.co.jp/wp/books/isbn978-4-7872-9223-0 |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

2011年の第55回 東京名物 神田古本まつり
|
○青空掘り出し市
【神田神保町古書店街】
平成26年10月25日(土)~11月3日(月祝)
10:00~19:00 (最終日18:00終了 雨天中止)
○特選古書即売展 青空掘り出し市より1日早く開催します!
【東京古書会館地下催事場 (千代田区神田小川町3-22)】
平成26年10月24日(金)~10月26日(日)
10:00~18:00 (最終日17:00終了)
○古本チャリティーオークション
【さくら通り イベント会場】
平成26年11月1日(土)14:00~ (雨天順延)
○ビブリオバトルin 神田古本まつり
【東京古書会館 7階】
平成26年11月1日(土)18:30~20:30(18時開場)
などなど内容盛りだくさん!
詳しくはこちら http://jimbou.info/
平成26年度神田古本まつりの一環として,「神田古本まつり特選古書即売展」が来たる10月24・25・26日の3日間 東京古書会館地下1階で開催されます。(午前10時~午後6時 最終日午後5時閉会)
和洋古典籍・古地図・歴史学、民俗学等の学術書・近現代日本文学の初版本や草稿・映画・美術・趣味 など個性あふれる14店が参加いたしますので是非ご来会の程お願い申しあげます。
今回は新企画としまして、同会場の東京古書会館2階にて24・25日の両日「希少書籍展示コーナー」を開設いたします。 また会期内の会場決済に限り、総額1万円以上のお買い上げにはクレッジト決済がご利用できます。
会期内、会場で5千円以上お買い上げのお客様には送料無料券を提供いたします。
目録の発行は10月8日ごろの予定です。
ご希望の方は切手500円同封の上 101-0051 千代田区神田神保町2-14-6 谷地ビル2階 魚山堂書店までお申し込みください。 |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|
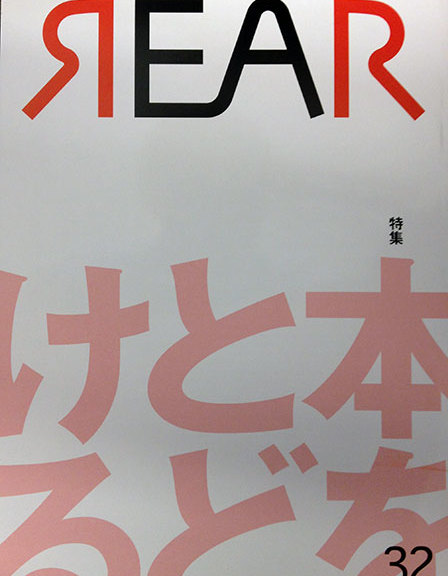
『芸術批評誌REAR 32号 特集「本をとどける」』
増田千恵(リア制作室)
|
| 芸術批評誌REAR(リア)は、2003年1月に特集「名古屋発/名古屋脱」で創刊しました。 以来、特集・批評・レビューを軸に構成している批評誌です。中部地域の芸術を「後衛(rear)」として批評・記録しながら、書き手や読者の広がりとともに視野を拡大してきました。
10年30号を超え、美術界隈ではそれなりに存在を知られるようになってきましたので、きちんとした事務所で編集者たちはバリバリと…と思われがちなのですが、みな他に本業を持ちながらの非営利活動で、某シアトル系カフェを本拠地に編集会議を行っています。 メンバーもゆるやかに新陳代謝を繰り返しながらなんとか続けています(実働部隊が2人になってしまったときはさすがに限界を感じました…)。
8月に32号(特集「本をとどける」)を発行しました。
本の製作、出版から流通、販売、活用や保存にいたるまで、さまざまな立場から論じていただきました。創刊以来はじめて「本」をテーマにしましたが、思わぬ反響の大きさに驚いています(このメルマガのような依頼がきたのもはじめてです!ありがとうございます)。
特集のきっかけは、美術館で発行される展覧会図録の「分厚さ」でした。
書籍の電子化に注目が集まる中で、それに逆行するような存在感の図録が多くなったように感じ(代表例は東京都現代美術館の『大竹伸朗 全景 1955-2006』(2007年、grambooks)厚さ13cm、重さ6kg!持って帰るのも大変です)、編集会議を重ねました。
結果的に今回の特集ではこの事象については触れられませんでしたが、研究成果をふまえた論考や資料の充実した大型図録が発行される背景や、最初に書店流通を行った図録は何の展覧会だったのか、など興味は尽きません。
編集作業では、わたしたちが本を手にするまでの間にはとても多くの人の手が実際に介在しているのだ、という当たり前のことを何度となく実感することになりました。
取り上げられなかった装丁や造本・印刷なども含め、「モノ」としての「本」だからこそ人から人へ手渡され残されていくのだと、それぞれの「手」を思い浮かべています。
巻頭対談をお願いした菊地敬一氏(ヴィレッジヴァンガード会長)と古田一晴氏(ちくさ正文館書店本店店長)、進行役をつとめて下さった石橋毅史氏(『「本屋」は死なない』著者)をはじめ、たくさんの方にご寄稿・ご協力いただきましたが、静かで熱い気持ちがまっすぐに伝わってくる特集になったと自負しています。
ぜひ本屋さんで手にとってください。
次号では今年生誕100年を迎えた画家・浅野弥衛を特集します。
みなさまの手にとどく場面を想像しながら、よりよいものになるよう丁寧に取り組んでいきたいです。
◆リア制作室では小誌刊行にご援助をいただく賛助会員を募集しています。
詳しくはHPをご覧ください。
http://2525kiyo.cocolog-nifty.com/blog/2008/09/post-2ad2.html
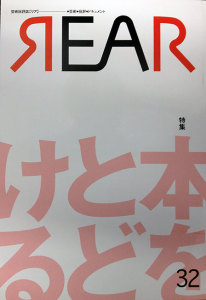
『芸術批評誌REAR 32号 特集「本をとどける」』
リア制作室 定価:450円+税 好評発売中
http://2525kiyo.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/32-91a2.html |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

第100回全国図書館大会開催迫る
第100回全国図書館大会事務局長 西野 一夫
|
| 10月31日(金)11月1日(土)の2日間にわたって、全国図書館大会が開催されます。全国の図書館関係者が一堂に会して、図書館にかかわるさまざまな課題や問題を議論する大会です。
今年の大会は、第100回目の大会となります。明治39(1906)年、上野に作られた帝国図書館新築落成に合わせ、東京帝国大学(当時)を会場に、全国図書館員大会が開催されて以降、全国図書館大会は、第2次大戦による中断を余儀なくされた時期(昭和15年~昭和22年)を除き、毎年開催されてきました。
会場となる明治大学駿河台キャンパスは、東京駅から中央線快速電車で2駅目の御茶ノ水駅から徒歩5分という交通至便の地にあります。御茶ノ水駅を挟んで反対側には、日本の近代公共図書館の嚆矢ともいわれる、明治5年に開設された「書籍館」(しょじゃくかん)がおかれた湯島聖堂が指呼の間にあります。
また、図書館大会が開催されるこの時期には、「東京名物神田古本まつり」(10月25日~11月3日)と「神保町ブックフェスティバル」(11月1日~3日)が開催され、この地域が読書と本にあふれた1年のうちで最もにぎわいを見せる時期でもあります。 大会第1日目に開催する記念フォーラムは、今大会を特色付けるイベントの一つです。元NHKアナウンサー山根基世さん、雑誌『暮らしの手帖』編集長で文筆家の松浦弥太郎さん、ブックディレクター幅允孝さんをお招きし、それぞれの方の本と読書にかかわる活動を映像でご紹介しながら、読書と生きる力、生活の中の読書と人生、図書館と読書のある生活について、語り合っていただく企画です。
今大会の後援団体になっていただく、「本の街・神保町を元気にする会」や「神田古書店連盟」などのご協力により、一般公募で応募された市民100名を大会にご招待し、市民に開かれた図書館大会を目指しています。 また、大会財政を支えるためにたくさんの寄付をお願いしています。下記のURLにアクセスしていただき、大勢の方々の善意と熱意によって第100回大会が成功できますよう、ぜひ、ご協力をお願いいたします。
http://justgiving.jp/c/10708
日本図書館協会主催 「第100回全国図書館大会 東京大会」について
http://jla-rally.info/tokyo100th/index.php/ |
|
Copyright (c) 2014 東京都古書籍商業協同組合
|

2011年の古本屋ツアー・イン・ジャパン活動報告
古本屋ツーリスト 小山力也
|
| 神戸・日立・飯倉・角田・福島・焼津・つくば・蒲郡・草津・高崎・静岡・高岡・信濃追分・川名・北三条・栃木・須賀川・北軽井沢・鹿島神宮・秩父・鶴岡・塩釜・水沢・横手・前橋・月江寺・仙台・盛岡・益子・中之条・磐田・飯田・大津・小名浜・京橋・大阪・別府・小倉・小山…2011年12ヶ月分のブログを遡り確かめた、古本屋さんを訪ねた地方の街を列挙してみた。今年は都心近くの、訪ねるべき未踏の古本屋さんが少なくなっているため、より地方に足を延ばすことを心がけたのである。がんばったな、と言う気もするが、やはりまだまだな感じは否めない…いや、本心を言うと“感じ”の話などではないのだ。単純にもっと行きたいのだ!地方に!遠くに!行ったことの無い古本屋さんに!こうまで意気込んでしまうのは、やはり三月の大震災の影響があるのかもしれない。“今見に行かないと、絶対に後悔する。
本当にいつ無くなってしまうか判らないから”と言う漠然とした不安からの行動…しかしこれが逆に自分のエネルギーとなり、“とにかくお店を記録に留めるのだ!”と、時間と財布の許す限りの、リミッター外しかけの、綱渡りな九ヶ月を過ごしてしまう(もちろん現在も継続中である…)。特に復興に向かう東北には、何度も訪れることとなった。すっかり元通りに立ち直ったお店、再興中のお店、残念なことに閉じてしまったお店もあった。しかし、実際のお店を目にしたことにより、自分の中では何かが形作られて行く…。店主本人からも『ウチの本は一冊も落ちなかった!』『もう店の中はテンヤワンヤ』『すぐ外に飛び出しちゃった』『友達が行方不明なんじゃ』などと聞いたりしながら、とにかくお店を闇雲に訪ね、古本を買い、自身の脳内古本屋地図を作成更新して行く。おかげで地震前より、確実に蔵書が増えてしまうことになり、『本を買うのは、なるべく控えよう…』などと思っていたのは何処へやら。以前は部屋の中でタワーとして存在感を放っていたのが、家内のそこかしこで低い台地として、生活圏をジワリジワリと侵食し続けている…。
またこの年は、予想以上に新規開店のお店が多かった。都内を中心に何と34軒!最近はやりのカフェ&雑貨屋兼業のスタイルだけではなく、古本屋さん一本のお店も次々とオープンし、新世代のうねりをダイナミックに感じさせてくれた。何度この勇気あるお店たちに、ツアーの危機を救われたことか。それと同時に、店頭販売を辞めるお店も、多く目の当たりにすることとなった。業界の新陳代謝と受け取れば明るく思考出来るのだが、やはりお店を閉じられるのは非常に寂しいとしか言いようがない。
そしてこれだけ“古本屋ツーリスト”と勝手に称して、古本屋さんを巡っていると、時に身に余る依頼が舞い込んだりする。まずは3/19に『西荻ブックマーク』と言うイベントで、岡崎武志氏とのトークショーを行うことに。地震後の非常に慌ただしい状況ではあったが、ガチンガチンに緊張しながらおよそ50名の観客を前に二時間。精も根も尽き果てるが、何か古本屋さんを巡り続ける思いの丈を話しまくれたようで、自分にとっての心のターニングポイントとなった。その場に居た、すべての方に感謝したい。これがきっかけとなり、10/29には、何と敵の本丸のひとつである『神奈川県古書籍商業協同組合』からトークの依頼があり、古書の日の『古本屋開業講座』の一環として、またもやド緊張しながら人前で話しをすることに。古本屋さんになりたい方々と、プロフェッショナルの古本屋さんに周囲を固められながらも、ほとんどブログの勢いそのままに、古本屋さんについて語らせていただいた。これはもう本当に懐の深い、神奈川県古書組合のみなさまに感謝である。
さらに12/10からは、ようやく念願の古本販売を開始することに。買う一方だった私が、ついに供給側へと足を踏み入れてしまったのだ!西荻窪『盛林堂書房』さんの常設棚貸しイベント『古本ナイアガラ』の最下段で、「フォニャルフ」と称し、常時三十冊ほどの本を並べさせていただいている。これが始めてみると非常に面白く、テーマに頭を悩ませたり、補充をしたり、売れたり売れなかったり、お店が気になってしょうがなくなったり、棚に合う本を探したり買ってみたりと、新鮮な体験の連続なのである。もちろん私などは、児戯の域を出ない棚造り&販売なのだが、何か新しい一歩を踏み出せたようで、これからも真剣に頭を悩ませて、良い古本を並べて行きたいと思っている。
最後に、私にとって今年は、たくさんの探している本と、安値で出会えた幸せな年でもあった。その収穫を挙げてみると、集英社コバルト文庫「文彦のたたかい」「水瓶座の少女」共に野呂邦暢で100円、サンリオSF文庫「猫城記/老舎」50円、講談社文庫「工場日記/シモーヌ・ヴェイユ」100円、秋田書店「怪獣ウルトラ図鑑(裸本)」1000円、鹿島出版会「近代建築ガイドブック[北海道・東北編][東海・北陸編]」共に800円、小学館「森やすじの動物カット集」100円、改造社「哀しき父(裸本)/葛西善蔵」200円、明治書院「おはなし電気學/佐野昌一」800円などなど。まぁ状態の善し悪しはあるにはあるが、ネット販売ではなく、お店に直接出向いたからこその成果であると言えよう。これだから古本屋ツアーはやめられない…。
2012年も、探し求めている素晴らしい本たちや、まだ見ぬ古本屋さんとの出会いを切実に求め、全国を駆けずり回って行くつもりである。さて、一体どんな一年になりますことやら…。
『古本屋ツアー・イン・ジャパン』
日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ。お店をダッシュで巡ること多々あり。調査活動は今年でいよいよ五年目へと突入する。最近は「フォニャルフ」の屋号で古本販売も始めた。あぁ、私は一体何がしたくて、果たして何処へ向かっているのだろうか…。
http://blogs.dion.ne.jp/tokusan/ |
|
Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合
|

古本屋が『映画学の道しるべ』を読み解けば 3
稲垣書店 中山信如
日本古書通信 2012年1月号より転載
|
| さて一読は済んだ。しかし、それにしても、牧野守という人はなんて不運な人なんだろう。あれだけのエネルギーとパッションをつぎ込み私蔵の資料を使って次々と作り上げた復刻版の反応反響は、少なすぎはしまいか。すでにそれなりに利用されはじめているという海外はさておき、肝心のわが国内でである。すぐに反応があったのは原本を提供する業者側のほうばかりで、学問の発展を受け入れようと思う古本屋は、原本の古書価の値崩れをなげきながらも耐え忍ぶばかりだ。そんなことはいいとしても、牧野や佐藤が本書中や宣伝用リーフレットで繰り返し表明しているように、資料の私蔵はやめ、リプリントしてはパブリックなものとして共有し、新しくやってくるだろう次なる研究者たちに供するという目論見は、はたしてどれだけ進んでいるのだろう。残念ながら私の目には、はなはだ心もとなく映ってならない。
また各地に点在する大学や図書館や資料館のネットワークはどうか。研究者ならば常日頃気になるところで、「ガクノススメ」でもフィルムセンター、早大演博、日大芸術学部図書館はじめ阪急池田文庫、調布市立図書館など、当店でもお付きあいのある機関に出かけていっては現状をレポートしているが、館同士の情報の交換交流はどこまで進んでいるのか。館ごとの電脳面での進歩は格段に進んでいるとも聞くが、館同士の横のつながりの密度じたいはどうなのか。
そしてなにより気がかりなのが、牧野が目指した在野とアカデミズムとの架け橋である。とりわけ私も初期に参加させてもらっていた日本映像学会文献資料研究会の破綻を思うにつけ、悲観的な気持にならざるをえないが、研究者たちによる官民一体となっての大同団結は、本当に無理なのか、夢なのか?
しかし、それにしても、牧野守という人はなんて不運な人なんだろう。四十年にもわたり、想像を絶するようなパワーと信念で風を起こそうと駆けぬけてきたというのに、風は思うように吹いてはくれなかった。人間の感情を一つにまとめるというのは至難の技とはいっても、文字通り満身創痍の牧野の生あるうちに、せめて一条の光だけでも射すところを見せてやれないものか。そのためにも第二第三のマキノマモルが現れいでてこないものか。そしてその時にはわが業界にも、私のように儲け度外視で協力してあげる後継者が、現れいでてくれないものか。
著者の願いをくみ、連載を一回休んでまでしてブックレビューに挑んでみたが、結局この程度のことしか書けなかった。だが映画史研究の未来に志を抱く若者たちよ、本書の存在を知ったなら、是非とも読んでみるがいい。
------------------------------
中山信如氏の主な著書
『古本屋「シネブック」漫歩』(ワイズ出版)
『古本屋おやじ』 (ちくま文庫)
------------------------------
今回は、転載ご了承いただきました、中山信如氏と日本古書通信社様に感謝致します。 |
|
前のページへ
|
|
Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合
|

古本屋が『映画学の道しるべ』を読み解けば 2
稲垣書店 中山信如
日本古書通信 2012年1月号より転載
|
| しかし、それにしても、牧野守という人はなんて幸運な人なんだろう。もはやここまでくれば、幸運というより強運といったほうがいいかもしれない。その強運の典型がコロンビア大への整理搬出を一人で手伝い、「キネマ旬報」昭和戦前期復刻版の編集を一人でつとめ、本書の編集を四年かけ一人でこなした佐藤洋(よう)の存在だろう。牧野には申し訳ないが佐藤の存在なしにはこの本は出なかった、出せなかった。つまり本書は牧野守の著作であると同時に、若き研究者佐藤洋の身につけた知識と方法論を世に問うた発表の場でもあったのである。それを追体験する意味でも、私は本書を私がたどったと同じコースで読んでみることをおすすめしたい。
コースといっても別段ややこしくはない。ただ最初に、巻末の三段組十ページにわたる佐藤の解説「牧野守論」を読んでからスタートしてみるだけだ。こうして全体のあたりをつけたら、最初に戻って普通に「ガクノススメ」から始めよう。これは「キネ旬」に連載当時、一般誌としては異色のカタい内容として好評ならざるものだったが、今になって読み直してみると、佐藤の綿密な校訂のおかげもあって荒っぽかった牧野の文も影をひそめ、意外と読みやすく、自らの研究環境の記録を念頭に当時の学問状況や交流の様子をとどめんとしたタイムリーな話題も豊富で、おもしろい。
これで牧野の研究の概要を知ったら、次に研究者になる前の前史としての、記録映画やプロキノこと日本プロレタリア映画同盟などに関する論考へ。ほとんどがドキュメンタリー作家としての出自から記録映画関係の業界紙誌に書いた論考ゆえ、私を含めた一般の映画ファンには読みにくいしなじみにくい。でもこれこそ著者牧野がいちばん書き残しておきたかった要諦である以上、削るわけにはいかないのだ。だから我慢して読みおえれば、あとは実作者を卒業し蒐集家書誌学者となって以降の文献資料考をはさんで、再びラストの佐藤の牧野論「このさびしさを、きみはほほ笑む」に戻る。この解説は、いい。改めて読み返してみれば、五十年に及ぶ牧野の過去と業績がストンと腑に落ちる。
そのためにも同じ佐藤がコレクション整理最中の五年前、牧野に聞き出し早大映画学研究会発行の「映画学」20号に載せた、「長い回り道・牧野守に聞く」だけは収録してもらいたかった。これは発行当時から牧野という人物と研究内容がよくわかって感心させられたものだが、分量的な制約上古くてアクセスしにくいものだけにしぼらざるをえないとのコンセプトのため、残念ながら見送られてしまったが、是非とも一読をすすめたい。ついでにもう一つないものねだりをすれば、『日本映画文献書誌』明治大正期の続編、すでにカードはできているという昭和戦前期を、雄松堂にもうひとふんばりして出してもらいたい。
いずれにせよ牧野にとって五十以上も歳の離れた佐藤という協同者に出会えたことは、強運というほかない。また佐藤にとってもこれからの長い研究者人生において、得がたい経験になるだろうことは間違いない。 |
|
前のページへ | 次のページへ
|
|
Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合
|

古本屋が『映画学の道しるべ』を読み解けば 1
稲垣書店 中山信如
日本古書通信 2012年1月号より転載
|
| しかし、それにしても、牧野守という人はなんて幸運な人なんだろう。数年前『日本映画検閲史』『日本映画文献書誌 明治・大正期』とたてつづけに出せただけでも充分めぐまれているというのに、またこんどの『映画学の道しるべ』である。いくら本人の類いまれなエネルギーとバイタリティーのたまものとはいえ、この出版不況のさなか、間違いなく映画文献史上に残るとはいえ、こんな売れそうにもない本を次から次と出してもらえるなんて。しかもこれまでのようなメインの研究テーマや書誌ではなく、周辺について書いた過去の文章までかき集めて本にしてもらえるなんて。おかげで前半に収録された「キネマ旬報」連載の「ガクノススメ」ひとつとってみても、日々東奔西走するフットワークのよさを通して、牧野守という蒐集家にして研究者の輪郭がくっきりと浮かびあがってくるではないか。
しかし、それにしても、牧野守という人はなんて幸運な人なんだろう。「キネマ旬報」大正期復刻版を出した雄松堂から、引きつづき『日本映画文献書誌』を出してもらえ、今刊行中の「キネマ旬報」昭和戦前期復刻版の版元文生書院から、併せてこんどの『映画学の道しるべ』まで出してもらえるなんて。いずれの版元もわが古書業界の人。いくら牧野が業界にとって文献資料を買いまくってくれたありがたい客だったからといって、矢継ぎばやに出す復刻版はオリジナルの市場価格を下げる原因ともなり、牧野の活動に功罪があるとすれば、古本屋にとって正直罪のほうが大きいかもしれぬ。
それでも牧野の強烈な蒐集意欲の磁力に巻き込まれ、手助けしてやろうと現れる古本屋は引きも切らず。が、苦労したであろう購入のための資金ぐりのことではソゴをきたさぬこともなく、古くからの業者は一人また一人と去り、ふと気づけば今は私一人。その私とて途中破局の危機がなくはなかったが、あのパッションと憎めない人柄に根負けし、ついつい損覚悟で協力してしまう。
しかし、それにしても、牧野守という人はなんて幸運な人なんだろう。みずから私設映画図書館と称して開放した自宅書庫に次々と通い来る海外の映画研究者たちが育ち、母国に戻って実績を積み、行く着くところ膨大な文献資料は〈マキノコレクション〉として海の向こう、米コロンビア大学東アジア図書館に納まってしまうとは。いくらわが国では珍しいグローバルでオープンな発想のもと、内外の研究者に研究基盤を提供しつづけたたまものとはいえ、アーロン・ジェロー、阿部・マーク・ノーネス、ジェフリー・ディムなどなど、当店にやってきた外来の研究者のほとんどは牧野私設図書館経由であり、ほかに外国の研究者はいないのかと思ってしまうほどだ。
有名な、外出せず仕事に没頭しやすいよう誰彼なく無償でふるまいつづけたSOMEN(外人にソーメン!)のお礼としては、報われすぎとは言えないか。私はソーメンのご相伴にはあずかれなかったが、一度泡盛のつまみに今どき珍しいミリンボシを出されて驚いたことがある。でも今にして思えばソーメンといいミリンボシといい、それこそマキノマモル流の飾らぬ精一杯の歓待法だったのだろう。 |
|
次のページへ
|
|
Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合
|

「長い絆で培われて刊行された書物『映画学の道しるべ』」
牧野 守
|
| 本年の「日本古書通信」一月号に掲載された稲垣書店の中山信如さんの書評「古本屋が『映画学の道しるべ』を読み解けば」を新春にふさわしい読物として拝読した。
中山さんのウィットに富んだタッチの軽妙さは定評がある文章力でわたしも常に愛読するところであったが、今回の題材はそうはいかない、実はわたしの書いた本を題材とした書評であったからである。
中山さんは自らも認め、都心で一番客のこない古書店の店主として知られている、古本にも客にもユニークな一家言の持ち主であるが、彼の専門分野である映画書の著書も複数出版されていて、わたしもその愛読者の一人として注目してきた。それだけに果してどんな書評を俎板に載せて料理したか興味しんしんであった。多分一筋なわではおさまらない油断もすきもないといったことになるのであろうといったハイテンションの緊張感に襲われながら見開き二頁にわたる記事を一気に読みあげた。
中山流のレトリックは今でも健在で記述した文章中には微苦笑させられ、時には大笑いもさせられたりしたが、単なる映画書解説というより今日の社会時評の鋭い警醒を発する文明評論であることに感服した。
ところで、中山評の冒頭は「しかし、それにしても、牧野守という人はなんて幸運な人なんだろう」に始まり、そのフレーズは文中に繰返して記述されている。いかにも中山さんらしい表現であって、彼の表現通りに受け取ると逆転の発想の展開となって、最後には彼一流の辛口の分析による評価が書かれ、結末では「しかし、それにしても、牧野守という人はなんて不運な人なんだろう」としめくっているのだが、それに到達する思考過程での問題提起には中山式経営から映画書籍の流通問題と映画ジャーナリズム、映画論壇そして映画美学の教育分野が直面する潮流を見すえた発言という警抜な内容となっている。 まさに、短いけれどこの書評に今日の日本の文化現象のすべてが要約されていて、筆者の出る幕はない。しかしながら筆者に紙面を提供して頂いた折角の機会に、当事者なりの数々のハードルを乗り越えて刊行に至る経過と長きに渡る様々の関係者の努力の一端を補足しておきたい。
まず、この出版の企画段階の仕掛人として登場するのが文生書院の小沼良成社長がキーマンとして果した役割である。小沼さんとの絆が培われたのは今から五年前の二〇〇七年の頃からで文生書院創業八〇周年記念出版の企画として「キネマ旬報」復刻版(昭和戦前期)の企画が開始されたことにもとづいている。実はわたしもこの「キネマ旬報」復刻版に一貫して従事してきて、雄松堂からゆまに書房と出版社を経緯して実現してきた。この文生書院バージョンの昭和戦前期は空白期として刊行が見送られてきたのである。
当然なことなのだがそれなりの理由があっての困難な問題が解決できなかったのだが、その一つに原本の完全版の獲得という難題があった。実はそれも解決してくれたのが、今回の書評でユニークな発言をしている稲垣書店の中山さんであった。彼が復刻版の空白期を埋めるための原本を長年にわたって蒐集していてしかも復刻にたえる原本のハイクオリティーを保障する「キネ旬」を揃えていたのであった。それに着目した小沼良成社長が、名のりを上げることで懸案の復刻版が刊行スタートすることになり、わたしもその企画監修の立場で参加することでこの企画の準備体制が出来上がったのである。そして今日に至るまでほぼ三年間にわたり、この復刻版の刊行は進行途上にあるのだが、この経過のなかでキネ旬連載のわたしのコラムやマイナー媒体に発表した映画史関連の記述も復元する当書の刊行企画も検討されてきた。
そのための重要な役割を果たすことになったキーマンの一人として、若き研究者の佐藤洋さんが浮上することとなった。重要な役割を担った佐藤さんについては中山さんも書評文中にもふれている様に彼の構成、編集の原典主義の実務に徹した作業がなければこの書物の刊行は実現しなかった。長期にわたる手弁当のむくわれない繁雑な調査そして執筆作業に打ち込んで刊行の実現にこぎつけることが出来たのである。この手間の掛かるライブラリー調査と若いジェネレーションの視点からの作業の前提として佐藤洋とわたしとの関係があり、その信頼感の絆が続いていたことで、わたしの一つの転機を迎えることになった。
長年にわたって収集してきた映画文献を、わたしも映画研究のテーマにする実証的記述と、書誌的な調査による研究の手がかりとして内外の研究者に提供してきたので、私の資料はマキノコレクションとして知られてきたが、そのマキノコレクションを保存することがアメリカニューヨーク市の名門であるコロンビア大学図書館の関係者によって合意に達した。そのコレクションの搬出という長期にわたる困難な作業に従事することで佐藤洋映画研究の方法論も力をつける結果となった。当書の『映画学の道しるべ』の解説で佐藤洋も記述しているが、コレクションが資料として一人立ちする前提として、このコレクションの設立の意図を明らかにしているのが本書である。
この様にして、当書の刊行の目標としてコロンビア大がプロジェクト企画したイベント・昨年十一月十一日に催されたパネルディスカッション「マキノコレクションの現在と未来」を設定。内外の映画研究者を含めて日本からも数名がパネリストとしてスピーチすることが出来た。わたしとの交流も深い旧知のアメリカ研究者も多数参加してこのイベントが充実したことが報じられていた。そのデータの詳しい内容は、まだわたしのもとには届いていないが、東南アジア地域の映画研究の一ステップとして今後の礎となることに期待している。当書『映画学の道しるべ』もこのイベントに滑り込みセーフで間に合わせることが出来た。これが不運なわたしから中山さんへの解答である。
プロフィール
牧野 守
映画史・映画文献資料研究者。1930年樺太生まれ。
テレビ・映画ディレクターのかたわら映画史を研究。集約した内外の映画資料はマキノコレクションとして知られ、2007年にコロンビア大学図書館に収蔵された。『キネマ旬報』等の基本文献を復刻しながら、映画運動・理論・制度史を研究。『日本映画検閲史』(パンドラ、2003)等の著書を発刊している。 |
|
Copyright (c) 2012 東京都古書籍商業協同組合
|
Just another WordPress site