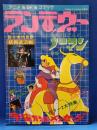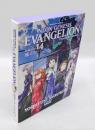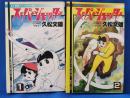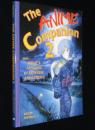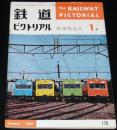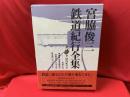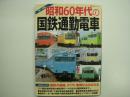リクエストを送る
新世紀エヴァンゲリオン30年 - SF・ロボットアニメを中心に

SF コミックス リュウ 別冊アニメージュ 1~7
¥3,000

カルト怪獣コレクション
¥2,000
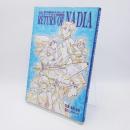
ふしぎの海のナディアアニメーション原画集
¥7,680

エヴァンゲリヲン新劇場版 : Q 記録集
¥1,600

アニメック 14号 -昭和55年12月-
¥1,000

クイック・ジャパン Vol.12 ―特集
¥600

ペーパームーン SFアニメファンタジィ 完全保存版
¥1,150
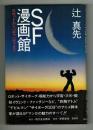
SF漫画館 ロボットからハチャハチャまで
¥4,950

ヱヴァンゲリヲン新劇場版
¥1,100

オタクの遺伝子
¥990

SFアニメ大全集 <別冊奇想天外>
¥2,500
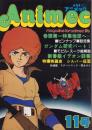
アニメック 11号 -昭和55年6月-
¥1,000

デジタル映像ワークショップ
¥3,440

SFアニメの科学 <知恵の森文庫>
¥2,000

フィギュア通信 vol.1
¥1,000

ヤング・アイドル・ナウ別冊号 アニメロボット大特集
¥1,120

カレンダー 新世紀エヴァンゲリオン 1998年
¥3,500
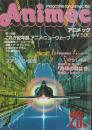
アニメック 23号 -昭和57年4月-
¥1,000

シン・ウルトラマン 空想特撮映画 デザインワークス
¥1,200

解析!昭和のTVアニメ特撮主題歌大百科
¥3,000

アニメ作画のきほん
¥2,200

大ロボット博
¥1,000
山手線環状運転開始100年 - 鉄道、都市交通

東京外圓鉄道工業株式会社 創立広告印刷物2点
¥132,000

通勤電車テクノロジー 電車の基本技術とその歩み
¥1,000
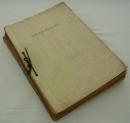
鉄道省電気局電化課ファイル「新幹線其他電化計画調書」
¥110,000
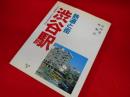
鉄道と街 渋谷駅 渋谷駅開業100周年記念
¥5,000

鉄道ピクトリアル 1989年12月号 No.520
¥1,200

東武鉄道中吊りポスター一括
¥30,800

絵葉書でつづる中央線今昔ものがたり
¥2,625
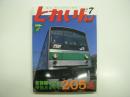
とれいん 2008年7月号 No.403
¥3,000
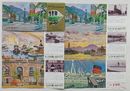
神戸市営地下鉄山手線開通 地下鉄バス記念乗車券
¥5,350

中央線写真帖
¥50,000

日本鉄道旅行歴史地図帳 5号
¥490

【絵葉書】(東京市の交通機関)山手線電車(駒込附近)
¥15,000
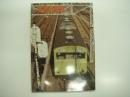
東京の国電
¥5,500

東京新誌
¥900

鉄道模型趣味
¥66,000

明治の私鉄と産業発展 日本鉄道+甲武鉄道+総武鉄道
¥2,750

山手線ウグイス色の電車今昔50年
¥1,000
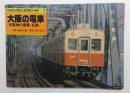
大阪の電車―京阪神の国電・私鉄(ヤマケイのレイルシリーズ〈7〉)
¥10,000

はとバス 東京観光地図
¥2,700

キャンブックス
¥11,000
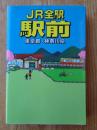
JR全駅駅前 東京都・神奈川県
¥800

探検鉄道 4 首都圏II(私鉄)
¥3,000
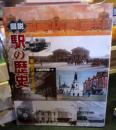
図説駅の歴史
¥1,000

交通博物館資料チラシ 6枚
¥1,200

写真集 山手線
¥6,200

東京新誌
¥1,320
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.