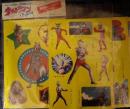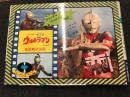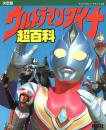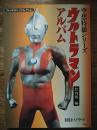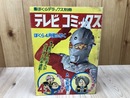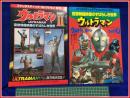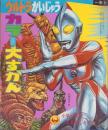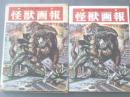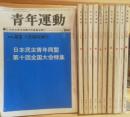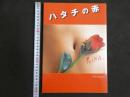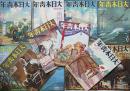リクエストを送る
ウルトラQ60年 - 特撮、SFドラマの魅力

戦え! ウルトラマン
¥4,000
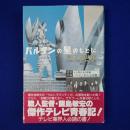
バルタンの星のもとに
¥7,700
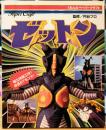
ウルトラシリーズ ゼットン(くもんのペーパークラフト)
¥5,000

ウルトラ怪獣大図解
¥3,000

ウルトラマン・ウルトラセブン
¥3,500

ウルトラマン大辞典 <ウルトラマン (テレビドラマ)>
¥3,000

特撮と怪獣
¥7,500

続ウルトラマン大百科 <ケイブンシャの大百科 39>
¥3,000

ウルトラマン80 ひかりのくにのテレビ絵本
¥3,500

ウルトラマンA(エース) 全2冊 Comic Mate
¥11,000

ウルトラセブン研究読本 <洋泉社MOOK 別冊映画秘宝>
¥3,000

ウルトラ怪獣えほん 全4冊揃 テレビ名作えほん
¥15,000
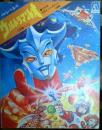
ウルトラマンレオ (レコード)
¥5,090

戦後ヒーローの肖像
¥3,000

ウルトラQ全
¥4,600
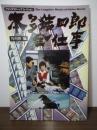
本多猪四郎全仕事 <ファンタスティックコレクション>
¥4,000

新資料解読 ウルトラセブン撮影日誌
¥5,500

ウルトラQ伝説
¥5,800

テレビマガジン平成元年8月号増刊 ウルトラマン大特集号
¥4,400

ウルトラマンR/B超全集 【てれびくんデラックス愛蔵版】
¥5,500
成人式 - 大人への第一歩、新たなる人生

年中行事を「科学」する
¥1,100
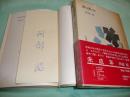
未成年
¥6,600

『通信青年』 <2巻7号~3巻7号揃13冊>
¥22,000
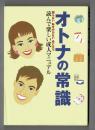
オトナの常識
¥1,500

青年カード 第1部揃(1~36集+付録2部) 紐綴合本
¥10,000

青年の心理と生活
¥390

新 ヘアと帯結び’09 成人式 十三参り 七五三
¥3,000

オリジナルプリント六切(未トレミング)付 戦後の若者たち
¥100,000

青年団の新紀元
¥8,800

青年期の心に迫る
¥400

詩集・二十歳
¥880

二十歳の原点 <新潮文庫> 改版
¥500

成人の日を祝って 明日をつくる
¥3,000

青年の環 5冊揃 1-5 <岩波文庫> 初版1刷
¥10,000

若者よ、マルクスを読もう
¥390
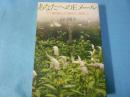
あなたへのEメール
¥1,000

青年唱歌集:新調韻文 第1編・第2編
¥165,000
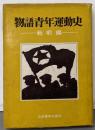
物語青年運動史〈戦前編〉
¥390
青年と台湾 [報恩感謝・勤労奉仕・国語尊重・資源愛護・心身鍛練]
¥22,000
成年後見事件の審理 ドイツの成年後見事件手続からの示唆
¥5,500
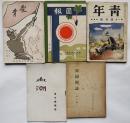
青年団・報国団誌 大正12年〜昭和14年 5冊
¥7,630

二十歳のころ 立花ゼミ『調べて書く』共同製作
¥2,500
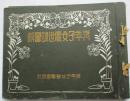
青年子女處世訓圖解
¥10,000
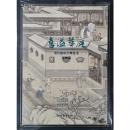
喜溢華庭:清代宮中少年生活文物展
¥20,900
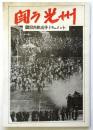
闘う光州-韓国民衆闘争ドキュメント
¥22,000

実践成年後見 (19)
¥5,161

ドキュメント 未成年 遠原美喜男写真集
¥19,600

新青年傑作選(全5巻揃)
¥8,000
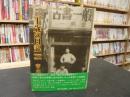
「二十歳の日記」 昭和28年/東京下町
¥700

彷書月刊 1992年01月号 特集:はたちの頃に読んだ本
¥1,200

二十歳(はたち)の君へ
¥2,200
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.