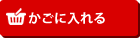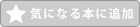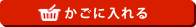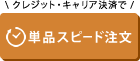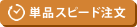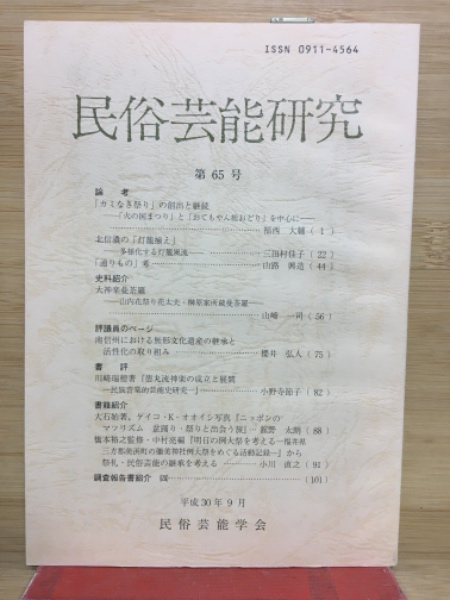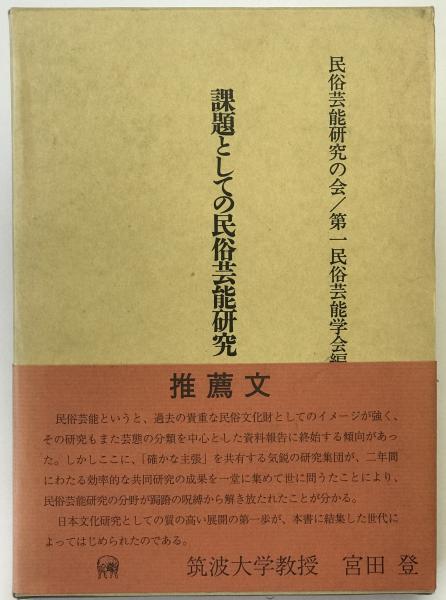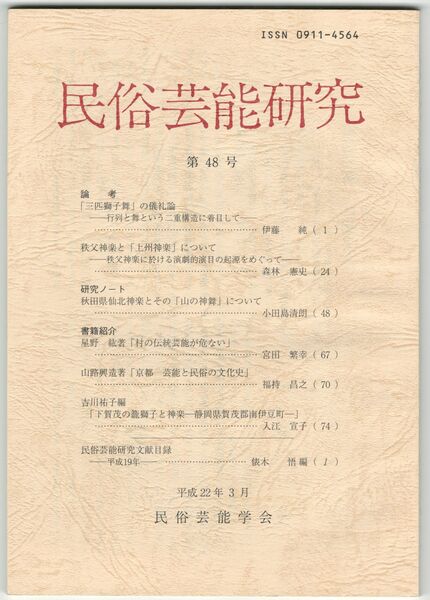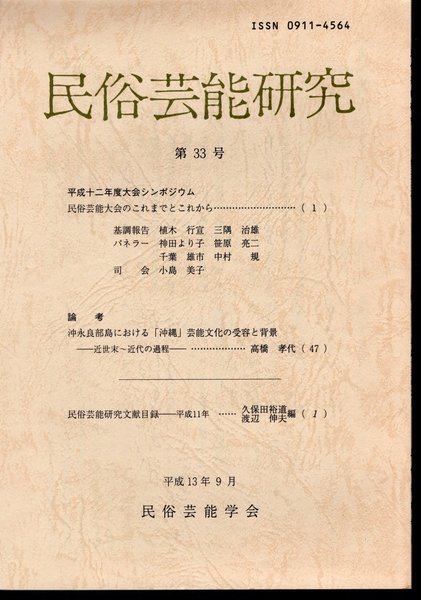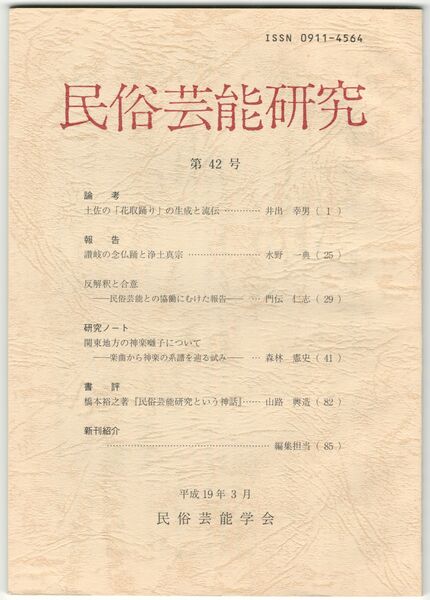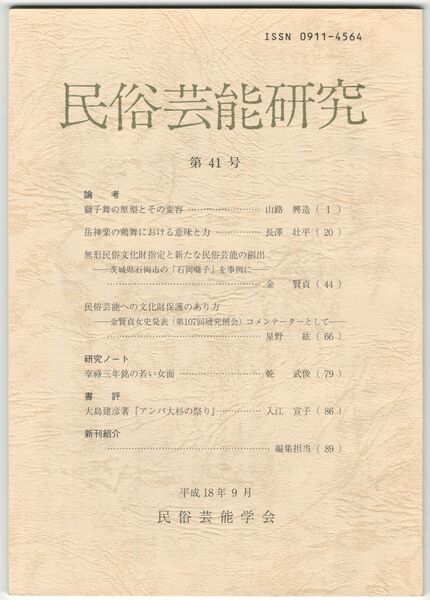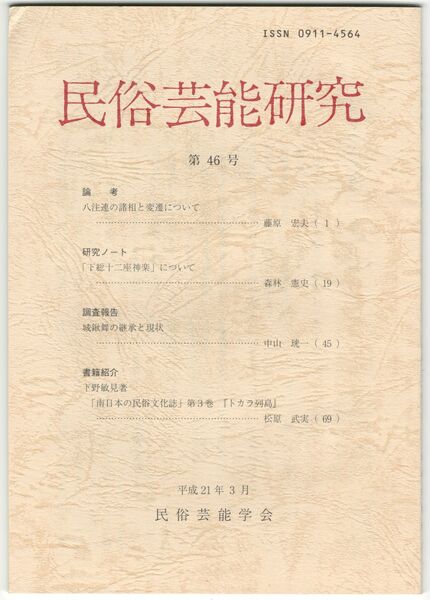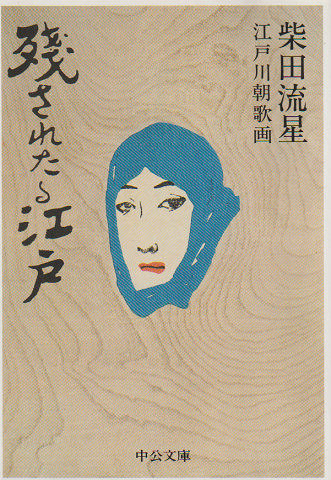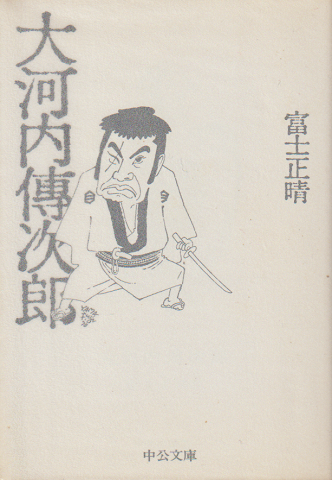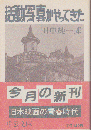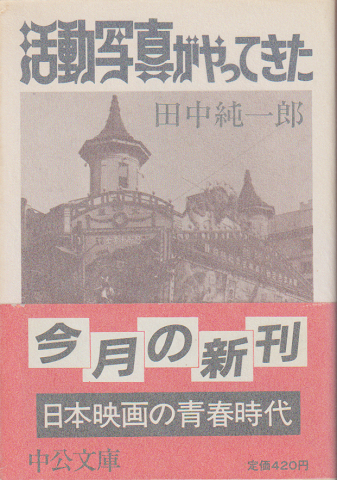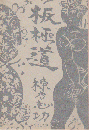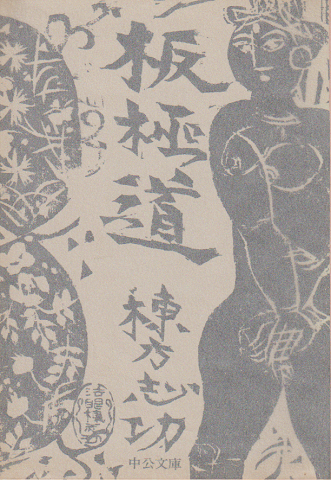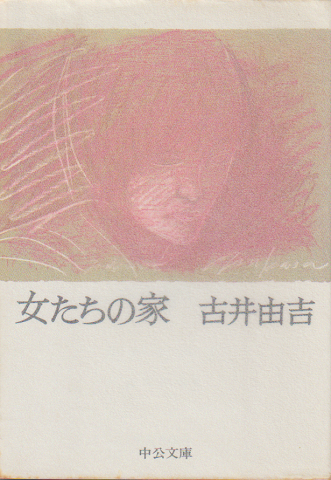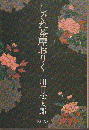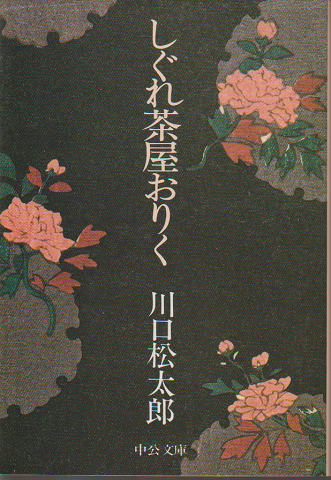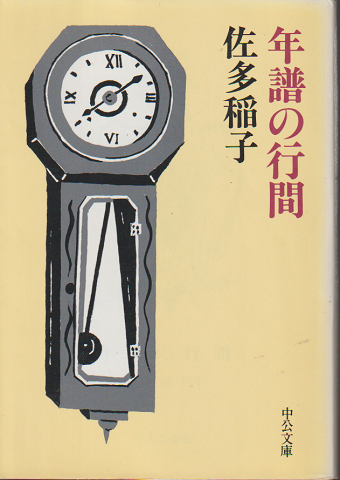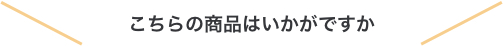
キーワード「折口信夫の世界」の検索結果
岡山県倉敷市昭和
東京都新宿区西早稲田
北海道札幌市清田区
東京都青梅市成木8-33-
沖縄県宜野湾市真栄原
沖縄県宜野湾市真栄原
愛知県岡崎市日名本町
東京都八王子市東町
東京都世田谷区赤堤
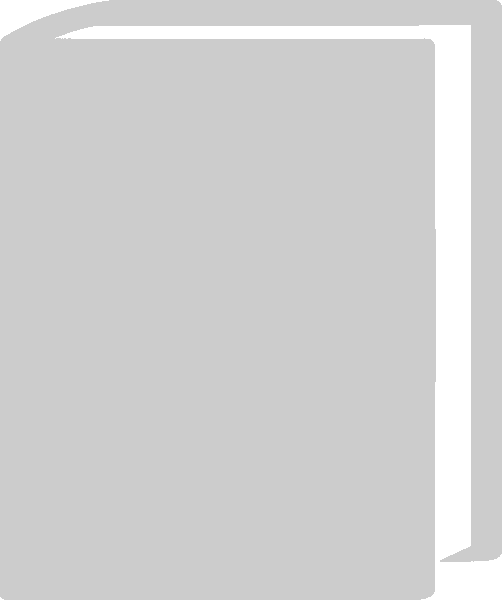
試行 第55号、1980年11月(小浜逸郎「文学の挫折(一)」、高島敏夫「中島敦小論」、盛 忍「『それから』論(一)」、村瀬学「離反・心的離反」、梶木剛「折口信夫の世界Ⅹ」、浮海 啓「箱船 他四篇」、篠原博輝「宇野経済学批判(四)」ほか)
沖縄県宜野湾市真栄原
東京都世田谷区赤堤
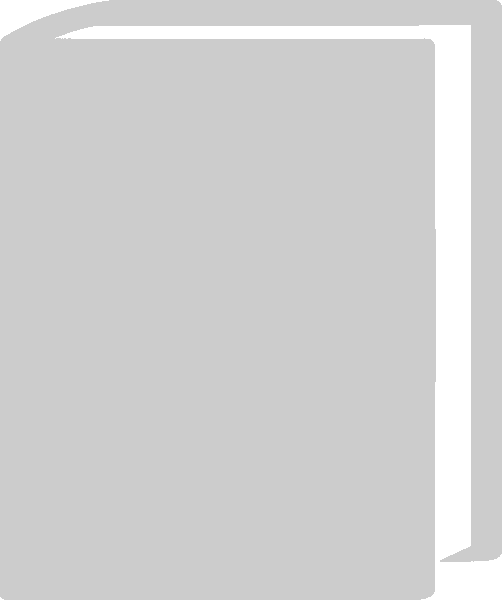
試行 第58号、1982年3月(横田雅明「ニーチェの解体(一)」、北岡輝紀「支配とは何か(一)」、上村武男「西田幾多郎における<実在と認識>(二)」、梶木剛「折口信夫の世界ⅩⅢ」、外山泰「ホッブスの政治理論と近代の政治的解放」ほか)
東京都世田谷区赤堤
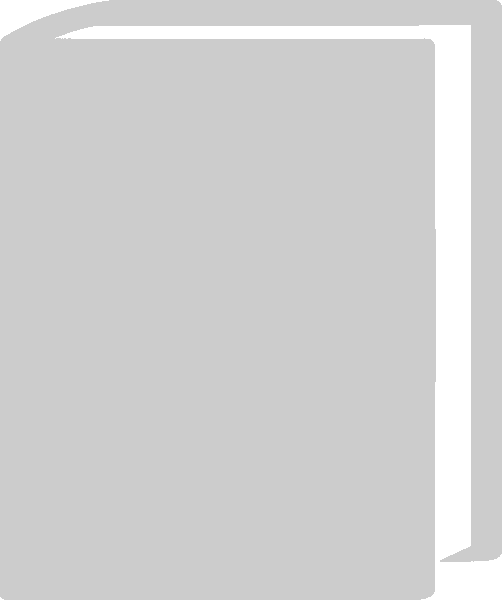
試行 第57号、1981年10月(小浜逸郎「文学の挫折(三)」、盛 忍「『それから』論(三)」、上村武男「西田幾多郎における<実在と認識>(一)」、梶木剛「折口信夫の世界Ⅻ」、滝村隆一「唯物史観と階級闘争の理論」、東 是人「唯物弁証法の基本構造(四)」ほか)
東京都世田谷区赤堤
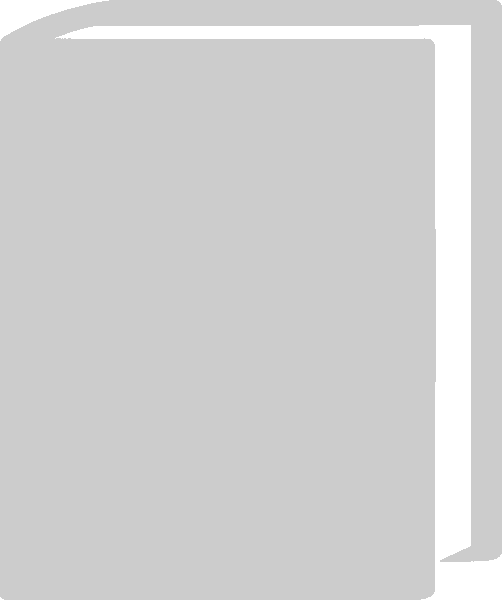
試行 第52号、1979年6月(小浜逸郎「太宰治の場所(一)」、野々垣利明「明治の<痼疾>Ⅴ」、芹沢俊介「芥川龍之介の宿命(十)」、梶木剛「折口信夫の世界Ⅶ」、滝村隆一「モンテスキュー小論」、宮下真二「イェスペルセンの文法論(四)」ほか)
東京都世田谷区赤堤
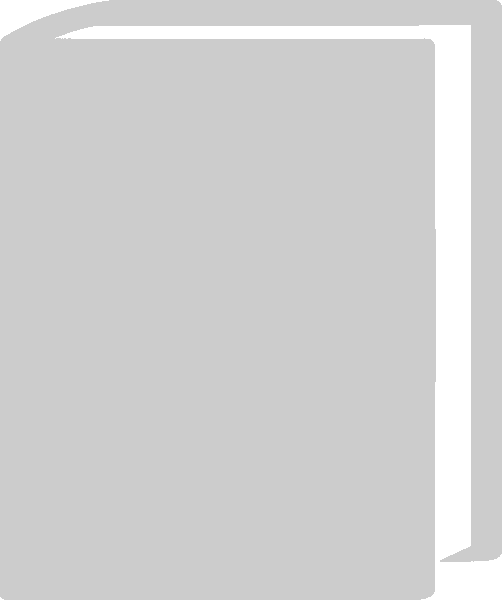
試行 第56号、1981年4月(小浜逸郎「文学の挫折(二)」、木嶋孝法「宮沢賢治と<悟り>」、盛 忍「『それから』論(二)」、梶木剛「折口信夫の世界Ⅺ」、永瀬清子「短章集抄(十九)」、滝村隆一「唯物史観と国家論の方法」、篠原博輝「宇野経済学批判(五)」ほか)
東京都世田谷区赤堤
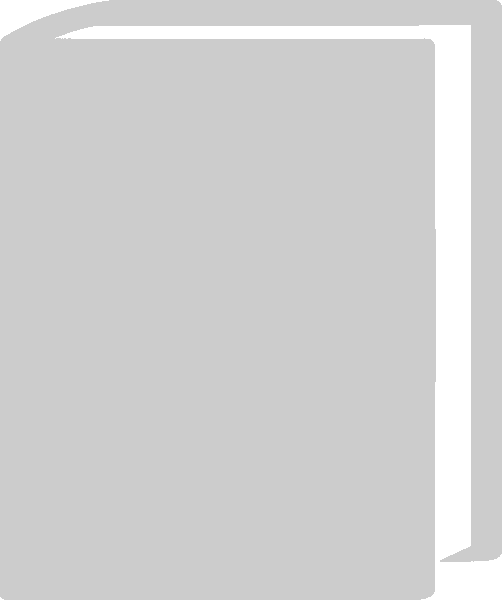
試行 第46号、1976年9月(梶木剛「折口信夫の世界Ⅰ」、芹沢俊介「芥川龍之介の宿命(五)」、野々垣利明「明治の<痼疾>Ⅰ」、三浦つとむ「言語・記号・象徴(上)」、高橋一郎「新興宗教成立の根源」ほか)
東京都世田谷区赤堤
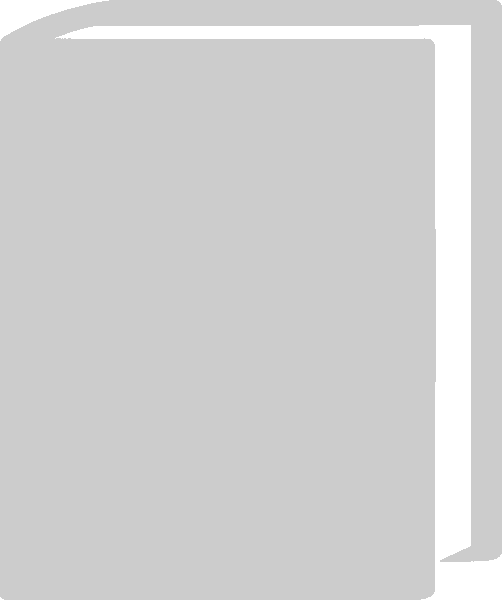
試行 第53号、1979年12月(小浜逸郎「太宰治の場所(二)」、末次弘「『行人』論(二)」、野々垣利明「明治の<痼疾>Ⅵ」、芹沢俊介「芥川龍之介の宿命(十一)」、梶木剛「折口信夫の世界Ⅷ」、滝村隆一「統治形態とは何か?」、篠原博輝「宇野経済学批判(二)」、宮下真二「イェスペルセンの文法論(五)」、今井昭夫「<アジア的>・考」ほか)
東京都世田谷区赤堤
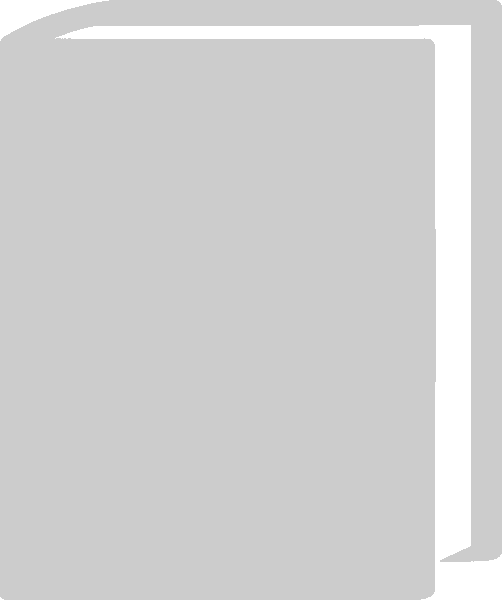
試行 第48号、1977年7月(梶木剛「折口信夫の世界Ⅲ」、芹沢俊介「芥川龍之介の宿命(七)」、三浦つとむ「珍珍妙妙『甘え』の構造」、池上達也「経済学と外部(二)」、宮下真二「哲学者の命題論」、高橋一郎「新興宗教成立の根源Ⅱ」ほか)
東京都世田谷区赤堤
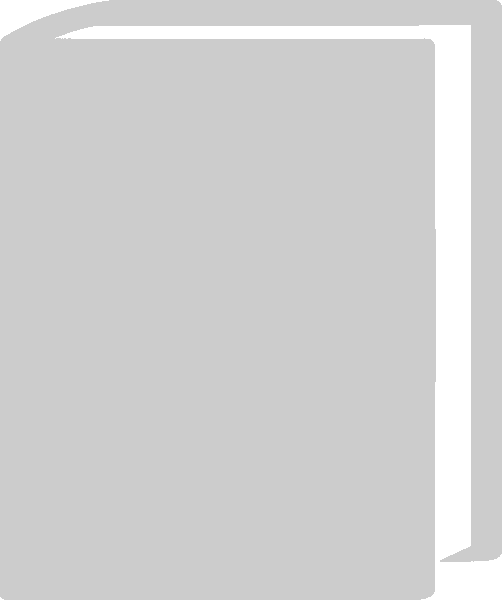
試行 第47号、1977年2月(梶木剛「折口信夫の世界Ⅱ」、芹沢俊介「芥川龍之介の宿命(六)」、野々垣利明「明治の<痼疾>Ⅱ」、高橋徹「『帰去来』とはなにかⅢ」、三浦つとむ「言語・記号・象徴(下)」、池上達也「経済学と外部」ほか)
東京都世田谷区赤堤
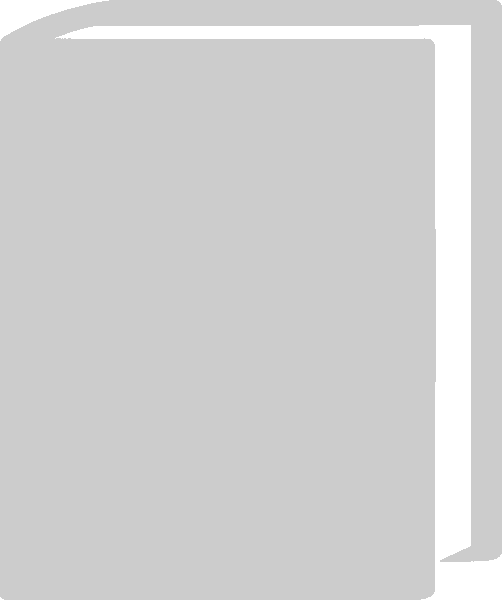
試行 第51号、1979年1月(木嶋孝法「『銀河鉄道の夜』論」、齋藤裕「赤人歌の「清」と「吉野」」、野々垣利明「明治の<痼疾>Ⅳ」、芹沢俊介「芥川龍之介の宿命(九)」、梶木剛「折口信夫の世界Ⅵ」、滝村隆一「<三権分立>とは何か?」、清水市郎「マルクス『エピクロス研究』覚書Ⅲ」ほか)
東京都世田谷区赤堤
き筋・裏表紙上部縁に僅かに汚れシミ、背表紙:少ヤケ・少汚れ・上部と下部に僅かな傷み(糊補修)、天:ヤケ・埃汚れやや強、小口:ヤケ・汚れやや強、地:ヤケやや強・少汚れ、線引き・書込みなどなく、本文、紙質・印字とともに状態良好
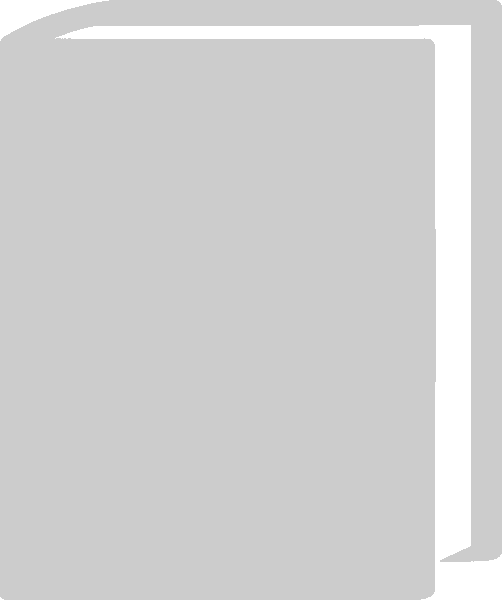
試行 第50号、1978年6月(丹羽一彦「M・ブーバー論」、齋藤裕「萬葉羇旅歌考(2)」、高橋徹「『帰去来』とはなにかⅥ」、芹沢俊介「芥川龍之介の宿命(八)」、梶木剛「折口信夫の世界Ⅴ」、滝村隆一「国家的支配の形式と過程」、清水市郎「萬葉羇旅歌うクス『エピクロス研究』覚書Ⅱ」、宮下真二「イェスペルセンの文法論(二)」ほか)
東京都八王子市明神町
宮城県仙台市青葉区本町
福岡県福岡市城南区別府
歳の夜の来訪神/越年・迎春の芸能/春日若宮おん祭をめぐって ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ、表紙にハガシ跡
福岡県福岡市城南区別府
こもりの古代誌―芸能発生の起点/神楽における籠る演出/沖縄における籠りの儀礼と芸能 ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
今様時代の「芸謡」性について―『梁塵秘抄』を中心に/近世歌謡・民謡と邦楽の谷間 ほか
経年ヤケ・シミ・ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
宮廷歌謡成立の機会/平成大礼の意義―儀礼文化学の立場から―/大嘗祭の構造新論 ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
講談がつくった忠臣蔵/忠臣蔵 その虚と実/仇討ちのドラマトゥルギー―浪花節の忠臣蔵をめぐって― ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
柳田國男と芸能/折口信夫/小寺融吉の舞踏研究 ほか
経年ヤケ・シミ・ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
昭和十年代の女剣劇/根を下ろした女性講談/女流義太夫の百年 ほか
ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
熊野灘沿岸に残る魚釣り儀礼/御座船の芸能誌―東京湾口の竜島における― ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
「鷹の井戸」の追跡/『重衝』の復曲/日本の能から世界の能へ ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
錯誤による成熟―世阿弥から寿天まで―/山伏神楽をめぐる地域―早池峰大償を中心として―/笑いの解釈―熱田神宮酔笑人神事を事例として ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
著者名「芸能学会編」の検索結果
東京都千代田区神田神保町
北海道札幌市清田区
東京都国分寺市本町
東京都千代田区神田神保町
神奈川県川崎市麻生区早野
大阪府吹田市江坂町
沖縄県宜野湾市真栄原
長野県小諸市菱平
沖縄県宜野湾市真栄原
沖縄県宜野湾市真栄原
福岡県福岡市城南区別府
外観強めのヤケ・シミ・ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
東北修験系神楽の「蘇我」―番楽を中心に 高山茂/能の曽我物概観 羽田昶 ほか
外観強めのヤケ・シミ・ヨゴレ
大分県別府市弓ケ浜町
大分県別府市弓ケ浜町
大分県別府市弓ケ浜町
大分県別府市弓ケ浜町
大分県別府市弓ケ浜町
大分県別府市弓ケ浜町
大分県別府市弓ケ浜町
沖縄県宜野湾市真栄原
大分県別府市弓ケ浜町
大分県別府市弓ケ浜町
大分県別府市弓ケ浜町
沖縄県宜野湾市真栄原
沖縄県宜野湾市真栄原
大分県別府市弓ケ浜町
大分県別府市弓ケ浜町
沖縄県宜野湾市真栄原
沖縄県宜野湾市真栄原
芸能6月号 2-6 大正期の小芝居を語る 人形まわしの村・阿波 ほか
大分県別府市弓ケ浜町
芸能8月号 9-8 対談吉右衛門と寛美 トシドンの来訪 ほか
大分県別府市弓ケ浜町
芸能 再刊2号 金丸座見聞記 一つのケース「日本のサーカス」ほか
大分県別府市弓ケ浜町
芸能4月号 2-4 歌舞伎のアメリカ公演についての問題点 ほか
大分県別府市弓ケ浜町
愛知県岡崎市日名本町
芸能7月号 10-7 島万神社の風流 どんぺからつこ・ねっけど-最上の昔話- ほか
大分県別府市弓ケ浜町
沖縄県宜野湾市真栄原
沖縄県宜野湾市真栄原
沖縄県宜野湾市真栄原
沖縄県宜野湾市真栄原
大阪府高石市東羽衣
尾張一宮住吉踊と万作・全編(鈴木道子) / 近代の猿まわしの歴史的変遷と現代的展開-周防猿まわしを事例に(篠原晶子) / シンポジウム(平7年度沖縄大会)祭りから芸能へ-南東の島々に探る ほか
大阪府高石市東羽衣
大阪府高石市東羽衣
鳥海山蕨岡修験の祭りと芸能(神田より子) / 集合する芸能-遠野八幡宮祭礼を中心として(久保田裕道) / 資料 宮崎智恵彦記「豊前岩戸神楽 山内神楽講」 / 嘯吹八幡神社湯立三十三番神楽と豊前岩戸神楽についての若干の説明(茂木栄) / 南島民俗芸能研究の沿革(宜保栄治郎)
沖縄県宜野湾市真栄原
福岡県福岡市城南区別府
歳の夜の来訪神/越年・迎春の芸能/春日若宮おん祭をめぐって ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ、表紙にハガシ跡
福岡県福岡市城南区別府
こもりの古代誌―芸能発生の起点/神楽における籠る演出/沖縄における籠りの儀礼と芸能 ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
今様時代の「芸謡」性について―『梁塵秘抄』を中心に/近世歌謡・民謡と邦楽の谷間 ほか
経年ヤケ・シミ・ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
宮廷歌謡成立の機会/平成大礼の意義―儀礼文化学の立場から―/大嘗祭の構造新論 ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
昭和十年代の女剣劇/根を下ろした女性講談/女流義太夫の百年 ほか
ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
熊野灘沿岸に残る魚釣り儀礼/御座船の芸能誌―東京湾口の竜島における― ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
「鷹の井戸」の追跡/『重衝』の復曲/日本の能から世界の能へ ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
講談がつくった忠臣蔵/忠臣蔵 その虚と実/仇討ちのドラマトゥルギー―浪花節の忠臣蔵をめぐって― ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
柳田國男と芸能/折口信夫/小寺融吉の舞踏研究 ほか
経年ヤケ・シミ・ヨゴレ
福岡県福岡市城南区別府
錯誤による成熟―世阿弥から寿天まで―/山伏神楽をめぐる地域―早池峰大償を中心として―/笑いの解釈―熱田神宮酔笑人神事を事例として ほか
経年ヤケ・シミ・少ヨゴレ
書誌カタログから探す
「日本の古本屋」では、書籍ごとの基本情報を「書誌カタログ」にまとめております。書誌カタログからは欲しい本のリクエストが可能です。
お探しの本が「日本の古本屋」に追加された場合に自動通知をお送りさせていただきます。

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索
古書追分コロニーの新着書籍
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分