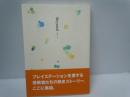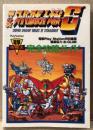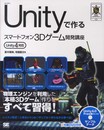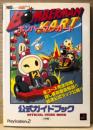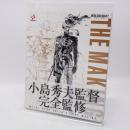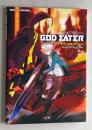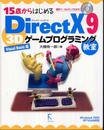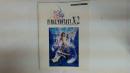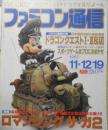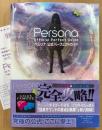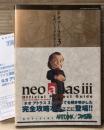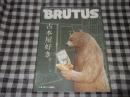プレイステーション海外発売30年- 3D、高性能、ゲーム機の進化

ファイナルファンタジーIX Vジャンプ緊急増刊
¥3,900
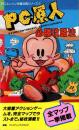
PC原人必勝攻略法
¥4,000

獣王記 アタックマニュアルブック セガメガドライブ
¥3,000

ファイナルファンタジーⅩ Vジャンプ緊急増刊
¥2,000

Resident Evil 4 (輸入版
¥6,101

ぱふ 1999年9月号(No.294)
¥500

魔界戦記ディスガイア ザ・コンプリートガイド
¥1,000

OpenGL+GLSLによる物理ベースCGアニメーション
¥1,000

サンライズ英雄譚Rキャラクターガイド
¥1,800
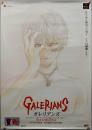
ポスター プレイステーション ガレリアンズ
¥3,500

PS4を100倍使いこなす本 (100%ムックシリーズ)
¥1,086

ゲーム戦線超異状 任天堂vsソニー
¥2,500

ストリートファイターZERO2 コマンドブック
¥3,000
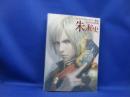
朱ノ秘史
¥2,000
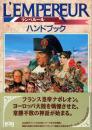
ランペルール ハンドブック
¥5,000
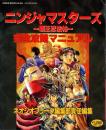
ニンジャマスターズ 覇王忍法帖 完全攻略マニュアル
¥8,000
読書の秋 - 秋の古本まつり全国で開催

世界の名著(中公バックス) 全81冊揃
¥44,000

古書のざわめき
¥500

世界童話大系 復刻版 全23巻
¥79,980

為永春水作 人情本コレクション 梅児誉美シリーズ全揃含む一括25冊
¥350,000
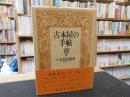
「古本屋の手帖」
¥500
世界の古書 ABAJ創立十周年紀念古書大即売展
¥8,500

一古書肆の思い出 1~5 全5冊揃
¥5,000

書苑 覆刻版 全10巻100冊揃
¥40,000

古本屋の蘊蓄
¥500

稿本神田古書籍商史三編(昭和54年~平成12年)
¥4,400

古本屋の蘊蓄
¥500

味道探求名著選集 全11巻揃い
¥51,000

夕ばえ作戦
¥3,160

古書街を歩く <福武文庫>
¥500

神田神保町書肆街考
¥3,500

古書店地図帖 東京・関東・甲信越
¥1,250

横尾忠則ポスター 神田古本まつり50周年記念
¥5,500

古典籍総合目録 揃三冊
¥19,800

「補訂版 国書総目録 全9揃」+「古典籍総合目録 全3揃」12冊
¥14,000

駈け出しネット古書店日記
¥390

新興古書会即売展畧畧目 (昭和15年度) 川瀬一馬旧蔵
¥4,000
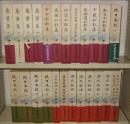
新日本古典文学大系 全106巻揃 全100+別巻5+総目録
¥63,000
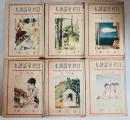
白秋童謠讀本 全6冊揃
¥50,000
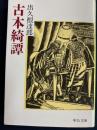
古本綺譚 <中公文庫>
¥400

妖怪博士 <初版>
¥12,000

河岸の古本屋 現代日本のエッセイ
¥500

紙魚之会 目録 6冊セット
¥4,000
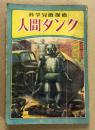
科学冒険探検 人間タンク
¥55,000
増補古活字版之研究 上中下 3冊揃
¥190,000
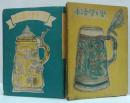
変り学読本
¥2,500
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.