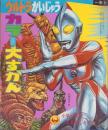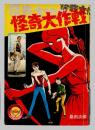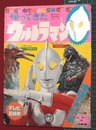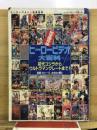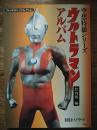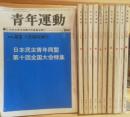ウルトラQ60年 - 特撮、SFドラマの魅力

帰ってきたウルトラマン 音できく怪獣シリーズ(1)
¥25,000

ウルトラ怪獣アートワークス1971-1980
¥3,000

ウルトラマン・クロニクル
¥9,000

ウルトラマンネクサス
¥5,000

戦え! ウルトラマン
¥4,000

ウルトラマン ファンタスティックコレクションNo.32
¥1,000
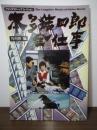
本多猪四郎全仕事 <ファンタスティックコレクション>
¥4,000

円谷一
¥4,000

ウルトラ兄弟物語/アクションコミックス版/全5巻揃
¥11,000

ウルトラQ 海底原人ラゴン 小5テレビコミックス
¥15,000

続ウルトラマン大百科 <ケイブンシャの大百科 39>
¥3,000

特撮と怪獣
¥7,500
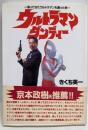
ウルトラマン・ダンディー
¥5,000

ウルトラマン大百科 <ケイブンシャの大百科 26>
¥3,000

(未開封トランプ)ウルトラマン -任天堂-
¥13,000

ウルトラセブン 宇宙超兵器写真集
¥4,500

怪獣怪人大全集4 ウルトラマン大百科
¥7,500

写真集 特技監督 円谷英二
¥6,000
成人式 - 大人への第一歩、新たなる人生

成年後見法研究 第16号
¥6,840

青年期の精神分析Ⅰ
¥300

年中行事を「科学」する
¥1,100
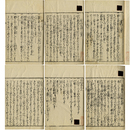
大諸礼集
¥132,000
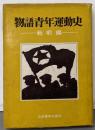
物語青年運動史〈戦前編〉
¥390

新時代の青年団
¥7,700

成人式・七五三 ヘアと帯結び 18
¥3,000
女子青年学習書 巻1~3(3冊)
¥6,600
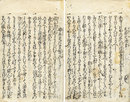
元服之次第
¥19,800

二十歳の詩集
¥600

自己成長の基礎知識2 身体・意識・行動・人間性の心理学
¥3,000
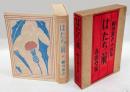
はたち前
¥55,000

未成年 創刊〜9号(終刊)
¥550,000

ビートルズも人間だった
¥400
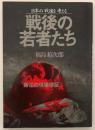
戦後の若者たち
¥11,000

ヒカリ 第2巻第2号(通巻第6号)昭和18年2月15日
¥240,000

『新青年』読本
¥7,800

青年期の心に迫る
¥400

新 ヘアと帯結び’09 成人式 十三参り 七五三
¥3,000

元服之次第
¥10,000
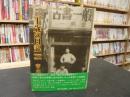
「二十歳の日記」 昭和28年/東京下町
¥700
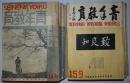
青年教育 第146~169号(昭和10~12年) 不揃20冊
¥22,000

青年の精神病理 全3巻揃
¥6,600
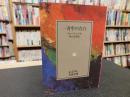
「一青年の告白」 <岩波文庫>
¥400
青年と台湾 [報恩感謝・勤労奉仕・国語尊重・資源愛護・心身鍛練]
¥22,000
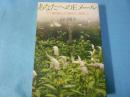
あなたへのEメール
¥1,000

新青年傑作選(全5巻揃)
¥8,000

青年バレエグループ 公演プログラム 4部
¥11,000

若者よ、マルクスを読もう
¥390
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.