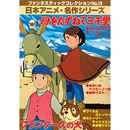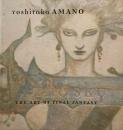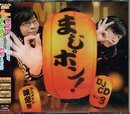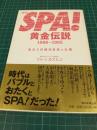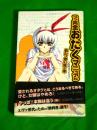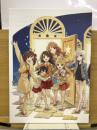人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に
青年君主昭和天皇と元老西園寺
¥3,300

昭和・戦争・失敗の本質 初版第1刷
¥2,200

昭和天皇発言記録集成 上・下2冊 第1刷
¥11,000
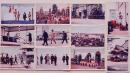
聖上陛下 絵はがき
¥11,000

天皇の戦争責任
¥2,200

昭和天皇
¥1,830

象徴天皇の現在
¥2,000
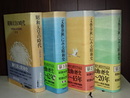
文藝春秋にみる昭和史 全3巻+別巻「昭和天皇の時代」
¥1,800

昭和天皇の戦い 昭和二十年一月~昭和二十六年四月
¥2,600

歴史問題ハンドブック <岩波現代全書 065> 第1刷
¥2,200

昭和天皇 上・下
¥3,000
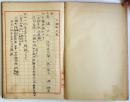
天皇皇族実録抄本(04の191)
¥4,800,000
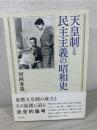
天皇制と民主主義の昭和史
¥2,200

昭和
¥1,980

昭和史探索
¥2,750

1945日本占領
¥1,980

昭和天皇ご家族大判古写真 4枚
¥33,000

昭和天皇の思い出
¥2,200

目撃者が語る昭和史 全8冊組 全8巻揃
¥4,273

昭和天皇実録評解 1・2
¥2,500
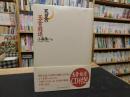
「天皇の玉音放送」
¥900

伊勢志摩に両陛下をお迎え志て
¥5,300
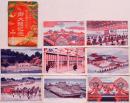
昭和三年十一月 今上天皇御即位式御大禮記念 絵はがき
¥11,000

天皇讃歌
¥15,000

天皇の研究
¥2,500

昭和天皇
¥8,800

陛下の\人間\宣言
¥3,280

高松宮日記 全8巻
¥11,550

「昭和天皇拝謁記」を読む
¥1,800
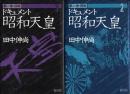
ドキュメント昭和天皇 全8冊
¥9,000

大元帥・昭和天皇 3 第7刷
¥3,300

侍従長の遺言
¥5,000

侍従長の回想
¥6,000
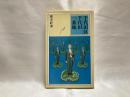
千代田区千代田一番地
¥1,000

いま甦る昭和天皇の肉声 復刻版 人間天皇
¥2,200
コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ
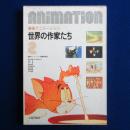
世界の作家たち <講座アニメーション 2>
¥19,800
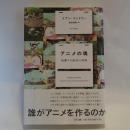
アニメの魂
¥1,200

SFアニメの科学 <知恵の森文庫>
¥2,000
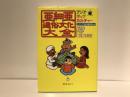
亜細亜通俗文化大全
¥1,000

現代日本のアニメ
¥2,500

アニメーション
¥3,500

東大オタク学講座
¥1,220
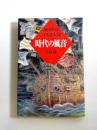
時代の風音
¥2,500

日本人の「男らしさ」
¥7,700

アニメーターになれる本
¥2,000
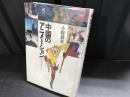
中国のアニメーション
¥9,000

ハルヒin USA
¥3,300

アニメが「ANIME」になるまで
¥3,500

コスプレする社会
¥2,924

アニメは越境する (日本映画は生きている 第6巻) 6
¥2,490

ポップ・カルチャー年鑑2007
¥1,500
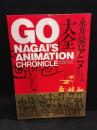
永井豪TVアニメ大全
¥9,900

コミックマーケット 30’sファイル 1975-2005
¥3,850

日本アニメーション映画史
¥4,450

手塚治虫全史
¥4,000

ポップ・カルチャー
¥1,000

日本SFアニメ創世記 虫プロ、そしてTBS漫画ルーム
¥3,850

村上春樹論 サブカルチャーと倫理
¥4,000
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.




![[絵葉書] 昭和参年十二月於横浜港外 御大禮特別大観艦式記念](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12010425/20240919133729599339_fbc6959f2345ba04cb04b650be173901.jpg)