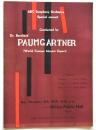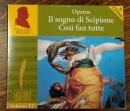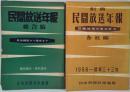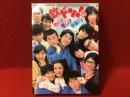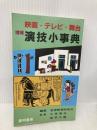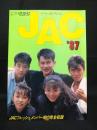モーツァルト生誕270年 - クラシック音楽を中心に
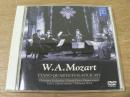
DVD モーツァルト:ピアノ四重奏曲第1番、第2番
¥4,500

鍵盤音楽の歴史
¥2,700

Mozart
¥3,400

モーツァルト全集 (9) 宗教音楽1 小学館 海老沢 敏
¥44,728

子どもの伝記物語 1~30巻
¥11,000

名作オペラブックス 既刊分全31冊揃
¥44,000
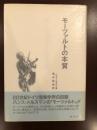
モーツァルトの本質
¥2,600
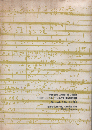
モーツァルトアイネ・クライネ・ナハトムジーク成立と分析
¥5,500

モーツァルト大全集 揃 CD 125枚+解説書
¥50,000

モーツァルト 人と作品
¥3,500

Mozart
¥4,000

新装復刊 モーツァルト その人間と作品
¥4,400

モーツァルト全作品事典
¥3,300
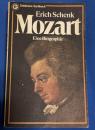
Mozart. Eine Biographie.
¥3,500
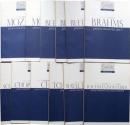
ピアノ協奏曲集 1~12
¥5,500
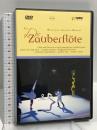
輸入盤 モーツァルト
¥3,620

音楽と我が人生
¥3,820

モーツァルトその音楽と生涯:全5巻/名曲のたのしみ、吉田秀和
¥15,800
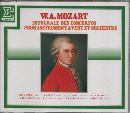
CD「モーツァルト 管楽器のための協奏曲全集」4枚組
¥4,400

標準版 モーツァルト作品集
¥3,238
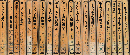
モーツァルト叢書<1~20巻(14巻は未刊)>19冊揃
¥22,000
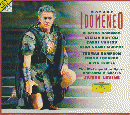
CD 『モーツァルト歌劇 クレータの王イドメネーオ』
¥3,300
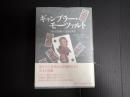
ギャンブラー・モーツァルト
¥2,500
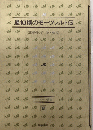
最初期のモーツァルト モーツァルト叢書18
¥3,000

シャーマニズムと想像力
¥3,300

モーツァルトピアノ独奏曲―楽曲構成と演奏解釈
¥3,279
のど自慢80年 - テレビ番組の思い出

東京放送連続テレビ映画 「チャコちゃん社長」 台本 9冊
¥16,500

ACC CM年鑑 '69 (1969)
¥6,600

テレビ演出入門
¥14,500
![[台本] 13点 ライオン奥様劇場 夫婦さかさま](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/10291842_6901e17d52bd1.jpg)
[台本] 13点 ライオン奥様劇場 夫婦さかさま
¥15,000

NHKテレビ放送台本 「あすをつげる鐘 永遠の背番号 沢村栄治」
¥33,000

連続テレビ小説ひまわり 全2集揃 NHKDVD DVD全14枚揃
¥16,500
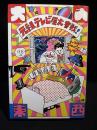
元祖テレビ屋大奮戦
¥9,800
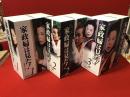
【DVD-BOX】家政婦は見た! 全5巻のうち、①~③3点一括
¥22,000

テレビジョン発達史
¥12,000
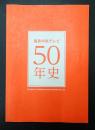
福島中央テレビ50年史
¥15,000

HTB豆本 1~62
¥33,000

TV台本東京物語 前・後編/カット割台本 セット図4枚付
¥100,000

元祖テレビ屋ゲバゲバ哲学
¥9,500
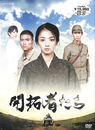
開拓者たち DVD4枚組 NHKDVD
¥11,000
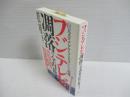
フジテレビ凋落の全内幕
¥9,800
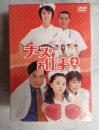
DVD‐BOX ナースのお仕事2 全4巻
¥75,000

ベルトクイズQ&Q―なんでもわかる本(ベストブックス)
¥9,900

いちにのさんすう・さんすうすいすい台本
¥50,000

『週刊NHK新聞』 <昭30~33年内159部>
¥132,000
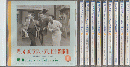
CD「思い出のラジオ・テレビ主題歌集」10枚セット
¥11,000

テレビアニメーション 放映リスト No.1.2 2冊
¥5,000
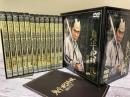
鬼平犯科帳 第2シリーズ DVD-BOX(全12枚)
¥9,000
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.




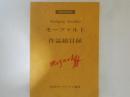


![[16点] フィルハーモニー : N.H.K. SYMPHONY ORCH...](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/26040270/20231018192839244444_4c1a2b1e09f2d930320f1c373f57bfce.jpg)