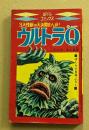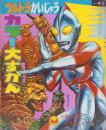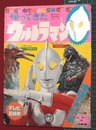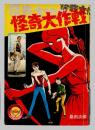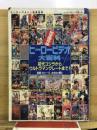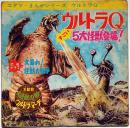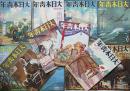ウルトラQ60年 - 特撮、SFドラマの魅力

ウルトラQ 海底原人ラゴン 小5テレビコミックス
¥15,000

ウルトラマン大辞典 <ウルトラマン (テレビドラマ)>
¥3,000

特撮と怪獣
¥7,500
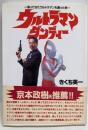
ウルトラマン・ダンディー
¥5,000

ウルトラマンA TAC超兵器写真集
¥4,000

ウルトラマン・クロニクル
¥9,000

円谷一
¥4,000

少年ブック 1966年7月号 「ウルトラQ」付録漫画付
¥70,000

ウルトラマン大百科 <ケイブンシャの大百科 26>
¥3,000

「館長庵野秀明 特撮博物館」展カタログ 2冊セット
¥3,960
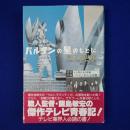
バルタンの星のもとに
¥7,700

ウルトラマンタロウ 石川賢とダイナミック・プロ 初版
¥4,980
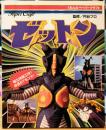
ウルトラシリーズ ゼットン(くもんのペーパークラフト)
¥5,000

怪獣絵ばなし 2 【「ウルトラセブンの歌」フォノシート付】
¥11,000

少年ブック 昭和41年5月号 付録漫画4冊付
¥50,000

講談社テレビコミックス ウルトラセブン 第2集
¥27,500

続・ウルトラマン大百科 ケイブンシャの大百科39
¥3,500
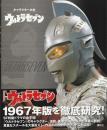
ウルトラセブン <キャラクター大全>
¥3,000
成人式 - 大人への第一歩、新たなる人生
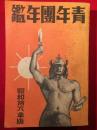
昭和十六年 青年団年鑑
¥11,000
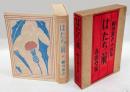
はたち前
¥55,000

'78 成人の日に若人の広場
¥3,000
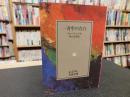
「一青年の告白」 <岩波文庫>
¥400

『通信青年』 <2巻7号~3巻7号揃13冊>
¥22,000

行動の機構
¥1,760

処女の友【復刻版】 全5巻・別冊1
¥93,500

青年期との対決
¥400

現代ドイツ成人教育方法論
¥3,800

新時代の青年団
¥7,700

二十歳の原点 <新潮文庫> 改版
¥500

青年の心理と生活
¥390

青年心理学 岩崎書店 赤塚 泰三
¥10,350

実践成年後見 (19)
¥5,161

青年団の新紀元
¥8,800
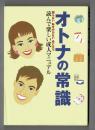
オトナの常識
¥1,500

青年部指導集 3 <創価学会青年思想シリーズ>
¥12,204
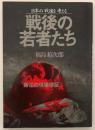
戦後の若者たち
¥11,000

ビートルズも人間だった
¥400

新青年傑作選(全5巻揃)
¥8,000

二十歳のころ 立花ゼミ『調べて書く』共同製作
¥2,500
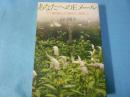
あなたへのEメール
¥1,000

若い世代と学問 1<青年双書>
¥390

成人式・七五三 ヘアと帯結び 18
¥3,000

青年カード 第1部揃(1~36集+付録2部) 紐綴合本
¥10,000
青年と台湾 [報恩感謝・勤労奉仕・国語尊重・資源愛護・心身鍛練]
¥22,000

青年カウンセリング
¥440

青年學校 家庭科敎科書 1〜3巻
¥10,000

愛知県成人式プログラム
¥3,000
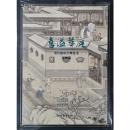
喜溢華庭:清代宮中少年生活文物展
¥20,900

京都美術青年会会誌 全21巻揃 復刻版
¥12,000

青年の環 5冊揃 1-5 <岩波文庫> 初版1刷
¥10,000

成人式と通過儀礼
¥2,800
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.