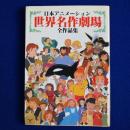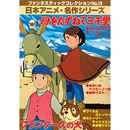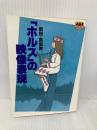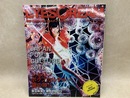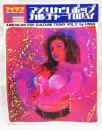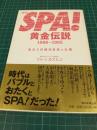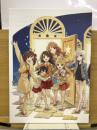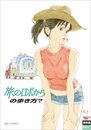人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に
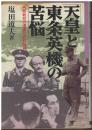
天皇と東条英機の苦悩
¥440

昭和天皇 第1部 (日露戦争と乃木希典の死) 第1刷
¥2,200

昭和天皇
¥8,800

天皇の真実 憲法一条と九条よ!地球を一つに繋げ!
¥1,800
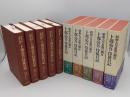
昭和天皇最後の側近 卜部亮吾侍従日記1~5 全5冊
¥5,000

戦後史の天皇・総解説
¥2,200

昭和天皇実録評解 1・2
¥2,500

昭和四年神戸行幸に関する警備警衛関係資料一括
¥253,000

大元帥・昭和天皇 3 第7刷
¥3,300

天皇の戦争責任
¥2,200

昭和天皇の歴史教科書国史
¥1,800

昭和天皇の戦争 <昭和天皇実録> 第1刷
¥2,980

象徴天皇の現在
¥2,000

目撃者が語る昭和史 第1巻
¥2,980
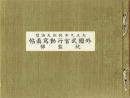
大正九年特別大演習 外国武官行動写真帖
¥176,000

侍従長の回想
¥6,000

歴史問題ハンドブック <岩波現代全書 065> 第1刷
¥2,200

昭和天皇実録
¥33,000

敗戦の記憶 身体・文化・物語 1945~1970
¥3,300
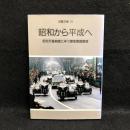
昭和から平成へ
¥18,000

高松宮日記 全8巻
¥11,550

平和の海と戦いの海
¥1,500

天皇裕仁 <河出人物読本> 増補新版
¥500

昭和大礼京都府記録 上下巻
¥6,000

裕仁天皇
¥15,000

昭和天皇新聞記事集成 昭和元年~15年
¥7,700

天皇の研究
¥2,500

昭和天皇のおほみうた
¥4,400

昭和天皇と昭和軍閥
¥4,500

伊勢志摩に両陛下をお迎え志て
¥5,300

昭和維新の朝 二・二六事件と軍師齋藤瀏
¥990

天皇七拾年
¥6,800
コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ

おたくの本
¥1,000
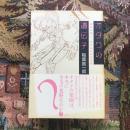
オタクの遺伝子 長谷川裕一・SFまんがの世界
¥1,100
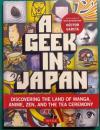
A Geek in Japan
¥500

20年目のザンボット3●オタク学叢書 VOL.1
¥4,000
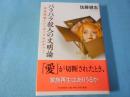
バラバラ殺人の文明論
¥1,500
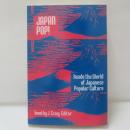
Japan Pop
¥3,300

ポップ・カルチャー年鑑2007
¥1,500
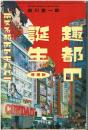
趣都の誕生
¥1,200
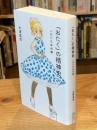
「おたく」の精神史 一九八〇年代論 <星海社新書>
¥2,000

日本アニメーション映画史
¥4,450

ニッポンのマンガ*アニメ*ゲームfrom 1989
¥1,500

12人の作家によるアニメーションフィルムの作り方
¥5,500
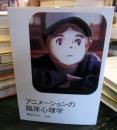
アニメーションの臨床心理学
¥4,200

アニメーターになれる本
¥2,000

アニメは越境する (日本映画は生きている 第6巻) 6
¥2,490

アニメーション
¥3,500

東大オタク学講座
¥1,220

SFアニメの科学 <知恵の森文庫>
¥2,000
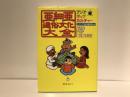
亜細亜通俗文化大全
¥1,000
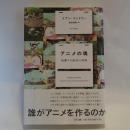
アニメの魂
¥1,200

漫画家・アニメ作家人名事典
¥2,800

日本TVアニメーション大全 テレビアニメ50年記念
¥8,500
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.



![[絵葉書] 昭和参年十二月於横浜港外 御大禮特別大観艦式記念](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12010425/20240919133729599339_fbc6959f2345ba04cb04b650be173901.jpg)