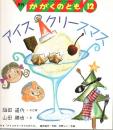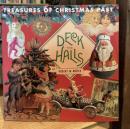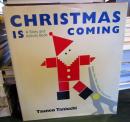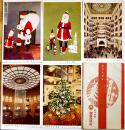クリスマス、冬の風物誌 - 歳時記、年中行事
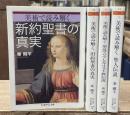
美術で読み解く 全4冊揃い(ちくま学芸文庫)
¥3,300

ヨーロッパの祝祭典
¥1,000
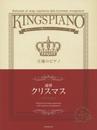
王様のピアノ クリスマス【連弾】
¥8,262

音楽劇 赤ずきんちゃんの森の狼たちのクリスマス
¥5,000

1880年代のクリスマス ヴィクトリアン カード
¥3,500
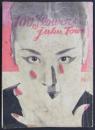
新宿百花 12月クリスマス創刊号
¥44,000
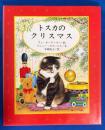
トスカのクリスマス <講談社の翻訳絵本>
¥600
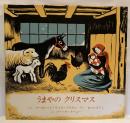
うまやのクリスマス
¥3,000
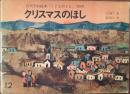
クリスマスのほし <こどものとも 105号>
¥1,500

女性たちが創ったキリスト教の伝統
¥4,500
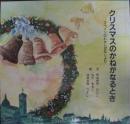
クリスマスのかねがなるとき
¥9,700

Margaret Fulton Christmas
¥8,136

トナカイの社会誌
¥2,200

藤田嗣治 木版摺グリーティンクカード 「キリスト」
¥350,000

The Tall Book of Christmas 【英語】
¥10,000
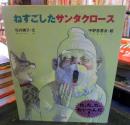
ねすごしたサンタクロース
¥4,000
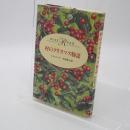
村のクリスマス物語
¥5,800

えほん お母さんと子供の せいしょのおはなし
¥7,000
クリスマス兼用趣味の年賀状 フランス人形 NO.1
¥24,000

1880年代のクリスマス ヴィクトリアン カード
¥3,500
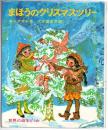
まほうのクリスマス・ツリー (世界の幼年どうわ22)
¥1,260
ドイツ製クリスマスカード
¥5,000
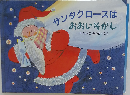
サンタクロースは おおいそがし
¥3,003

手摺り木版 クリスマスカード 6種12枚 未使用
¥13,200
よいこのくに 特集 くりすますのおはなし 第4巻第9号
¥3,300

北越雪譜 全7冊揃 明治刷
¥140,000
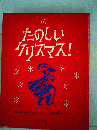
たのしいクリスマス!
¥3,305
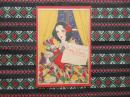
〈クリスマスカード〉雪の中のカレン(仮題)
¥4,000

【浮世絵】月岡芳年「雪月花の内 岩倉の宗玄 尾上梅幸」明治23年
¥1,500,000

さいこうのクリスマスプレゼント
¥500
年の瀬、新年 - 抱負、目標への指南

人生を変える80対20の法則 増補リニューアル版
¥1,100

サライ 築地 最後の年の瀬を歩く
¥3,000

財界巨人伝
¥1,650

ERP/サプライチェーン成功の法則
¥1,979
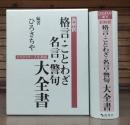
新解釈格言・ことわざ・名言・警句大全書
¥4,290
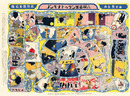
ノンキナトゥサン出世双六
¥22,000

ライフ 大空への挑戦
¥20,000

成語大辞典 故事ことわざ名言名句
¥4,000
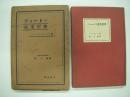
フォードの産業哲学
¥6,000
スタア誕生双六
¥45,000

正月料理
¥2,000
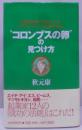
コロンブスの卵の見つけ方
¥2,980

一関町謹賀新年商売繁栄双六
¥66,000

武井武雄 年賀状 1969年−79年 11枚
¥50,000

短歌名言辞典
¥6,600
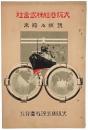
大阪商船株式会社 現状及将来
¥18,000

格闘技が紅白に勝った日 2003年大晦日興行戦争の記録
¥1,000

民友マンガ博’85 日本漫画家協会会員の肉筆赤ベコ年賀状155枚 石森章太...
¥2,000,000

滑稽二日酔 上編大晦日之部 下編元日之部 揃2冊
¥77,000

中医名言大辞典
¥14,600

創造への挑戦
¥8,000

聖書名言辞典 講談社 荒井 献
¥4,000

組織の成功哲学
¥20,424

江戸日本橋商人の記録―〈にんべん〉伊勢屋髙津伊兵衛家の古文書
¥11,440
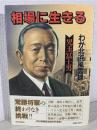
相場に生きる
¥3,400

中国国有企業の政治経済学 改革と持続
¥6,600

四柱推命の使い方
¥3,000

豆蔵豆男 絵本一粒万倍
¥495,000

図解マーフィー奇跡の成功ノート
¥1,100

人間向上の知恵
¥4,500
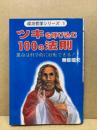
ツキを呼び込む100の法則
¥4,000

向上之青年 第5巻4号~6巻12号内15冊
¥29,700

見て覚える茶の湯の数字ことば
¥1,600

チャールズ・エリスが選ぶ大投資家の名言
¥3,500
新年初刊用見本
¥200,000

何が歴史を動かしたのか 第2巻 弥生文化と世界の考古学
¥6,490
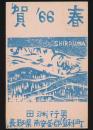
田淵行男木版画入り年賀状 横山元昭宛(昭和41年)
¥44,000
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.