人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に

皇位継承事典
¥2,100

昭和天皇
¥1,830

侍従長の回想
¥6,000
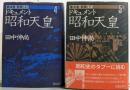
ドキュメント昭和天皇 第4・5巻 敗戦 上下巻セット
¥2,370

天皇の戦争責任
¥2,200

昭和天皇のおほみうた
¥4,400
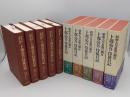
昭和天皇最後の側近 卜部亮吾侍従日記1~5 全5冊
¥5,000
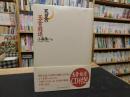
「天皇の玉音放送」
¥900
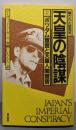
天皇の陰謀
¥950

昭和天皇崩御資料 12点一括
¥30,000

昭和天皇の秘密
¥2,200

昭和天皇 戦後 全3巻揃
¥3,300

卑弥呼誕生-畿内の弥生社会からヤマト政権へ
¥1,650

天皇の真実 憲法一条と九条よ!地球を一つに繋げ!
¥1,800

昭和天皇発言記録集成 上・下2冊 第1刷
¥11,000

いま甦る昭和天皇の肉声 復刻版 人間天皇
¥1,800

昭和天皇の戦い 昭和二十年一月~昭和二十六年四月
¥2,600

昭和天皇新聞記事集成 昭和元年~15年
¥7,700
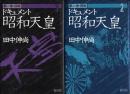
ドキュメント昭和天皇 全8冊
¥9,000
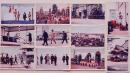
聖上陛下 絵はがき
¥11,000
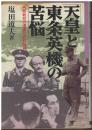
天皇と東条英機の苦悩
¥440

遅すぎた聖断
¥3,000

近代日本語表出論
¥500
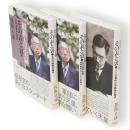
昭和天皇実録その表と裏 全3冊
¥3,000
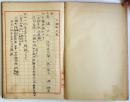
天皇皇族実録抄本(04の191)
¥4,800,000
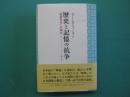
歴史と記憶の抗争
¥5,500

昭和大礼京都府記録 上下巻
¥6,000
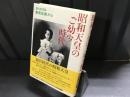
昭和天皇のご幼少時代
¥2,000

サンデー毎日 緊急増刊 昭和天皇崩御
¥1,800
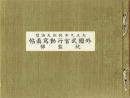
大正九年特別大演習 外国武官行動写真帖
¥176,000

朝日新聞 1989年1月7日号外 天皇崩御 昭和終わる 昭和天皇
¥10,000
コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ

イアン・ビュルマ/訳
¥4,950
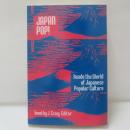
Japan Pop
¥3,300

NOW 【サイン入り】
¥9,000

日本人の「男らしさ」
¥7,700
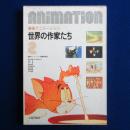
世界の作家たち <講座アニメーション 2>
¥19,800

オタク学入門
¥1,100
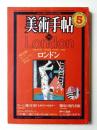
美術手帖 1982年5月号 No.496 <特集
¥1,100
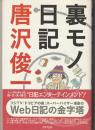
裏モノ日記
¥1,200

国際おたく大学
¥1,520
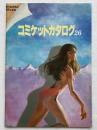
コミケットカタログ 26
¥1,500
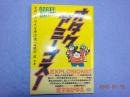
オタクアミーゴス!
¥2,500
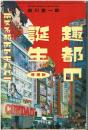
趣都の誕生
¥1,200
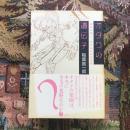
オタクの遺伝子 長谷川裕一・SFまんがの世界
¥1,100
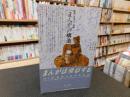
「まんが」の構造 商品/テキスト/現象
¥800

日本アニメーション映画史
¥4,450

アニメーション入門
¥5,500

8ミリアニメ映画の作り方 <現代カメラ新書>
¥6,000
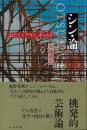
シン・論 おたくとアヴァンギャルド
¥2,000
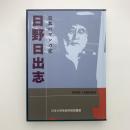
日本のマンガ家 日野日出志
¥7,700

ポップ・カルチャー年鑑2007
¥1,500

コスプレする社会
¥2,924

ジ・オウム
¥5,000

コミックマーケット 30’sファイル 1975-2005
¥3,850
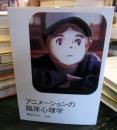
アニメーションの臨床心理学
¥4,200

ポップ・カルチャー
¥1,000
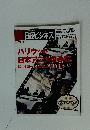
ハリウッド日本アニメを呑む 2007年12月3日号
¥3,000
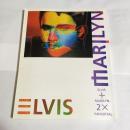
マリリン・モンローとエルヴィス・プレスリー展
¥1,000

現代日本のアニメ
¥2,500
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.









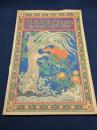
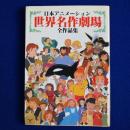


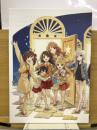
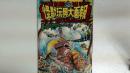
![二次元世界に強くなる 現代オタクの基礎知識 [単行本(ソフトカバー)] ライブ](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/13030080/20250912121157279566_fd92699de3f25da40908313771c390aa.jpg)





