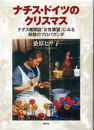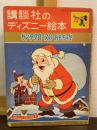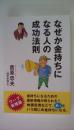クリスマス、冬の風物誌 - 歳時記、年中行事

トナカイの社会誌
¥2,200
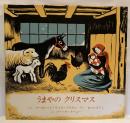
うまやのクリスマス
¥3,000

ミッシェル・ドラクロアリトグラフ 「クリスマス・ツリー」
¥26,400

さいこうのクリスマスプレゼント
¥500

わたしたちのクリスマス劇集
¥3,300
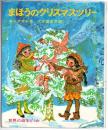
まほうのクリスマス・ツリー (世界の幼年どうわ22)
¥1,260

藤田嗣治 木版摺グリーティンクカード 「キリスト」
¥350,000

【浮世絵】月岡芳年「雪月花の内 岩倉の宗玄 尾上梅幸」明治23年
¥1,500,000

音楽劇 赤ずきんちゃんの森の狼たちのクリスマス
¥5,000

山口素絢筆 泊船冬景図
¥440,000

標準コドモヱ文庫 第1巻第8号 昭和6年12月
¥45,000

芹沢銈介型絵染 クリスマス & 新年カード 7枚セット
¥22,000

ドイツ語版 絵本 Weihnacht (クリスマス)
¥190,000
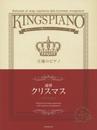
王様のピアノ クリスマス【連弾】
¥8,262
ドイツ製クリスマスカード
¥5,000

図説キリスト教文化史 全3冊
¥3,000

サンタクロースを探し求めて
¥2,000
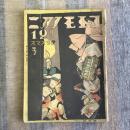
コドモノクニ 第十一巻 第十四號 12月クリスマス号
¥44,000

かみさまからのクリスマスプレゼント
¥700
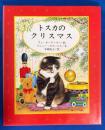
トスカのクリスマス <講談社の翻訳絵本>
¥600

Margaret Fulton Christmas
¥8,136

クリスマス事典
¥2,200
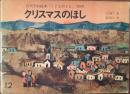
クリスマスのほし <こどものとも 105号>
¥1,500
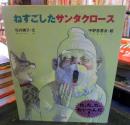
ねすごしたサンタクロース
¥4,000

<チラシ>森山良子 クリスマス・コンサート
¥4,000
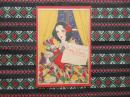
〈クリスマスカード〉雪の中のカレン(仮題)
¥4,000

The Tall Book of Christmas 【英語】
¥10,000
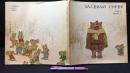
008 【献呈署名サイン入り】どんくまさんの くりすます
¥7,000

北島雪山書幅 草春風雪句紙本連幅 双幅
¥295,000
年の瀬、新年 - 抱負、目標への指南

四柱推命 完全マニュアル
¥1,150

セブンーイレブン・イトーヨーカ堂の流通情報革命
¥3,300

ポルシェ
¥2,200

言行彙鑒 第一編
¥5,500
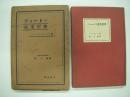
フォードの産業哲学
¥6,000

江戸日本橋商人の記録―〈にんべん〉伊勢屋髙津伊兵衛家の古文書
¥11,440

大晦日曙草紙
¥198,000

一関町謹賀新年商売繁栄双六
¥66,000

滑稽二日酔 上編大晦日之部 下編元日之部 揃2冊
¥77,000

格闘技が紅白に勝った日 2003年大晦日興行戦争の記録
¥1,000

中医名言大辞典
¥14,600

向上之婦人 7冊
¥20,000

年中行事を「科学」する
¥1,980

真宗親鸞・蓮如現代名言法話文書伝道全書
¥4,500

闘魂の記録
¥3,500
教育名言辞典
¥4,400

想い出の紅白歌合戦
¥1,500

老人キラーは出世する
¥30,000

四柱推命の使い方
¥3,000

易経の智恵
¥6,000

ERP/サプライチェーン成功の法則
¥1,979

成語大辞典 故事ことわざ名言名句
¥4,000

古代国家と年中行事(講談社学術文庫1859)
¥1,320
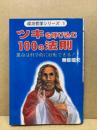
ツキを呼び込む100の法則
¥4,000

武井武雄 年賀状 1969年−79年 11枚
¥50,000

新しき時代の精神に送る 矢部友衛宛署名入
¥165,000
新年初刊用見本
¥200,000

全国年中行事辞典
¥3,700

だいまる 第12巻第1号 <大正16年1月号>
¥25,300

中国国有企業の政治経済学 改革と持続
¥6,600

人間向上の知恵
¥4,500

元祖テレビ屋ゲバゲバ哲学
¥9,500

見て覚える茶の湯の数字ことば
¥1,600

悩みも苦しみもメッタ斬り!
¥3,520
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.