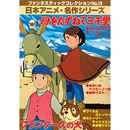人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に

昭和天皇新聞記事集成 昭和元年~15年
¥7,700
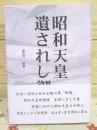
昭和天皇遺されし御製
¥2,000

昭和
¥1,980
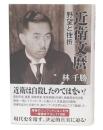
近衛文麿
¥2,480
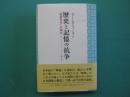
歴史と記憶の抗争
¥5,500

昭和大礼京都府記録 上下巻
¥6,000

「昭和天皇拝謁記」を読む
¥1,800
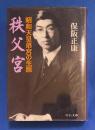
秩父宮
¥2,000

天皇の戦争責任
¥2,200

昭和天皇 戦後 全3巻揃
¥3,300

歴史問題ハンドブック <岩波現代全書 065> 第1刷
¥2,200

昭和天皇の戦争 <昭和天皇実録> 第1刷
¥2,980

天皇の研究
¥2,500

昭和天皇
¥1,830

遅すぎた聖断
¥3,000

昭和御即位式京都行幸紀念 昭和3年11月発行
¥5,500

昭和天皇 写真集
¥3,000

昭和天皇と田島道治と吉田茂
¥1,800

昭和天皇 上・下
¥3,000

昭和維新の朝 二・二六事件と軍師齋藤瀏
¥990

昭和天皇 第1部 (日露戦争と乃木希典の死) 第1刷
¥2,200
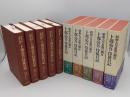
昭和天皇最後の側近 卜部亮吾侍従日記1~5 全5冊
¥5,000

サンデー毎日 緊急増刊 昭和天皇崩御
¥1,800

いま甦る昭和天皇の肉声 復刻版 人間天皇
¥1,800

卑弥呼誕生-畿内の弥生社会からヤマト政権へ
¥1,650
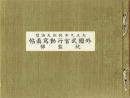
大正九年特別大演習 外国武官行動写真帖
¥176,000

昭和天皇最後の側近卜部亮吾侍従日記 全5巻
¥7,700

昭和天皇の思い出
¥2,200

大元帥・昭和天皇 3 第7刷
¥3,300

侍従長の回想
¥6,000
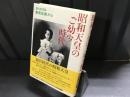
昭和天皇のご幼少時代
¥2,000
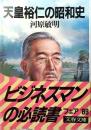
天皇裕仁の昭和史 <文春文庫> 5刷
¥1,000

昭和天皇の戦争指導 <昭和史叢書 2 天皇制>
¥4,500
コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ
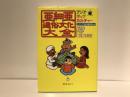
亜細亜通俗文化大全
¥1,000
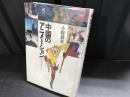
中国のアニメーション
¥9,000

アニメーション
¥3,500

アニメは越境する (日本映画は生きている 第6巻) 6
¥2,490

SFアニメの科学 <知恵の森文庫>
¥2,000

揃 東映動画長編アニメ大全集 上下
¥6,000
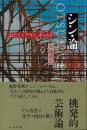
シン・論 おたくとアヴァンギャルド
¥2,000

12人の作家によるアニメーションフィルムの作り方
¥5,500
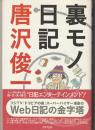
裏モノ日記
¥1,200

戦闘美少女の精神分析
¥3,000

ハルヒin USA
¥3,300

ポップ・カルチャー
¥1,000

村上春樹論 サブカルチャーと倫理
¥4,000
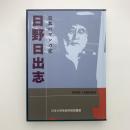
日本のマンガ家 日野日出志
¥7,700

美術手帖 1968年1月号 No.293 <特集
¥1,100

手塚治虫全史
¥4,000
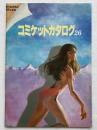
コミケットカタログ 26
¥1,500

ポップ・カルチャー年鑑2007
¥1,500
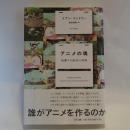
アニメの魂
¥1,200
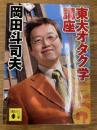
東大オタク学講座 <講談社文庫>
¥1,100

おたくの本
¥1,000
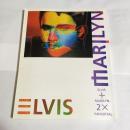
マリリン・モンローとエルヴィス・プレスリー展
¥1,000
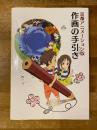
京都アニメーション版 作画の手引き
¥6,000

北斗の拳 スーパープレミアムBOX DVD26枚組
¥25,000

アニメーターになれる本
¥2,000
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.










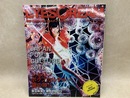
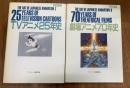




![二次元世界に強くなる 現代オタクの基礎知識 [単行本(ソフトカバー)] ライブ](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/13030080/20250912121157279566_fd92699de3f25da40908313771c390aa.jpg)