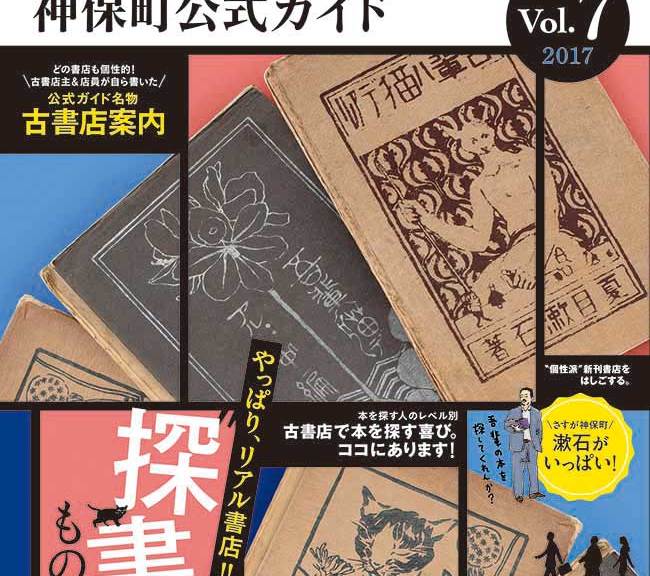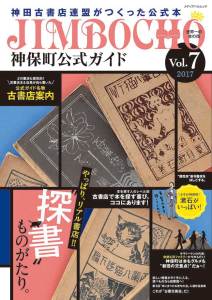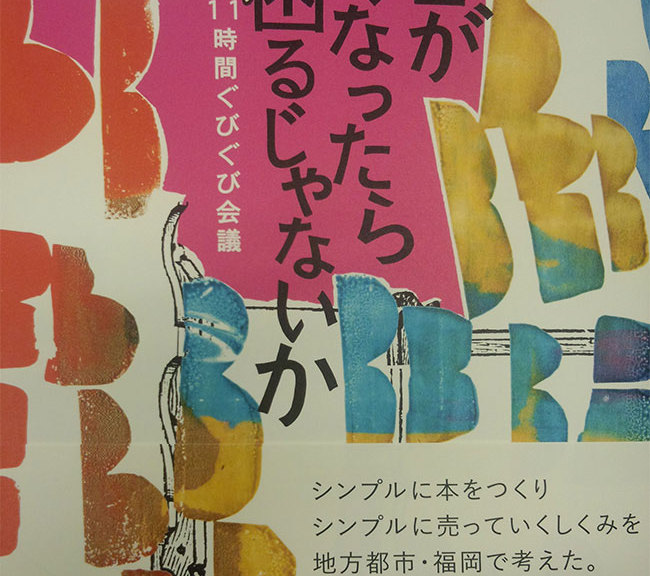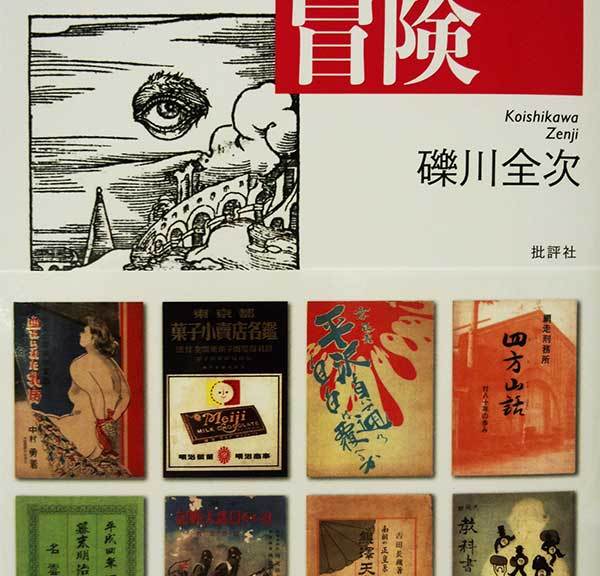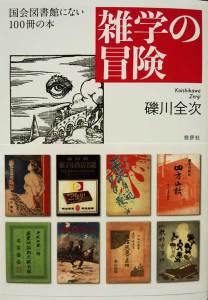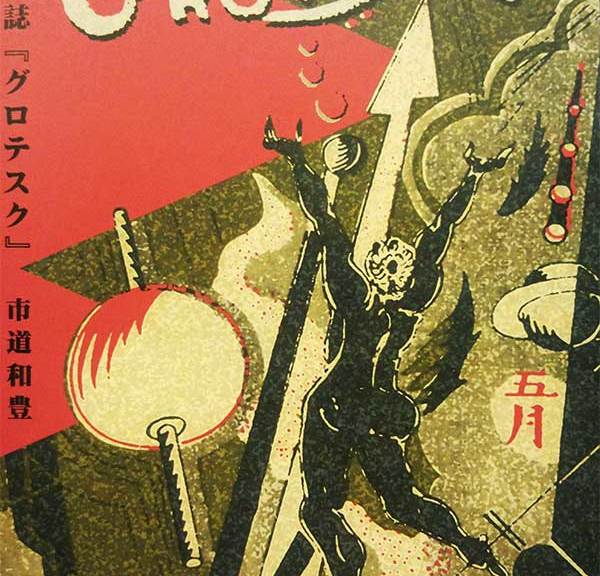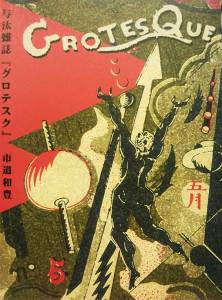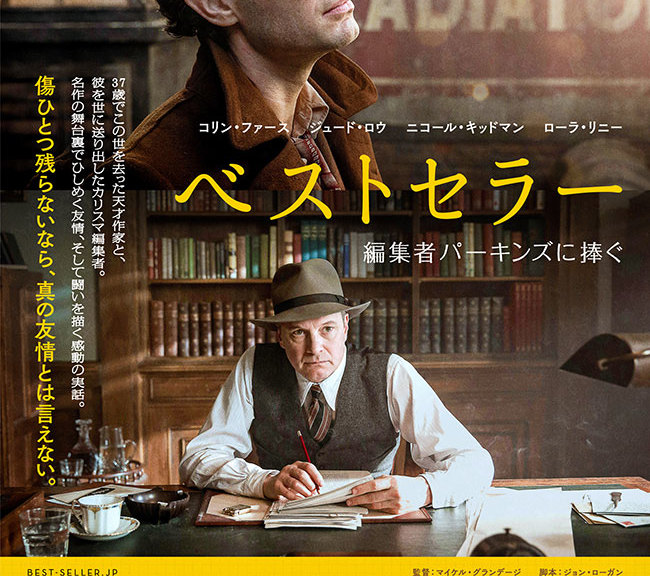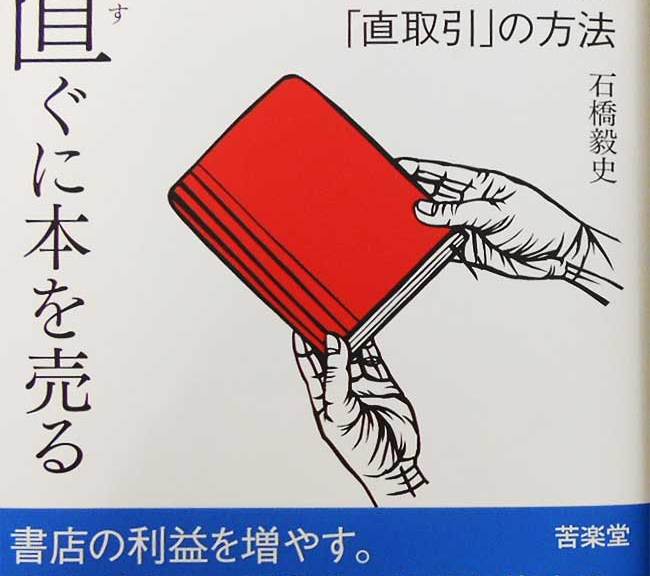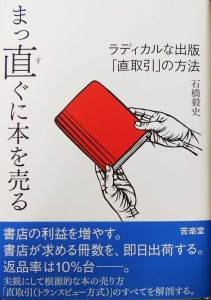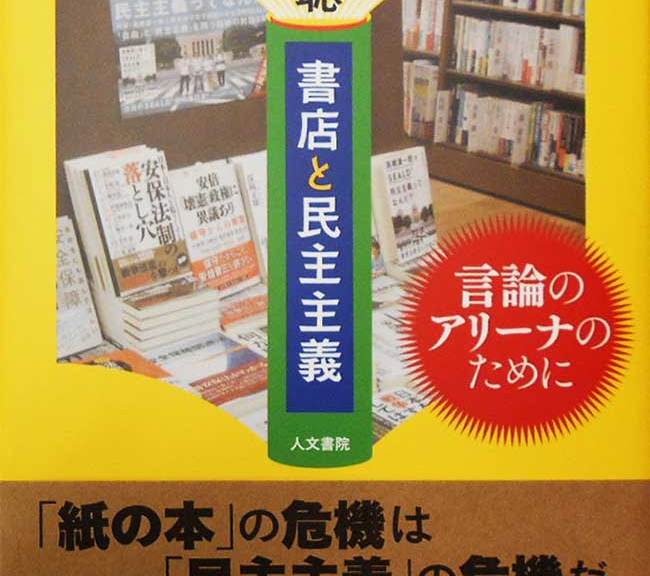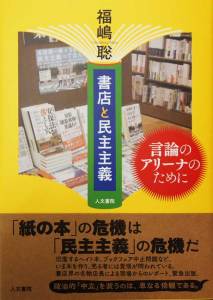■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
。.☆.:* その208・7月25日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆INDEX☆
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
1.古本屋ツアー・イン・ジャパンの2016年上半期活動報告
古本屋ツーリスト 小山力也
2.『まっ直ぐに本を売る–ラディカルな出版「直取引」の方法』
石橋毅史
3.「書店は面倒くさい。民主主義は面倒くさい。されど、さればこそ」
福嶋 聡
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
━━━━━━━【古本屋ツアー・イン・ジャパン】━━━━━━━
古本屋ツアー・イン・ジャパンの2016年上半期活動報告
古本屋ツーリスト 小山力也
古本神のひとりである岡崎武志氏と力を合わせ、この三月に「古本
屋写真集」を上梓出来たのは、過分な幸甚であった。年始早々から
ほぼその制作に全力を注ぎ、己の職業でもないのに、古本屋に身も
心も捧げるような三ヶ月間…だが実はその裏で、今年で九年目に突
入した古本屋ツーリスト人生を揺さぶりまくる大プロジェクトも、
すでにその歯車をギクリギクリと動かし始めていた…。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=2832
『古本屋ツアー・イン・ジャパン』 2008年5月からスタートした、
日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、全調査踏破を目指す
無謀なブログ。「フォニャルフ」の屋号で古本販売に従事すること
も。ブログ記事を厳選しまとめた『古本屋ツアー・イン・ジャパン
(原書房)』と、神保町についてまとめた『古本屋ツアー・イン・
神保町』さらには首都圏沿線の古本屋約700軒をガイドした『古本屋
ツアー・イン・首都圏沿線』(共に本の雑誌社)、さらにさらに「古
本屋ツアー・イン・ジャパン それから(原書房)」が発売中。共編
に『野呂邦暢古本屋写真集』があり、同著と兄弟編の岡崎武志氏との
共著『古本屋写真集』(共に盛林堂書房)も発売中。とにかく派手に
どこまでも古本屋にまみれ、『全国古本屋全集』を作る野望に着々と
前進しながらて生きている。
http://furuhonya-tour.seesaa.net/
━━━━━━━━━━【自著を語る(167)】━━━━━━━━━━━
『まっ直ぐに本を売る――ラディカルな出版「直取引」の方法』
石橋毅史
これから出版社や書店を始める人。本に関わる仕事をする可能性が
ある人。 まずは、そうした人たちに知ってほしいと願いながら書
きました。
新本の流通に問題があると感じている人。
本が生まれ、読者に届くまでの過程に関心のある人。
そうした人たちにも、読んでほしいと思っています。
2001年に創業した出版社・トランスビューを主な取材対象とし、
「出版社―書店間の直取引」について、その方法をできるだけ詳しく、
わかりやすく紹介することを目指しました。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=2840
『まっ直ぐに本を売る』 石橋 毅史 著
苦楽堂 定価:1800円+税 好評発売中!
http://kurakudo.co.jp/
━━━━━━━━━━【自著を語る(168)】━━━━━━━━━━━
「書店は面倒くさい。民主主義は面倒くさい。されど、さればこそ」
福嶋 聡
「嫌韓」「呆韓」「誅韓」・・・。ある日気がつくと、店の書棚が
隣国を誹謗するタイトルで溢れている。一方で、日本がどれだけ優
れているかを自画自賛する本が立ち並ぶ。相手を貶めて自分を優位
に見せるという、最もみっともない驕りの姿である。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=2845
『書店と民主主義』 福嶋 聡 著
人文書院 定価:1,600円+税 好評発売中!
http://www.jimbunshoin.co.jp/book/b222590.html
━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━
『雑学の冒険 国会図書館にない100冊の本』礫川 全次 著
批評社刊 価格 1,700円+税 好評発売中!
http://www.hihyosya.co.jp/ISBN978-4-8265-0644-1.html
『与太雑誌『グロテスク』』 市道 和豊 著
自費出版 頒布価格 2,000円(税・送料込)
申込み先ページ
http://www.kosho.ne.jp/contact.html
━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━
8月~9月の即売展情報
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=19
┌─────────────────────────┐
次回は2016年8月中旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその208 2016.7.25
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:殿木祐介
編集長:藤原栄志郎
==============================