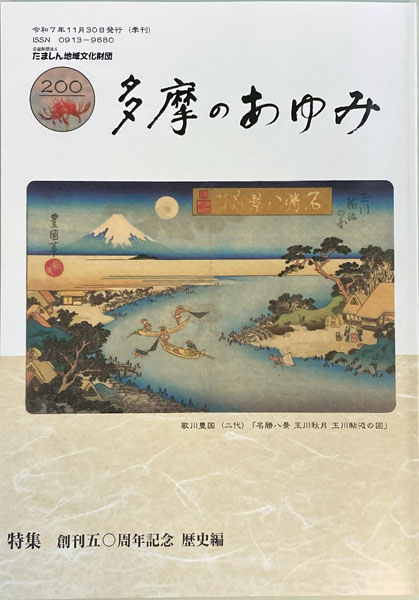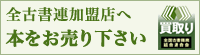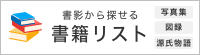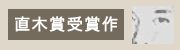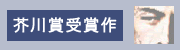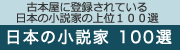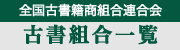「書店は面倒くさい。民主主義は面倒くさい。されど、さればこそ」福嶋 聡 |
| 「嫌韓」「呆韓」「誅韓」・・・。ある日気がつくと、店の書棚が隣国を誹謗するタイトルで溢れている。一方で、日本がどれだけ優れているかを自画自賛する本が立ち並ぶ。相手を貶めて自分を優位に見せるという、最もみっともない驕りの姿である。 ぼくはいささが不快になった。大型店の店長として、ぼくは自らの信念に適う本だけを並べておきたいと思うほど潔癖ではなく、非現実的ではない。だが、それにしても、ちょっとひどすぎはしないか?書く著者も、つくる出版社も、並べる書店も、そして買う読者も。 2014年の秋、『NOヘイト!』(ころから)という本が出た。出版界の人たちが「ヘイト本」が量産される業界を自己批判する、小さいけれど転轍機となりうる本だと思い、ぼくはすぐにその本を応援しようと決めた。そして書評を書き、ブックフェア「店長本気の一押し!『NOヘイト!』」を展開した。 年が明けると、そのフェアに対していくつかのクレーム電話がかかってきた。「お前は、韓国や中国などというとんでもない国の肩を持つのか?」「本屋が、そんな偏った思想を客に押し付けていいと思っているのか?」 9月には、安保関連法案強行採決への反対運動の盛り上がり、SERLDsの登場を受けて開催した系列書店のブックフェア「自由と民主主義のための必読書50」が攻撃され、一時撤去を余儀なくされる「事件」もあった。 ぼくは、それらの「書店に対する風当たり」を、「まだまだ書店が存在感を保持している証左だ」と、むしろ歓迎した。クレームは、「向こう傷の誉れ」だと嘯いた。 そして、思った。高橋源一郎がいう「民主主義」の定義=「たくさんの、異なった意見や感覚や習慣を持った人たちが、一つの場所で一緒になっていくシステム」を採用するならば、それぞれの著者がさまざまな主張や思いを籠めた多くの本たちが所狭しと並ぶ書店店頭こそ、民主主義そのものの顕現の場ではないだろうか。 だからぼくは、自分の信念に基づいて、堂々と商品を並べアピールする。一方で、自分の主張と敵対するような書物も、排除するつもりはない。意見を持つことと、他の意見を排除することは違う。民主主義は、限りない議論と説得という、とても面倒くさいシステムなのだ。その面倒くささに耐え切れなくなると、「正義」が他を制圧しようとする。 書店は面倒くさい、民主主義は面倒くさい、だがその面倒臭さゆえにこそ、大切にいとおしまなければならない。『書店と民主主義』というタイトルに、ぼくはそんな思いを託した。
|
|
Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |