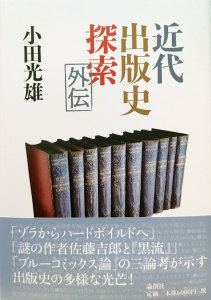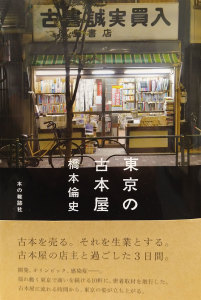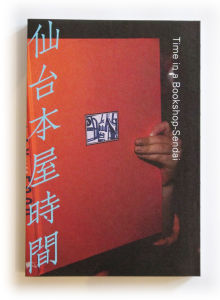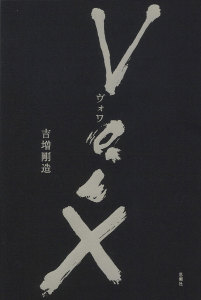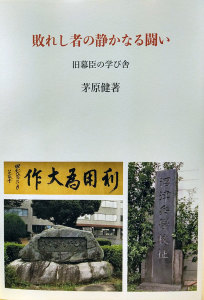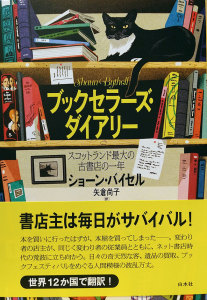ズレて、ズラして、ズラされて――時代と価値観からのスピン・オフ (古本の読み方1)書物蔵 |
| ■古本の買い方ならぬ読み方 古本読書術というお題は成立するだろうか。古本の「買い方」本には意外と「読み方」が書かれていない。それらは、買い方+自分がオモシロいと思った古本の紹介、というパターンがほとんどで、「なんで自分がその本をオモシロいと思えたか」「どうしてその本がユニークだと気づけたか」といったメタな記述、つまり、購書術ならぬ読書術はあまり見当たらないのだ。気づいた結果は書いてあるのに、なぜ気づけたのか、プロセスがないのは、無意識的な動作だからだろう。 そこで改めて考えてみた。 ■古本とは、時代のズレを楽しむ本のこと ■ズレとは、読み手がつくるズラシのことでもある ■(事例)日本は図書分類法でさきの大戦に勝利した……のか!? ■(読み方)体制変換をまたぐとオモシロい ■(読み方)拡張概念で、自分の読みたい本を過去の方向へ殖やす *書物蔵「カードと分類で大東亜戦争大勝利!:もうひとりの稲村さん、国際十進分類に挺身す(あったかもしれない大東亜図書館学; 6)」『文献継承』(22) p.11-16 (2013.4) 書物蔵 ツイッター |
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |
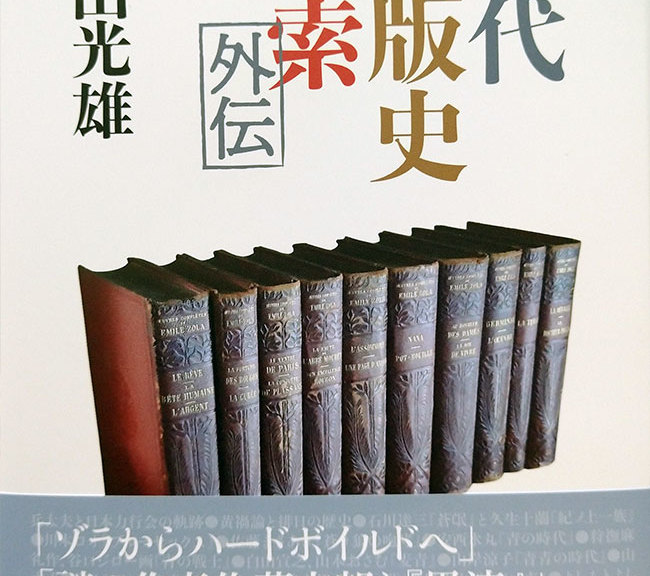
『近代出版史探索外伝』について
『近代出版史探索外伝』小田光雄 |
| 今回の拙著はこれまでの『近代出版史探索』五冊の短編連作と異なり、「ゾラからハードボイルドへ」「謎の作者 佐藤吉郎と『黒流』」「ブルーコミックス論」からなる三本立てである。映画を見始めた1960年代は雑多な三本立て上映が主流であって、それを模してみようと思った。 これは日本の古本屋メールマガジンの配信なので、ここでは「謎の作者 佐藤吉郎と『黒流』」にふれてみたい。この論考は十年以上前に書いているのだが、その後何ら新しい情報も得られず、さらなる知見を加えることができていない。ただひとつの進展はこの『黒流』という小説が国会図書館の蔵書デジタル化によって、誰でも読めることになったという事実であろう。 だが依然として古書市場にはまったく見出せず、私が書いた時の状況と変わっていない。その私にしても、ずっと『黒流』を探していて、ようやく入手したわけではなく、古本屋の棚に置かれていたのを偶然に購入しただけである。確か古書価は千円であった。この四六判並製、函入六四六ページの長篇小説は佐藤吉郎という作者も含め、『日本近代文学大事典』を始めとするアーカイブにもまったく見当たらず、それは東北書房なる版元も同様だった。 出版されたのは大正十四年十月であるので、大正文学に位置づけられようが、そちらの方面をたどってみても、その痕跡はどこにも残されていなかった。それゆえに、『黒流』という一冊と物語自体に謎を求めるしかなかった。確かに著者の写真は掲げられ、「自序」も示され、「今日地球上に於いて、最も重大な問題は、階級戦と人種戦である」と始まっている。そして次のような言葉も見られる。 ” 私は一箇の放浪者だ。十九の秋から八年の間は、殆ど南洋に、メキシコに、キユーバに、北米にと云ふ様に放浪の旅を続けて居た。それも他の漫遊者の様に旅費を持つての放浪ではなかつた。だから冒険的な放浪であつた。一寸日本に居る人達の想像の出来ない様な経験もして居るのは云ふ迄もない。” この「自序」によって、『黒流』が長きにわたる南北アメリカの「冒険的な放浪」にベースを置き、「階級戦と人種戦」を描いていることが示唆される。しかもこの長篇小説『黒流』は当初千五百枚だったが、それを八百五十枚に縮めたので、「筋はそれ丈面白い処のみを取つて来た」とも述べられている。 つまり現在の言葉に置き換えれば、エンターテインメント、もしくは冒険小説のようにして提出されたことになろう。そのために、『黒流』は大正文学にあって、まったく異形の小説、戦後の大藪春彦の小説に先駆けるようなかたちで出現している。 その一方で、黄禍論と排日の歴史もたどり、『黒流』の物語を分析し、石川達三の『蒼氓』に近代日本の南米移民史を追っている。また久生十蘭の『紀ノ上一族』に、『黒流』とは異なるかたちでの、アメリカにおける「階級戦と人種戦」を検証してもいる。 『近代出版史探索外伝』 小田光雄著 |
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |
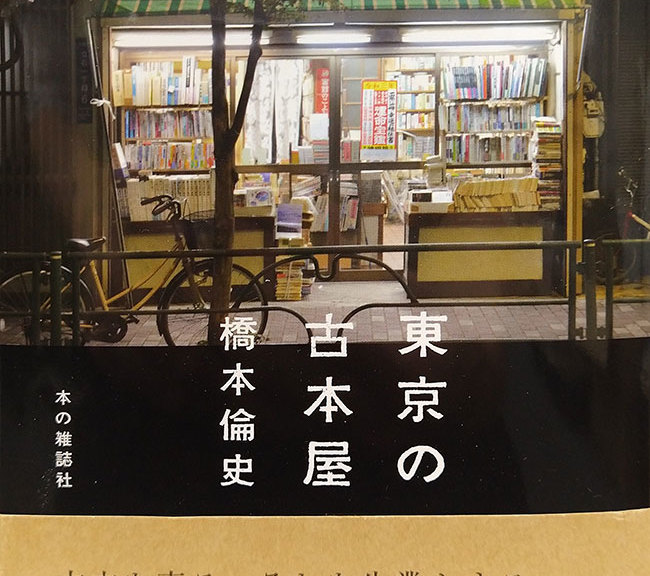
『東京の古本屋』
『東京の古本屋』橋本倫史 |
| きっかけは、ふとした一言だった。 大学4年生を迎えた春、単位がまだ足りなくてどの授業を履修しようかと頭を悩ませていたところに、同郷の友人がアパートを訪ねてきた。ちょうどそのとき、テーブルの上に『SPA!』を広げてあった。毎週購読していたわけではなく、その週はたまたま買い求めて、テーブルに置いてあった。開いていたページには、福田和也さんと坪内祐三さんによる対談連載「これでいいのだ!」が掲載されていた。それを目にした友人が、「この人、早稲田で授業やってるよ」と教えてくれた。「レポートさえ出せば誰でも単位もらえる授業らしいけど」と。 ぼくが通っていたのは早稲田大学ではなく、学習院大学だったけれど、単位交換システムがあり、その授業はぼくでも履修できるようだった。最初はただ「単位がもらえるなら」と申し込んだのが、坪内さんの「編集・ジャーナリズム論」という授業だった。そんなよこしまな気持ちで履修したものの、内容に引き込まれ、大学4年間で唯一欠席しなかった授業になった。 それからほどなくして、「わめぞ」というグループが立ち上がった。早稲田と目白と雑司ヶ谷で、本にまつわる仕事をしている人たちが集まり、「古書往来座」では外市という古本市が定期的に開催されるようになった。ぼくは買い物客として立ち寄りながら、「古書現世」の向井透史さんに誘ってもらって、打ち上げの席に混ぜてもらったり、飲み会があるときには声をかけてもらったりするようになった。そうして少しずつ古本屋の人たちと遊ぶようになり、楽器もできないのに、古書店主たちとボエーズというバンドまで組んでいた。ぼくは「記録係」ということになっていたけれど、ライター仕事で使うICレコーダーを持ち出し、演奏を録音しながらビールを飲んでいただけだった。大塚にあったオレンジスタジオで練習したあとは、サービスデイには焼酎の一升瓶が1300円で入れられる居酒屋「江戸村」でしこたま飲んで、酔っ払いながら都電脇を雑司ヶ谷に向けて歩いた。ぼくは古本屋で働いたこともなければ、頻繁に古本屋で買い物をするよいお客さんでもないけれど、そうしてお酒を飲んでいるうちに、古本屋の生活に少しだけ触れたような心地がした。そして、それをいつか言葉にしたいと、ずっと思っていた。 ボエーズのボーカルを務めるのは、イラストレーターの武藤良子さんだ。その武藤良子さんが金沢の龜鳴屋から『銭湯断片日記』という本を出版する運びとなり、目白のブックギャラリーポポタム」で刊行記念トークイベントが二夜連続で開催された。その一夜目のゲストは「石神井書林」の内堀弘さんだった。 武藤良子さんの『銭湯断片日記』は、本にまとめるつもりで書かれた文章ではなく、銭湯を訪れたときのことを日記としてつらつらと綴り、ブログに掲載されていたものだ。ただ、それがブログに綴られたままのテキストではなく、一冊の本にまとまったことで見えてくるものがあると、内堀さんは言った。 「山口先生にはすごくお世話になって、いろんなことを教わったんですけど、そのひとつが『コレクションというのは、集めることで初めて見えてくるものがあるんだ』ということで。たとえば本草学も、いろんな葉っぱをとってきて、これはあれに効く、これに効くと、コレクションから見えてくるものがあったと言うんですね。明治以前の日本にはコレクションの思想があって、その最たるものが日記だ、と。日記というのは日々のコレクションで、それだけを抜き出すと大したことは書いてないんだけど、それがまとまることで見えてくるものがある。その話を聞いてから、日記って面白いんだなと思うようになったんですよね」 ぼくは以前から日記を書いたり読んだりするのが好きだったけれど、この夜のトークイベントを聞いているうちに、日記の面白さをあたらめて感じたような気がした。古本屋のことを書くのであれば、日記として綴ろう。ビールを飲みながらふたりの話を聞いているうちに、そう決めたのだった。 『東京の古本屋』 橋本倫史 |
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |
2021年10月8日号 第332号
■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
古書市&古本まつり 第105号
。.☆.:* 通巻332・10月8日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━
コロナ禍古本屋生活1
火星の庭 前野久美子
新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが発生し、非日常
が日常になって久しい。かつて、わたしの店ではトークイベントや
ライブを開催し、店内は多くの人で賑わっていました。それも遠い
昔のようです。今は、静かになった店内でお客様から買った本をき
れいに拭いた後、値付けをして棚に並べるといった古本屋の仕事を
続けられることに感謝の日々を過ごしています。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7288
火星の庭ホームページ https://kaseinoniwa.com/
Twitter https://twitter.com/kaseinoniwa
『仙台本屋時間』
https://kasei003.stores.jp/items/605b5f5dd263f03059a1a9b2
━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━
第33回 退屈男さん ちょっとずつ「本の世界」に関わるひと
南陀楼綾繁
この連載は、古本や古本屋と自分なりに付き合ってきた人に話を
聞くことを目的としている。インタビューの場では、その人の話を
引き出すために、私自身の体験を話すこともあるが、文章にまとめ
る際には極力カットしている。
しかし、以前からの知り合いだとそれがやりにくい。つい、自分
の思い出を通して、その人を描いてしまう。相手と私を切り離して
書きにくいのだ。だから、数人の例外を除き、旧知の人はなるべく
外している。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7270
南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)
1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一
文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、
図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年
から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」
の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。
「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ
・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を
つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に
『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市
の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、
『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』
(ちくま文庫)、共著『本のリストの本』(創元社)などがある。
『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著
皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!
http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/
※ご好評いただきました『シリーズ古本マニア採集帖』は、今回を
持ちまして終了します。連載のご愛読ありがとうございました。
なお、11月に皓星社から刊行予定です。ご期待ください。
━━━━━━━━━【東京古書組合からお知らせ】━━━━━━
「コショなひと」始めました
東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画
配信をスタート。
古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して
売っている古書店主の面々も面白い!
こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書
店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。
お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない
店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない
ことも・・・
古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!
是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)
杉野書店 杉野 基
BOOKS 青いカバ
YouTube 東京古書組合
https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w
━━━━━【10月8日~11月15日までの全国即売展情報】━━━━━
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている
即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。
お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
-------------------------------
城南古書展【会場販売します】
期間:2021/10/08~2021/10/09
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
-------------------------------
第21回 四天王寺 秋の大古本祭り(大阪府)
期間:2021/10/08~2021/10/12
場所:大阪 四天王寺 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18
http://kankoken.main.jp/
-------------------------------
MARUZENギャラリー「秋の古本まつり」(福岡県)
期間:2021/10/13~2021/10/26
場所:ジュンク堂書店福岡店 2階 MARUZENギャラリー特設会場
-------------------------------
ア・モール古本市(北海道)
期間:2021/10/14~2021/10/19
場所:アモールショッピングセンター1階センターコート
旭川市豊岡3 条2丁目2‐19
-------------------------------
ぐろりや会【会場販売します】
期間:2021/10/15~2021/10/16
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
http://www.gloriakai.jp/
-------------------------------
本の散歩展
期間:2021/10/15~2021/10/16
場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4
-------------------------------
第24回 天神さんの古本まつり(大阪府)
期間:2021/10/15~2021/10/19
場所:大阪天満宮 大阪府大阪市北区天神橋2丁目1-8
http://osaka-koshoken.com
-------------------------------
港北古書フェア(神奈川県)
期間:2021/10/20~2021/10/29
場所:横浜市営地下鉄 センター南駅
(市営地下鉄センター南駅の改札を出て直進、右前方 ※駅構内)
http://www.yurindo.co.jp/store/center/
-------------------------------
秋の阪神古書フェア(大阪府)
期間:2021/10/20~2021/10/25
場所:阪神百貨店梅田本店 8階催場 大阪市北区梅田1丁目13-13
-------------------------------
秋の古本掘り出し市(岡山県)
期間:2021/10/20~2021/10/25
場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア
-------------------------------
特選古書即売展【会場販売します】※10/4WEBページ更新予定
期間:2021/10/22~2021/10/24
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
TEL:03-5280-2288(会期中のみ会場直通)
https://tokusen-kosho.jp/
-------------------------------
好書会
期間:2021/10/23~2021/10/24
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
-------------------------------
第24回紙屋町シャレオ古本まつり(広島県)
期間:2021/10/25~2021/10/31
場所:シャレオ中央広場 広島市中区基町地下街100号
https://twitter.com/koshohiroshima
-------------------------------
浦和宿古本いち(埼玉県)
期間:2021/10/28~2021/10/31
場所:JR浦和駅西口 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前
https://twitter.com/urawajuku
-------------------------------
洋書まつり
期間:2021/10/29~2021/10/30
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
http://blog.livedoor.jp/yoshomatsuri/
-------------------------------
名古屋古書会館古書展示即売会(愛知県)
期間:2021/10/29~2021/10/31
場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12
電話:052-241-6232
※JR「鶴舞駅」名大病院口より徒歩5分/※地下鉄「鶴舞駅」1番出口より徒歩6分
https://hon-ya.net/
-------------------------------
杉並書友会
期間:2021/10/30~2021/10/31
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
-------------------------------
東京愛書会
期間:2021/11/05~2021/11/06
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
http://aisyokai.blog.fc2.com/
-------------------------------
古書愛好会※中止になりました
期間:2021/11/06~2021/11/07
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
-------------------------------
11月反町古書会館(神奈川県)
期間:2021/11/06~2021/11/07
場所:神奈川古書会館1階特設会場
http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm
-------------------------------
BOOK & A(ブック&エー)
期間:2021/11/11~2021/11/14
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
-------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33
┌─────────────────────────┐
次回は2021年9月下旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその330 2021.9.10
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:志賀浩二
編集長:藤原栄志郎
==============================
2021年9月25日号 第331号
■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
。.☆.:* その331・9月27日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約640万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆INDEX☆
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
1.『ブックセラーズ・ダイアリー
―スコットランド最大の古書店の一年』 矢倉尚子
2.「敗れし者の静かなる闘い」について 茅原健
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
━━━━━━━━━━━━【自著を語る(277)】━━━━━━━━
『ブックセラーズ・ダイアリー
―スコットランド最大の古書店の一年』
矢倉尚子
翻訳は――人によって違うのだろうが少なくとも私の場合は―
―どこかの時点で憑依というか、原著者に乗り移ってもらって語
り出すことができなければ、満足な仕事にはならない。そこで著
者のことばに重なりそうな材料を探し求めて、まず最初に古本を
買いまくる。どの資料がいつ必要になるかわからないので、図書
館は役に立たない。あちこち歩きまわっている時間はないから、
とりあえずはネットで買う。慣れてくると鼻が利いて、これは使
えそう、というのがかなりの勝率で当たるようになる。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7282
『ブックセラーズ・ダイアリー』 ショーン・バイセル 著
矢倉尚子 訳
白水社 定価3,300円(本体3,000円+税)好評発売中!
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b584634.html
━━━━━━━━━━━【自著を語る(278)】━━━━━━━━━
「敗れし者の静かなる闘い」について
茅原健
我が家の家系を辿ると、曽祖父から流れている旧幕臣という素性
意識がわだかまっている。これは、時代錯誤といわれるかも知れな
い。しかし、戊辰戦争に敗れて虱だらけになって帰還した曽祖父の
無念を継いだ祖父は、旧幕臣の系譜にこだわり、薩長の栗は喰まな
いという気概を秘めて東北に流れて、その地方新聞に筆を執り、
「東北に平民政治を」という論調を掲げた。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=7273
『敗れし者の静かなる闘い』 茅原健
日本古書通信社刊 定価:2000円+税 好評発売中!
https://www.kosho.co.jp/kotsu/
━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━
『近代出版史探索外伝』 小田光雄著
論創社刊 6000円+税 9月下旬刊行予定
https://ronso.co.jp/
『東京の古本屋』 橋本倫史
本の雑誌社刊 本体2000円+税 好評発売中!
https://www.webdoku.jp/kanko/page/4860114620.html
吉増剛造 詩集 『Voix(ヴォワ)』
思潮社 2800円+税 10月20日頃発売
http://www.shichosha.co.jp/
━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━
9月~10月の即売展情報
※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている
即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。
お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=38
┌─────────────────────────┐
次回は2021年10月中旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその331 2021.9.27
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:志賀浩二
編集長:藤原栄志郎
==============================
コロナ禍古本屋生活1
コロナ禍古本屋生活1火星の庭 前野久美子 |
| 新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが発生し、非日常が日常になって久しい。かつて、わたしの店ではトークイベントやライブを開催し、店内は多くの人で賑わっていました。それも遠い昔のようです。今は、静かになった店内でお客様から買った本をきれいに拭いた後、値付けをして棚に並べるといった古本屋の仕事を続けられることに感謝の日々を過ごしています。 そうした中、違和感を感じるときがあります。コロナの自宅療養者は全国で60,532人に上り(厚労省サイト2021年9月17日現在)、こうしている間にも誰にも看取られずに亡くなる人、必要な医療を受けることができずにいる人のことをふと思い浮かべるときです。「もし瓦礫の下に6万人が生き埋めになっていたとしたら、すぐにも救助するだろうね」と友人が言っていました。自宅療養者という言葉の陰でリアルなイメージが描けないからなのか、多くの人が自分たちが過ごしている日常とパンデミックの深刻さのギャップを埋めるのが難しいと感じています。この感覚は東日本大震災のときに感じたものとどこか似ている気がします。あの頃もいつも通り店に立ち、古本を売りながら、10数キロ先で起きた大津波、80キロ先で起きている原発事故が、現実のものと思えずにいました。 わたしが住む仙台市は東北では新型コロナウイルスの感染者数が最も多く、昨年の流行が始まると、県外はもとより市外の人からも「仙台に行くのはちょっと」という声が聞こえるようになりました。コロナ以前、店には週末になると県外から多くの方が訪れていました。岩手、山形、福島などに加え、首都圏をはじめ関西や沖縄からも来店がありました。ときには台湾、韓国、中国、欧米など外国からのお客様もいらしていました。 中には、後日再び立ち寄ってくれる人もいて、「友人に火星の庭の話をしたら」などと後日談を聞かせてくれたりもします。そのおかげでこの狭い古本屋は思いがけないほど、広い世界と接することができました。それらはすべてお客様との出会いを通して作られた世界だったのだと今になって気がつきます。 しかし、悪いことばかりではありません。2020年の春、宮城県にも緊急事態宣言が発令されて、古本は不要不急ということになり、古本屋に休業要請が出され3週間店を休業することになったときのことです。休業する前日、常連のお客様がやってきました。お会計のときに、「明日から休むことになりました」と伝えると、さっと顔色が変わったのです。いつもじっくり本棚を見られて、だまって本を買っていかれる方です。その日、帰り際にドアまで近づいたところで急に立ち止まり、こちらに背中を向けたまま、「困るんだよ、古本屋に休まれると。行くところがなくなるから!」と叫んだのです。一瞬のことでした。そして、足早に去って行かれました。予想外の出来事に茫然としつつも「辛いのは店主だけじゃないんだ。いや店主は休業中も店に来れるじゃないか。ドアの鍵を閉めてしまったらお客様は入ることはできない。その方が辛いのかもしれない」、そんな思いが頭に浮かびました。お客様の「困るんだよ!」という声がいつまでも店内に反響しているようでした。 昨年4月の休業要請以降は、定休日以外は休まずに営業しています。売り上げは戻りませんが、閉店後にその日いらしたお客様の顔を思い浮かべて、以前より地域の古本屋であることを実感する日々です。そうした中でもときに県外からのお客様が立ち寄ってくれることがあります。お客様すべてと会話するわけではありませんが、中には声を潜めて「実は◯◯県から来たんです」とこっそり語ってくれる人もいます。 見方によれば、コロナ禍の今は店を閉めオンライン販売だけにした方が、感染防止の上でも経営的にも正しいのだと思う。でも、古本屋がなくてはならない場所になっている人もいます。そういう人のためにもお店を続けようと思います。お店を開けるかどうかは、自分だけの問題ではない。あのお客様の叫び声を聞いてから思うようになったからです。小さくなった世界で何ができるだろうか。あらためて考えているこの頃です。 火星の庭ホームページ https://kaseinoniwa.com/
|
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |
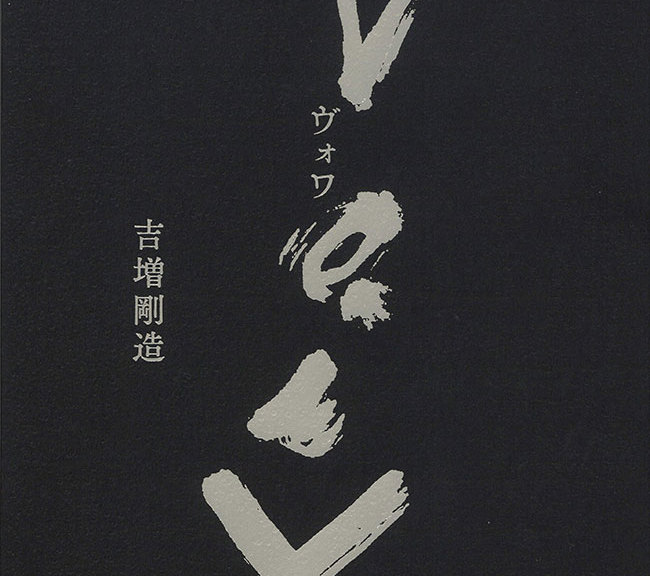
詩集の芯に、イ(i)の樹木(き)の君が立って来ていた
詩集の芯に、イ(i)の樹木(き)の君が立って来ていた吉増剛造 |
| “メズラシキゴイライニセッシ、コヽロオドリジャクヤクシオリソロ(稀らしき御依頼に接し、心躍り雀躍し居候)”と、何処かへと“ウナ電(至急電報)”を打ってみたい気持が湧いて来ていた。 これは、旧知の吉成秀夫さんからの書状での御依頼に接した折のemotion=エモーション、“感情”と綴ろうとして、しばらく途惑っていて、“emotion=エモーション”といたしましたのには、理由があって、…というのよりも、ここで、その“理由”が芽生(めば)えて来ていて、それに誘われて、こう、綴っていたのだった。このこと、後述、……。 さて、心躍りの一端、……うーん、“一端”というのよりも端緒(たんしょ)は、“古ということ”にあったのであって、“どうしてかしら、=I don’t know why”ぼくは「古書」というものがすきなのだ。と、こうして、はっきりと云ってはみたのだけども、その、そう“古書がすきだ”という、“emotion=エモーション”の正体というのか心の芯は判らないまゝなのだ。“一計を案じて”……というのよりも、ある心景が脳裡にひかるようにして、通り掛って、これは「書肆吉成」の吉成さんに話し掛けるようにして綴ってみたい。札幌なのか神田なのかパリかニューヨークなのか判らないのだが、どこかの古書肆の狭い本棚に挟まるようにして、俯(うつむ)き様(ざま)の山口昌男がいて、紙の皺(しわ)を指先で撫(な)でる音(おと)だけがしている。みたこともないのに、はっきりと心に浮かんで来る、景色(けいしょく)がわたくしはすきなのだ。古書に、埋まるでもない、ただ読んでその鋭利な頭脳に刻み込むだけではない、このぼくの“古書というものがすきなのだ”という、少し襤褸(ぼろ)の何処かの馬の骨のような座敷童子(ざしきわらし)の小声をも聞きとって、そう古景色(コケイショク)の姿そのものになっているような山口昌男がすきなのだ。 これで、そう「落(おと)し咄(ばなし)」の枕(まくら)にはなったのでしょうか。もう、この「落(おと)し咄(ばなし)」の枕(まくら)」にも、終始をしたい位なのだけれども、ご依頼の「自著を語る」、十月の中旬頃には、思潮社(ご担当髙木真史氏、装本中島浩氏)より上梓の予定の、……わたくしの最後の詩集、……流石にこう書くと、心が奥の方で、なにか“キー”と鳴る気がしていて、少しフデがとまるのだけれども、この“最後の、…”のことを、少しだけ語ることにする。たった今、無意識に繰り返した、この“少し”という小声の聞こえるところに、“古(フ)ル”ということの根(ネ)のようなものがあるのであって、思い掛けないことに、“古(フ)ル”で、論旨の筋道は、一息に途・切・ら・れ・ていた。(傍点のところ、これも、後述をいたします。)あるいは、こ・れ・も・、無意識の神木(き)の不意の言葉であったのかも知れなかった。途・切・ら・れ・た論旨が辿ろうとしていたのは、わたくしたちの古典の「古(ふ)る」、「古(いにし)え」には、微弱でもいい、未来への胎動のようなものがないのが、寂(さび)しいことだが、……であったのだが、おそらく、無意識の繰り返しと、次の光の糸がルビの“フ”と、“古(フ)ル”を、綴らせていたらしい。この“らし、…”が、直観といわれるものなのだ。 新著—最後の詩集『Voix(ヴォワ)』(思潮社、二〇二一年十月刊)は、二〇一九年夏の第二回Reborn Art Festivalへのご招待を契機に、誕生をすることになりました。石巻市鮎川地区の「詩人の家」(島袋道浩、青葉市子、松田朕佳、志村春海さんら)のほかに、島周(しまめぐり)の宿(やど)さか井の遠藤社長のお志によって、金華山を眼前にする二〇六号室が創作とみなさまのお声と記憶の溜るあるいは沈むあるいは白い煙のようにして立つ場所、部屋、つまり結界となって来ていた。大津浪や災厄のもたらしました空気がさまざまに姿を変え形を変えて立ち現れて来る、ある種の、霊の部屋となって来ていたのだった。このことは、アートフェスティバルの会期が終了をしてからも、ほゞ毎月のようにして、三日か四日、そこに戻って行こうとする旅人(わたしくのことですが)の心の挙措(きょそ)、……なんでしょう、みえない運命に導かれるようにしてそこに戻って行こうとしているらしいこと、その“らし、…”によって確実に察知することが出来るものだ。「霊の部屋」とは、フランスの詩人Charles Baudelaire(1821-1867)の作品で、詩人の社会における孤獨を、ほゞ完璧に表現した傑作だったのだけれども、ここでは、このホテル「さか井」の二〇六号が、街角とも往来ともいえない、みなさんの吐息、溜息、言葉になりにくい、白い雲か煙が、棚引く、そうした「霊の部屋」となって行った。そこで絶えず、お客様をお迎えする人の心持ちの推移、変幻は察していたゞけることだろうと思います。たゞでさえ、孤獨がちで幻想的な「詩人の家」が、こうして、共同の、……“共同”という言葉を使いたくないと思いつつ、……そう、“まったくことなったそれぞれのともに、……”という言葉というのよりも、“口舌(くぜつ)”が、口を衝(つ)く。そうすると、夢見も、無意識も、白い煙の姿のようになって参ります。これはもう、この六月の最終校正に近いときでしたのですが、詩集『<Voix>』とともに、心血を注ぐようにしておりました新書(講談社、現代新書『詩とは何か』二〇二一年十一月刊予定)の「序」の何度かの手入れのときに、このときも、このホテルさか井の二〇六号室だったのですが、こんな言葉の湧き方あるいは言葉の小さな噴水に、書き手も、驚いてしまっていたのです。こうでした。 (以下、校正原稿より引用) 「詩」は、思いがけないところで、煙か白雲のように、不図、その姿のようなものをあらわすことがあります。ごく最近の経験を申し上げてみたいと思いますが、三年程をかけまして、石巻のホテルの一室に籠もって綴りました詩を、詩集(Voix<ヴォワ>)として、上梓をしようとして最終校正をいたしておりました。二〇二一年の六月のある日のことでしたが、どうもここは、イメージになっていないし、弱いな、消そうかしらという内心の囁きが聞こえてしまったのかも知れません。女川(おながわ)で大津波に逢われた方のお心が、ホテル(ニューさか井二〇六号室)の一室の通気口から入ってこられる一夜、……というところで、そうだ、思いのようなものが、白い煙か白雲のようにこの部屋に入ってきたというところで、詩人(作者)」の心にもまた、白い煙か白雲の一筋のような詩の姿形が入って来ていました、……この弱く、儚(はかな)い、白雲か煙のようなものこそが「詩」の姿形の一端であると気がついたことがありました。「純粋言語」とか「根源」とか、ひち面倒ないい方から漏れていってしまいますもの、漏れていってします、弱いもの儚いもののすぐ傍(そば)にこそ、詩の出入口があるようなのです。そしてこの「漏れる」ということからは、「音楽」にも「絵」にも、あるいは思考にもとどくような小径が、ふと、現れて来るのかも知れません。 (引用、ここまで) こうして、おそらく、白い雲か煙の筋か精のようなものの姿に添うようにして、詩集に喩が、未知の心の芯のようなものが登場をして来ていたのです。 イ(i)の樹木(き)の君が立って来ていた 「イ(i)」は、アイヌの方々のとても大切にされている髭箆(イクパスイ)からの信号か知らせのようなものであったのかも知れません。北の親友(とも)たち(中森敏夫氏、中川潤氏、木ノ内洋二氏)に感謝の心のこめて、ご報告をし、なければならない。ホッカイドーを“根(ね)の邦(くに)”と呼んだことがあった。知里真志保さんを先頭に、この未知未聞の深い魂の在りどころからの、この一行、 イ(i)の樹木(き)の君が立って来ていた が、不意に、襲なり合う、白い雲か煙の下(シタ)や傍(ソバ)から、…何か「位置」や「空間」が判然とはしないのだが、そして、「声音(こわね)」といっても、あるいは英語の“gh”(無音=サイレント)の小脇の吐声のようなものであったのかも知れなかった。その背後に隠れている、小さな妖精のような“i”からの信号(“しるし”のようなもの)であったのかも知れなかった。判らないのです。ある程度までは、作者(詩人)にも説明は叶います。しかし、芯(シン)は朧(オボ)ろだ、…。 もしかしたら、いま綴ったばかりの“芯(シン)は、朧(オボ)ろだ、…”は、いつも手にしている鉛筆や“ball-point pen=小鋼球ペン”の小声、あるいはさらに「絵筆」領域を拡げていうことが叶うならば、左手に支えるようにしている“video camera=ビデオの眼と耳”の呟いている声なのだといえるのかも知れない。わたくしたちの内部言語野は、確実にそこにもとどいているのであって、その“手の触手”の囁きをも聞いているのかも知れないのであって、たとえばこれは燃(も)え滾(たぎ)るようなヴァン・ゴッホについて書かれた論文に引かれていたのだが、“線からじかに読み取れるような生の方向にむかってすすんで”といいながら、Jean-Clet Martin=ジャン=クレ・マルタンはヘーゲルの次の言葉を引用していた。これは「書」に親しんでいる東洋の人の心にとどくような考えの刹那なのではなかったのだろうか。ヘーゲル曰く「いわば全精神が手の中に移行するといった奇跡」と。(『物のまなざし』大村書店、二〇〇一年刊、一一四頁)このことを、若き日の吉本隆明氏にもみて、一心に綴ったのが『根源乃手』(響文社、二〇一六年刊)と『怪物君』(みすず書房、二〇一六年刊)であったといえるのだ。そしていま、こんなこれも奇跡のようなときの到来に接して考えていると、“芯(シン)は、朧(オボ)ろだ、…”の何処から聞こえて来るのかは判然としない、この囁き声は、思い切って、これは“万物が触れること=touch or touching”あるいは“万物が触れるとき=the time of touching”といってみたいという心のうごくところ、働くところにまで、小文はたどり着いたものらしい。そしてこの“芯=core”は、W・B・イェイツの“心の芯=heart core”の掠れたような小声からとどいているものでもあったのだ。 「技術」「作法」「様式」それらの古きことから、あたうるかぎり、遠く離れたところに「創る」場所を、創ること、それをこの”芯(シン)は、朧(オボ)ろだ、…”が伝えて来ている、そうして、これは、そう、…“誕生しつつ、誕生していること=be borning and already arrived”なのかも知れないのであって、ここまで、こうして綴ってみると、もう、“途上にあるもの=the things on the road”“未完成=unfinished”ということも出来ないのだ。 小文の冒頭に“後述します”と申しました“emotion=エモーション)について。このことは、吉成秀夫氏、コトニ社の後藤亨真氏によるU-Tube配信の最近作で気がつかれた方もいらっしゃることでしょうが、わたくしは所謂コンピュータ難民なのですが、あらためて、あるいは初めて“/”=“slash=スラッシュ”を、激しく、ほとんど無意識が怒りこめて発語をしていたのでしょうか、その“slash=スラッシュ)”=“さっと切る”力の深さの顕現に驚き、そして、次の刹那、五十年もの昔、若年のわたくしは“.ᐟ”=“exclamation=絶叫をする”を、連発をして、識者の顰蹙(ひんしゅく)を買っておりましたことに、その刹那のようなところに、戻って来ていたのです。 吉増剛造 詩集 『Voix(ヴォワ)』 |
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |
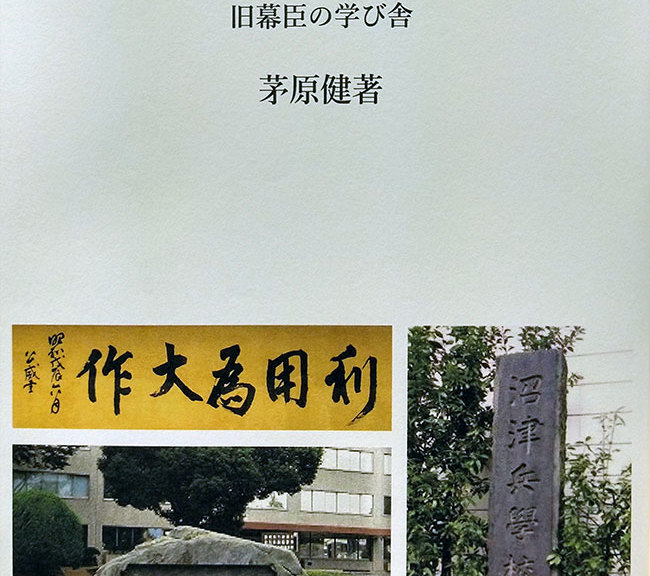
「敗れし者の静かなる闘い」について
「敗れし者の静かなる闘い」について茅原健 |
| 我が家の家系を辿ると、曽祖父から流れている旧幕臣という素性意識がわだかまっている。これは、時代錯誤といわれるかも知れない。しかし、戊辰戦争に敗れて虱だらけになって帰還した曽祖父の無念を継いだ祖父は、旧幕臣の系譜にこだわり、薩長の栗は喰まないという気概を秘めて東北に流れて、その地方新聞に筆を執り、「東北に平民政治を」という論調を掲げた。 その末裔に連なる者としてやはり曽祖父、祖父の衣鉢を継がねばならない。それに、時代は変転し、その有り様は違うが、昭和ヒトケタ生まれの者が経験した日本の敗戦は、まさに敗者であった。いくさが終った訳ではない。いくさに敗けたのであるあとがきに添えた拙句の「疎開地や米食へぬ日々敗戦忌」は、疎開地での東京者の生活は惨憺たるものであったことを伝えるとともに、その敗者の心理を戊辰戦争で敗者となった旧幕臣の心情に重ねて詠んだつもりである。 その戊辰敗者が、覇権奪還という大掛かりな企みではなく、敗者の精神的復活を期するために官学教育ではない、私塾教育による人間像を形成するという永劫不変なテーマに取り組んだ。本書は、そこに着目したのである。 静岡学問所や沼津兵学校は旧幕臣の学び舎として典型的な例だが、戊辰敗者の大鳥圭介、榎本武揚など「逆賊」が私塾に掛けた思いは強いものがあった。 とくに「この輩を養成する経費なし」と体よく文部省の役人に断られて官許が得られず、私立学校として設立された商法講習所(現・一橋大学)や工手学校(現・工学院大学)の設立については、渋沢栄一の惜しみない援助があった。
|
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |
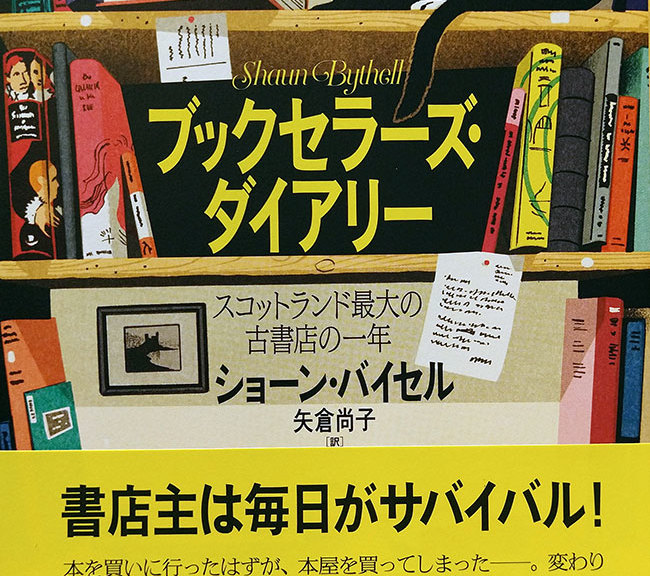
『ブックセラーズ・ダイアリー―スコットランド最大の古書店の一年』
『ブックセラーズ・ダイアリー―スコットランド最大の古書店の一年』矢倉尚子 |
| 翻訳は――人によって違うのだろうが少なくとも私の場合は――どこかの時点で憑依というか、原著者に乗り移ってもらって語り出すことができなければ、満足な仕事にはならない。そこで著者のことばに重なりそうな材料を探し求めて、まず最初に古本を買いまくる。どの資料がいつ必要になるかわからないので、図書館は役に立たない。あちこち歩きまわっている時間はないから、とりあえずはネットで買う。慣れてくると鼻が利いて、これは使えそう、というのがかなりの勝率で当たるようになる。
だから私の周囲に積み上げられた本は、本来の趣味嗜好とはあまり関係がない。4年ほど前に訳した小説に実験用のチンパンジーが登場したときは、机のまわりに霊長類研究の本が散乱し、どちらを向いても表紙のチンパンジーと目が合った。その前はイランの現代史や古典が並んだ。今回はいみじくも古書店主の日記を訳すことになったため、手始めに日本の古本屋さんが書いた古本を買い漁った。 バイセルの店、その名も「ザ・ブックショップ」は、スコットランド南部の海岸に面したウィグタウンという美しい小さな町にある。ここは1999年に厳正な審査を経て選ばれた、スコットランド政府指定の「ブックタウン(古書の町)」である。人口1000人足らずの町に古本屋が少なくとも16軒、他に書籍や美術関係のさまざまなビジネスがあるそうだ。 日記はいかにもインテリ英国人らしいひねくれたユーモアで、客やアマゾンとの駆け引きが面白おかしく書かれているのだが、このバイセル氏、本の町ウィグタウンの発展を支えてきた中心人物でもあるらしい。ちょうどこの原稿がウェブに載るころにはウィグタウン・ブックフェスティバルが開催されているはずだ。これをヨーロッパでも指折りの魅力的なイベントに育て上げたのも、彼の力が大きいという。 今回私が訳した日記にはほとんど触れられていないけれども、さまざまなブックタウン構想の中でも大成功を収めているユニークな企画が、Airbnbの「オープンブック」である。キッチン付きの洒落たワンベッドルームのアパートに最短1週間から最長2週間まで、2人で1泊約1万円で滞在できるのだが、じつはこの部屋には1階に自由に使える本屋がついている。つまり1~2週間の古書店主体験ができるわけだ。条件は、週に35時間以上店を開けること。もともと寄贈された本がたくさん置いてあるが、もちろん自分で持ち込んだ本を売ることもできる。作家やアーティストが自分の作品を売ることも多いという。ただし報酬はなく、利益は運営団体への寄付となり、維持費に使われる。 タイムズ紙などの記事によると、ヨーロッパやアメリカ、カナダなどで大型書店を経営している人が昔の小さな店を懐かしんでやってきたり、逆に新しく書店の開業を考えている人が、体験学習の場として訪れることもあるらしい。もちろん、一生に一度でいいから本屋をやってみたかったという人も多い。地元の人たちはみな親切で好奇心旺盛で、つぎつぎに店を覗きにきたり食事に誘ってくれたりするようだ。あちこちのメディアに取り上げられたおかげで、ヨーロッパ全土どころか南北アメリカ、アジアからも、本屋になりたい滞在希望者が殺到して、現在は3年先まで予約が埋まってしまい、ウェイティングリストに登録するようになっている。 じつはAirbnbのサイトでオープンブックを検索してみたとき、最初に現れた口コミ(もちろん体験者の)が日本人女性だったのには驚かされた。韓国や中国からは、ビジネスモデルを教えてほしいという問い合わせが相次いでいるそうだ。このアイデアを日本でも試みれば、町おこしの絶好の目玉アイテムになるのではないだろうか。体験してみようと思う方は、今すぐにもウェイティングリストに登録することをお勧めする。
|
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |
第33回 退屈男さん ちょっとずつ「本の世界」に関わるひと
第33回 退屈男さん ちょっとずつ「本の世界」に関わるひと南陀楼綾繁 |
| この連載は、古本や古本屋と自分なりに付き合ってきた人に話を聞くことを目的としている。インタビューの場では、その人の話を引き出すために、私自身の体験を話すこともあるが、文章にまとめる際には極力カットしている。 しかし、以前からの知り合いだとそれがやりにくい。つい、自分の思い出を通して、その人を描いてしまう。相手と私を切り離して書きにくいのだ。だから、数人の例外を除き、旧知の人はなるべく外している。 最終回に退屈男さんに出てもらったのは、最後にプライベートな友人の話を聞いてみたかったからだ。その話の中には当然、私も出てくる。友人と云っても、一回り以上年下で、ふだんは「退屈くん」と呼んでいるので、ここでもそう書かせてもらう。 2004年6月にはじまったブログ「退屈男と本と街」は、新刊書店や古本屋をめぐって買った本の話を書くという点では、ほかの本好きによるブログと変わらない。しかし、取り上げる本の雑多さと、それにまつわる情報の豊富さでは突出していた。 この第1回一箱古本市で、退屈くんは自転車で走る私を目撃しているが、会話は交わさなかったように思う。はじめて話をしたのは、この年9月、私が谷中で開催した「一部屋古本市に、退屈くんが参加したことだった。「こんなに若いのか!」とびっくりしたことを覚えている。日は違ったが、このイベントには当時は「書物奉行」と名乗っていた書物蔵さんも参加している。 1982年、新潟県小千谷市に生まれる。当時は祖父母、父母、2つ下の妹の6人家族。父は市役所に勤めていたので、家の本棚には行政の実務書ばかり。文学全集は屋根裏に眠っていた。 小学生では宗田理の「ぼくら」シリーズやスニーカー文庫などのライトノベル、中学生になると夏目漱石や太宰治、藤沢周平や山田風太郎などの時代小説も読んだ。しかし、小説よりはノンフィクションの方が好きで、中公新書や講談社現代新書の歴史ものを読んだり、山際淳司や近藤唯之のスポーツもの、現代教養文庫で佐高信が監修して復刊したノンフィクションの名作を読む。 2000年、法政大学二部(夜間)に入学する。父が公務員であることや、高校のとき岩波文庫で『石橋湛山評論集』を読んだことから、政治学科を選ぶ。昼間はゴルフ練習場やコンビニでアルバイトして、夕方から授業に出た。 在学中、先に書いたようにブログ「退屈男と本と街」を開始した。 卒業後の退屈くんは、神保町の〈三省堂書店〉でアルバイトをする。知らない本が見られるのが面白く、古本屋に近いのもよかった。その頃、若き日の母親が、神保町のすぐ隣の神田三崎町にあった製本工場で10年間働いていたことを知った。「(近くにあった喫茶店の)〈エリカ〉はまだあるの?」などと聞かれ、驚いた。近代映画社の『スクリーン』などを製本する会社だったという。 本好きではあるけれど、モノとしての本にはそれほど興味がなく、電子書籍で読むことも多い。以前は部屋が本だらけだったが、引っ越しをするたびに処分して、いまは本棚に収まるだけしかない。 この文章を書くために、久しぶりに「退屈男と本と街」を開いてみたら、まだ本人と会う前の2005月1月に「二〇〇四年の五冊」という記事が見つかった。私の最初の単行本『ナンダロウアヤシゲな日々 本の海で溺れて』(無明舎出版)について書いている部分を、気恥ずかしいが引用する。
南陀楼綾繁 ツイッター
※ご好評いただきました『シリーズ古本マニア採集帖』は、今回を持ちまして終了します。連載のご愛読ありがとうございました。 |
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |