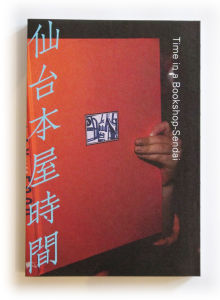コロナ禍古本屋生活1火星の庭 前野久美子 |
| 新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが発生し、非日常が日常になって久しい。かつて、わたしの店ではトークイベントやライブを開催し、店内は多くの人で賑わっていました。それも遠い昔のようです。今は、静かになった店内でお客様から買った本をきれいに拭いた後、値付けをして棚に並べるといった古本屋の仕事を続けられることに感謝の日々を過ごしています。 そうした中、違和感を感じるときがあります。コロナの自宅療養者は全国で60,532人に上り(厚労省サイト2021年9月17日現在)、こうしている間にも誰にも看取られずに亡くなる人、必要な医療を受けることができずにいる人のことをふと思い浮かべるときです。「もし瓦礫の下に6万人が生き埋めになっていたとしたら、すぐにも救助するだろうね」と友人が言っていました。自宅療養者という言葉の陰でリアルなイメージが描けないからなのか、多くの人が自分たちが過ごしている日常とパンデミックの深刻さのギャップを埋めるのが難しいと感じています。この感覚は東日本大震災のときに感じたものとどこか似ている気がします。あの頃もいつも通り店に立ち、古本を売りながら、10数キロ先で起きた大津波、80キロ先で起きている原発事故が、現実のものと思えずにいました。 わたしが住む仙台市は東北では新型コロナウイルスの感染者数が最も多く、昨年の流行が始まると、県外はもとより市外の人からも「仙台に行くのはちょっと」という声が聞こえるようになりました。コロナ以前、店には週末になると県外から多くの方が訪れていました。岩手、山形、福島などに加え、首都圏をはじめ関西や沖縄からも来店がありました。ときには台湾、韓国、中国、欧米など外国からのお客様もいらしていました。 中には、後日再び立ち寄ってくれる人もいて、「友人に火星の庭の話をしたら」などと後日談を聞かせてくれたりもします。そのおかげでこの狭い古本屋は思いがけないほど、広い世界と接することができました。それらはすべてお客様との出会いを通して作られた世界だったのだと今になって気がつきます。 しかし、悪いことばかりではありません。2020年の春、宮城県にも緊急事態宣言が発令されて、古本は不要不急ということになり、古本屋に休業要請が出され3週間店を休業することになったときのことです。休業する前日、常連のお客様がやってきました。お会計のときに、「明日から休むことになりました」と伝えると、さっと顔色が変わったのです。いつもじっくり本棚を見られて、だまって本を買っていかれる方です。その日、帰り際にドアまで近づいたところで急に立ち止まり、こちらに背中を向けたまま、「困るんだよ、古本屋に休まれると。行くところがなくなるから!」と叫んだのです。一瞬のことでした。そして、足早に去って行かれました。予想外の出来事に茫然としつつも「辛いのは店主だけじゃないんだ。いや店主は休業中も店に来れるじゃないか。ドアの鍵を閉めてしまったらお客様は入ることはできない。その方が辛いのかもしれない」、そんな思いが頭に浮かびました。お客様の「困るんだよ!」という声がいつまでも店内に反響しているようでした。 昨年4月の休業要請以降は、定休日以外は休まずに営業しています。売り上げは戻りませんが、閉店後にその日いらしたお客様の顔を思い浮かべて、以前より地域の古本屋であることを実感する日々です。そうした中でもときに県外からのお客様が立ち寄ってくれることがあります。お客様すべてと会話するわけではありませんが、中には声を潜めて「実は◯◯県から来たんです」とこっそり語ってくれる人もいます。 見方によれば、コロナ禍の今は店を閉めオンライン販売だけにした方が、感染防止の上でも経営的にも正しいのだと思う。でも、古本屋がなくてはならない場所になっている人もいます。そういう人のためにもお店を続けようと思います。お店を開けるかどうかは、自分だけの問題ではない。あのお客様の叫び声を聞いてから思うようになったからです。小さくなった世界で何ができるだろうか。あらためて考えているこの頃です。 火星の庭ホームページ https://kaseinoniwa.com/
|
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |