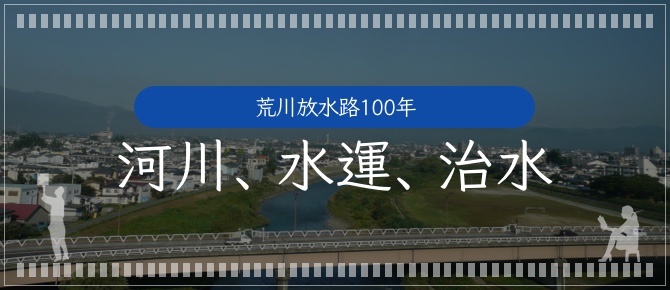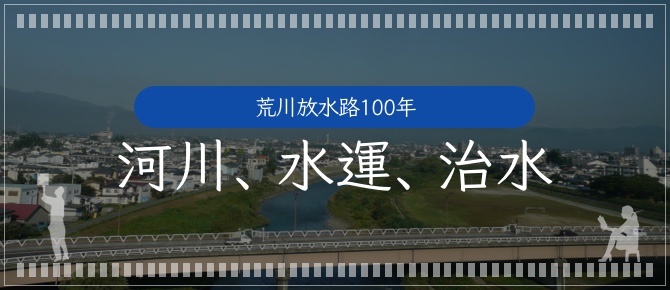-
ホーム
-
特集
-
荒川放水路 100年 - 河川、水運、治水
特集449 荒川放水路 100年 - 河川、水運、治水(2024年11月29日〜2024年12月13日 ホーム掲載)
1924(大正13)年10月12日、岩淵水門完成、放水路への注水が開始。「荒川放水路」とは荒川のうち、岩淵水門から江東・江戸川の区境の中川河口まで開削された人工河川を指す。1910(明治43)年8月、関東地方で長雨が続き荒川(現・隅田川)を含む利根川や多摩川などの主要河川が軒並み氾濫し、死者700人以上に上る関東大水害が発生した。翌年、政府は根本的な首都の水害対策の必要性を受け、利根川や多摩川に優先して荒川放水路の建設を決定。1965(昭和40)年に正式に荒川の本流とされ、それに伴い岩淵水門より分かれる旧荒川全体が「隅田川」となった。それまでは現在の千住大橋付近までが荒川、それより下流域が隅田川と区別されていた。荒川放水路の完成に伴い、それまで地続きだった道路、鉄道などには橋がかけられるので、ルートが大幅に変更されるケースもあった。東武伊勢崎線では、以前は北千住の次の駅は西新井で、駅間が直線的につながっていたが、放水路上に真っ直ぐ橋を架けるために、北千住駅から北東方向に「小菅駅」が、そこから西新井へ向かって「五反野駅」「梅島駅」が計画され、同年10月1日に開業している。
書籍一覧
寺田寅彦と現代 等身大の科学をもとめて
(池内了)