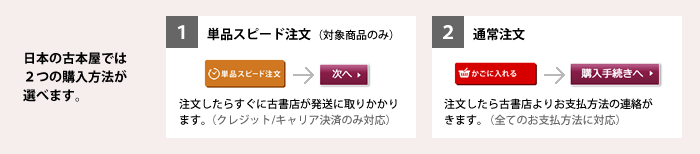S棚2箱
妙心寺 六世住持の拙堂宗朴、足利氏に反旗をひるがえした大内義弘と関係が深かったため、将軍足利義満の怒りを買った。応永6年、義満は妙心寺の寺領を没収して青蓮院の義円に与え、拙堂宗朴は大内義弘に連座して青蓮院に幽閉の身となった。義円は没収した寺領をさらに南禅寺の廷用宗器に与え、廷用は寺号を「龍雲寺」と改めた。こうして妙心寺は一時中絶することとなった。妙心寺が復活するのは永享4年のことである。同年、廷用は微笑塔の敷地をその頃南禅寺にいた根外宗利に与えた。関山慧玄の流れを汲んでいた根外は、犬山瑞泉寺から日峰宗舜を迎えて妙心寺を復興させた。このため日峰は妙心寺中興の祖とされている。妙心寺は応仁の乱で伽藍を焼失したが六祖雪江宗深の尽力により復興。永正6年には利貞尼が仁和寺領の土地を購入して妙心寺に寄進し、境内が拡張された。利貞尼は関白一条兼良女、美濃加納城主斎藤利国の室である。その後の妙心寺は戦国武将などの有力者の援護を得て、近世には大いに栄えた。