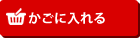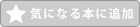- ホーム
- 暢気堂書房
- 弘道館記述義 回天詩史 第2輯 <皇国精神講座> 小林一郎著 昭和16年初版 出版社 平凡社 ページ数 402p サイズ 22cm 藤田東湖 1806-1855幕末期の水戸藩士。尊皇攘夷推進派の巨頭。名は彪、字は斌卿、東湖は号。幼名武次郎、虎之介と称し、のち藩主より誠之進の名を賜る。水戸藩儒官藤田幽谷の子で幼時より文武の修練に励み、父の死後彰考館に入り一時総裁代理となる。藩主徳川斉昭をたすけ藩政改革に尽力。藩校弘道館設立は藩主斉昭と共に成し遂げたものであり、水戸学を振興しその中心人物となった。遺された「弘道館記」は東湖の草案によるものである。安政2年10月に起こった大地震の時、母親を助けようとして逃げ遅れ圧死した。年50。「回天詩史」他著書多し。