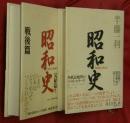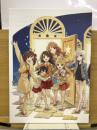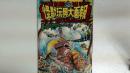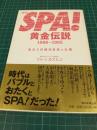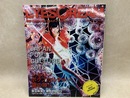- 美術出版社(14)
- 文化学園・文化出版局(8)
- 日本図書センター(7)
- 文芸春秋(4)
- チャイルド本社(3)
- 大修館書店(3)
- 平凡社(2)
- 彰国社(2)
- 春秋社(2)
- 朝日新聞社(2)
- 毎日新聞社(2)
- 鳥影社・ロゴス企画部(2)
- 鹿島出版会(2)
- アクシス(1)
- シナリオ作家協会(1)
- シンコーミュージック・エンタテイメント ウルトラ・ヴァイヴ(1)
- ドメス出版(1)
- メディカルレビュー社(1)
- モリサワ(1)
- 八甲田山植物実験所 (東北帝国大学)(1)
- 共立(1)
- 国際情報社(1)
- 國學院大學綜合企画部(1)
- 大日本雄弁会講談社(1)
- 大阪市自然史博物館(1)
- 婦人之友社(1)
- 学燈社(1)
- 学燈社×2(1)
- 富士書店(1)
- 小学館(1)
- 山口女子大学櫻圃會(1)
- 山繭の会(1)
- 岩波書店(1)
- 建知(1)
- 彩流社(1)
- 扶桑社(1)
- 文化出版局(1)
- 新建築社(1)
- 日本ハウジングセンター建築知識事業部(1)
- 日本図書文化協会(1)
- 日本放送出版協会(1)
- 日本未来派(1)
- 日活株式会社製作配給(1)
- 朝日新聞(1)
- 東京都歴史文化財団(1)
- 東方書店(1)
- 毎日中学生(大阪)(1)
- 海軍機關學會(1)
- 潮出版社(1)
- 潮書房光人新社、光人社(1)
- 石風社(1)
- 誠信書房(1)
- 誠文堂新光社(1)
- 鳳山社(1)
- 鹿島研究所出版会(1)
- もっと出版社を見る
人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に

二〇世紀日本の天皇と君主制
¥4,000
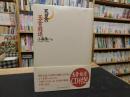
「天皇の玉音放送」
¥900

昭和維新の朝 二・二六事件と軍師齋藤瀏
¥990

天皇七拾年
¥6,800

昭和天皇新聞記事集成 昭和元年~15年
¥7,700
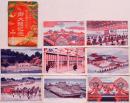
昭和三年十一月 今上天皇御即位式御大禮記念 絵はがき
¥11,000

高松宮日記 全8巻
¥11,550

侍従長の回想
¥6,000

卑弥呼誕生-畿内の弥生社会からヤマト政権へ
¥1,650
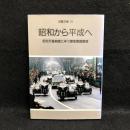
昭和から平成へ
¥18,000

昭和天皇ご家族大判古写真 4枚
¥33,000

昭和史探索
¥2,750

昭和天皇の戦争 <昭和天皇実録> 第1刷
¥2,980

昭和天皇崩御資料 12点一括
¥30,000

サンデー毎日 緊急増刊 昭和天皇崩御
¥1,800

ドキュメント 昭和天皇 1~5巻
¥3,850

昭和天皇 戦後 全3巻揃
¥3,300

目撃者が語る昭和史 全8冊組 全8巻揃
¥4,273
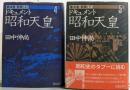
ドキュメント昭和天皇 第4・5巻 敗戦 上下巻セット
¥2,370

伊勢志摩に両陛下をお迎え志て
¥5,300

昭和天皇 写真集
¥3,000

天皇の研究
¥2,500
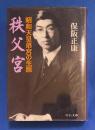
秩父宮
¥2,000
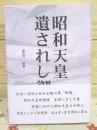
昭和天皇遺されし御製
¥2,000

昭和天皇 第1部 (日露戦争と乃木希典の死) 第1刷
¥2,200

侍従長の遺言
¥5,000
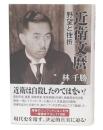
近衛文麿
¥2,480

昭和天皇の秘密
¥2,200

朝日新聞 1989年1月7日号外 天皇崩御 昭和終わる 昭和天皇
¥10,000
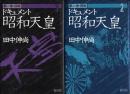
ドキュメント昭和天皇 全8冊
¥9,000

昭和天皇
¥1,830

昭和四年神戸行幸に関する警備警衛関係資料一括
¥253,000

裕仁天皇
¥15,000
コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ
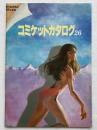
コミケットカタログ 26
¥1,500
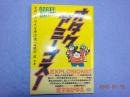
オタクアミーゴス!
¥2,500
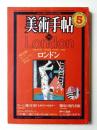
美術手帖 1982年5月号 No.496 <特集
¥1,100

日本人の「男らしさ」
¥7,700

ポップ・カルチャー年鑑2007
¥1,500

12人の作家によるアニメーションフィルムの作り方
¥5,500

マニフィック 昭和54年新年号
¥3,000
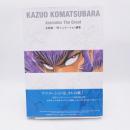
小松原一男アニメーション画集
¥25,000
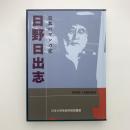
日本のマンガ家 日野日出志
¥7,700
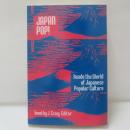
Japan Pop
¥3,300
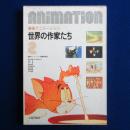
世界の作家たち <講座アニメーション 2>
¥19,800

「秋葉原は今」
¥1,600
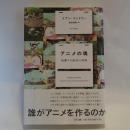
アニメの魂
¥1,200

サブカルチャー文学論 <朝日文庫>
¥4,000

ジ・オウム
¥5,000

日本TVアニメーション大全 テレビアニメ50年記念
¥8,500

特別功労賞 日本のアニメをつくった20人
¥3,000

おたくの本
¥1,000

漫画家・アニメ作家人名事典
¥2,800
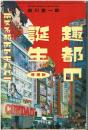
趣都の誕生
¥1,200

アニメーション
¥3,500

ポップ・カルチャー
¥1,000
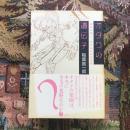
オタクの遺伝子 長谷川裕一・SFまんがの世界
¥1,100

イアン・ビュルマ/訳
¥4,950
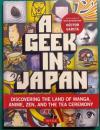
A Geek in Japan
¥500

揃 東映動画長編アニメ大全集 上下
¥6,000

大塚康生インタビュー アニメーション縦横無尽
¥3,000
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.




![[絵葉書] 昭和参年十二月於横浜港外 御大禮特別大観艦式記念](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12010425/20240919133729599339_fbc6959f2345ba04cb04b650be173901.jpg)