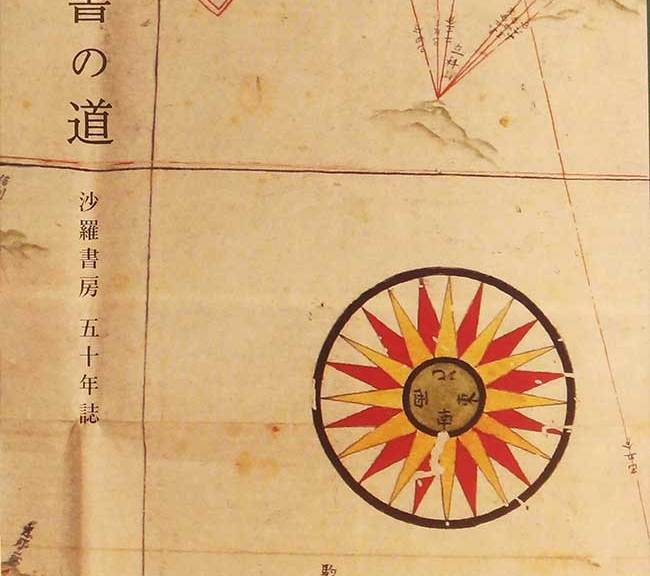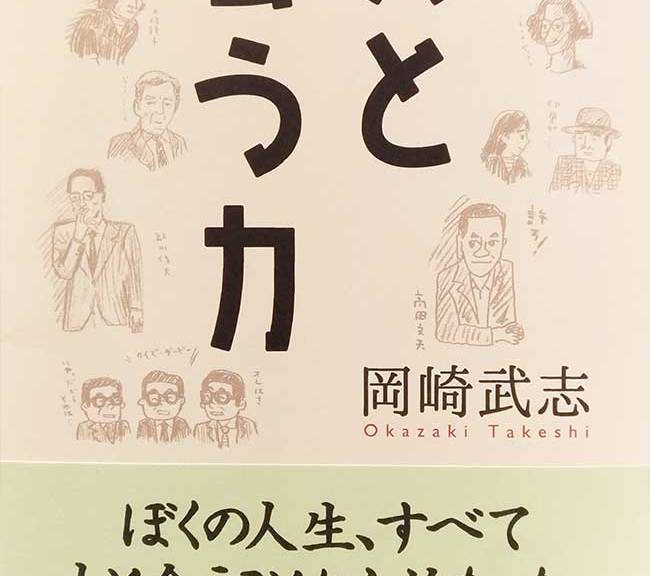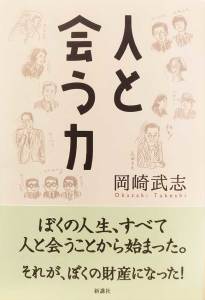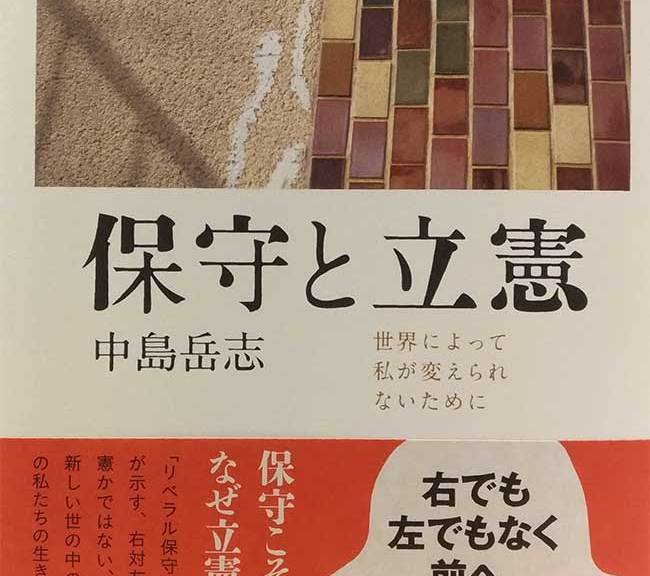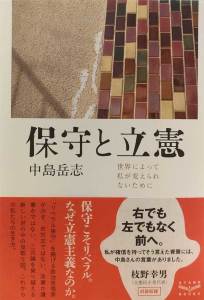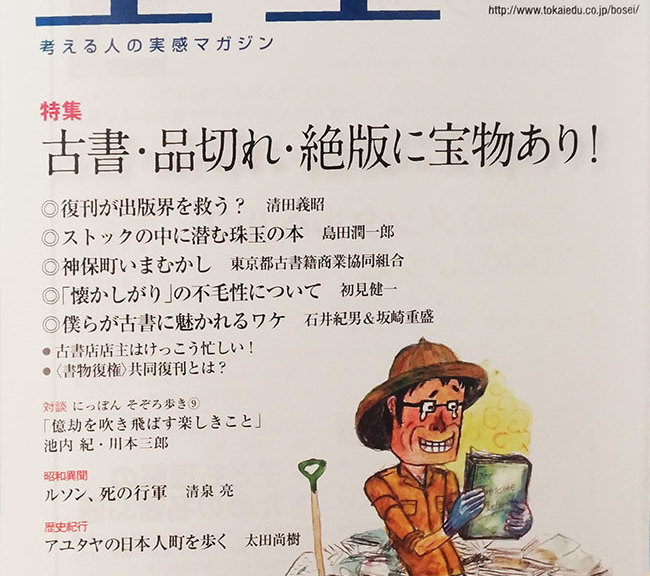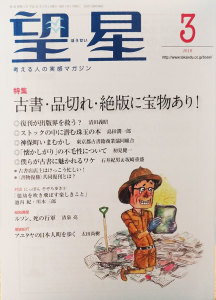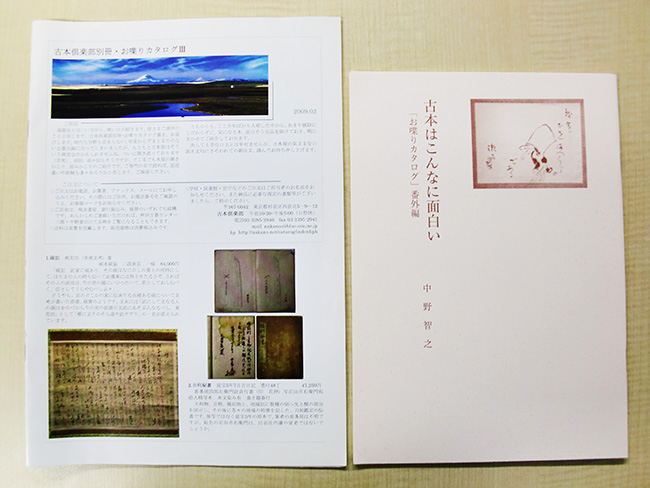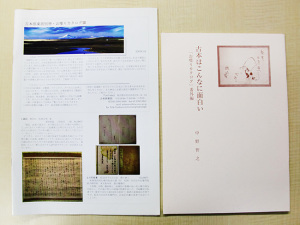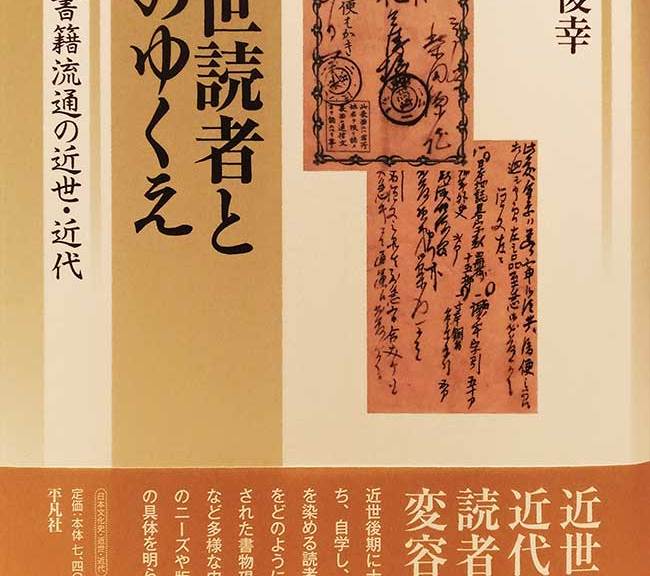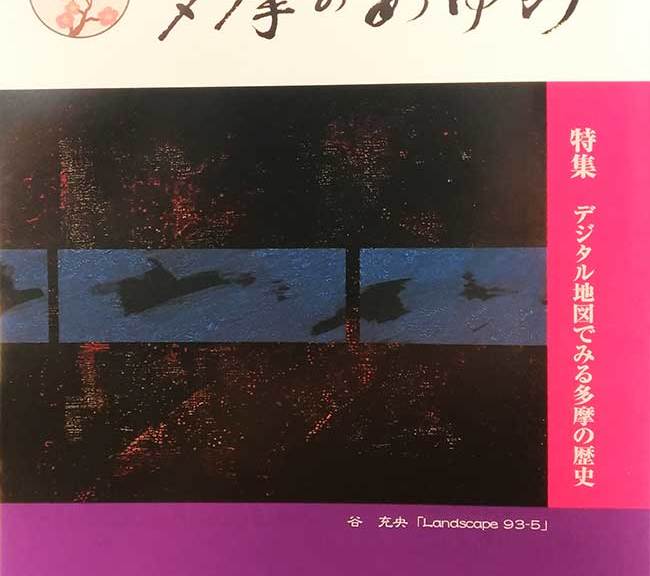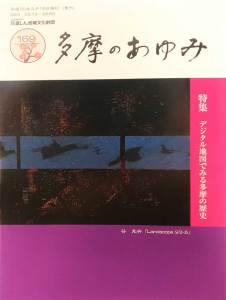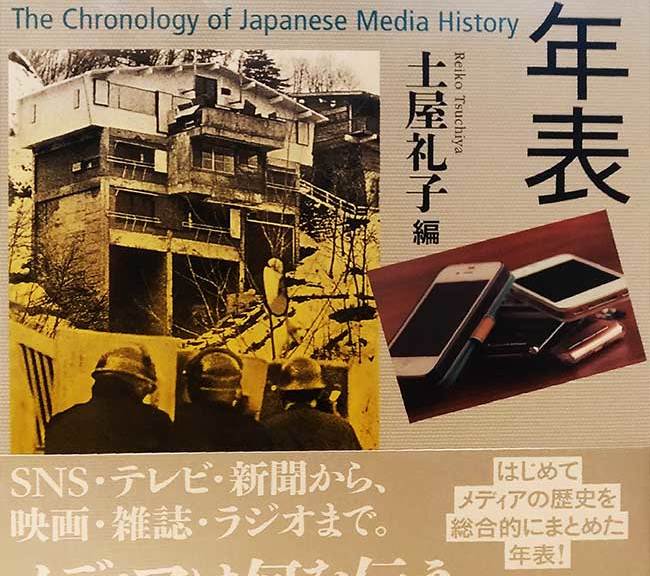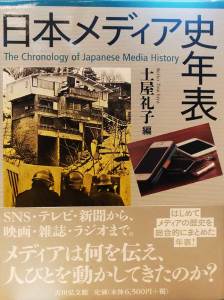■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
。.☆.:* その245・2月23日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆INDEX☆
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
1.『近世読者とそのゆくえ ―読書と書籍流通の近世・近代』
鈴木俊幸
2. (公財)たましん地域文化財団の季刊郷土誌『多摩のあゆみ』
第169号「デジタル地図でみる多摩の歴史」のご紹介
(公財)たましん地域文化財団 歴史資料室 坂田 宏之
3.『日本メディア史年表』について
吉田則昭(立教大学兼任講師)
4.古本屋ツアー・イン・ジャパンの2017年総決算報告
古本屋ツーリスト 小山力也
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
━━━━━━━━━━━【自著を語る(201)】━━━━━━━━━━
『近世読者とそのゆくえ ―読書と書籍流通の近世・近代』
鈴木俊幸
旧著『江戸の読書熱』(2007年、平凡社)で触れたが、書籍その
もの、それを生み出し流通させていくシステム、また大方の書籍へ
の接し方は、江戸時代の後期、19世紀になって大きな変化を見せる。
それは、民間における知の底上げに根ざすものであった。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=3695
『近世読者とそのゆくえ 読書と書籍流通の近世・近代』 鈴木俊幸 著
平凡社 本体 : 7,400円+税 好評発売中!
http://www.heibonsha.co.jp/book/b325541.html
━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━━
(公財)たましん地域文化財団の季刊郷土誌『多摩のあゆみ』
第169号「デジタル地図でみる多摩の歴史」のご紹介
(公財)たましん地域文化財団 歴史資料室 坂田 宏之
私ども(公財)たましん地域文化財団の郷土誌『多摩のあゆみ』は、
昭和50年(1975)11月、当財団の設立母体である多摩中央信用金庫
(現・多摩信用金庫)が店頭で無償配布する「茶の間の郷土誌」と
して創刊されました。以来、2・5・8・11月の各15日発行の季刊誌と
して、東京都の西部に位置する多摩地域の歴史・民俗・地理・自然
などをテーマに、論考や情報などを掲載しています(A5判、毎号120
頁前後、発行部数14,000部)。現在も多摩地域に82店舗ある多摩信
用金庫各店で、無料で入手できます。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=3706
公益財団法人 たましん地域文化財団
http://www.tamashin.or.jp/index.html
『多摩のあゆみ』ホームページ
http://www.tamashin.or.jp/ayumi/index.html
━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━
『日本メディア史年表』について
吉田則昭(立教大学兼任講師)
今日、新聞・テレビなど従来のマスメディアに加え、インターネ
ット・SNSなど、新旧メディアが入り乱れて、メディア大激変の
時代となっている。メディア史は近現代史の一部でもあるが、独自
の領域を持っている。しかし、この自明のことが正面から取り上げ
られることは少なかった。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=3702
『日本メディア史年表』 著者 土屋礼子 編
吉川弘文館 定価:本体6,500円+税 好評発売中!
http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b329681.html
━━━━━━━━━【古本屋ツアーインジャパン】━━━━━━━
古本屋ツアー・イン・ジャパンの2017年総決算報告
古本屋ツーリスト 小山力也
すでに2018年がスタートして二ヶ月が経ってしまったが、遅れば
せながら2017年を一言で言い表すと、『どうにか乗り切った一年』
が相応しいだろう。結局上半期にボヤいていた『遠出が出来ない状
況』が、ズルズルと一年間続いてしまった。恐ろしいことに地方に
行けたのは、十一月に目黒考二氏とのトークイベント開催に便乗し
て乗り込んだ、愛知・中京競馬場前「安藤書店」(夕方に早くも沈
み込む街の駅前で輝く、深い棚造りに長けた良店であった)の一店
だけであった。その他のおよそ364日は、東京周辺の古本屋さんを巡
りまくり、ウダウダダラダラと古本を買って過ごしていたのである。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=3714
小山力也
2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売ってい
る場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン
・ジャパン』管理人。「フォニャルフ」の屋号で古本販売に従事す
ることも。古本屋に関する著書ばかりを出し続けており、それらの
出版社や形状は違えど、全部を並べたらいつしか“日本古本屋大全
集”となってしまうよう、秘かに画策している。「本の雑誌」にて
『毎日でも通いたい古本屋さん』連載中。
http://furuhonya-tour.seesaa.net/
━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━
沙羅書房 創業50周年記念誌 『古書の道』
1冊 2,500円 送料込
http://www.sara-shobo.com/news/20170623.html
『望星』3月号 古書・品切れ・絶版に宝物あり!
株式会社東海教育研究所 本体556円+税 好評発売中!
http://www.tokaiedu.co.jp/bosei/
━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━
2月~3月の即売展情報
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=22
┌─────────────────────────┐
次回は2018年3月中旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその245 2018.2.23
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:小野祥之
編集長:藤原栄志郎
==============================