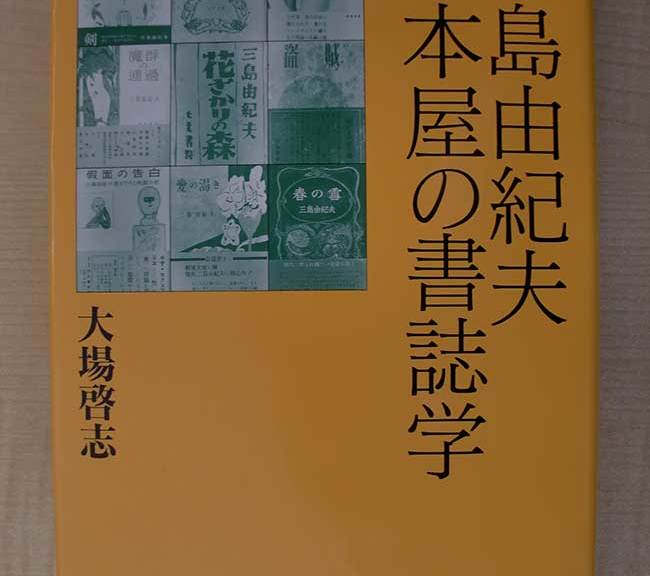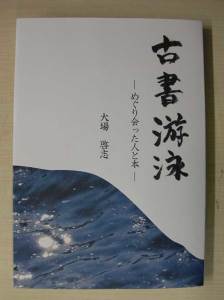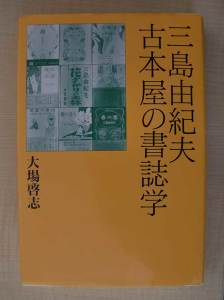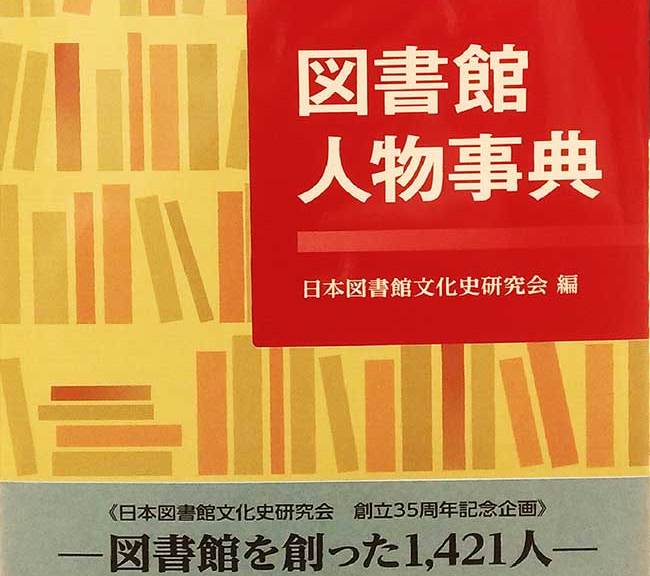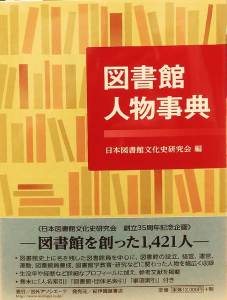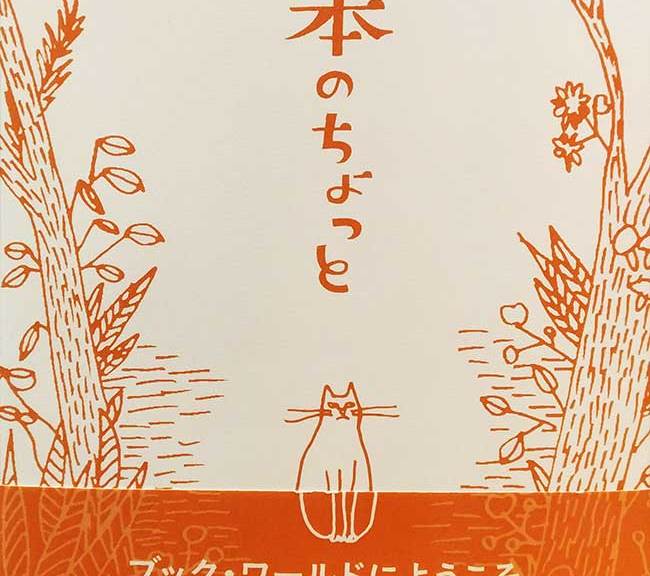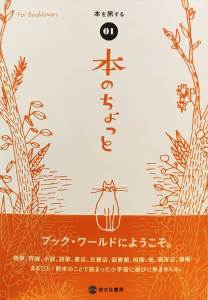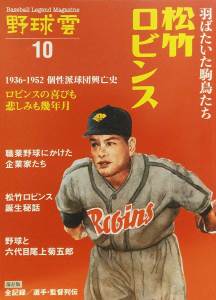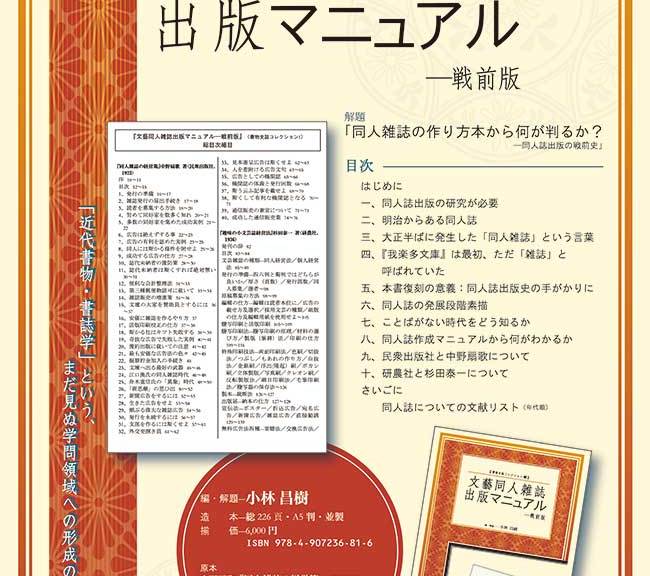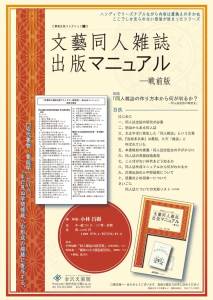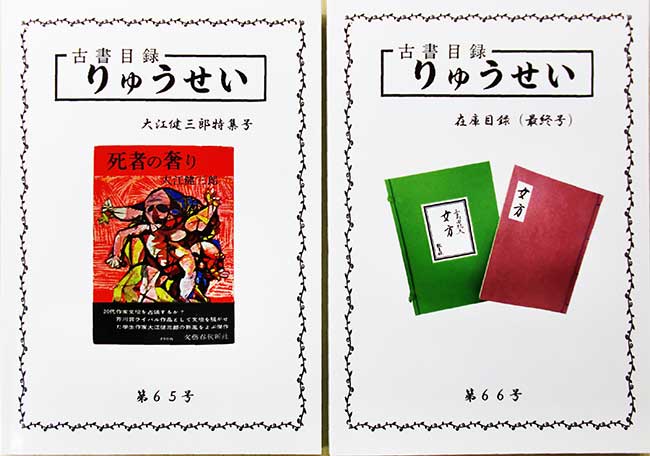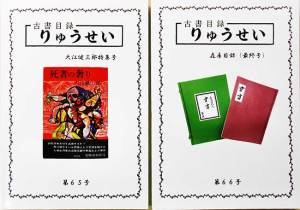古本屋ツアー・イン・ジャパンの2017年総決算報告古本屋ツーリスト 小山力也 |
|
すでに2018年がスタートして二ヶ月が経ってしまったが、遅ればせながら2017年を一言で言い表すと、『どうにか乗り切った一年』が相応しいだろう。結局上半期にボヤいていた『遠出が出来ない状況』が、ズルズルと一年間続いてしまった。恐ろしいことに地方に行けたのは、十一月に目黒考二氏とのトークイベント開催に便乗して乗り込んだ、愛知・中京競馬場前「安藤書店」(夕方に早くも沈み込む街の駅前で輝く、深い棚造りに長けた良店であった)の一店だけであった。その他のおよそ364日は、東京周辺の古本屋さんを巡りまくり、ウダウダダラダラと古本を買って過ごしていたのである。もう二三年前の、週に一度は地方にあっちこっち飛んでいた状況とは、月とスッポンである。そんな無茶なことが可能だったのはとてもスゴいことであり、それが出来ない今はやはり寂しくもある…だがこういう時は無理にあがいてもどうしようもないので、『待てば海路の日和あり』と、出来ることをしながら、また地方を飛び回れるようになることを、虎視眈々と忍び待つしかないのであろう。 それに決して負け惜しみではないのだが、このスッポンもなかなか良いものなのである。当然行ったことのあるお店への再訪再々訪がほとんどなのだが、古本屋に行くというよりは、古本を買うということに重心を移すと、今までとはまた違った景色や棚の様相が立ち現れてくる。なんたって首都圏は、神保町・早稲田・中央線沿線を中心に、全盛期より数を減らしているとは言え、まだまだ古本屋さん的にはとても恵まれた状況にあるのだ。おかげで前期に報告した「バリケード・一九六六年二月/福島泰樹」「探偵小説 幽霊塔/江戸川乱歩」「10・21とはなにか」「魔法入門」「団地七つの大罪」に加え、後期には寶文館「黄いろい楕圓/北園克衛」を500円で、筑摩書房「幸福論/小山清」を3000円で、暮しの手帖社「暮しのなかで考える/浦松佐美太郎」を100円で、磯部甲陽堂「幽霊探訪/大窪逸人(山中峯太郎!)」を300円で、博文館文庫「スミルノ博士の日記/S・A・ドゥーゼ」を100円で見つけたりして、ブックハントを存分に満喫する。やはり古本屋さんや古本市には、わざわざ足を運ぶ価値あり!の思いを強くする掘出し物体験であった。 そして最近は、今までとは違った形で古本屋さんにアプローチすることも増えて来ている。西荻窪の「盛林堂書房」では『盛林堂イレギュラーズ』と称し、買取バイトに同行させてもらっている。主に本の束をひたすら運ぶ下働きが中心だが、お店では決して見られぬ古本屋さんの仕事や、人様の棚や書庫が見られるのは、とても刺激的な体験である。その様子は買取先に許可をいただいた上で時々ブログ上で公開しているのだが、ミステリ評論家の新保博久氏と日下三蔵氏のレポートは凄まじいものになっているので、ご一読していただければ幸いである。他にも「古書音羽館」で一日バイトをして、補充しっ放しの店頭棚の人気の秘密を知り、「@ワンダー」の地方買取バイトでは、山越えでトランクのタイヤがバーストし、本の重さの恐ろしさを知る。また、特殊古本屋「マニタ書房」・とみさわ昭仁氏と特殊翻訳家・柳下毅一郎氏とアダルトメディア評論家・安田理央氏の三人が時たま行う『古本せんべろツアー』に同行させていただいている。これは午前のうちから飲み屋に集合し、古本屋と飲み屋を夜の八時くらいまで訪ね歩く、まるで天国のようだが最終的には地獄のように酒精に溺れる古本屋巡りである。いつも酔い過ぎないよう気をつけているのだが、アルコールが入っていると気が盛大に緩んで大きくなり、ついついたくさん古本を買ってしまうのが恐ろしいところである。 そんな風に古本屋を訪ね回り、血眼で安値の良本を探しながら目撃したお店の開店&閉店を列挙してみよう。言祝ぐべき開店は、下北沢の「古書明日」、駒込の「BOOKS青いカバ」、八王子の「古書むしくい堂」、曙橋の「おふね舎」、みのり台の「smoke books」、新小金井の「古本・雑貨 尾花屋」、吉祥寺の「一日」、とうきょうスカイツリーの「書肆スーベニア」、三軒茶屋の「Cat’s Meow Books」、豪徳寺「nuibooks」、黄金町「9Bricks」。そして悲嘆すべき閉店は、神保町「澤口書店 小川町店」、戸塚「ブックサーカス 戸塚モディ店 トツカーナ店」、武蔵関「古本工房サイレン」、新中野「プリシラ古書店」、上田「斉藤書店」、鎌倉「ウサギノフクシュウ」、渋谷「巽堂書店」、早稲田「谷書房」。もちろん東京近辺の狭い地域の話なのだが、開店数と閉店数が微妙に拮抗しているのが不思議なところである。そして開店する新店の名を見れば一目瞭然なのだが、正統派な『~書店』『~書房』などは見当たらず、奇妙な名の割合が高い。つまりは新世代の古本屋さんが増えて来ているのである。 そして今年で古本屋を勝手に調査するブログ『古本屋ツアー・イン・ジャパン』が、活動を開始してから十年目に突入している。我ながら良く続いて来たものだと思う。その節目と言っては何だが、二月には二千冊の古本を家から運び出し、「古本屋ツアー・イン・ジャパン大放出市 2DAYS」を行い、十月には恥ずかしながら「さすらいの十年展」と銘打ち、東京古書会館の情報コーナーで記念の展示を開催した。もはや完全に古本と古本屋さんとは、切っても切れぬ強力な縁で、人生ががんじがらめにされている。そう覚悟して、今後も古本屋さんには思いっきり関わって行く所存である。その手始めに、東京古書籍協同組合とささやかなリーフレットを作ったり、盟友・岡崎武志氏と今年も楽しい古本屋本を作り上げたいと考えている。 かように活動は色々変容しながらも、大好きな古本屋さんへの旅は続いて行く。もうすぐ春ですが、今年もよろしくお願いいたします。
|
|
Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |