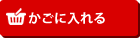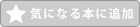- ホーム
- 暢気堂書房
- マルクス主義の解縛──「正統的な科学」を求めて 千石好郎マルクスが復活しつつある今だからこそ日本の左翼を呪縛してきたマルクス主義の根本的検討が必要である。分化理論によって現代社会を分析する。2009年1月16日刊行A5判 上製 272頁 マルクス主義の解縛──「正統的な科学」を求めて:目次まえがき序章 マルクスの革命論は、なぜ時代遅れになったのか 第1節 1882年の「『共産党宣言』ロシア語第2版の序文 第2節 マルクスのアメリカ論 第3節 マルクス革命論の空想性 第4節 マルクスからレーニンへ第1部 レーニン主義とは何だったのか 第1章 レーニンの諸実践の再検証 第1節 「未完のレーニン」か、「グッバイ・レーニン」か 第2節 レーニンの政治的実践をめぐる事実認定をめぐる諸問題 第3節 レーニン主義の本質 第4節 今後の課題 第2章 レーニン『何をなすべきか』の逆説 はじめに 第1節 『何をなすべきか』の骨子 第2節 ロシア革命以前における危惧 第3節 ロシア革命以後の告発 国家社会主義社会の実体 第4節 「新しい階級」論の普遍化を目指して 終 節 三者の予測と暫定的結論第2部 ポスト・マルクス主義の先駆者ダニエル・ベル 第3章 初期における政治的立場と理論的パラダイム 第1節 ダニエル・ベルの経歴と業績 第2節 初期ベルの政治的立場と理論的パラダイム 第4章 中期におけるポスト・マルクス主義の模索 第1節 模索の過程 第2節 アメリカ・マルクス主義運動の内在的総括 第5章 マルクス社会理論に対する全面的対決 第1節 後期ベルのマルクス批判 第2節 マルクス理論形成史に対するベルの見解 第3節 ベルのマルクス理論批判の概要 第4節 マルクス未来社会像 第5節 ベルのマルクス評価の最終結論第3部 唯物史観の再検討 第6章 アンソニー・ギデンズの「史的唯物論の現代的批判」