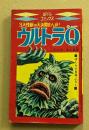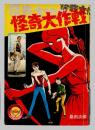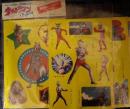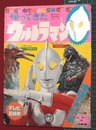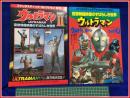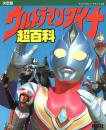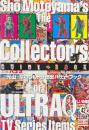ウルトラQ60年 - 特撮、SFドラマの魅力

こいでのえあわせ ウルトラマンA
¥3,000

テレビマガジン平成元年8月号増刊 ウルトラマン大特集号
¥4,400

戦後ヒーローの肖像
¥3,000

写真集 特技監督 円谷英二
¥6,000
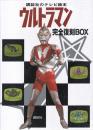
講談社のテレビ絵本 ウルトラマン 完全復刻BOX
¥12,000
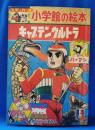
ステッカー版 小学館の絵本 キャプテンウルトラ
¥15,000

新案カード ウルトラマン図鑑 楽しい幼稚園 ウルトラ怪獣絵本51
¥28,000
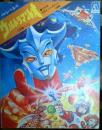
ウルトラマンレオ (レコード)
¥5,090

ウルトラマン・クロニクル
¥9,000

ウルトラQ伝説
¥5,800

ウルトラマン ウルトラセブン/大怪獣 カード
¥15,000

ウルトラマン大辞典 <ウルトラマン (テレビドラマ)>
¥3,000
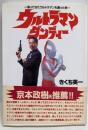
ウルトラマン・ダンディー
¥5,000

続ウルトラマン大百科 <ケイブンシャの大百科 39>
¥3,000

ウルトラマンR/B超全集 【てれびくんデラックス愛蔵版】
¥5,500

怪獣絵ばなし 2 【「ウルトラセブンの歌」フォノシート付】
¥11,000

怪獣少年の〈復讐〉 70年代怪獣ブームの光と影
¥4,000

円谷一
¥4,000
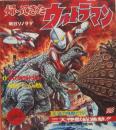
帰ってきたウルトラマン
¥4,000

少年ブック春休み増刊号 1966年4月 付録漫画付
¥50,000
成人式 - 大人への第一歩、新たなる人生
青年と台湾 [報恩感謝・勤労奉仕・国語尊重・資源愛護・心身鍛練]
¥22,000

新青年傑作選(全5巻揃)
¥8,000
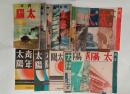
『青年太陽』 <創刊~3巻5号内21冊>
¥49,500

赤と黒 上下巻揃い <岩波文庫>
¥400
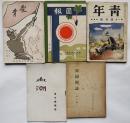
青年団・報国団誌 大正12年〜昭和14年 5冊
¥7,630

青年心理学 岩崎書店 赤塚 泰三
¥10,350

ビートルズも人間だった
¥400

はたちすぎ
¥1,000

『新青年』読本
¥7,800

実践成年後見 (19)
¥5,161
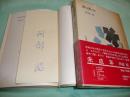
未成年
¥6,600
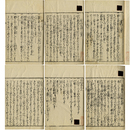
大諸礼集
¥132,000

自己成長の基礎知識2 身体・意識・行動・人間性の心理学
¥3,000
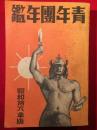
昭和十六年 青年団年鑑
¥11,000

若者よ、マルクスを読もう
¥390

ヒカリ 第2巻第2号(通巻第6号)昭和18年2月15日
¥240,000

はたちの人生相談
¥3,000

青年期の精神分析Ⅰ
¥300

青年団の新紀元
¥8,800

青年期の心に迫る
¥400

'78 成人の日に若人の広場
¥3,000

彷書月刊 1992年01月号 特集:はたちの頃に読んだ本
¥1,200

原刊本影印 新青年 全13冊揃
¥80,000
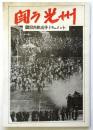
闘う光州-韓国民衆闘争ドキュメント
¥22,000

萬國青年大會講演集
¥22,000
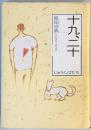
十九、二十
¥2,200

書を捨てよ、町へ出よう <第2版第3刷>
¥8,800
女子青年学習書 巻1~3(3冊)
¥6,600
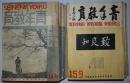
青年教育 第146~169号(昭和10~12年) 不揃20冊
¥22,000

若い世代と学問 1<青年双書>
¥390

青年論 国民文庫
¥300
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.