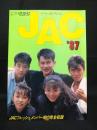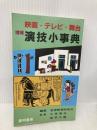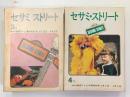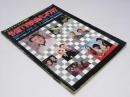モーツァルト生誕270年 - クラシック音楽を中心に
モーツァルト 人と音楽
¥3,300

モーツァルト全作品事典
¥3,300

正しい装飾音奏法
¥7,000

ベイルマン 魔笛 モーツァルト
¥3,500

オペラ魔笛のことが語れる本 初版
¥3,300

モーツァルトその音楽と生涯:全5巻/名曲のたのしみ、吉田秀和
¥15,800

プリマ・ドンナの歴史 ⅠⅡ揃い
¥4,620

名曲解説事典 全10巻
¥3,000

古典派音楽の様式
¥9,800

モーツァルトとベートーヴェン その音楽と病
¥3,000
モーツァルト ディスク叢書 第2輯
¥3,300
モーツァルトとナチス 第三帝国による芸術の歪曲
¥2,750

名作オペラブックス 既刊分全31冊揃
¥44,000

モーツァルトの至高性 音楽に架かるバタイユの思想
¥3,000

Mozart
¥3,400

Mozart
¥4,000

最良の教養としてのモーツァルト3大オペラ
¥11,000

超越の響き モーツァルトの作品世界
¥3,050
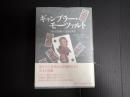
ギャンブラー・モーツァルト
¥2,500
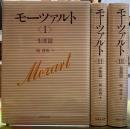
モーツァルト 生涯篇 声楽篇 器楽篇 全三冊
¥3,300

モーツァルト 伝説の録音 全3巻揃
¥58,300
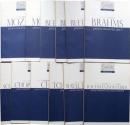
ピアノ協奏曲集 1~12
¥5,500

鍵盤音楽の歴史
¥2,700

サリエーリ 生涯と作品 (新版)
¥2,500
のど自慢80年 - テレビ番組の思い出
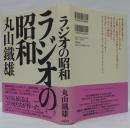
ラジオの昭和
¥1,500

テレビアニメーション 放映リスト No.1.2 2冊
¥5,000
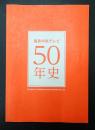
福島中央テレビ50年史
¥15,000

NHK NEWS 11
¥3,000

テレビジョン発達史
¥12,000
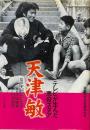
天津敏
¥7,000
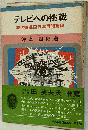
テレビへの挑戦
¥7,346

一括テレビドラマ 1959年9月~1964年7月
¥49,000

テレビドラマ 伝説の時代
¥5,000
テレビマンユニオン史 1970~2005
¥5,500
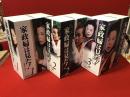
【DVD-BOX】家政婦は見た! 全5巻のうち、①~③3点一括
¥22,000

NHKテレビ放送台本 「あすをつげる鐘 永遠の背番号 沢村栄治」
¥33,000

TV台本東京物語 前・後編/カット割台本 セット図4枚付
¥100,000

どっきりカメラに賭けた青春
¥5,000
日本テレビ70年史 1953~2023
¥55,000
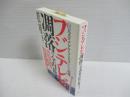
フジテレビ凋落の全内幕
¥9,800

スペシャルドラマ 弟 石原裕次郎ドリームBOX DVD6枚
¥16,500
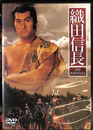
織田信長 DVD2枚揃 TBSDVD
¥6,160

連続テレビ小説ひまわり 全2集揃 NHKDVD DVD全14枚揃
¥16,500
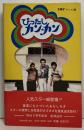
ぴったしカンカン
¥6,000

『週刊NHK新聞』 <昭30~33年内159部>
¥132,000

日本アニメクラシックコレクション DVD4枚組
¥22,000
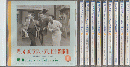
CD「思い出のラジオ・テレビ主題歌集」10枚セット
¥11,000
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.



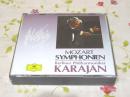

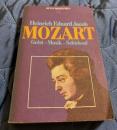
![[中古レコード]モーツァルト:歌劇「魔笛」全曲 カール・ベーム指揮 ウィー...](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/21000190/20230816143301045877_07a3915b1ff0ea6619697a3c72e63404.jpg)




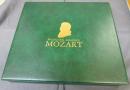

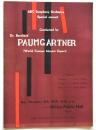
![世界大音楽全集 [第1] 第71 (器楽篇 ギター名曲集)](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12032620/20181121124849534023_38fa29b3e7d769f37c3f827ebbf37e99.jpg)