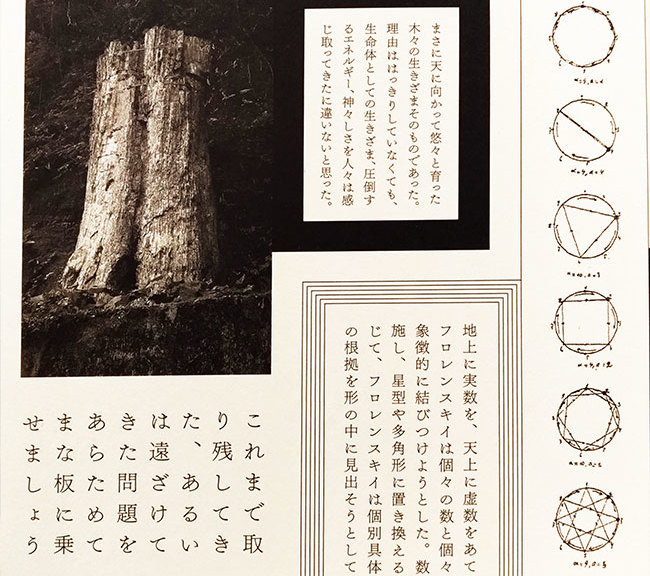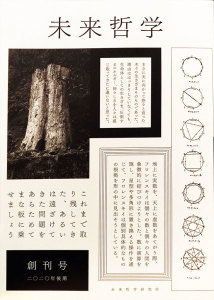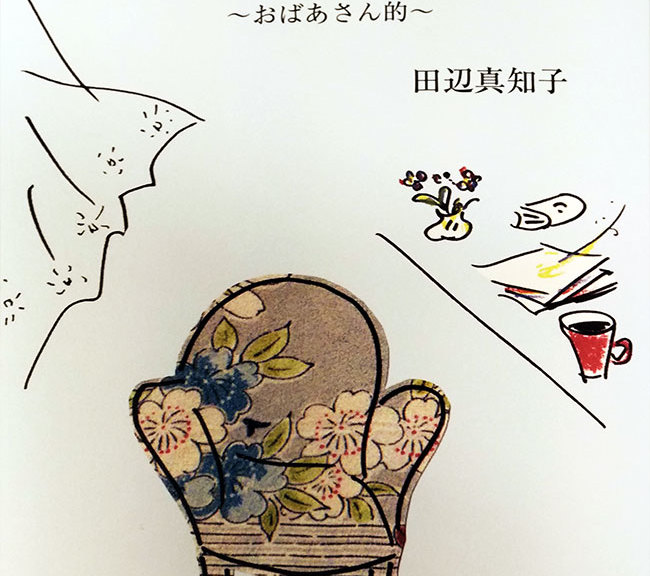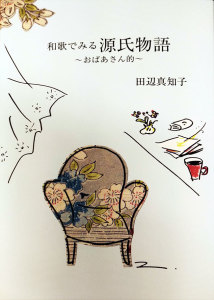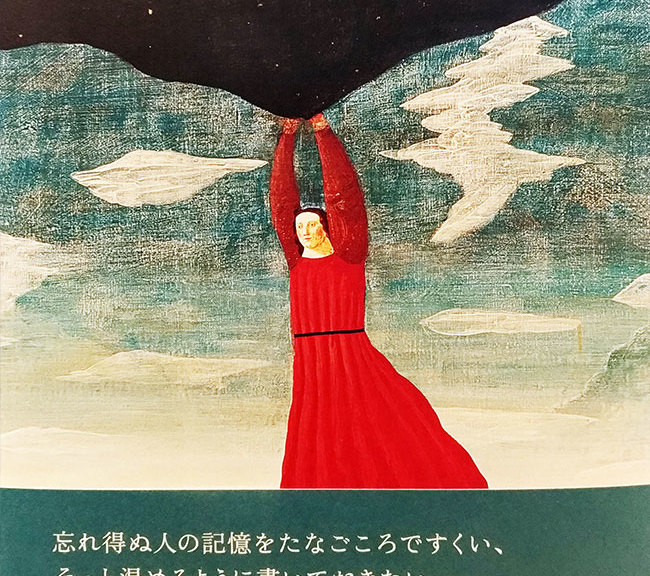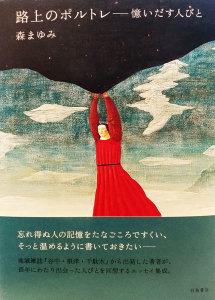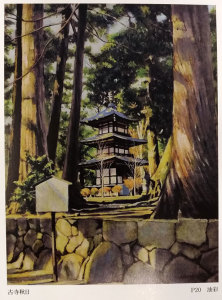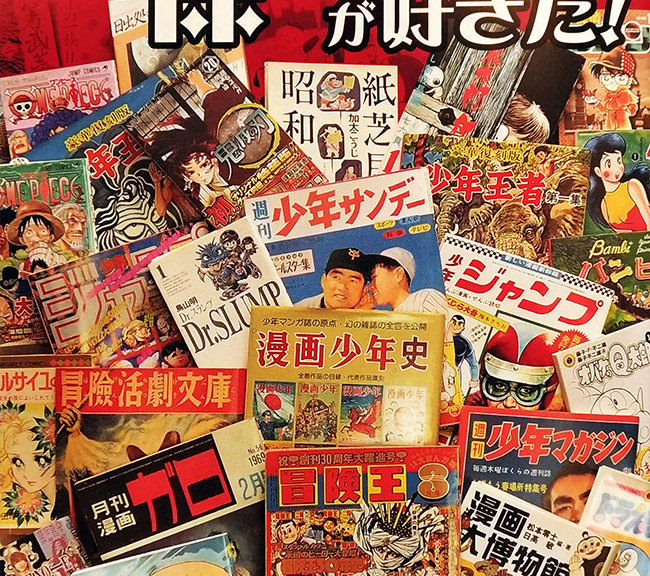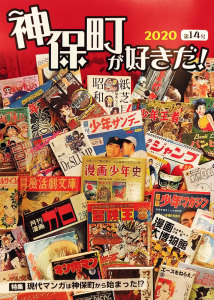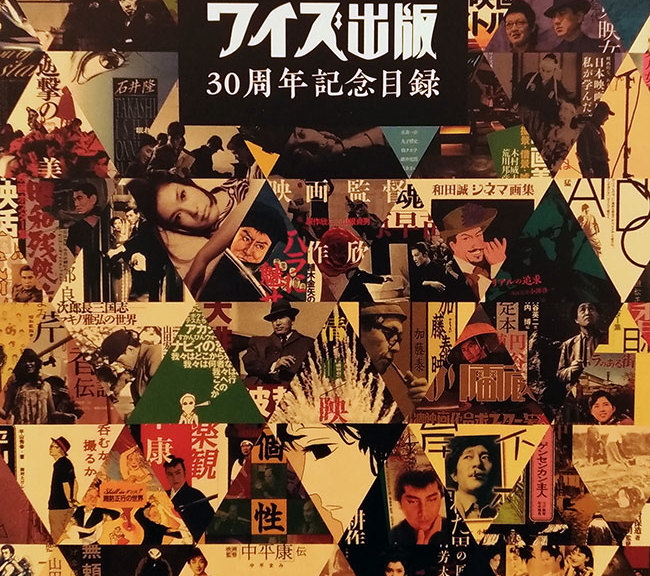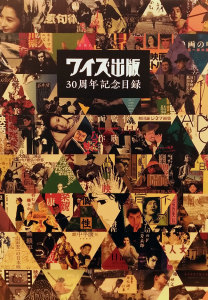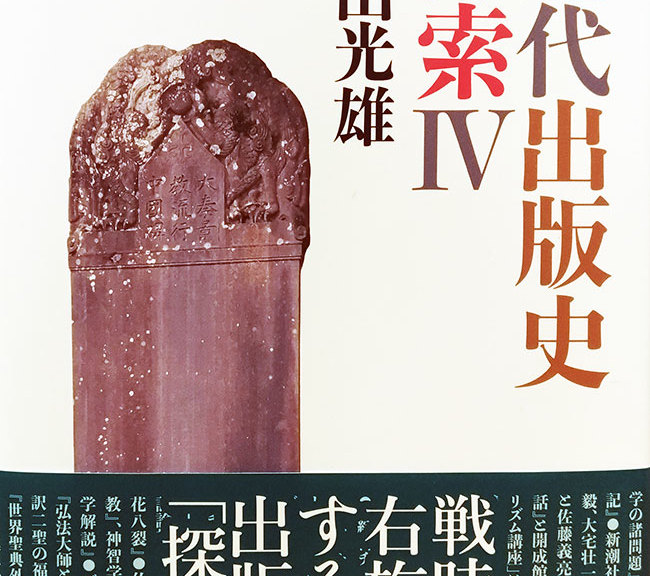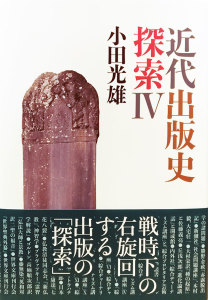■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
古書市&古本まつり 第95号
。.☆.:* 通巻312・12月10日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━
古書組合の役割と古書業界の仕組み その3
東京古書組合前事務局長 高橋秀行
これまで二回のお話で、古書組合の中では一番の肝は市場(交換
会)であることがお分かりいただけたと思います。また、古書業者
が古書籍に関わる知識を日々蓄積、研鑽していることもご理解され
たと思います。今回は最終回となりますので、古書組合にとっても
う一つの肝であるインターネット「日本の古本屋」についてお話し
したいと思います。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6515
━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━
第23回 村田亮太さん アルバイトと趣味を両立するひと
南陀楼綾繁
「最近、うちにアルバイトに来ている大学生がかなりの古本好きな
んですよ」
この連載の編集を担当している皓星社の晴山さんからそう云われ
て会った村田亮太さんは、温厚そうな青年だった。
「古書会館や池袋〈三省堂書店〉など、東京で開催される古書市は
ぜんぶ通っています。だから、新型コロナウイルスの影響で即売会
が中止になったときは辛かったです。東京古書会館の即売会が再開
した7月6日には、もちろん駆けつけました」
さっきも即売会に行ってましたと、収穫物の入った袋を見せてく
れる。その下からもう一袋が出てきた。計4900円なり。とにかく即
売会に通うのが楽しくて仕方ないらしい。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6522
南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)
1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一
文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、
図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年
から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」
の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。
「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ
・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を
つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に
『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市
の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、
『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』
(ちくま文庫)などがある。
ツイッター
https://twitter.com/kawasusu
『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著
皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!
http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/
━━━━━【12月10日~1月15日までの全国即売展情報】━━━━━
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている
即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。
お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
-------------------------------
赤札古本市
期間:2020/12/10~2020/12/13
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
-------------------------------
浦和宿古本いち(埼玉県)
期間:2020/12/10~2020/12/13
場所:さくら草通り
JR浦和駅西口下車 徒歩5分 マツモトキヨシ前
https://twitter.com/urawajuku
-------------------------------
富山の魅力を発信する古本市 BOOK DAY とやま駅(富山県)
期間:2020/12/10~2020/12/10
場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)
-------------------------------
新興古書大即売展
期間:2020/12/11~2020/12/12
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
-------------------------------
第18回 つちうら古書倶楽部古本市(茨城県)
期間:2020/12/12~2020/12/20
場所:つちうら古書倶楽部
〒300-0036 茨城県土浦市大和町2-1 パティオビル1階
TEL&FAX 029-824-5401
-------------------------------
第18回 つちうら古書倶楽部 師走の古本まつり(茨城県)
期間:2020/12/12~2020/12/20
場所:土浦市大和町2-1 パティオビル1階
-------------------------------
12月反町古書会館(神奈川県)
期間:2020/12/12~2020/12/13
場所:神奈川古書会館1階特設会場
http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm
-------------------------------
港北古書フェア(神奈川県)
期間:2020/12/16~2020/12/25
場所:横浜市営地下鉄 センター南駅
-------------------------------
ぐろりや会
期間:2020/12/18~2020/12/19
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
http://www.gloriakai.jp/
-------------------------------
五反田古書展
期間:2020/12/18~2020/12/19
場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4
-------------------------------
アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)
期間:2020/12/19~2021/01/06
場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前
千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1
-------------------------------
下町書友会
期間:2020/12/25~2020/12/26
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
-------------------------------
2020 歳末阪神古書ノ市(大阪府)
期間:2020/12/26~2020/12/28
場所:阪神百貨店 梅田本店 8階催場
大阪市北区梅田一丁目13番13号
-------------------------------
好書会
期間:2020/12/26~2020/12/27
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
-------------------------------
アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)
期間:2020/12/19~2021/01/06
場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前
千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1
-------------------------------
立川フロム古書市
期間:2021/01/05~2021/01/19
場所:立川駅北口徒歩5分フロム中武
http://mineruba.webcrow.jp/saiji.htm
-------------------------------
第41回古本浪漫洲 Part.1
期間:2021/01/07~2021/01/09
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)
新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111
https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/
-------------------------------
東京愛書会
期間:2021/01/08~2021/01/09
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
http://aisyokai.blog.fc2.com/
-------------------------------
杉並書友会
期間:2021/01/09~2021/01/10
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
-------------------------------
第41回古本浪漫洲 Part.2
期間:2021/01/10~2021/01/12
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)
新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111
https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/
-------------------------------
第19回 上野広小路亭古本まつり
期間:2021/01/11~2021/01/17
場所:谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36
-------------------------------
第41回古本浪漫洲 Part.3
期間:2021/01/13~2021/01/15
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)
新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111
https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/
-------------------------------
さんちか古書大即売会(兵庫県)
期間:2021/01/14~2021/01/19
場所:神戸さんちか3番街さんちかホール
http://www.hyogo-kosho.net/
-------------------------------
フィールズ南柏 古本市(千葉県)
期間:2021/01/14~2021/02/03
場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7
-------------------------------
富山の魅力を発信する古本市 BOOK DAY とやま駅(富山県)
期間:2021/01/14~2021/01/14
場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33
┌─────────────────────────┐
次回は2020年12月下旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその312 2020.12.10
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:志賀浩二
編集長:藤原栄志郎
==============================