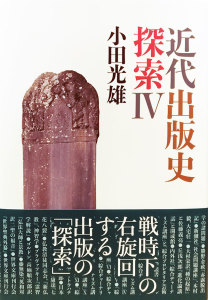『近代出版史探索Ⅳ』小田光雄 |
| 『近代出版史探索』シリーズの各編はそれぞれが2千字から3千字の短い論稿の集積ではあるけれど、続けて第4巻目を刊行することになった。 この12年間に及ぶ『近代出版史探索』の長編連作の試みの目的として、第1巻から3巻の本文や「あとがき」、及び本メールマガジンへの寄稿でもさまざまにふれてきている。 だがこの『近代出版史探索Ⅳ』に至って、中国社会と経済地理学研究者ウィットフォーゲルの『東洋的社会の理論』を取り上げた際に、ようやく吉本隆明の『共同幻想論』に言及することができた。吉本は同書でウィットフォーゲルの「東洋的専制主義」の日本論に異議を発し、日本の場合、大規模な灌漑工事や運河開削は必要としなかったが、日本の初期国家の首領たちにとって文化と文明は大陸からの輸入品で、それを分布させるために財力や権力として、専制力は発揮されたと述べている。 それは「〈観念のアジア〉的専制」というべきもので、また初期国家においては地理的条件から考えても、海部民、農耕民、狩猟民が多層的に混住していた。それが共同観念の構造を複雑化し、大陸とは異なる「〈アジア〉的特性のひとつの典型」を生みだしたのである。そして吉本はいっている。 “わが初期国家の専制的首領たちは、大規模な灌漑工事や、運河の開削工事をやる代りに、共同観念に属するすべてのものに大規模で複合された〈観念の運河〉を掘りすすめざるを得なかった。その〈観念の運河〉は、錯綜していて、〈法〉的国家へゆく通路と、〈政治〉的国家へとゆく通路と、〈宗教〉的イデオロギーへゆく通路と、〈経済〉的な収奪への通路とは、よほど巧くたどらなければ、つながらなかった。〈名目〉や〈象徴〉としての権力と、じっさいの政治的権力と、〈宗教〉的なイデオロギーの強制力とは別個のものであるかのように装置されていて、よほど、秘された迷路に精通しないかぎり、迷路に陥むように構成された。そこには、現実の〈アジア〉的特性は存在しないかのようにみえるが、共同幻想の〈アジア〉的特性は存在したのだ、と……。” これは『共同幻想論』のエッセンスともいうべき重要な部分であり、省略して引用できず、長くなってしまった。実はここで吉本が述べている初期国家ならぬ、近代の「〈観念〉の運河」がどのように生成されていったのかを追求することも、『近代出版史探索』の目的のひとつなのである。 日本の近代出版業界の始まりは生産、流通、販売、つまり出版社・取次・書店という出版流通システムの誕生ととともにあった。それは何よりもまず社会経済問題として論じられるべきだったが、たまたまそれに併走するようにして近代文学の発生を見たこともあって、出版物が単なる商品ではなく、作品だというコンセプトと同時に、作者と読者も召喚されることになった。それに教科書出版、アカデミズムと立身出世の物語も重なる。 そして明治後半からの出版業界の成長に合わせ、特価本、造り本、赤本などのもうひとつの出版業界も台頭し、さらには古書業界の隆盛へともつながっていく。こうした複雑な「出版の運河」が生産、流通、販売をコアとして、それらをリサイクル、リバリューするバックヤードとしての特価本、古書業界を生み出した。これらは吉本の言葉を借りれば、「よほど、秘された迷路に精通しないかぎり、迷路に陥むように構成され」、そこに日本の出版の共同幻想の特性が生じたと考えられる。そのような近代出版の迷路の一端を読者に伝えられれば幸いに思う。 『近代出版史探索Ⅳ』 小田光雄 著 |
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |