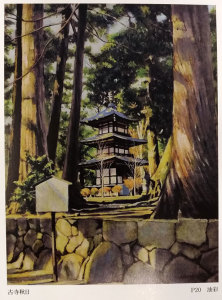古書組合の役割と古書業界の仕組み その3高橋秀行 (前 東京古書組合事務局長) |
| これまで二回のお話で、古書組合の中では一番の肝は市場(交換会)であることがお分かりいただけたと思います。また、古書業者が古書籍に関わる知識を日々蓄積、研鑽していることもご理解されたと思います。今回は東京古書組合にとってもう一つの肝であるインターネット「日本の古本屋」についてお話ししたいと思います。
メルマガ読者の皆さんは、すでにインターネットが元々はアメリカ軍の軍事技術が民間に開放されたものであることはご存じだと思います。1990年当時の日本ではインターネットはまだまだ一般に認知されていませんでしたが、古書業界の中でいち早く関心を向けたのは京都組合と東京組合でした。1996年に東京組合は東京都の支援を受け、古書業界の将来像を見据えた活性化ビジョン調査事業を行うことが決まり、実施されました。この調査事業は結果的に古書業界にとって非常に大きなエポックをもたらすものとなったのですが、その中で将来的にインターネット事業への参画が示唆されました。当時の東京組合理事の一部には、ドメイン名を取得するのに約200万円かかることに理解が及ばないこともあったのですが、将来への投資として承認された経緯があります。 1997年に全国の古書組合組織の会合で、インターネット事業の将来像について報告がなされ、着々と方向性を探っていた時、翌1998年になって大日本印刷と三菱商事から共同でインターネットの共同実験事業を開始するお誘いを受けることになります。この実験事業を実質的に行ったのは東京組合ですが、全国の組合ではインターネット事業の成果を東京組合に独占されるという疑心暗鬼があったのは事実で、各地組合は全古書連事業として行うことに固執していた時期もありました。しかしながら、実質的に資金を拠出できるのは東京組合でしたし、組合員の認知度も高く、理解も得やすい環境にありました。また、東京組合は全組合の本部でもあり、参加も全国公平に実施するべく、全組合の同意を得て実験事業を行うことになります。 1999年1月に全古書連のインターネット事業「日本の古本屋」として、三者共同による実験事業が開始されます。当初は参加組合員も少なく、登録書籍数もあまり多くなく、発注を受けた後の対応や決済方法も不便で、あまり使い勝手のよいものではありませんでした。 2002年1月、東京古書組合の単独事業としてインターネット「新・日本の古本屋」は再出発を果たします。この事業は、東京組合の「インターネット運営委員会」という部内の組織が運営管理しており、構成員も東京の組合員です。無論、職員も従事しております。当運営委員会では、様々な運営上の改善と改修を行い、「日本の古本屋」のトップ画面に買い入れ広告を掲載する件やサイトにバナー広告を掲載する件等も討議され、2009年にはクレジット決済が導入されました。近年では検索エンジンの上位表示のための改修やスマホ対応も行ってリニューアルしていますが、ご利用される皆様の利便性の向上とニーズにお応えするため一層の努力をしております。 これまで述べてきたように、古書業界にとって1995年からの10年ほどは大きな転換点であり、東京組合の活性化ビジョン調査事業の実施、阪神淡路大震災、インターネット事業の開始、非組合員大型店(ブックオフ等)の台頭、組合員の即売展開催に関わる規制の撤廃、東京組合の本部会館新築完成等々、様々な出来事が起こっておりました。それらの個別の問題については、少し説明も必要なのですが、今回は紙数がつきましたので、またの機会にさせていただきます。このような時流の中で、インターネット事業が古書流通の一大転換をもたらし、営業基盤の一助となっていることは古書業界にとって大きな成果であると思っています。 |
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |