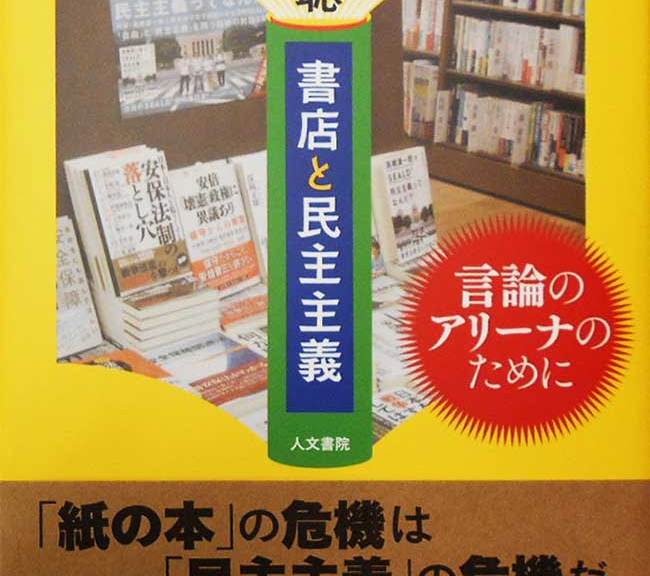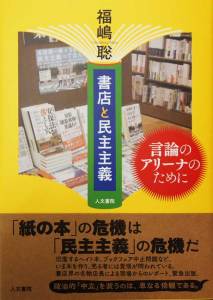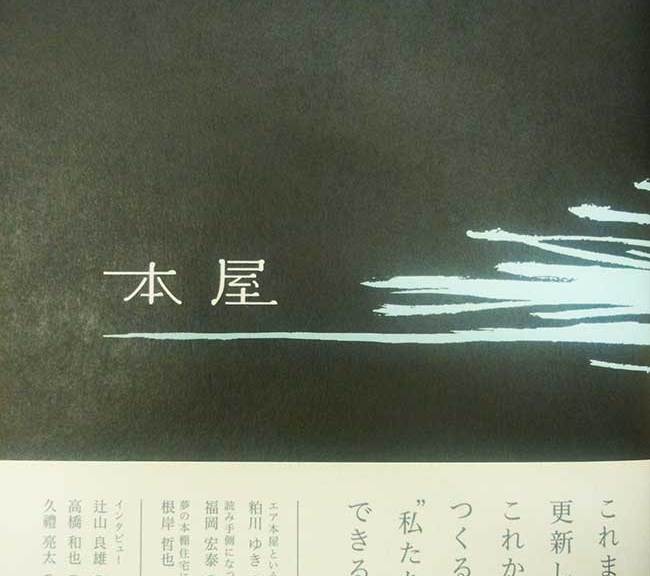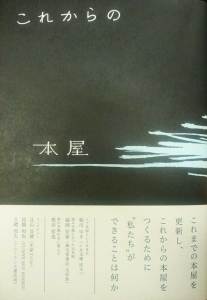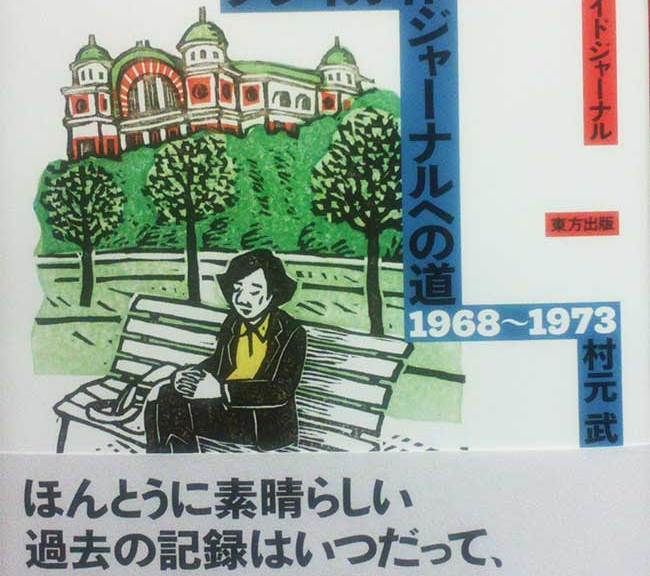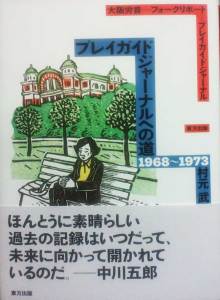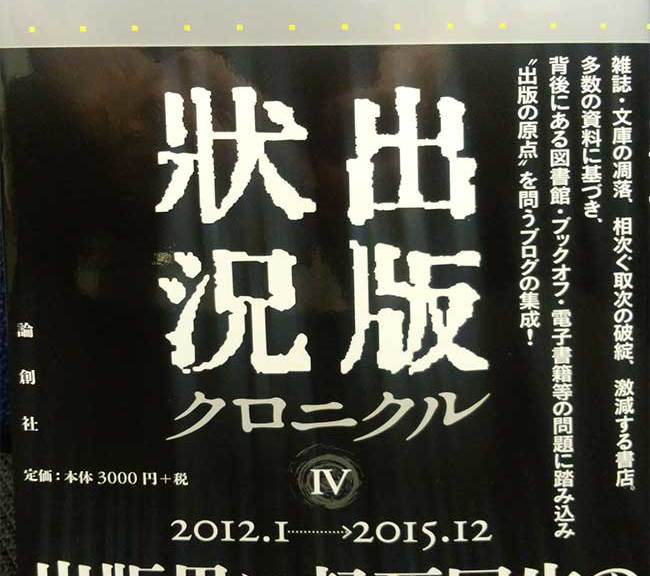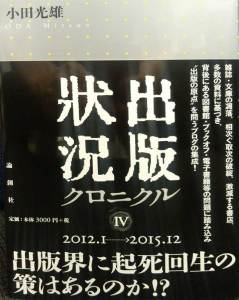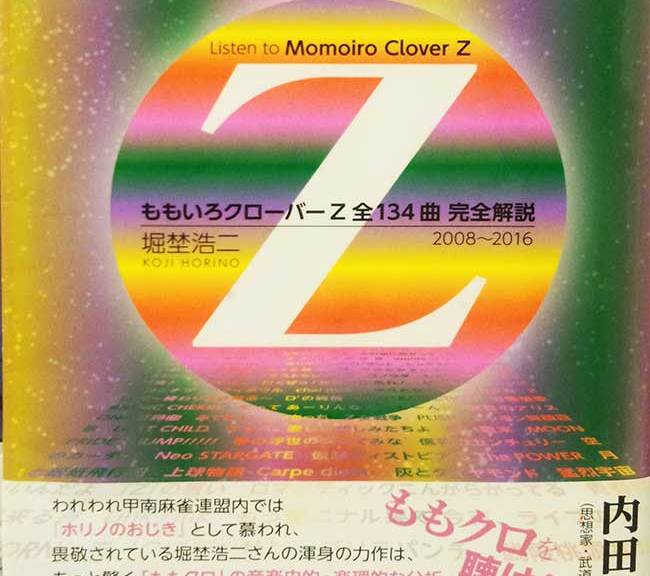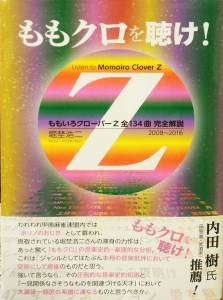古本屋ツアー・イン・ジャパンの2016年上半期活動報告古本屋ツーリスト 小山力也 |
| 古本神のひとりである岡崎武志氏と力を合わせ、この三月に「古本屋写真集」を上梓出来たのは、過分な幸甚であった。年始早々からほぼその制作に全力を注ぎ、己の職業でもないのに、古本屋に身も心も捧げるような三ヶ月間…だが実はその裏で、今年で九年目に突入した古本屋ツーリスト人生を揺さぶりまくる大プロジェクトも、すでにその歯車をギクリギクリと動かし始めていた…。 そのプロジェクトとは、『未知の古本屋大陸進出』とも言える、本格的な関西方面古本屋ツアーである。私は所詮関東の人間。ブログタイトルに『古本屋ツアー・イン・ジャパン』と名付け、全国の古本屋さんに足跡を残しつつあると言っても、遠い地になればなるほどその数はたかが知れているものとなり、目的の全店踏破にはいつたどり着くのやら、まったく持って不明なのである。今までツアー出来た関西方面のお店と言えば、仕事でミュージシャンの全国ツアーに帯同したついでに訪れたもの、私的な旅行で訪れたもの、突発的な日帰りで訪れたものなどの、点としてのツアー先が徐々に徐々にジワジワと、地道にその数を増やして行ったものに過ぎないのである。だが今年の一月から、そんなチンタラしたツアーは、全面的に不可能となってしまった。 原因は、去年書き上げた本の雑誌社「古本屋ツアー・イン・首都圏沿線」にある。これと同じような本を、関西編で作ってみるのはどうだろう…作ったら面白いんじゃないか…作れないか?…いや、作るのだ。というわけでもう決まってます、と厳命されたのである。関西…そこにお店はいったい何軒あるのだろうか? 京都…大阪…神戸…主だったお店を合わせるだけでも、優に二百店は越えるだろう。それをこれからたった一人で…土地鑑ほぼゼロのまま…まるで狂気の沙汰ではないか。 かくてあまりに孤独な、関西の古本屋さんと闘う日々がなし崩しに始まった。本来ならば、関西に仮の居を定め、腰を落ち着けツアーするのが一番正しいやり方であろうが、時間と様々な大人の事情が、さすがにそれを許さない。なので三月から、夜行バスで関西に乗り込み、ひと月の三分の一~半分ほどをあちらで過ごすことを繰り返している。それは予想以上に刺激的で楽しく、そして確実に無茶で疲弊する、大変に過酷な日々である。普段のツアーとは違う、見知らぬ土地で旅人として過ごす逗留。しかもそのほとんどを、古本屋を訪ねることに傾注する、取材という名の異常で情熱的なたったひとりのさすらい。こんなことは、生まれて初めての経験である。もちろんすべてのお店を訪ねることは叶わぬが、エトランジェとして己の目で見て歩いた軌跡が、少しでも関西古本屋地図の一端を浮かび上げることになれば、もはや本望である。というわけで、旅はまだ必死に継続中。終わるかどうかも分からぬのだが、本が秋口に出る予定だけは決まっている…ブルブル…。 さて、半分は関西で過ごしていても、半分はもちろんお馴染みの関東平野で過ごしているのである。それものうのうと羽を休めているわけではなく、古本屋調査を欠かすことは決してない。だが、こちらではほとんどの古本屋さんに行き尽くした感があるので、お店を楽しみつつも古本を買う方に主眼が移され始めている。しかも、気になるお店を見に行くだけではなく、そのお店を組み込んだツアールートを造り出し、買い漁ってしまうのだ…どうも本が急速に増えるわけだ…。神保町では店頭を中心に「日本書房」「原書房」「田村書店」「八木書店」「三茶書房」を組み込んだパトロールルート、中央線では「都丸書店」から「藍書店」を経て「サンカクヤマ」に至るミニルート、それに荻窪「ささま書店」「竹陽書房」から西荻窪へ向かうテクテク徒歩ルート、武蔵小山「九曜書房」から西小山の「ハイカラ横丁」まで歩き東急線網の沿線店を巡るルート、祖師ケ谷大蔵「祖師谷書房」から小田急線を遡り豪徳寺〜経堂とさまようルートなど、その組み合わせは無限に広がって行く。 さらにそこに時々ではあるが、新しいお店もオープンしたりするので、ルートが延伸したりすることも稀ではない。一月は谷根千界隈の出店ラッシュが猛威を振るった。根津の「ひるねこBOOKS」、千駄木の「OLD SCHOOL」、さらに根津・弥生坂途中の植物とともに古本を売る「緑の本棚」、そして少し遅れたが日暮里の骨董店との融合タイプ「古書 鮫の歯」。短い期間に四店ものお店が出来たのは、驚嘆すべき出来事である。国分寺には「ら・ぶかにすと」の跡に「七七舎」が出店し、オープニング当日はチンドン屋が宣伝して回る手法にあっけにとられる。三鷹にはひっそりと「藤子文庫」が出現し、惜しまれながら閉店した伊勢佐木町「なぎさ書房」跡には若く勇気と希望に満ちあふれた「馬燈書房」が開店。明大前の裏通りには出版社の一部を古本屋にした変わり種「七月堂古書部」が。下板橋には倉庫の一部を開放したような「水たま書店」が出来、そこから大山「ぶっくめいと」「銀装堂書店」まで歩き、さらに下赤塚「司書房」まで足を延ばすと、かなり充実した古本屋ルートが浮かび上がるのを新発見とし、子供のように喜ぶ始末である。 そして生まれるお店があれば、入れ替わるように表舞台から姿を消すお店もある。一月には前述した伊勢佐木町の名店だった「なぎさ書房」と、神保町の鉄道に強い「篠原書店」が、華やかに見送られながら営業の幕を下ろした。五月には鶴見の「閑古堂」が、衝撃の看板落下事件に端を発し閉店。ついに鶴見の純粋な古本屋さんは、「西田書店」ただ一軒になってしまった…。新潟の大型店「ブックス・バザール」突然の閉店も、心に暗い影を落とす悲報であった。さらにもはや下半期に入るが、七月二日には新宿の老舗「昭友社書店」が袋詰めセールと半額セールを賑やかに行い、派手に退場。また門前仲町の「朝日文庫」も通販への移行を決定し、店舗を閉店。そして大阪の最高齢文学青年「青空書房」坂本健一氏が、古本屋として天寿を全うされ、名物店は七月四日に閉店となった。実に実に寂しい限りである。だが悲しんでばかりはいられない。これらのお店から受け継いだ、本や魂を腕と胸に抱いて気持ちを新たにし、さらに深くなる古本屋の森を、これからも歩き続けて行かなければならぬのだ。 それにしても、やはり未知の古本屋さんばかりである関西は、熱い! おっかなびっくりツアーしながらも、すでに取材は後半戦に突入。新しく移転開店した京都「町家古本はんのき」やオープン間近の大阪・守口市「たられば書店」もどうにかして、貪欲にツアーしたいものである。そんな風に興奮必至の旅の空を繰り返しているのだが、毎日古本屋さん十軒強を生身に浴び続ける反動が、いずれ襲い掛かって来そうで、何だか不安でもある。いや、その前にちゃんと本を完成させなければ…タイトルもまだ決まっていないが、とにかく関西古本屋に血眼中であることを、ここにお伝えしておく次第である。
|
|
Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |