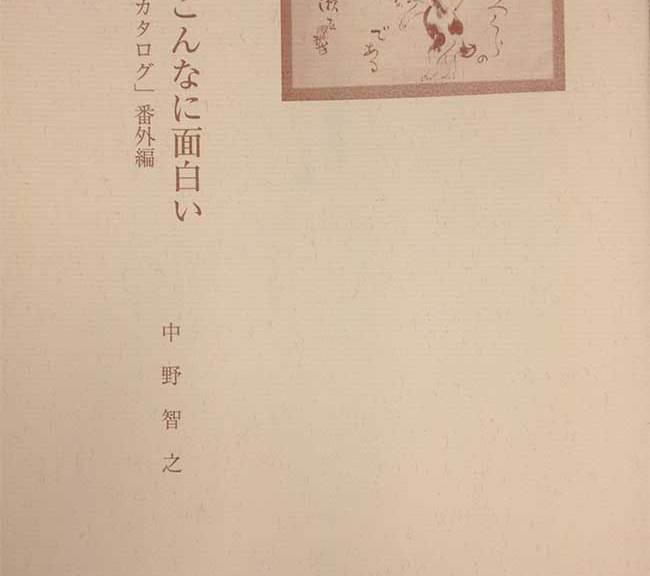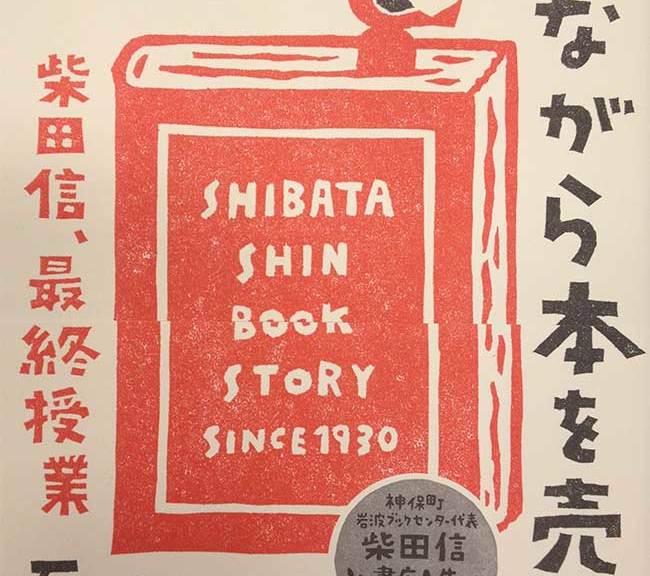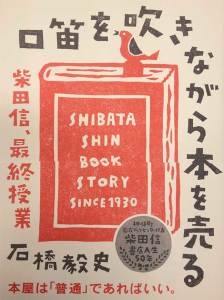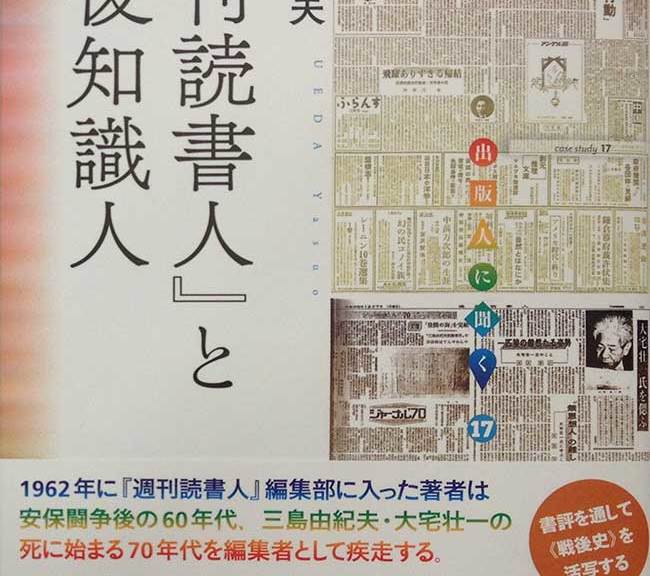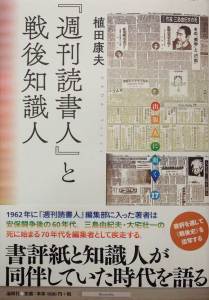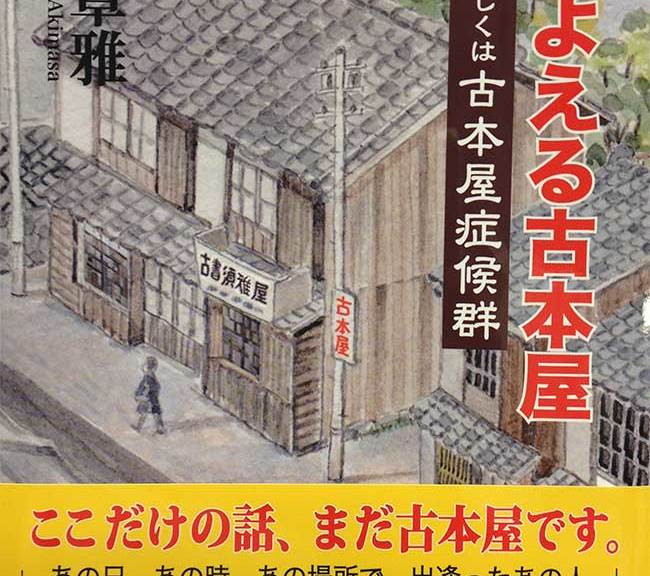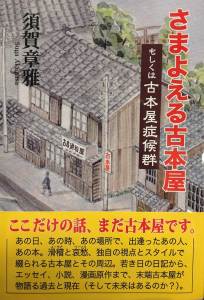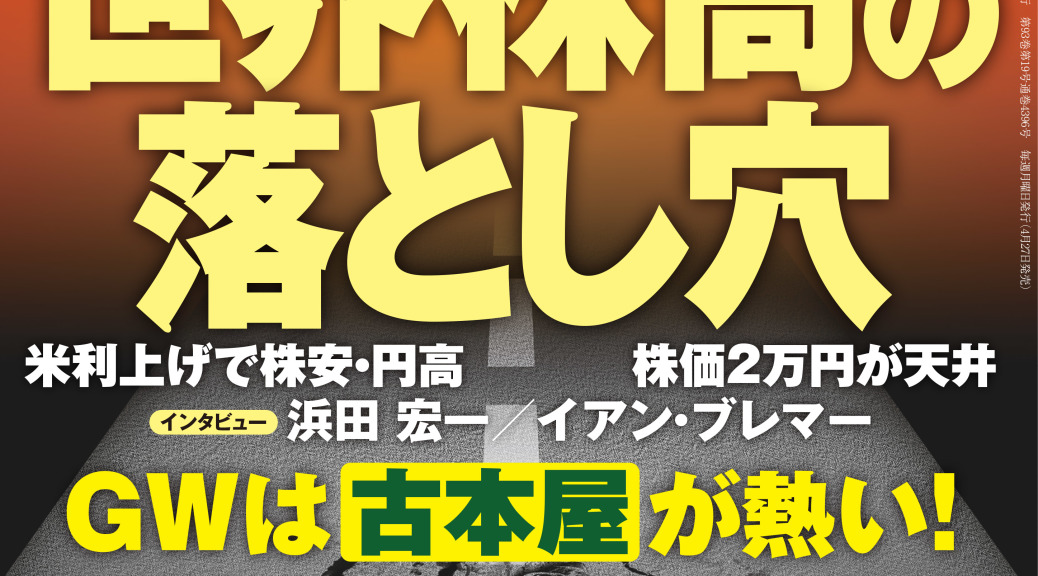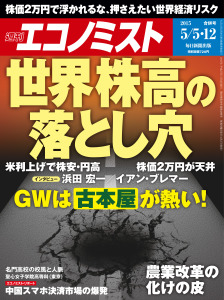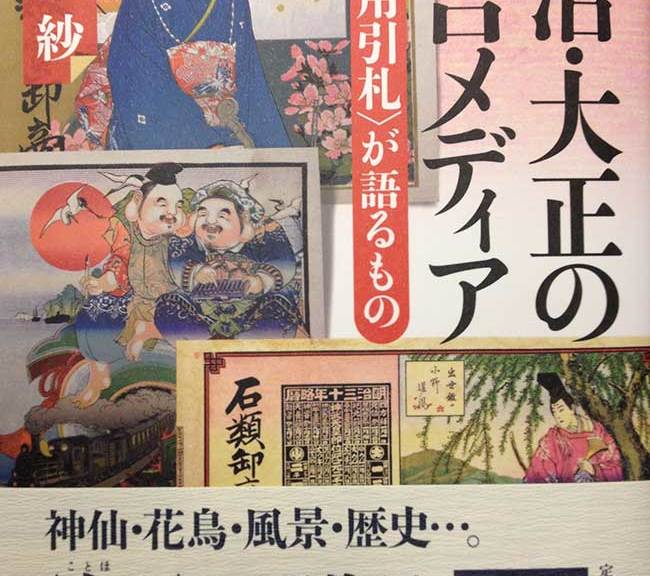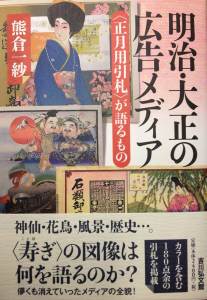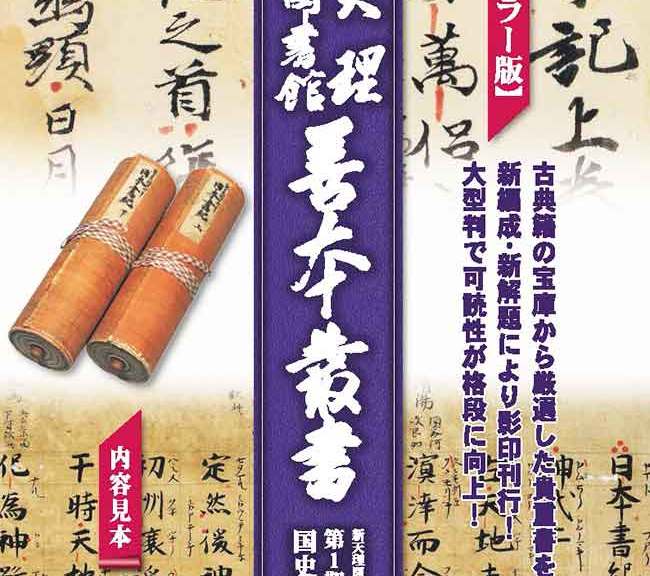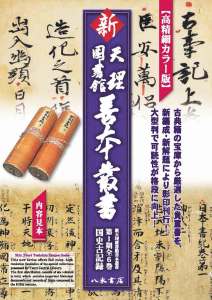■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
古書市&古本まつり 第31号
。.☆.:* 通巻181・5月13日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジンは、毎月2回の配信になりました!
初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、
イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ
お出掛けください。
次回メールマガジンは5月下旬に発行です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国935書店参加、データ約630万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━【5月13日~6月15日までの全国即売展情報】━━━━━
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
有隣堂イセザキ本店・古書ワゴンセール(神奈川県)
期間:2015/04/28~2015/05/16
場所:有隣堂伊勢佐木町本店 横浜市中区伊勢佐木町1-4-1
--------------------------
第5回 リブロ池袋本店 アートブックバザール
期間:2015/05/01~2015/05/31
場所:西武百貨店 池袋本店 書籍館2階
リブロ芸術書売場 特設会場
--------------------------
第19回 早稲田青空古本掘出市
期間:2015/05/11~2015/05/16
場所:早稲田大学 10号館前(大隈像裏の広場)
--------------------------
たにまち月いち古書即売会(大阪府)
期間:2015/05/15~2015/05/17
場所:大阪古書会館 (中央区粉川町4-1 TEL:06-6767-8380)
※谷四と谷六のちょうど中間
--------------------------
五反田遊古会
期間:2015/05/15~2015/05/16
場所: 南部古書会館 品川区東五反田1-4-4
--------------------------
下町書友会
期間:2015/05/15~2015/05/16
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
アツベツ「古書の街」(札幌市)
期間:2015/05/17~2015/05/19
場所:サンピアザ 1F 光の広場
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目
地下鉄東西線新さっぽろ駅直結
--------------------------
新橋古本市
期間:2015/05/18~2015/05/23
場所:新橋駅 SL広場
--------------------------
札幌ブキニスト in チ・カ・ホ(北海道)
期間:2015/05/18~2015/05/24
場所:札幌地下歩行空間 憩いの空間
--------------------------
浦和宿古本いち(埼玉県)
期間:2015/05/21~2015/05/24
場所:JR浦和駅西口下車 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前
--------------------------
趣味の古書展
期間:2015/05/22~2015/05/23
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
名鯱会(名古屋)
期間:2015/05/22~2015/05/24
場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12
--------------------------
中央線古書展
期間:2015/05/23~2015/05/24
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
第74回 彩の国所沢古本まつり(埼玉県)
期間:2015/05/27~2015/06/02
場所:くすのきホール 西武線所沢駅 東口 西武第二ビル8F
--------------------------
第20回 BOOK & A(ブック&エー)
期間:2015/05/28~2015/05/31
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
和洋会古書展
期間:2015/05/29~2015/05/30
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
有隣堂イセザキ本店・古書ワゴンセール(神奈川県)
期間:2015/05/30~2015/06/20
場所:有隣堂伊勢佐木町本店 横浜市中区伊勢佐木町1-4-1
--------------------------
城南古書展
期間:2015/06/05~2015/06/06
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
反町古書会館展(神奈川県)
期間:2015/06/06~2015/06/07
場所:神奈川古書会館 1階特設会場
横浜市神奈川区反町2-16-10
--------------------------
新興古書大即売展
期間:2015/06/12~2015/06/13
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
大均一祭
期間:2015/06/13~2015/06/14
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
新宿古書展
期間:2015/06/14~2015/06/15
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
※初日14日(金)は、11時開場です。
--------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=2
┌─────────────────────────┐
次回は2015年5月下旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその181 2015.5.13
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:殿木祐介
==============================
・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら
https://www.kosho.or.jp/mypage/
・このメールアドレスは配信専用です。
返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。
・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。
・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は
melma@kosho.ne.jp までお願い致します。
・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い
いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に
遅れる場合もございます。ご了承下さい。
============================================================
☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・
============================================================