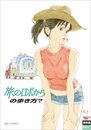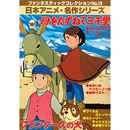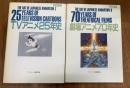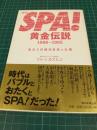人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に

目撃者が語る昭和史 第1巻
¥2,980
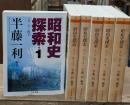
昭和史探索
¥1,980
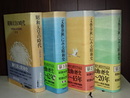
文藝春秋にみる昭和史 全3巻+別巻「昭和天皇の時代」
¥1,800

昭和史探索
¥2,750

昭和天皇最後の側近卜部亮吾侍従日記 全5巻
¥7,700
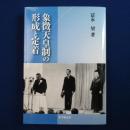
象徴天皇制の形成と定着
¥6,930

歴史問題ハンドブック <岩波現代全書 065> 第1刷
¥2,200

昭和御即位式京都行幸紀念 昭和3年11月発行
¥5,500
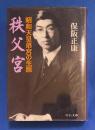
秩父宮
¥2,000

近代日本語表出論
¥500
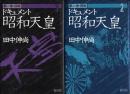
ドキュメント昭和天皇 全8冊
¥9,000

目撃者が語る昭和史 全8冊組 全8巻揃
¥4,273

ナショナリズムの昭和
¥3,000

平和の海と戦いの海
¥1,500

戦後50年日本人の発言 上下巻
¥2,640

昭和天皇 写真集
¥3,000

二〇世紀日本の天皇と君主制
¥4,000

ドキュメント 昭和天皇 1~5巻
¥3,850

昭和天皇の歴史教科書国史
¥1,800
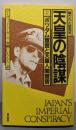
天皇の陰謀
¥950

昭和天皇と田島道治と吉田茂
¥1,800

大元帥・昭和天皇 3 第7刷
¥3,300

裕仁天皇
¥15,000
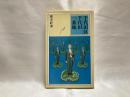
千代田区千代田一番地
¥1,000
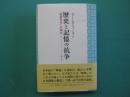
歴史と記憶の抗争
¥5,500

伊勢志摩に両陛下をお迎え志て
¥5,300

二・二六事件裁判の研究
¥17,800

日本精神史
¥1,980

昭和天皇のおほみうた
¥4,400

昭和天皇を惟う
¥3,000

昭和天皇新聞記事集成 昭和元年~15年
¥7,700

昭和天皇 戦後 全3巻揃
¥3,300

昭和天皇
¥8,800
コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ
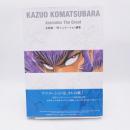
小松原一男アニメーション画集
¥25,000

日本アニメーション映画史
¥4,450
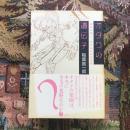
オタクの遺伝子 長谷川裕一・SFまんがの世界
¥1,100
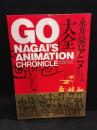
永井豪TVアニメ大全
¥9,900

アニメーターになれる本
¥2,000

ポップ・カルチャー年鑑2007
¥1,500

20年目のザンボット3●オタク学叢書 VOL.1
¥4,000

日本SFアニメ創世記 虫プロ、そしてTBS漫画ルーム
¥3,850
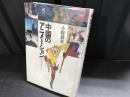
中国のアニメーション
¥9,000

それは『ポン』から始まった
¥11,000

おたくの本
¥1,000

漫画家・アニメ作家人名事典
¥2,800
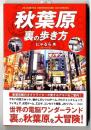
秋葉原裏の歩き方
¥500

コミックマーケット 30’sファイル 1975-2005
¥3,850
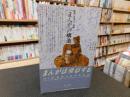
「まんが」の構造 商品/テキスト/現象
¥800

8ミリアニメ映画の作り方 <現代カメラ新書>
¥6,000
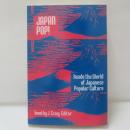
Japan Pop
¥3,300

イアン・ビュルマ/訳
¥4,950

ゴジラと御真影
¥1,500
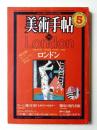
美術手帖 1982年5月号 No.496 <特集
¥1,100
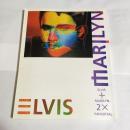
マリリン・モンローとエルヴィス・プレスリー展
¥1,000

手塚治虫全史
¥4,000

中華オタク用語辞典
¥1,980
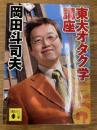
東大オタク学講座 <講談社文庫>
¥1,100
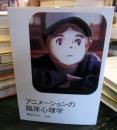
アニメーションの臨床心理学
¥4,200

日本TVアニメーション大全 テレビアニメ50年記念
¥8,500
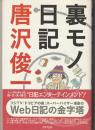
裏モノ日記
¥1,200
東京都古書籍商業協同組合
所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392
Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.



![[絵葉書] 昭和参年十二月於横浜港外 御大禮特別大観艦式記念](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/12010425/20240919133729599339_fbc6959f2345ba04cb04b650be173901.jpg)







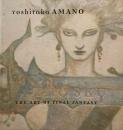
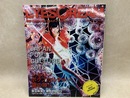

![二次元世界に強くなる 現代オタクの基礎知識 [単行本(ソフトカバー)] ライブ](https://www.kosho.or.jp/upload/save_image/13030080/20250912121157279566_fd92699de3f25da40908313771c390aa.jpg)