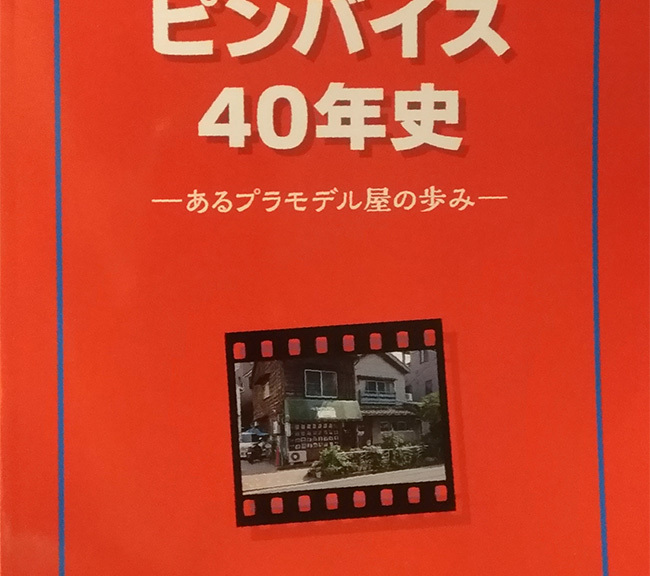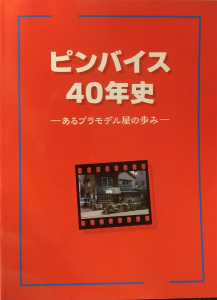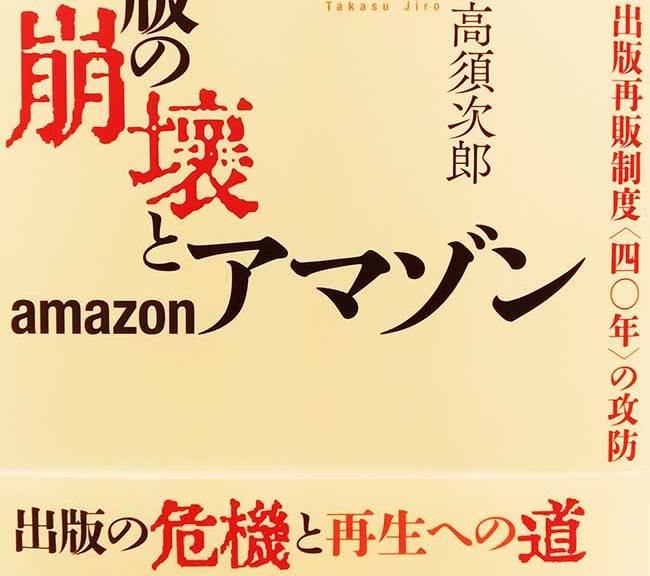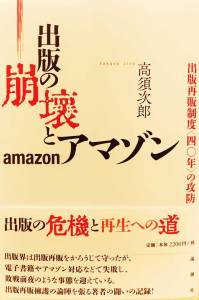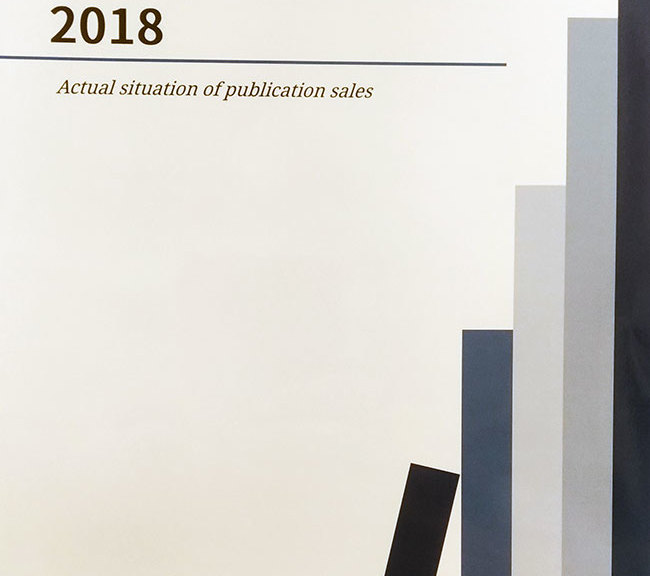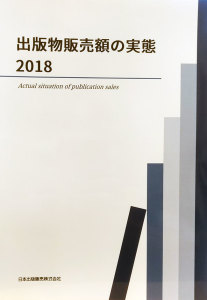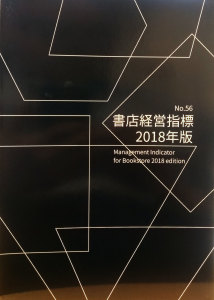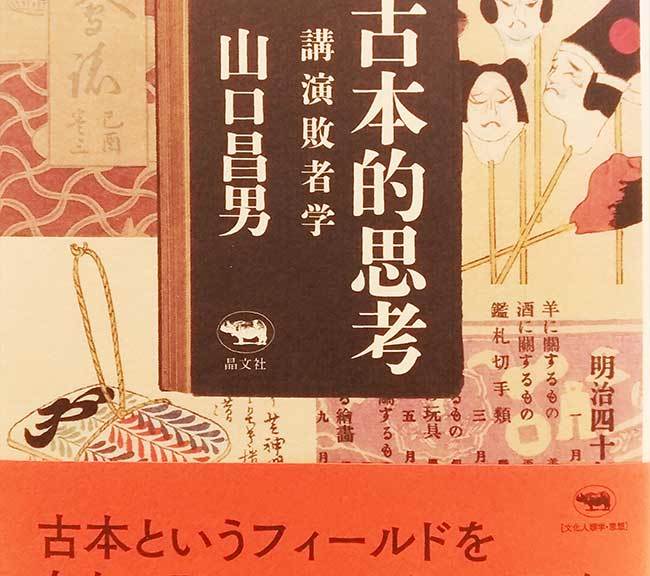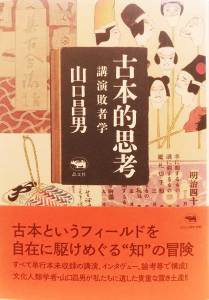■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
古書市&古本まつり 第71号
。.☆.:* 通巻266・1月10日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。
初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、
イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ
お出掛け下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「今回より、新連載南陀楼綾繁さんの「古本マニア採集帖」が、ス
タートします。
ナンダロウアヤシゲさんは、去年の8月に『蒐める人 情熱と執着
のゆくえ』(皓星社刊)を出しました。
今回の連載は、気になる古本マニアにインタビューして、その魅力
をメルマガで紹介します。お楽しみ下さい。」
━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━
古本マニア採集帖 第1回
かわじもとたかさん 古書目録から本をつくったひと
南陀楼綾繁
追悼号、畸人伝、すごろく、装丁家、序文……。かわじもとたかさ
んは、ほかの人が目をつけない独自のテーマに関する文献を集めた
書誌を30年近くにわたって刊行してきた。しかも、その情報のソー
スが主に古書目録だというのもユニークだ。連載のはじめにぜひご
登場いただきたいと、お住まいの近くの喫茶店でお会いした。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4456
南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)
1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一
文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、
図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年
から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」
の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。
「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ
・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を
つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に
『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市
の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、
『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』
(ちくま文庫)などがある。
ツイッター
https://twitter.com/kawasusu
『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著
皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!
http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/
━━━━━【1月10日~2月15日までの全国即売展情報】━━━━━
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
立川フロム古書市ご案内
期間:2019/01/05~2019/01/20
場所:フロム中武 3階バッシュルーム(北階段際)
立川駅北口徒歩5分 (ビッグカメラ隣)
--------------------------
第4回 調布の古本市
期間:2019/01/08~2019/01/22
場所:調布パルコ5階催事場 調布市小島町1-38-1
--------------------------
第35回 古本浪漫洲 Part1
期間:2019/01/09~2019/01/11
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)新宿区歌舞伎町1-2-2
--------------------------
有隣堂藤沢店フジサワ古書フェア(神奈川県)
期間:2019/01/10~2019/01/23
場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場
--------------------------
東京愛書会
期間:2019/01/11~2019/01/12
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/
--------------------------
京都マルイ新春古本市(京都府)
期間:2019/01/11~2019/01/14
場所:京都マルイ1階店頭(屋外・四条通側の屋根のあるスペース)
URL:http://machimachi-books.com/kyotomarui_bookfair.html
--------------------------
オールデイズクラブ古書即売会(名古屋)
期間:2019/01/11~2019/01/13
場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12
--------------------------
第35回 古本浪漫洲 Part2
期間:2019/01/12~2019/01/14
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2
--------------------------
大均一祭
期間:2019/01/12~2019/01/14
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
第19回 紙屋町シャレオ古本まつり(広島県)
期間:2019/01/12~2019/01/18
場所:紙屋町シャレオ中央広場 広島県広島市中区基町地下街100号
URL:http://furuhonmatsuri.blog.fc2.com/
--------------------------
第35回 古本浪漫洲 Part3
期間:2019/01/15~2019/01/17
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2
--------------------------
第35回銀座古書の市 ~美術書画・書籍コレクション~
期間:2019/01/16~2019/01/21
場所:松屋銀座8階イベントスクエア 中央区銀座3-6-1
--------------------------
さんちか古書大即売会(兵庫県)
期間:2019/01/17~2019/01/22
場所:神戸三宮さんちか3番街さんちかホール
--------------------------
第35回 古本浪漫洲 Part4
期間:2019/01/18~2019/01/20
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2
--------------------------
趣味の古書展
期間:2019/01/18~2019/01/19
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
第45回 鬼子母神通りみちくさ市
期間:2019/01/20
場所:雑司が谷 鬼子母神通り
URL:https://kmstreet.exblog.jp/
--------------------------
第35回 古本浪漫洲 Part5(300円均一)
期間:2019/01/21~2019/01/23
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2
--------------------------
和洋会古書展
期間:2019/01/25~2019/01/26
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
第131回 倉庫会
期間:2019/01/25~2019/01/27
場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12
--------------------------
五反田遊古会
期間:2019/01/25~2019/01/26
場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4
--------------------------
中央線古書展
期間:2019/01/26~2019/01/27
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
BOOK & A(ブック&エー)
期間:2019/01/31~2019/02/03
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
反町古書会館展(神奈川県)
期間:2019/02/02~2019/02/03
場所:神奈川古書会館1階特設会場
--------------------------
三省堂書店池袋本店古本まつり
期間:2019/02/05~2019/02/12
場所:西武池袋本店別館2階=特設会場(西武ギャラリー)
東京都豊島区南池袋1-28-1
--------------------------
書窓展(マド展)
期間:2019/02/08~2019/02/09
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
第5回古書会館de古本まつり(京都府)
期間:2019/02/08~2019/02/10
場所:京都古書会館3階 京都市中京区高倉通夷川上る
--------------------------
杉並書友会
期間:2019/02/09~2019/02/10
場所: 西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
オールデイズクラブ古書即売会(名古屋)
期間:2019/02/15~2019/02/17
場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12
--------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次回メールマガジンは1月下旬に発行です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国935書店参加、データ約630万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=22
┌─────────────────────────┐
次回は2019年1月下旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその266 2019.1.10
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:二見彰
編集長:藤原栄志郎
==============================