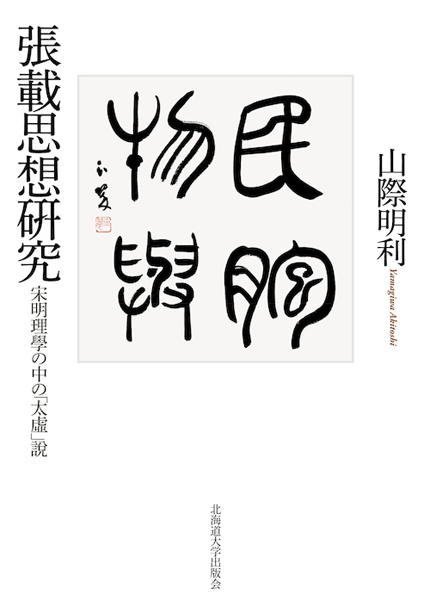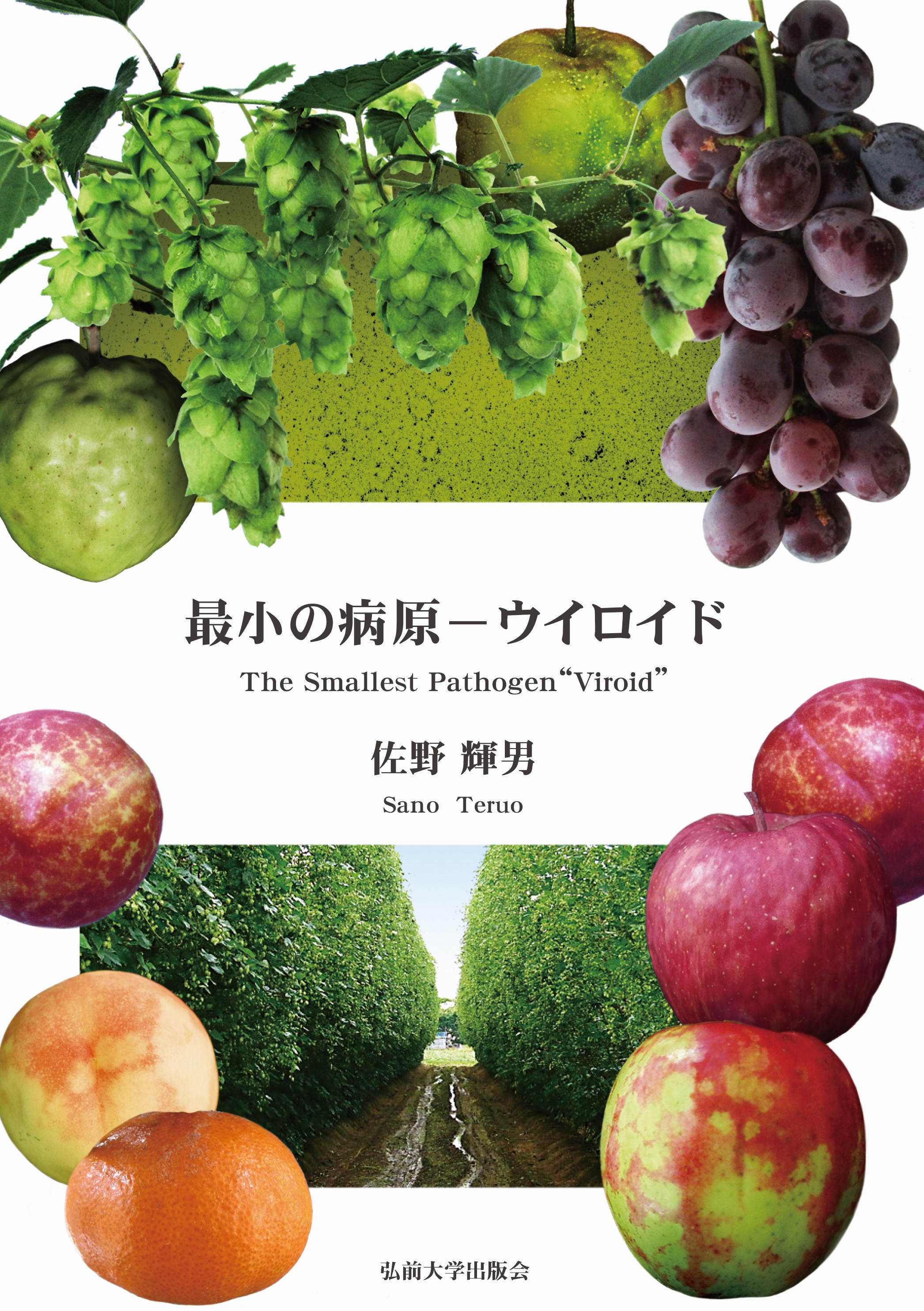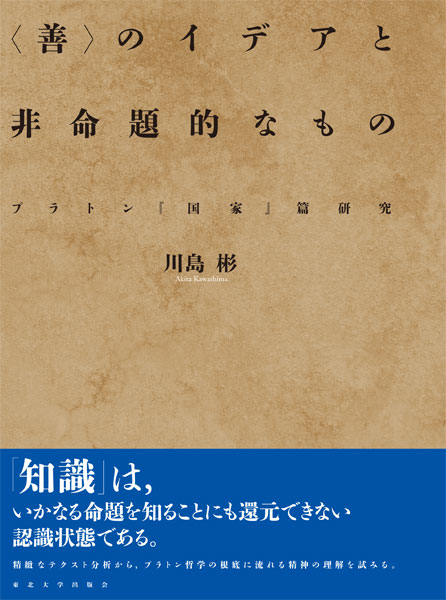『フォークナーの語りと創造世界』 【大学出版へのいざない7】梅垣昌子 (名古屋外国語大学教授) |
|
ノーベル賞作家のウィリアム・フォークナーには三つの顔があります。詩人、作家、そして脚本家の顔です。自らを「挫折した詩人」と呼んだフォークナーは、十代で詩を書きはじめたのですが、ロバート・フロストのように海外で知名度をあげるべく、渡欧の足がかりとしてニューオーリンズを訪れました。しかし意外にもそこで作家デビューを果たし、二十代の後半で長編第一作を出版する運びとなります。三十代のはじめ、ヨクナパトーファ・サーガの嚆矢となる作品を手がけたころから、経済的な事情もあって脚本書きの仕事を始め、故郷ミシシッピとハリウッドの間を断続的に行き来するようになります。四十代の後半、批評家マルカム・カウリーの編集による作品選集「ポータブル・フォークナー」が世に出てまもなくノーベル文学賞を受賞したフォークナーは、五十代の後半で映画の仕事に終止符を打ちました。
ノーベル文学賞の受賞スピーチで、フォークナーは次のように述べています。「昨今、ものを書く若い人たちは、人間の心の中に生まれる抜き差しならぬ葛藤を描くことを忘れてしまっています。この葛藤こそが優れた作品を生み出すのであり、唯一この葛藤こそが、七転八倒して文章を紡ぎ出すに値するテーマなのです。」作家にとって、何を語るかということが重要であることはいうまでもありません。しかし、第一次世界大戦の時に多感な思春期を過ごした「失われた世代」の一人であり、モダニズムの作家として知られるフォークナーは、「どう語るか」ということに終生、強いこだわりを示していました。すなわち、時代性や地域性と強く結びついた「葛藤」について、いかに普遍性を獲得した手法で語り尽くすのか、それが彼の創造性の根幹と強く結びついています。フォークナーは、あるインタビューの中で、芸術性や技量の高さの要求度という観点からすれば、詩が最高峰であり、その次が短編であるという考えを語っています。すなわち彼は、短編小説というのが、緻密な構成力と芸術的な手腕を要求する、重要な表現形式であると考えていたのです。 本書では、フォークナーの詩人と脚本家の側面を視野にいれつつ、彼の作家としての創作技法の特徴に照らして、その作品世界のひな型ともいうべき短編小説を主な考察の対象としています。本書の前半では、短編作品を重点的に扱い、フォークナー文学の根幹をなす語りの手法をつぶさに分析したうえで、後半では脚本の仕事に目を移し、彼の緻密な構成力を観察します。最後にフォークナーが詩人から作家へと変貌を遂げたニューオーリンズでの創作活動に注目し、彼の詩的想像力と語りの力の起源へ遡るという道筋をとっています。 フォークナーは、モダニズムの金字塔ともいうべき『響きと怒り』を執筆していますが、本書では、そこで芽生えたフォークナーの語りの四つの原型を出発点として、「土地」「時空間」「視点」「起源」という四つの軸を中心に、フォークナーの創造世界に分け入ります。フォークナーはかつて、自分の創造する世界を「宇宙の楔石(くさびいし)」にたとえ、「もしそれが失われたならば、宇宙自体が崩壊する」と語りました。創造することで崩壊をくい止めるフォークナーの楔石と、それを嵌め込む現実世界の迫石(せりいし)との接合面には、どのような摩擦が働き、その圧着を促していたのか。また、フォークナーのどのような語りがそれを可能にし、楔石が支えるアーチをくぐった先には、何が待っているのか。こういったことへの答えを探るべく、本書で扱う作品には、彼が重視した形式である短編を中心に、フォークナーの生きたアメリカ南部の現実を直接的あるいは間接的に鋭く照射するものを選びました。たとえば「あの夕陽」という作品では、白人の子供と黒人女性の交流の物語を黒人音楽のブルースとの関連性に触れつつ論じ、「乾燥の九月」については、ヘイトクライムを生んだ共同体のメカニズムに言及しています。そのほか、アメリカ先住民を扱った作品では、黒人奴隷との関係性に焦点をあてています。 フォークナーは1955年、米国国務省の文化親善大使として来日しました。その際、東京、長野、京都の各地でセミナーや座談会などに参加し、川端康成、大岡昇平、高見順らと直接語りあって、日本の文壇に鮮烈な印象を残しました。本書では、その後長く定着していた、ノーベル賞作家としてのフォークナー像に新たな光をあて、彼の作品に密着しつつその創造性の起源の多角的な解明を試みています。 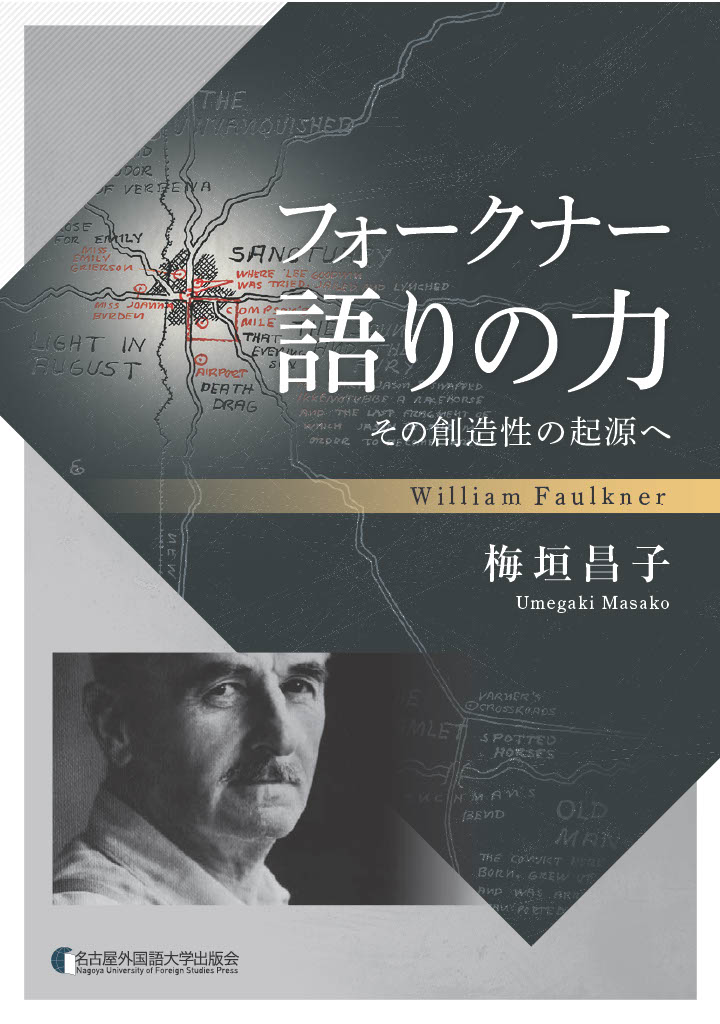 書名:『フォークナー 語りの力 その創造性の起源へ』 著者名:梅垣昌子 出版社名:名古屋外国語大学出版会 判型:A5/製本:形式上製/ページ数:445頁 税込価格:4,950円(本体4,500円) ISBNコード:978-4-908523-24-3 Cコード:0098 2023年8月下旬刊行予定 https://nufs-up.jp/ |
|
Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |