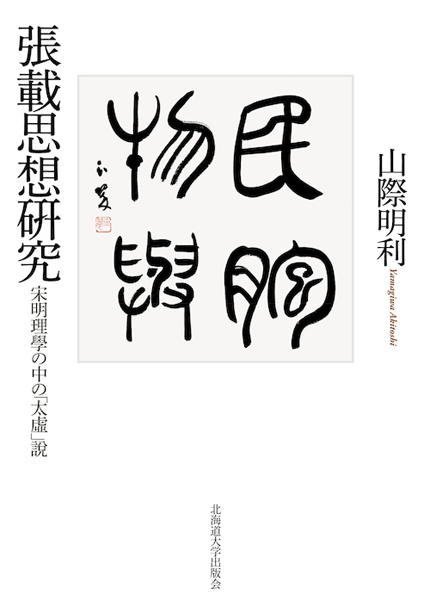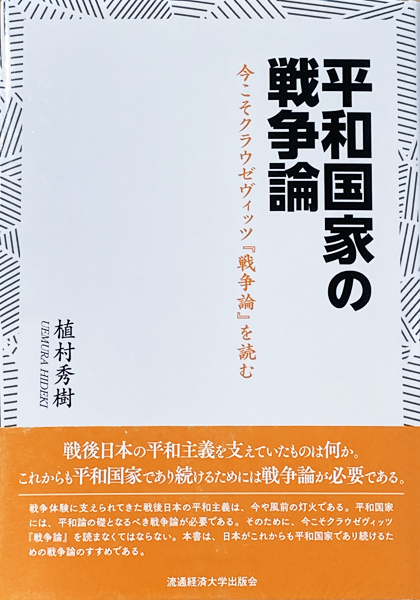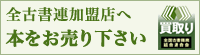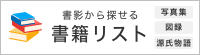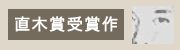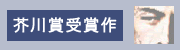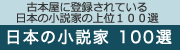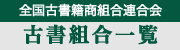『言葉を越えた対象との出会い』
|
|
プラトンの主著『国家』は謎に満ちた書物である。同対話篇はソクラテスの「僕は下って行った(κατέβην)」という言葉から始まる。ソクラテスがアテナイ市から下った先の外港
ペイライエウスは、対話が設定されている年代の後、ペロポネソス戦争終結後の混乱期に、 三十人政権の手による惨劇の舞台となった場所である。冒頭のソクラテスの言葉は、外の 世界を見た元囚人の洞窟への「下降」が語られる、第七巻の「洞窟の比喩」を暗示する。 他のすべてのイデアを超越しつつ、それらに可知性と実在性をもたらす〈善〉のイデア──これこそが「学ぶべき最大の事柄(μέγιστον μάθημα)」であるとも言われる──の構想が語られるのも、プラトンの対話篇中、「洞窟の比喩」を含む『国家』中心巻(第五〜七巻)の文脈においてのみである。しかし「洞窟の比喩」、先立つ「太陽の比喩」、両者を架橋する「線分の比喩」のいずれも、従来大きな解釈論争の的となってきた。プラトンの意図するところは、比喩によって、そして対話篇という形式そのものによって、いわば二重に隠されている。だがこれらの比喩は、ソクラテスが哲学者とはいかなる者なのか、哲学とはいかなる営みなのかを最高原理たる〈善〉と結びつけて語る文脈の内にある。およそプラトン哲学に関心があるすべての人にとって、避けては通れない重要箇所であるのは間違いない。 本書が目指したのは、その(ある意味では)極めて難解な『国家』という対話篇をプラトンの認識論に即して読み解くことである。 第一章で、『国家』第五巻末尾の議論(同対話篇ではここではじめて「イデア論」が登場する)に解釈を与えながら全般的な読み筋を提示し、続く諸章でその読み筋を肉付けしていく、という方針を取った。その際、プラトンが論じる「知識(ἐπιστήμη)」、あるいはそれと 以上のような読み筋をとろうと決めたのは、哲学とは何かそのようなものだという実感が、筆者にはあったからである。何か新しいもの、素晴らしいものと出会うことによって、人生は転換を迎え、先へと進む。筆者にとってそれは、高校時代のプラトンやデカルト、安部公房との出会い、大学進学以降の仙台、バークレー、東京などでのさまざまな人々との巡り会いであった。言葉のやり取りによってもたらされる、言葉を越えた対象との出会いという発想を 本書は2020年に東北大学に提出した博士論文が核となっているが、大幅な加筆・修正を施した。種々の制約から、博論では論じ切れなかった点がいくつもあったためである。実を言えば、プラトンで博論を書こうと決心したのは、高校生の頃だった。当時の筆者には、薄暗い教室で一斉に受験勉強に励む自分たちの姿が、洞窟の囚人の姿に重なって見えていたのかもしれない。本書を上梓することによって、高校生の自分との約束をようやく果たすことができた──そんな気がしている。 |
|
Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |