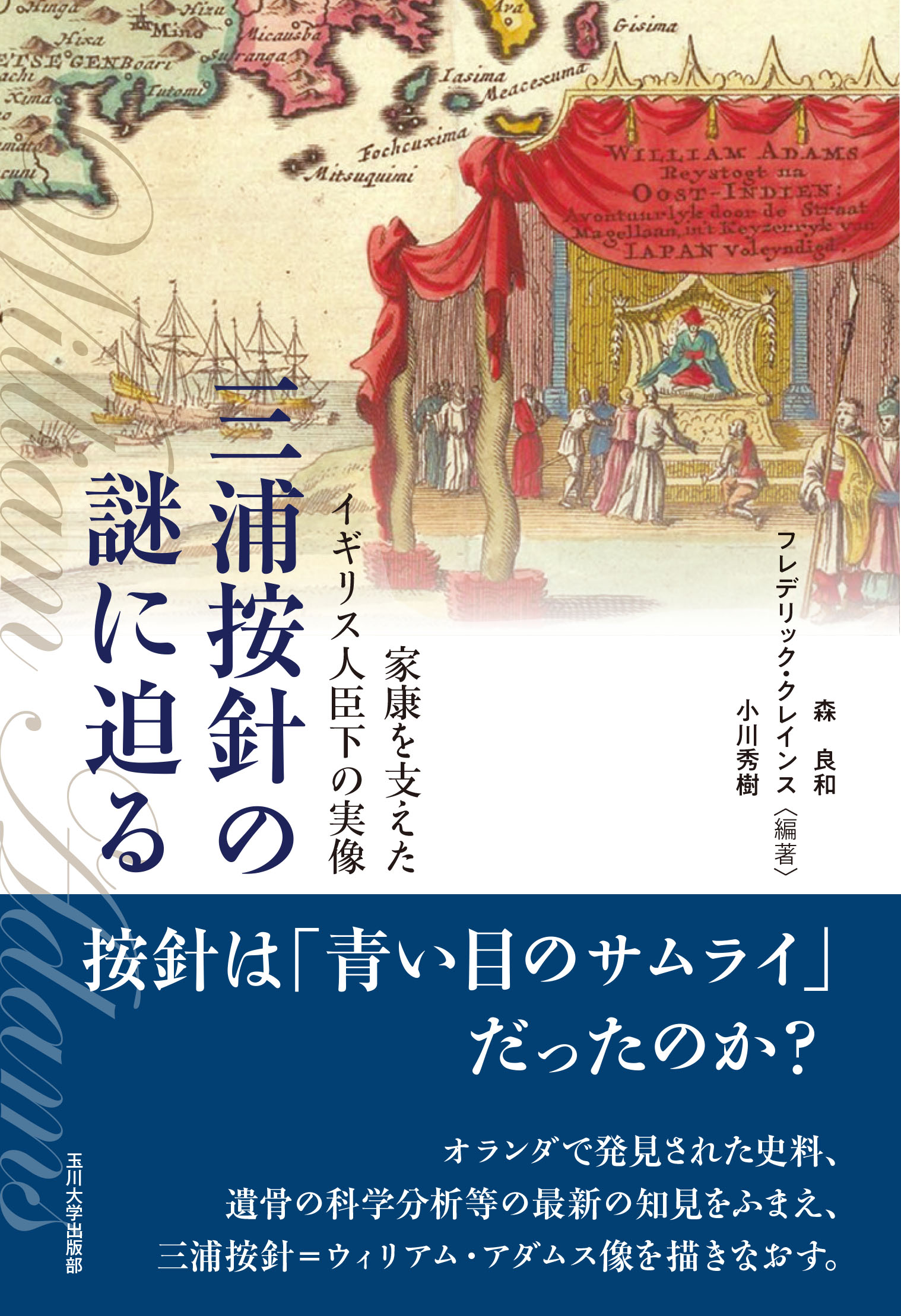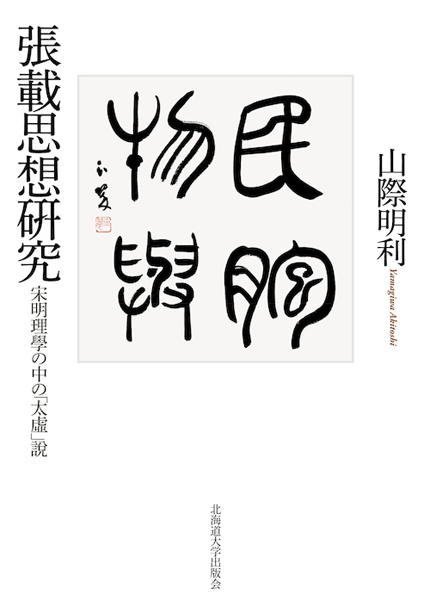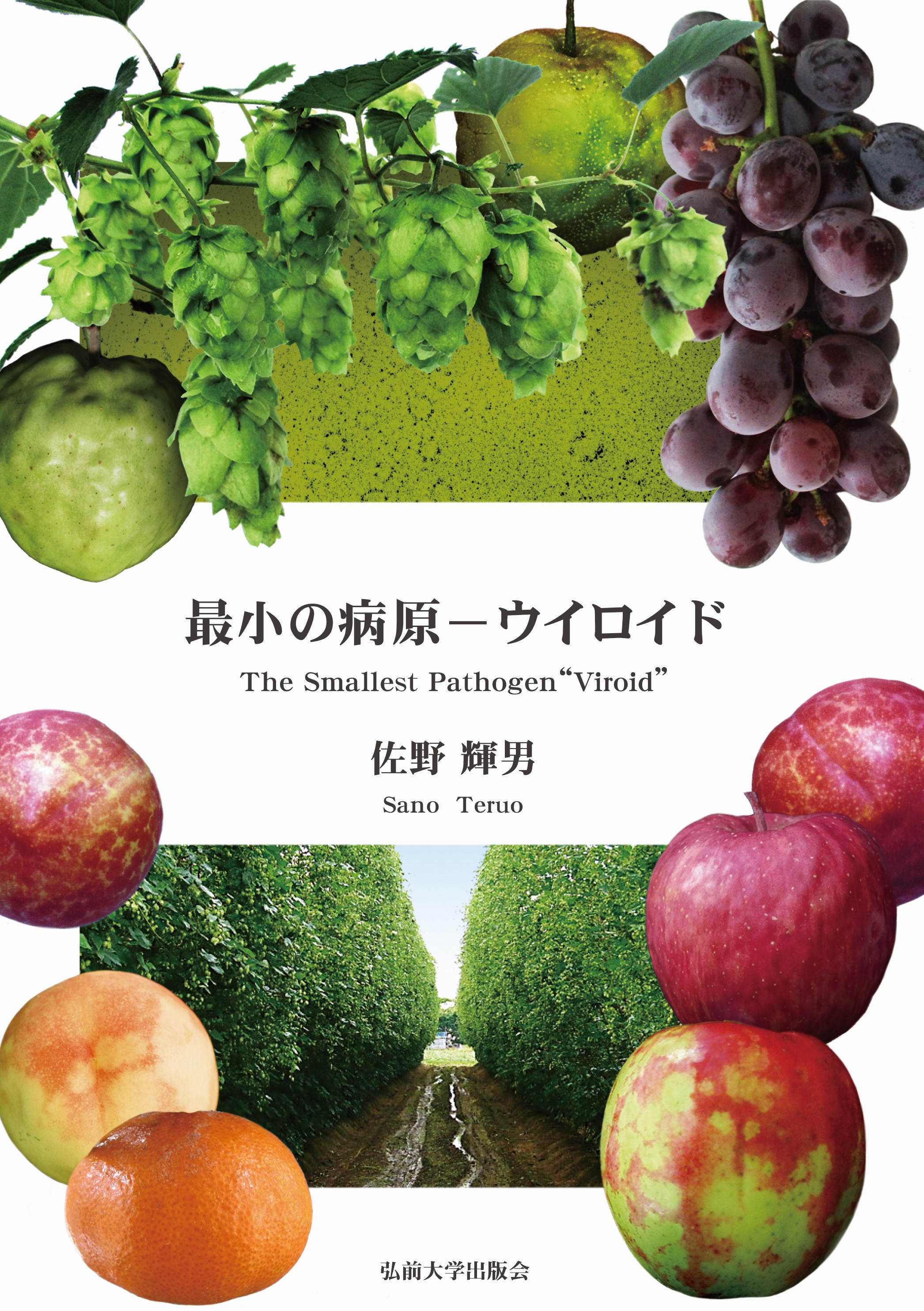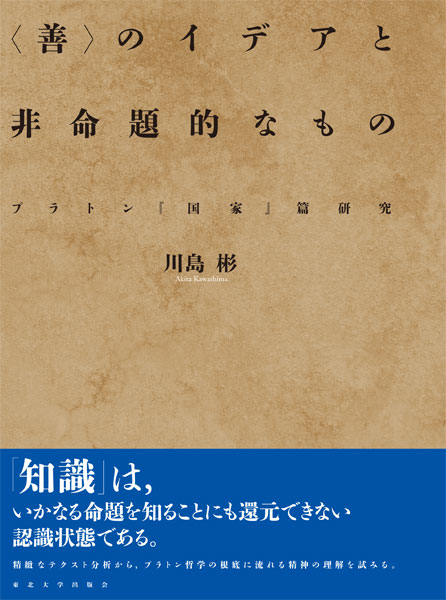『近年の新知見をふまえて三浦按針像を描きなおす』【大学出版へのいざない18】森 良和(元玉川大学教授) |
|
三浦按針をご存じでしょうか。
関ヶ原の戦いの半年前、オランダ船リーフデ号が豊後の海岸に辿り着きました。1年10ヶ月にも及ぶ過酷な航海で、生存者は出発時のほぼ5分の1、20数人にまで激減しました。その船の航海士がイギリス人ウィリアム・アダムス(日本名三浦按針、以下「按針」)です。まもなく按針は大坂に移送され、時の最高権力者徳川家康の尋問を受けます。家康は問いに誠実に答えるこの異人を大いに気に入り、自らの臣下に加えるとともに、やがて相模国に領地まで与えました。日本の歴史を通じて外国人が領主となった唯一の例です。 按針は西洋に関する多くの新鮮な情報を家康にもたらしました。それまで日本で得られる西洋の情報は、もっぱらカトリックの宣教師を通じてのものでしたが、按針はヨーロッパが宗教的に二分され、対立国同士が戦争状態にあることを教えました。さらに西洋船を建造して優れた西洋の技術を具体的に示すとともに、オランダやイギリス関係の外交文書を作成したり、大坂の陣で用いられた大砲の輸入を斡旋したりしました。 それでも按針の生涯や事績にはなお不明な点が多く残されています。1613年のイギリス船の来航以前に按針に言及した史料はかなり限られ、そのため根拠の乏しい創作話が流布する場合さえあります。歴史にロマンを求めることは楽しいですが、もちろん史実とフィクションには区別が必要です。本書ではそれを踏まえて、諸分野の専門家がそれぞれの立場から信頼のおける史料に基づいて作成した論考を集めています。 各章では従来あまり取り上げられなかった按針論や、先行研究とは異なる視点から捉えた論考が展開されています。すなわち、按針がオランダ船でやってきた背景、カトリック勢力との関係、幕府や平戸藩との権力関係、帰国しなかった理由、船手奉行向井一族との関わり、アダムスが作成した日本地図の探求、オランダ商館との関わり、イギリス商館衰退の理由などが追究されています。 さらに本書の構想段階で、平戸にある伝按針墓の発掘作業が終了し、そこから出土した遺骨の科学的鑑定結果も発表されました。本書でもかなりの紙幅を割いて、それについて論じています。詳細については内容にあるとおりですが、遺骨の年代測定やDNAの分析結果を援用して歴史学的検証と照合させると、遺骨が按針のものである確率はかなり高まったと言えそうです。 江戸時代初期は日本の近世史上でも例外的なグローバル時代でした。カトリック国のポルトガルとスペイン、プロテスタント国のオランダとイギリスなどが、極東の地でそれぞれ、両グループの内部対立も抱えながら相争い、これに中国明朝の商人も絡んで勢力拡大を図りました。按針はそのいずれとも多かれ少なかれ関わっています。 本書を一読した読者は按針の奥深い魅力にいっそう引き込まれるとともに、按針を通じて、近世初期の日本を舞台にした世界史的スケールでの歴史のダイナミズムを再認識できるでしょう。 |
|
Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |