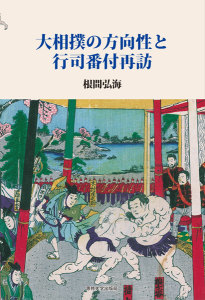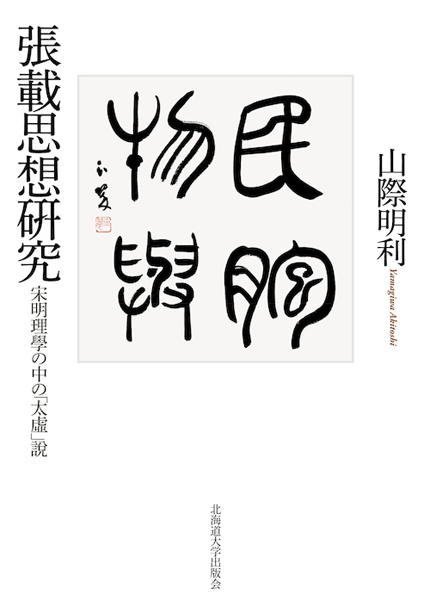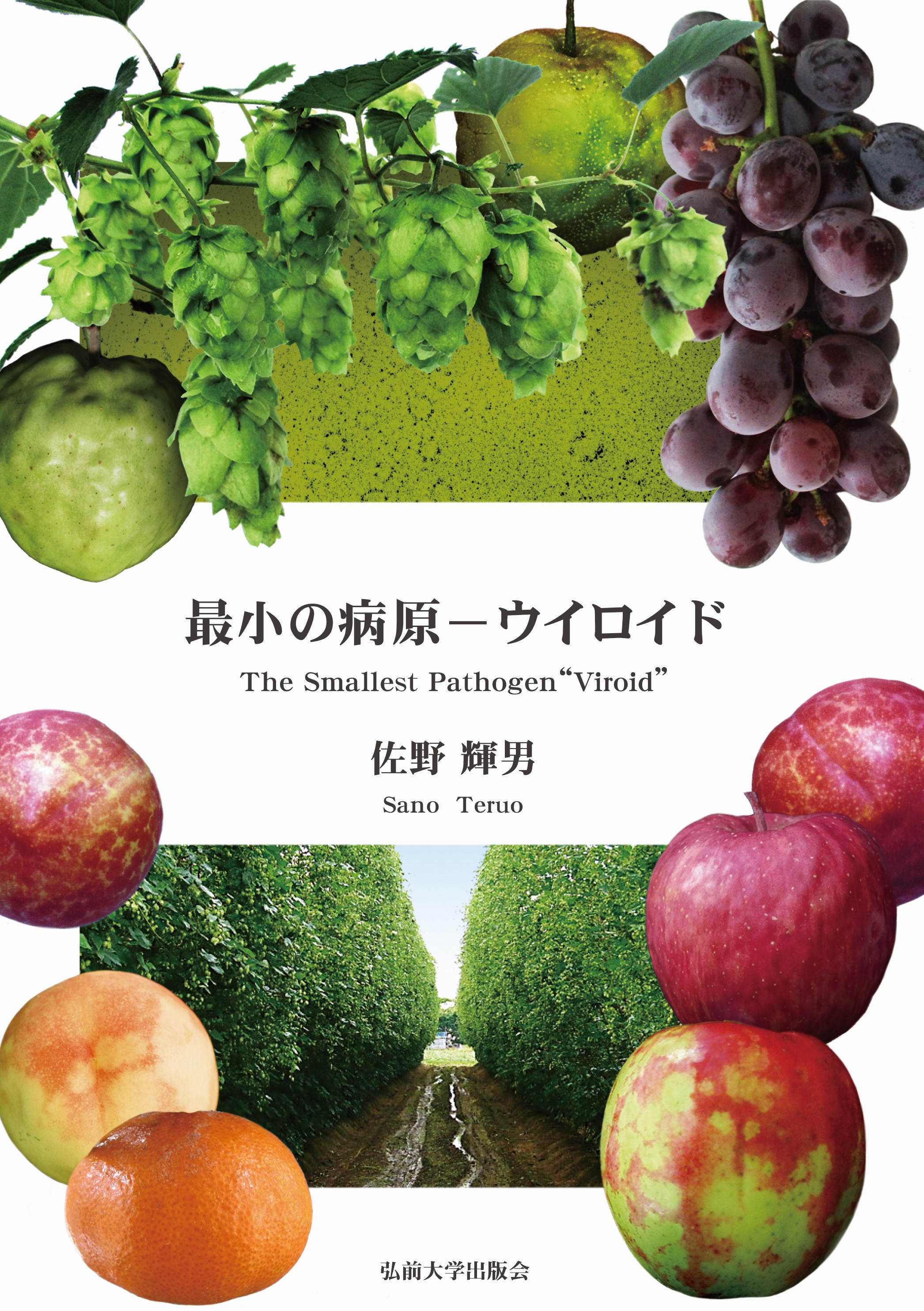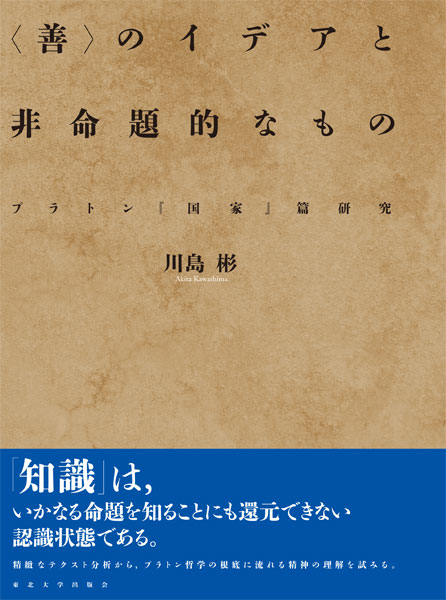筆者は長い間、大相撲の行司に焦点を絞り研究を続けている。行司は、相撲の取組を裁く
審判者としてだけでなく、大相撲という組織を裏から支えてきた。また行司の世界は、力士の世界や相撲界と同様にその歴史はさまざまな変遷を経ている。いずれの世界も密接に絡み合っているので、どのテーマであれ、面白い研究になるのである。
本書では、筆者の今までの研究の中から大相撲関連の九つの話題を取り上げ、それぞれを論考形式でまとめている。ここでは、その中から二つの話題を取り上げて紹介しよう。
一つ目は、「大相撲の儀式や所作には一定の方向がある」ことである。たとえば、横綱・
幕内・十枚目土俵入りでは、先導する行司と力士は土俵を左回りに一周する。力士が一定の
所作をしているあいだ、行司は蹲踞し、軍配房を右→左の順序で振り回す。また、勝負の取組で勝った力士が賞金を受け取るとき、その勝ち力士は左→右→中央の順序で手刀を切る。
土俵祭では、方屋開口の祝詞を唱えた直後に軍配を左右に振ったり、土俵の四つ角にお神酒を注いだりする儀式があるが、その順序は左→右→左である。清祓いの儀式でも榊の枝を振り
かざすのは、左→右→左の順序である。触太鼓土俵三周の儀式では、太鼓を叩きながら土俵を三周するが、それは左回りである。
儀式や所作では、なぜ一定の方向で動くのだろうか。中にははっきりしていないものもあるが、それぞれに理由がある。左→右→左の順序は、神道に基づいている。しかし土俵を三周
するのが神道に基づいているのかどうかは、まだ明白にできていない。本書では、それぞれの儀式の理由付けに関しては深い説明をしていない。今後深く追究してくれる方が現れることを期待している。
二つ目は、以前の著作に論考として掲載した「明治元年から大正末期までの行司番付」を再び取り上げた。本書で新しく変わっているのは、それぞれの行司の房色や履物(草履か足袋)を詳しく提示してあることである。たとえば、紫房には四つの変種(総紫房、准紫房、真紫白房、半々紫白房)があるが、それを各行司に提示してある。また、朱房行司には草履を履く
行司と履かない行司がいるが、その履物の種類を明確に提示することができた。
本書の番付研究では傘型表記を現代風に並列(または横列)表記にしてあり、行司間の序列が一瞬でわかる。ただし、青白房・紅白房・朱房行司の境界では各行司の階級が必ずしも明確でないので、その階級の分け方には問題があるかもしれない。特に、明治元年十一月から明治
二十九年冬場所までの各行司の階級判別にはかなり苦労した。番付表や星取表、それに大相撲勝負一覧表などを活用したのだが、階級を区別する空間がなく、その判別はかなり難しい。
字の大きさや太さは参考になるが、絶対的ではない。明治三十年以前の行司番付や房色は、
立行司は別として、これまでほとんど研究されていない。本書はそれに一石を投じ、叩き台のつもりでまとめてある。
番付を調べていくと、朱房昇進の年月が明確に指摘できない行司がときどき出てくる。
たとえば、木村朝之助(のちの十八代木村庄之助)の朱房昇進年月はいまでも資料で確認できない。他方、昇格年月が間違って理解されている行司もいる。たとえば、木村瀬平は慶応元年冬場所に幕内に昇格したとしばしば文献に記述されているが、実はそうでない。というのは、慶応元年冬場所や明治元年冬場所の番付表を見るかぎり、そのような地位に記載されていないからである。
また、木村竜五郎(のちの十六代木村庄之助)は明治六年に幕下十枚目(青白房)だったと
されているが、実際は幕下格(黒房)だった。明治六年の番付表を見るかぎり、三段目の
真ん中(右から六番目)に記載されている。この分析は星取表の行司欄二段目左端が十枚目格の行司であるという前提に基づいている。この前提については引き続き、今後も検討しなければならない。これらは番付表や星取表の行司欄を、根気強く読み解き、分析して見つけた結果である。
この二つ以外の話題としては、四本柱の四色と吉田司家の関係、三十五代木村庄之助との対談記事、行司の自伝や雑誌記事などの間違った記述、昇格年月の不明な行司、行司の研究などを取り上げている。力士や行司のちょっとして所作や動作、使われている色などにも歴史や由来が隠されている。それらを掘り下げていけばいくほどに興味深い話題や視点が現れてくる。
取組だけでなく大相撲の世界は奥深く興味深いのである。
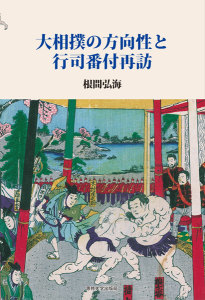
『大相撲の方向性と行司番付再訪』
根間弘海 著
専修大学出版局 刊
3,300円(税込)
ISBN:978-4-88125-393-9
好評発売中!
http://www.senshu-up.jp/author/a93212.html