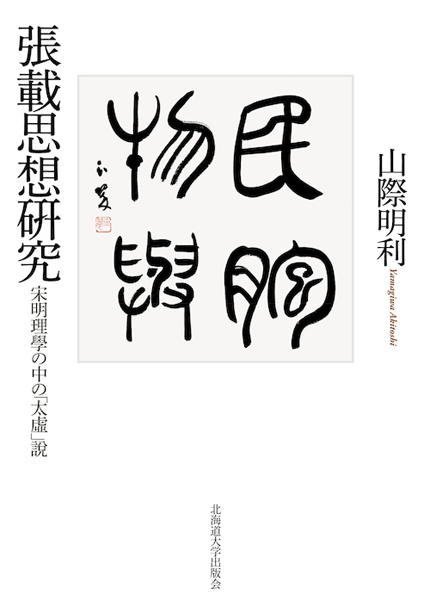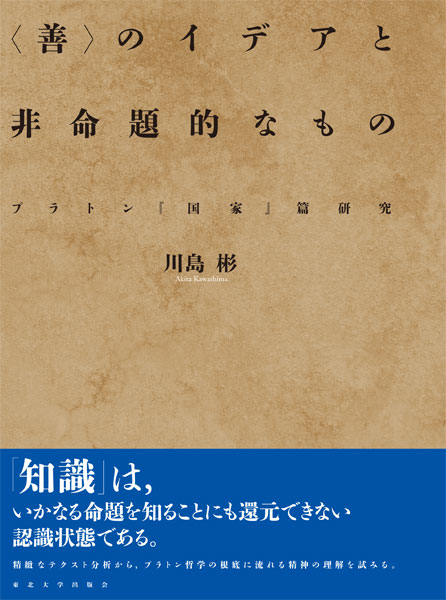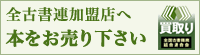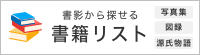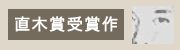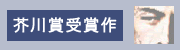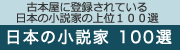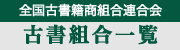平和国家の戦争論ー今こそクラウゼヴィッツ『戦争論』を読むー
|
|
「平和国家」を標榜してきた戦後の日本、すなわち日本国は、看板だけでなく実態も概ね
それを裏切るものではなかった。それが今、曲がり角に来ている。というより、むしろ風前の灯火と呼ぶべき状態にある。本書はそうした問題意識を背景としている。 私は主に戦後の再軍備過程とその後の防衛政策の展開、および日米安保体制との連関についての研究に取り組んできた。日米両国の一次史料に基づく実証研究に加えて、沖縄・普天間基地の間近に居を構え、半年余りにわたって現地調査に当たってこともある。しかし、このたび上梓したのは、そうした研究とは少々異なるものである。戦後平和論の限界がどこにあるのかを見極め、新しい平和論の礎石のひとつらんとの思いから執筆したものである。 結論を言えば、これからも平和国家であり続けるためには、戦争論の研究が必須である。 「哲学者たちの平均的教養の狭隘さと貧困……が原因で、クラウゼヴィッツの著作のような書物が哲学者たちの関心の外にあり、忘れ去られていたのだ。」 19世紀のプロイセンの将軍カール・フォンクラウゼヴィッツのこの古典的名著は、今もその輝きを全く失っていない。「クラウゼヴィッツはもはや時代遅れ」、「戦争は新しい段階に入った」という声もあるが、そうであろうか。ロシアのウクライナ戦争もイスラエルのガザ戦争も、国民国家(ネーション・ステート)によるネーションをめぐる武力行使、すなわち、ネーションの戦争という、フランス革命戦争以来の近代戦争の本質は、何ら変わっていない。 軍事的かつ歴史的、そして哲学的にネーションの戦争の本質に迫ったのが『戦争論』であり、今日に至るまで、これに代替しうる、ないし超えるものは現れていない。このことは先の このクラウゼヴィッツ『戦争論』を軽視してきたのが、わが日本国の平和主義者たちで 戦後民主主義の旗頭と目される政治学者の丸山眞男もしかりである。丸山の戦争観もまた軍隊体験に深く依存しており、したがってその平和論も体験からほとんど直接的に導き出されたものであった。このように戦争体験に依存した平和論がもはや、平和と繁栄を謳歌してきた現代の世代に響くものではなく、その当然の帰結として行き詰まりを見せているのは、当然の成り行きというべきであろう。 私の勤務する大学の学生の多くが「日米安保は、米国が日本を守ってくれる有り難いもの」と考えている。戦後体制――「戦後レジーム」と呼んでもよい――が敗戦後の占領と米国の 近年改善の兆しが見られるとはいえ、日本のクラウゼヴィッツ研究はきわめてお粗末な状態にある。「国民万歳」を叫んだフランス革命軍に接したゲーテは、「世界史は新たな段階に入った」と喝破した。その戦争を軍事的のみならず、歴史的、政治的、そして哲学的に深く 自分の本来の専攻領域を超えてまで、私がクラウゼヴィッツ『戦争論』の歴史的かつ哲学的背景――カント、モンテスキュー、マキアヴェリらの影響を考えることを抜きに『戦争論』は理解できない――にまで掘り下げて読み解き、これを平和論の基盤に据えようと私が提案するのは、平和国家・日本の行く末に対する危機感に他ならないが、同時に、戦後社会科学の欠落の一部を埋めるものとも考える所以である。 戦争論なき平和論は無力であろう。平和に関心を持ち、日本国がこれからも平和国家で |
|
Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |