前回取り上げた恩田逸夫と小沢俊郎氏に続き、同じく戦場・軍隊から大学に復学した研究者の宮沢賢治との関りについて続けたい。
日本近代史・思想史研究者色川大吉氏の『わだつみの友へ』(同時代ライブラリー164、1993)は、学徒出陣から復学した当時の若者・研究者の心情を伝える名著である。しかも
宮澤賢治が当時彼らにどう読まれていたかもわかって興味深い。
色川氏は昭和19年夏、大学に籍をおいたまま海軍に入隊し、土浦航空隊に配属になる。
その入隊前に読んでいた本について、同書の「汚辱の時代」に書いている。「入隊の直前まで、私たちがどんな本を読んでいたか。日記から拾ってゆくと慄然とする。ハウスホッパー(佐藤壮一郎訳)『太平洋地政学解説』、アドルフ・ヒトラー『演説集』『ナチス国家
原理』、エス・ニールス(久保田栄吉訳)『ユダヤ議定書』、四天王延孝『ユダヤ思想及
運動』、それにローゼンベルクやシュペングラーの著書、由良哲次らの日本国体合理化の
『実践哲学』等々であった」「シオニズムの恐ろしさを信じこみ、人類の救主としてナチスを支持しながら、大量虐殺の心理的な準備をしていたのかと思うと、ほとんどいうべき言葉を
失う」と。
そして「いっぽうで私たちは生命的なものを求めていた。ゲーテの『ウイルヘルム・マイスター』、ヘッセの『デミアン』、カロッサやロダンやブールデルやベートーベンなどのエッセイや書簡集、そしてもっとも自然な形で、もっとも温かく私たちの心に浸みていた宮沢賢治の思想。入隊の前日、私は賢治の『雁の童子』を読んで、その透き透るようなヒューマニズムに深く深く打たれた」と。
戦前、賢治の童話は、『注文の多い料理店』もしくは文圃堂書店の全集(昭和9~10年)か十字屋書店版全集(昭和14~19年)、羽田書店の松田甚次郎編『宮澤賢治名作選』(昭和14)、八雲書店の1冊だけ刊行された「宮沢賢治作品集」『フランドン農学校の豚』(昭和18)で読めたが、文圃堂版全集と『注文の多い料理店』は当時でも学生には手が出なかっただろう。羽田書店版『宮澤賢治名作選』には「雁の童子」も収録されている。八雲書店版には未収録である。
色川氏は2017年、第27回宮沢賢治賞・イーハトーブ賞を受賞し、「宮沢賢治の国際主義と非戦思想―戦中派世代に深い影響」と題した記念講演をされている(『イーハトーブの森で
考える―歴史家から見た宮沢賢治』河出書房・2019に収録)。そこで「わたしは戦争中から宮沢賢治の作品は読んでいました。賢治は昭和八年に亡くなっているんですね。わたしはそれから十年後の、昭和十八年に東京大学文学部に入って、そのとき松田甚次郎さんが編纂されていた『宮澤賢治名作選』という本を読んだのです。これを同級生で読み合い、勉強会もやっていた」と話している。賢治童話は子供の読み物の域を超えて大学生に熱心に読まれていたことがわかる。
「雁の童子」は、賢治が興味を抱いていた、中央アジア西域での古代都市発掘という状況を基に描いた「輪廻転生」の物語で法華経思想が非常に色濃い作品である。色川氏が「透き透るようなヒューマニズム」を読み取ったのはどんな点だろうか。小埜裕二氏は「慈悲と空間―
宮沢賢治「雁の童子」論」(上越教育大学紀要25巻・平成18)で、「賢治は現実世界を
〈修羅の世界〉と観じ、そこから救われよう、人々を救おうとする童話作品を創りだしていく一方、「天の童子」の思いに見られるような、現実世界の生あるものに情愛のまなざしを向ける慈しみの目をもっていた。
仏教が説く、業によって無限に転生を繰り返す、気が遠くなるような輪廻転生の理法のなかに〈再会の喜び〉をあじあわせる〈繰り返される因縁〉の存在を提示することは、(略)「天」へと昇り、仏の世界へ近づいていこうとするものにとっての救いとなる」と書いている。死を覚悟せねばならなかった当時の学生達には切実な思いで読まれたのだろう。文学に限らず芸術品は受容される時代状況の中で意味合いを変える。
色川氏は『わだつみの友へ』で同期入学、しかも同じ土浦航空隊に配属された青村真明という若くして亡くなった歴史家について書いている。まさに親友と呼べる存在だったようだ。
昭和28年肺結核により29歳で亡くなるのだが、翌年研究者仲間によって『青村真明遺稿集』(同刊行委員会・日本近代史研究会)が刊行される。この本は幸い「日本の古本屋」で入手出来た(有難いサイトである!)。
遺影、刊行のことば(服部之総が書く予定だったが病気で叶わず、日本近代史研究会として代筆)、論稿7編、書簡70通、追憶として27名の追悼文(母青村武子、色川、小西四郎、松島栄一、遠山茂樹、吉沢忠、宮川寅雄など)、年譜が収められている。
書簡には色川氏宛ての12通が収められているが、昭和21年2月21日の書簡に次の様な件がある。「兄が六日附で出した葉書昨十一日午後着いたので今日早速神田へ行った所、兄の依頼の賢治全集時既に遅し二、三日前に交換して行ったと云う光明堂(三光堂の隣)主人の話。
後の祭りで空しく長蛇を逸してすごすご帰ってきた。誠に期待に応えられず済まなく思う。
罪は何にあるか知らぬが縁がなかったものと諦めてくれ。尚新聞広告で承知かと思うが建設社内の日本読書組合で近刊予定になっている賢治全集(全八巻)でも申し込まれたら如何。
俺も一週一回位神田へ行くが賢治全集は珍本で容易に見当たらず、少なくとも俺の見た限り
去年の十月から今日まで名作選といい全集の一部といい本屋の交換棚に出たことがない始末だ。小生も名作選を求めているが縁がないのか遭遇しない」。ここで言っている全集は文圃堂版ではなく十字屋版であろうが、この時代は入手困難であったことがわかる。十字屋の戦後版は昭和22年からの刊行である。日本読書組合版『宮澤賢治文庫』全6冊は昭和21年12月からの刊行であった。
光明堂という古本屋は知らないが三光堂はつい最近まであった新刊書店(日本文芸社ビルの隣)である。交換棚というのは当時古本が不足して購入するためには交換する古本を持っていく必要があったのだ。全ての古書店がしていたわけではないと思う。ともかくも当時良質の
古書は不足していたのである。古本屋にとっては絶好機だが商品の仕入れも難しかったのだろう。
色川氏は戦時中に『宮澤賢治名作選』を友人と読み合い勉強会も開いたと書いている。彼らは当時同書をおそらくそれぞれに所持していたが、出征する際に処分したり、蔵書を戦災で焼失したのであろう。
去る11月に神奈川近代文学館で開かれていた「安部公房展」を見てきた。展示入口に三浦
雅士氏の言葉があって、安部の最後の作品『カンガルーノート』と賢治の『銀河鉄道の夜』は対応しているとあり、そうなんだと思ったが、安部が保管していた文庫本が展示され、その中に古色を帯びた新潮文庫『宮澤賢治集』があった。これは昭和24年7月刊行の古谷綱武編集の文庫である。この文庫、当時の読者の渇を癒したことだろうと思う。阿部は1924年、色川は1925年の生まれである。
恩田や小沢の参加した宮沢賢治研究会の機関誌「四次元」第2巻9号(昭和25年10月)に「宮澤賢治についてのアンケート」が掲載されている。新居格、正富汪洋、荻原井泉水、古谷綱武、串田孫一など29名が回答している。質問は4項目で1番目が「宮沢賢治を知った動機」である。岡本潤や竹内てるよは、自らも同人だった「銅鑼」でと答えているが、竹下数馬、
小沢俊郎、阿部次郎、藤森朋夫、恩田逸夫の4名は、『宮沢賢治名作選』もしくは羽田書店の本でと回答している。小沢俊郎氏が「尊敬する一先輩より推薦されて「風の又三郎」(羽田書店)を読んでから」と書いているのは、恩田が「高等学校の時、盛岡出身の友人が「名作選」を持っていたので始めて彼の名を知りました」と回答しているから、恩田から『名作選』を教えられ「風の又三郎」を読んだのであろう。戦時中から終戦直後にかけて宮沢賢治が受容されていく中で『宮澤賢治名作選』の果たした大きさを感じる。
ところで、恩田、小沢両氏には賢治の童話に関する論稿が少なくないが、タイトルに「雁の童子」をあげているものは無さそうである。恩田逸夫著『宮沢賢治論』3「童話研究他」に「宮沢賢治と天の童子」があり、恩田氏の賢治研究のキーワードともいえる「まことのちから」の視点から取り上げられているが「雁の童子」が中心テーマではない。『小沢俊郎 宮沢賢治論集』3冊には収録がない。「雁の童子」を論じたものとして先に小埜裕二氏の論考を
紹介したが、分銅惇作には「「雁の童子」―旅の意識と信仰の課題」と題したとした論稿
(双文社『宮沢賢治作品論』収録・昭和56)があり、未見だが杉浦静氏に「『雁の童子』序説―天人、壁画の中の子供らの系譜」(「国文学解釈と鑑賞」第53巻2号・1988)があるが、「銀河鉄道の夜」「風の又三郎」などに比べれば論稿数は多くないようである。しかし、出征直前の色川氏のこころを揺さぶったのは「雁の童子」であった。
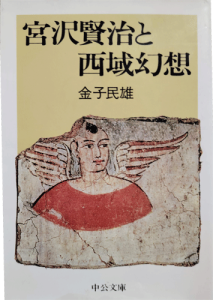
〇金子民雄『宮沢賢治と西域幻想』
ここからが「破棄する前に」に関する事項になるが、『動乱の中央アジア探検』『東ヒマラヤ探検史』『ヘディン伝』などの著書のある金子民雄氏に『宮沢賢治と西域幻想』(中公文庫・1994。元版1988白水社版の増補改訂版)がある。西域好きの金子さんが、語弊があるのを承知で言えば強引に賢治と西域を結び付けて論じた本だろうと思っていた。しかし小埜氏の論考を読んで、以前ブックオフで買ったこの文庫を持っていたのを思い出した。書庫からようやく見つけ出して中をみて、恐らくこの著書が「雁の童子」に関する最も詳しく重要な文献であると、素人なりに直観した。
巻頭「西域童話三部作」に次のように書いている。「西域童話というのは、いつごろからか賢治の作品研究者によって仮に呼ばれるようになったもので(略)賢治は自分から「西域
童話」とは言わなかったが、「西域異聞」という名称では呼んでいた。それは、現在、草稿で遺されている童話「雁の童子」の原稿の題名の右方に、赤インクで「西域異聞〔とも云ふべき(削除)/三部作中に/属せしむべきか〕と、記入してあったことによる」(略)「西域童話の三部作を、どれとどれに限定して呼んだのかということを記していない。
しかし、これは明らかに前後の事情から、「マグノリアの木」「インドラの網」「雁の童子」の三作品を、こう呼んだらしいことが推測される」「賢治が一生のうちに書いた、ざっと
百四十篇の童話の中の草稿のまま遺された作品で、最も完成度の高いものは、もしかするとこの三篇の西域童話だったかもしれない」と。さらに「「雁の童子」が注目されるのは、西域を扱った賢治の童話の中で、最も完成度が高いからである。もしこの童話がなかったら、改めて、賢治の西域童話を論ずるだけの価値があるかどうか疑わしいほどである」とまで書いている。
この文庫の表紙に印刷された翼のある「壁画の童子」が中心となって語られるのが「雁の童子」の話であり「天を飛ぶ雁が地上に落下し、鳥から人間になった子供を主人公にしたところが、新鮮であり、この種の西域作品としては最終的な完成品だったといえよう」とも書かれている。
色川氏は死を覚悟したような心情に中で「雁の童子」の本質と、賢治作品の中に占めるこの作品の位置を読みとったのであろう。
『宮沢賢治と西域幻想』捨てずに良かった。
※シリーズ古書の世界「破棄する前に」は随時掲載いたします。