「野町和嘉 人間の大地」展の衝撃
8月7日に、世田谷美術館で開催中の「野町和嘉 人間の大地」と題された写真展を見て来た。同館の学芸員野田尚稔さんから同題名の図録(A5判、231頁、定価3960円。クレヴィス刊行)を頂いていた。圧倒されるドキュメンタリー作品ですよと話されていたが、図録を見ると砂漠や荒涼とした大地に生きる人々を写した作品も、全て芸術的な香気に溢れ、ドキュメンタリーとは違うのではないかと考えていたが、図録に収められた作品と、展示会場で見た襖より大きなサイズに焼き付けられた作品は別物であった。野田さんがドキュンタリーであり圧倒されますよというのが実感出来た。フォトジャーナリスト野町和嘉さんが家畜と人間の間に壁を作るのが「文明」であると書かれているが、南スーダンの遊牧民の大きな角をもった牛と人間の共生する生活は正にその言葉を裏付けていた。日本でも牛や馬を使った時代の農民の暮らしは曲がり屋に代表されるように、確かに家畜と人々が共生していた。農耕民と遊牧民の差はあるとしてもどこか共通したものがある。現在の我々の文明から失われたものの一つであろう。
今回私がもっとも衝撃を受けたのは、第3部「エチオピア 旧約聖書の世界」と、第5部「メッカとメディナ イスラーム大巡礼」の各作品であった。メッカのアカバ宮殿や、ムハンマンドの廟墓のある聖地メディナに群集するイスラム教徒たちの様子は、しばしば報道されるので知ってはいたが、通常の日本人の感覚からはかけ離れたパワーが写真を通して響いてくる。またアフリカに初期キリスト教を伝える文化が残ると聞いたことはあったが、エチオピアの標高2500メートルの聖地ラリベラに褐色の肌に白いターバンと衣をまとった人々がクリスマスを祝うため遠隔地から巡礼の旅を重ねて集った群集の姿や熱気を初めて眼にすることが出来た。
またエチオピア北部ティグレ州の絶壁にある無数の岩窟教会と修道士たちの姿は、ローマ帝国の迫害に耐えて信仰を守り続けた初期キリスト教徒の姿を彷彿とさせるものがあった。それらの作品に対する衝撃に近い思いに捉われ、しばし写真の前に釘付けになった。現在世界は混迷の時代を迎えているが、今後世界情勢が危機を脱して良くなるにせよ、再び戦争の暗黒の世界が到来するにせよ、それは机上の政治学や経済学に裏付けられた理念ではなく、宗教的な群集のパワーの進む先にあるような気がする。
田川建三氏の訃報
そんなことを思っていた8月14日の新聞に、新約聖書学者田川建三氏(大阪女子大学名誉教授)の訃報が掲載された。2月19日に89歳で亡くなっており、ライフワーク『新約聖書 訳と註』全7巻8冊を発行した作品社から半年遅れで公式発表されたようだ。新聞の記事はごく簡単なもので、その後も詳しくその業績を伝える追悼記事は目にしなかった。日本のキリスト教信者は国民の1%にも満たないが、キリスト教文化が支配する西欧文明に憧れをもつ人は極めて多い。その少ない日本人キリスト教界でも異端に属する田川氏への関心が低いのも無理はない。私も田川氏の聖書学やその世界的な評価について詳しくは知ってはいないのだが、数行の訃報で済まされるべき研究者ではないことだけは分かる。
60~70年代の雑誌・出版文化
田川氏の『イエスという男』(1980年・勁草書房)など主な著作を構成する論稿や評論が掲載されたのは、アカデミックではない、傍流というべきカウンターカルチャーに属する60~70年代の雑誌であった。現在人々の社会意識を左右するのは雑誌や新聞ではなく、SNSなどのネット情報と言われる。
今から半世紀前、田川氏を支えた、現在とは比較にならないほど熱を帯びていた当時の雑誌文化を中心に考えてみたい。聖書学ばかりでばかりでなく、あらゆる研究には主流に対する傍流の存在が大切かと思う。私はクリスチャンではないが、キリスト教書を読むことは好きで、浅野順一氏やカール・バルトの著作にも触れて来た。現在の新教出版社の初代社長で、古書店から出発した長崎書店長崎次郎ことについても調べたことがある。田川建三氏の著作も所持していたはずと調べたら、『批判的主体の形成-キリスト教批判の現代的課題』(1971・三一書房)、『立ちつくす思想』(1972・勁草書房)と共著『はじめて読む聖書』(2014・新潮新書)が出て来た。今回、他の著作も改めて買い求めて読み始めると厳格な聖書学者と思っていたが、強烈な革新的研究者であったのを知った。唯我独尊的な言動も見受けられ、主流派から煙たがれるのも分かるが、そうした異端の研究も受容出来た60~70年代の出版界の懐の深さも感じるのである。
マルコ福音書
新潮新書『はじめて読む聖書』は田川氏のほか、山形孝夫(宗教人類学)、池澤夏樹(作家)、秋吉輝雄(旧約聖書・古代イスラエル宗教史)、内田樹(仏文学・思想家)、山我哲雄(聖書学者)、橋本治(作家)、吉本隆明(詩人・思想家)の8名に編集者・作家の松家仁之氏が『聖書』についてインタビューしたものである。田川氏の話のタイトルが「神を信じないクリスチャン」で集中一番多くの頁を割いている。この章だけ聞き手が湯川豊氏(元『文学界』編集長、後の東海大学教授など)である。ここで田川氏は分かりやすくこれまでの研究の歩みを語り、自著について触れている。
「マルコ福音書」に特別な思いを抱かれているのは何故かと問われ、大学院で修士論文を書いていたころ「マルコもマタイもルカもろくに区別されていなかったんです。正典ですから、四福音書正典と言って、四つの福音書は別々の著者が書いたものだけれども、同一の真理を表現している。相互に相違、矛盾はない。ローマ教皇からそういう勅令が出ていて、カトリックの人たちは大変だったんです。しかしプロテスタントも大部分はほぼ同じ雰囲気の中にありました。だから、四福音書はそれぞれ違うものです、などと言ったら、すぐに干されてしまいます」。
その点ブルトマンというドイツ人学者は「四つの福音書はそれぞれ別であり、それぞれ異なった意識を持つ人が書いている。そういう当たり前の認識をしっかりと方向づけしてくれ」た。「二〇〇八年の夏に出した『新約聖書 訳と註 第一巻』では、マルコとマタイの翻訳でその違いを細かく指摘する作業をいたしましたが、従来の翻訳がそもそもおかしいんです。マルコのこんなにわかいやすい鮮明な文章が、なんでこんな風に違って訳されてしまうのだろう。それは同じ話をマタイも書いていて、そのマタイの文をマルコに読み込むから、マルコの文を誤訳してしまうのです。そうではない、マルコは同じ話でも全然違う意味のことを言っているじゃないか。だから翻訳そのものをまず直していかなければいけない」のだと。こうした考えは、強烈な現キリスト教界への批判であり、反発を受けた研究だったと想像される。
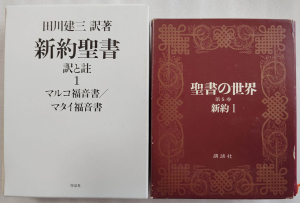
〇(左)「新約聖書 訳と註 第一巻」作品社
〇(右)「聖書の世界 第5巻 新約Ⅰ」講談社
田川氏の研究の核は「マルコ福音書」の研究にある。その最初の纏まった研究書は、勁草書房から刊行された『原始キリスト教史の一断面 福音書文学の成立』(昭和43年)である。「まえがき」で田川氏は本書の意図を次のように書いている。「原始キリスト教という実態は、普通考えられているよりもよほど幅の広い、複雑な要素のからみあっている実態である」「福音書記者の位置についての考察をぬきにして、原始キリスト教史を描くのは不可能である。その中でも最初の福音書であるマルコは原始キリスト教史の中で一つの改革的な試みを提出している」「福音書という文学類型をマルコが創造するにいたった理由を問う、ということが原始キリスト教史研究の重要な課題なのだ」と。私の基本的なキリスト教理解が足りないことを実感するのだが、現行の『新約聖書』は「マタイの福音書」「マルコの福音書」「ルカの福音書」「ヨハネの福音書」の順に収められている。1970年(昭和45)に田川・八木誠一・荒井献訳で出された『聖書の世界5 新約Ⅰ』(講談社)ではマルコ、マタイ、ルカ、ヨハネの順で、正典の『新約聖書』には収められていない「トマスによる福音書」を本邦初訳(荒井訳)で収めている。
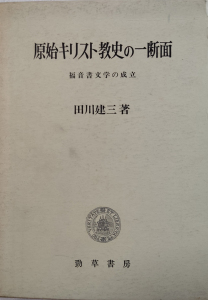
〇「原始キリスト教史の一断面 福音書文学の成立」勁草書房(昭和43年)
昭和43~45年は、既成概念に反抗して全国の大学で学園紛争が過熱していた時代である。勁草書房は『吉本隆明著作集』に象徴されるように当時最も活発な出版社であった。田川氏も「狭いキリスト教世界だけの会話ではなく、クリスチャンであろうとなかろうとだれにでも通用する学問的研究なのだ、という気持を、選んだ出版社によって表現したかったのである」と書いている。後のライフワーク『新約聖書 訳と註』でも勿論「マルコ福音書」が「マタイ福音書」の前に収められている。その解説で田川氏は「マルコ福音書」について次のように書いている。
「史上はじめて書かれたイエスという男の伝記、というよりも、イエスという男の伝記はこれ以外に書かれていない、といった方がいいかもしれない。他の三つの福音書はこれを神の子イエスの地上での顕現の物語に作り変えようと努力したものである」「当時のユダヤ教条主義が支配するおぞましい社会で、それを批判的にはねのけようとしたイエスのさまざまな言動を多く伝えている」「この人(注・マルコ)がイエスの伝記を書こうと思わなかったら、あの人類史上稀に見るすごい人物の姿が後世に伝わらなかったのは確かである。そもそも、イエスの伝記を書くという発想そのものが、マルコの独創であり、彼がそれを実現しなかったら、ほかの人たちがその改作を作ろうなどという気も起こさなかっただろう」。私もそうだが、福音書にこういう問題があることを知る人は稀だろう。そして、野町氏のエチオピアの聖地ラリベラの巡礼者たちの姿が重なるのである。
イエス伝
田川氏の著作で最も知られるのは『イエスという男 逆説的反抗者の生と死』(三一書房・1980)であろう。私の求めたのは1991年刊行の16刷であるが、「日本の古本屋」に2020年刊行の増補改訂版が出ている。田川氏は冒頭「歴史の先駆者」(第一章逆説的反抗者の生と死)で「イエスはキリスト教の先駆者ではない。歴史の先駆者である。歴史の中には常に何人かの先駆者が存在する。イエスはその一人だった。おそらく、最も徹底した先駆者の一人だった。そして歴史の先駆者はその時代の、またそれに続く時代の歴史によって、まず抹殺されようとする」「イエスは殺された男だ。ある意味では、単純明快に殺されたのだ。その反逆の精神を時代の支配者は殺す必要があったからだ。こうして、歴史はイエスを抹殺したと思った。しかし、そのあとを完全に消し去ることはできなかった。それで、今度はかかえこんで骨ぬきにしようとした」「体制は、その人物を偉人として誉めあげることによって、自分の秩序の中に組みこんでしまう」「イエスも死んだあとで教祖になった」。
これが現在のキリスト教界への大胆な批判であることは素人でもわかる。おそらく批難轟轟であったろうと思うが、滝沢克己は『聖書のイエスと現代の人間 田川建三「イエスという男」の触発による』(1981・三一書房)を刊行している。
興味深いのは、田川氏はこの本の元となった原稿を『歴史と人物』(中央公論社)と『情況』(情況社)に掲載したことである。しかも連載が『歴史と人物』から『情況』へ変わったについては問題が起こったようである。残念ながらその理由を書いた『情況』1974年3月号は所持していない。私の手元に68~70年発行の『情況』が20冊ほどあるが、田川氏が執筆しているのは1970年11月号「特集・市民社会と階級形成」のみである。「平田清明批判=個体性と共同性」と言う論稿で、後に『批判的主体の形成-キリスト教批判の現代的課題』(1971・三一書房)に収録されたものである。
(続く)
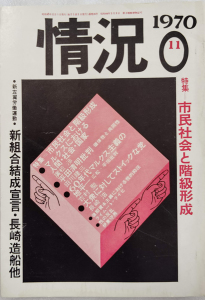
〇「情況 1970年11月号」情況社
樽見博
昭和29年生まれ。平成20年から「日本古書通信」編集長。先頃「早く逝きし俳人たち」(文学通信)を刊行、「戦争俳句と俳人たち」(トランスビュー)「自由律俳句と詩人の俳句」(文学通信)とあわせて三部作を完成。