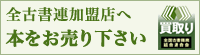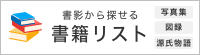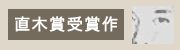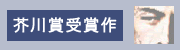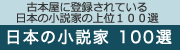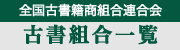田川建三氏と1960年~70年代の雑誌文化(中)樽見博(日本古書通信社) |
橋爪大三郎氏による追悼文大手新聞が田川建三氏の追悼記事を出さない中、『週刊読書人』が9月12日号(第3605号)に社会学者橋爪大三郎氏の「追悼・田川建三 信仰によって、聖書学を自らの使命とする」を掲載した。橋爪氏は田川氏より13歳下の全共闘世代、それ故の理解に立つ意義深い追悼文であった。 「聖書学と信仰は矛盾する。対立する。この基本をまずしっかり頭に刻まないと、田川博士の生涯がわからなくなる」「神の成立を解明するのか、神に根拠を置くか。聖書学に邁進する(=神を信じない)クリスチャン(=神に根拠を置く)という逆説が、田川博士その人なのである」「田川博士は信仰によって、聖書学を自らの使命とした」「田川建三博士のおかげで、日本語で読める聖書の質が格段に高まった。この恩恵は徐々に、しかし確実に、後の世代に及んでいくであろう。田川博士が受けた苦難の数々や不当な扱いは、取り返すことができないし、埋め合わせる方法もない。だがそれは、いまや博士の勲章である」。 大手新聞が田川氏の業績をほぼ無視した理由は分からない。それだけに、橋爪氏の『読書人』記事は貴重なものであると思う。現在の社会は主流のみを認め、確かに存在する傍流を認めようとしない、不寛容の考えが蔓延しているように私は考える。 第一、 第二、 第三、 第四、 橋爪氏があげた疑問は信仰者からのもののように感じる(日本福音ルーテル教会員)。クリスチャンではない私が聖書学や、パスカルの『パンセ』研究にひかれるのは、きわめて科学的な書誌研究を土台としているからである。多くの残された資料群を、様々な歴史資料を参考に比較対象して完全なテキストを求める。しかし科学的ではあるけれども、どこか人間の持つ業に由来する。書誌研究に共通の魔力である。信仰よりも、眼前にある複雑に絡み合う資料を実証的に解明することは魔力的な魅力がある。田川氏もその魔力に引き込まれた方のように私には思える。 『指』『情況』など田川氏の著書『批判的主体の形成-キリスト教批判の現代的課題』(三一書房・一九七一)に収められた論考は、自ら編集していた雑誌『指』の他、『理想』『構造』『日本読書新聞』掲載文に加筆されたもの。次の『立ちつくす思想』(勁草書房・一九七二)は『指』『日本読書新聞』『パイデイア』(同志社大学教育科学研究会)に掲載。著書の中で一番反響の大きかった『イエスという男-逆説的反抗者の生と死』(三一書房・一九八〇)は、『歴史と人物』(中央公論社)と『情況』に断続的に連載された論稿が核をなしている。つまりキリスト教界の雑誌ではなく、既成の「権威」に対する批判を是とする雑誌に発表されたものである。 『批判的主体の形成』に収録された「キリスト教と市民社会―平田清明批判」が掲載された『情況』一九七〇年十一月号が手元にある。「市民社会と階級形成」を特集し、廣松渉「ママルクス主義における人間・社会・国家」、吉村聖「六〇年代マルクス主義の地平」、長崎浩「大衆に対してストイックな党」と一緒に掲載されている。廣松は東大名誉教授で著名な哲学者。同誌への寄稿も多い。長崎は当時の『情況』に最も数多くの評論を掲載した社会評論家。吉村聖については知る所がない。 当時は主流ではないが、意義ある傍流の考えを発表できる雑誌文化が最盛期を迎えていたのではないだろうか。現在はインターネットの普及で、個人が意見を表明する手段は格段に広がった。しかし誹謗中傷する個人攻撃や、根拠のないデマや流言が横行しやすい。編集者の目が介在しないからだ。雑誌は、刊行すれば消去できるSNSとは違い、責任の所在が明確である。その点が言論の自由には必要不可欠なのだと思う。 『指』雑誌『指』については、『立ちつくす思想』の「あとがき」で詳しく解説されている。「雑誌『指』はかつて上原教会の牧師であった赤岩栄によって創刊された個人雑誌である。一九五〇年十二月号から一九六七年十一月の彼の死の直後(六七年二月号)まで続けられた。それは、出発当初は、当時大きなジャーナリスチックな問題をなげかけたところの「共産党入党宣言」を発表した赤岩栄の主宰する雑誌でありながら、よくあるキリスト教の伝道雑誌の一つににしかすぎなかった。彼の、キリスト教徒でありかつ共産主義者である、という主張は、所詮無理な主張ではあったが、もう一歩掘り下げれば、深刻な思想的問題設定をなしうるところまで行きつけたはずであるのに、その手前でジャーナリスチックに騒がれてしまったため、後の世代に何ら重要な影響をのこすことができず、赤岩自身は、キリスト教と、彼の理解した限りでの共産主義の両者に対して、護教論的にふるまうにとどまった」「この第一次『指』の終刊後一年近くしてから、我々、つまり宮滝恒雄氏と私とは、第二次『指』を刊行することにした。それは、第一次『指』と接点を保ちつつも、第一次『指』を克服する雑誌でもあった」と。
手元に、赤岩栄が編集発行人である『指』113号と115号(昭和35年4月と6月号)がある。日本基督教団上原教会(渋谷区上原町)が発行所で、A5判、24頁の薄い雑誌だが、太田愛人(デンマーク通信)、笠原芳光(映画「勝手にしたがれ」)、椎名麟三(春日遅々、自然の沈黙)、飯島宗享(モラルと記せば)などの他、赤岩が「巻頭言」「指」のコラムや、聖書の一節を当時の社会批評を基に語る文章が掲載されている(前記の号では、死と甦り、限界の中での行動)。当時の日本社会は安保闘争の渦中にあった。赤岩が書く「巻頭言」もその話題である。「これまでの基督教道徳の限界は、個人に対して強い影響を与えながら、国家というような公共性に何らの指導力をもたなかった点にある」など、半世紀近くたった現在にも通じる批評を展開している。しかし、日米軍事同盟が強化されると危惧する一方で「これまで支払った防衛分担金も、今度の新安保では不要ということになっている」と書いているが、密約的な事項であったのか、その認識が間違いであることは現状を見れば明らかである。私は当時6歳の保育園児だったが、テレビニュースで流れる社会全体を巻き込んでの安保闘争の様子、殊にどこか大きな病院の前で、白衣姿の看護婦らが一列になり腕を組み何か歌っているか叫んでいる場面は良く記憶している。同じ歳の園児が保母さんの周りを「あんぽんはんたい、あんぽんはんたい」と意味の分からぬままグルグル回っていたのを覚えているが、如何に社会的な大きな事象であったか分かる。 赤岩栄田川氏の『イエスという男』の「あとがき」で、「本書を書くにあたって、何人かの著者の「イエス」を対話の相手に選んだ。R・ブルトマン『イエス』(一九六二年・邦訳・未来社一九六三年)、八木誠一『イエス』(一九六八年・清水書院)、土井正興『イエス・キリスト』(一九六六年、三一書房)である。この三人に対する言及は、特に断りのない限りは、ここにあげた著作に関するものである。それ以外の著者については、必要のない限りはなるべく名前をあげて論及することはしなかった。本書の目的は諸説について論じることではなく、イエス像を描くことにあったからである」とある。 数ある日本人によるイエス伝の中でどうしてこの三冊なのか、田川氏は簡単に説明しているが、あまり説得力がない。同氏がある種否定的に継承した雑誌『指』の創刊者赤岩栄にも『イエス傳』(昭和25年・月曜書房)がある。赤岩が「後記」で「反キリスト教著作に大きな共鳴を感じながら、それでも、私はイエスとの関わりを断ち切ることが出来ないで苦しんでいたのだ。後で思えば、私にとってアンテイ・クリストとは結局、キリスト教探求の一つの方法に過ぎなかったのである」「お前は、決してアンテイ・クリストではない、たゞアンテイ・クリステントウムに過ぎないではないか」(注・おそらく反イエスではなく、現在の基督教界への懐疑・反発を意味していると思う)と、実際、私の肩を叩いて教えてくれたのは、(カール)バルトであった」「バルトのお蔭で私はイエスに向かって、まともに、目を向けることの出来るものとなったのである」と語る赤岩のイエス伝である。何故、田川氏はこの『イエス傳』を取り上げなかったのだろう。 次回もう少し詳しく触れるが、赤岩が『キリスト教脱出記』(一九六四年・理論社)などで提起した問題は、戦後のキリスト教界のみならず、広く社会に反響を呼んだのである。 |
|
Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |


-300x207.jpg)
-219x300.jpg)