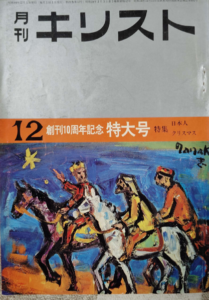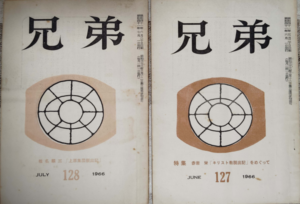田川健三氏と1960年~70年代の雑誌文化(下)樽見博(日本古書通信社)
|
|
田川建三が編集発行していた雑誌『指』の創刊者赤岩栄はどのような人物であったか、『キリスト教人名辞典』(日本基督教団出版局・1986)には下記のように書かれている。 赤岩栄 1903(明治36)4.6―1966(昭和41)11.28 牧師、上原教会創立者、文筆家。愛媛県に生まれる。父は小学校校長、牧師。幼少時母の信仰により影響を受ける。東京神学校で高倉徳太郎の福音主義信仰に接し、本格的に伝道を志す。卒業後日本基督教会佐渡伝道所へ赴任。2年余後高倉主宰の《福音と現代》誌発刊に際し東京に呼び戻され、編集担当。同時に小田急線上原で開拓伝道、月刊誌《言》(106号まで)と上原パンフレットによる文書活動を並行させる。 戦前の上原教会はカルヴァン主義信仰に立脚し、礼拝・祈念の厳守、教会中心の生活に徹し、バルト神学を吸収し、独自な宣教活動を展開。牧会者(ゼールゾルガー)として人間形成と教会形成に優れた手腕を発揮。敗戦を契機として赤岩の生涯と上原教会の歴史は変身と転換を遂げる。49年1月、日本共産党への入党決意を表明し、教界に波紋を投じた。彼の主体的実存は必然的に社会政治実践となり、教会も苦闘の末伝統的権威の殻を破って、果敢なキリスト教脱出を断行。それが個人の信仰思想の領域に限定されず、教会ぐるみの選択と決断であったことが特記される。 その後の展開が期待されたが、死によって中断された。ジャーナリズム界でも健筆を揮い、反戦・平和のために文化・政治活動を展開。全貌は《指》と『赤岩栄著作集』10巻と別巻(1970-71)に詳しい。」 『キリスト教脱出記』その赤岩栄の著書の中でも一番反響の大きかったのが『キリスト教脱出記』(理論社・1964)である。赤岩は「はじめに」で「戦後、史的イエスの研究に従事するようになって、教理の根拠として、これまで無条件で信じこんでいた事実が、神話的な架空なものであるということを次第に知らされていった。(略)キリスト教のラビリンスを遍歴して、その出口に立ってみることで、私はことあらたに人間の謎に満ちた問題性を示されたような気がしている。私にとってキリスト教からの脱出は、そのまま人間性(フマニタス)への回帰を意味するのである。」と書いている。前回、赤岩が編集刊行した『指』の紹介でも触れたが、戦時中のキリスト教界の反省の上に、戦後の社会的な問題を直視、自らの課題としていった帰結としてこの著書が刊行されたと言えるだろう。ただ、それまで極めて護教的な言動をしてきた牧師の行動故に反響は大きかった。 椎名麟三の憤怒私が所持する『キリスト教脱出記』は初版であるが、関西大学の久山康が編集発行人を務める雑誌『兄弟』(基督教学徒兄弟団発行)の第128号(昭和41年7月)を旧蔵者が箱に一緒に収めていた。B6判、48頁の冊子で串田孫一さんが表紙絵を描いている。そこに椎名麟三が「上原集団脱出記―赤岩栄「キリスト教脱出記」の書評として」を執筆している。椎名は「私は、昭和二十六年のクリスマスに赤岩栄牧師によって「父と子の聖霊の御名により」洗礼を受けた」という一節を10頁の中で5回もくり返している。書評というよりは、赤岩に裏切られたという憤怒の文章である。椎名は「私は、変節というものを一概に責めることはできないと思っている。というのは、私は、人間というものは試行錯誤を繰り返しながら生きているものだと思っているからだ。(略)だが、私のいまそれによって苦しめられている変節は、指導者面をしたそれなのだ。いずれこのことは詳しく書く機会もあると思うが、よしその変節が主体的なものであろうと、私たちに対して指導者面をしているかぎりにおいて、その変節には責任をともなうということだ。いいかえれば、以前の自分の考えを私たちに押しつけていたということに対する責任である」と書いている。かつて共産主義から転向しキリスト教徒となった椎名故に裏切られたという思いが強かったのであろう。椎名の著書『信仰というもの』(教文館・昭和39年)は『月刊キリスト』に連載されたものと『指』に掲載された「ある信仰―親鸞をめぐって」で構成されている。 手元に『月刊キリスト』の昭和44年12月創刊10周年記念特大号がある。椎名が巻頭言を書いている。編集後記にあたる「お知らせ」欄に「『ニューエイジ』が改題されて『月刊キリスト』としてNCCの文書事業部から創刊されたのは1959年、昭和34年の12月でした。ちょうど、新安保条約締結の前年で、11月には、安保阻止第八次統一行動のデモ隊二万人が国会にはいるという出来事が起こっています。その同じ月には、日本キリスト教宣教百年記念大会が行われているのです。いわば、『月刊キリスト』は、日本での百回目のクリスマスに生まれて、日米新安保条約体制下の10年を生きつづけてきたわけです」と書かれている。1960年代が政治の季節であったことを示している。 なお、『兄弟』の127号は「赤岩栄「キリスト教脱出記」をめぐって」と言う特集号とのことで、「日本の古本屋」に出ていた12冊の中に含まれているのを発見、購入した。 雑誌『兄弟』『兄弟』127号には、『キリスト教脱出記』に関する、久山康、小林信雄、米倉充、熊谷一綱という関西大学教授の座談会と、大塚野百合ほか6名の短評が掲載されている。中で『日本近代詩とキリスト教』『中原中也という場所』などの著書のある佐藤泰正のものが私には納得のいくものであった。「この書をめぐる教団離脱云々の問題は、埒外の私には何も言うことはない。ただ一読者としての率直な感想を言うならば、キリスト教が、教会が、ひとつの大きな転機に立つ、この時代に、著者が真剣な問題提出を試み、教会を揺さぶり、お互いに今日の教会とは、キリスト者とは何かという問いかけ、また論議の昂まりに、ひとつの梃入れを試みていられることは、よく分かる。その意味においてこの書は、教義的な問題を含めて大いに論じられてよいと思う」。この本は実際に信仰者の視点から真剣にとらえられて論議されている。 『兄弟』は他の号にも興味深い記事がある。今回入手した中で一番古い第三巻三号(昭和34年6月)には亀井勝一郎、遠藤周作、椎名麟三を囲んでの座談会「文学とキリスト教」、94号(昭和38年6月)には前記佐藤泰正の「中原中也の『朝の歌』をめぐって」があり、他にも西谷啓治を囲んだ「夏目漱石における「自然」」と題した座談会(140号・昭和42年9月)などがあるなどレベルの高い雑誌である。 『出会い=日本におけるキリスト教とマルクス主義』日本基督教団宣教研究所が1970年7月に開催した研究会の記録である。六章からなるが第三章が「戦後の赤岩問題、キリスト者平和の会について」で、飯島宗享、井上良雄、桜井秀教の討論である。飯島の冒頭の発題は「戦後のわれわれ自身の戦争責任意識と結び合って、戦後非常に早い時期から問題は登場しており、赤岩さんの問題提起と「キリスト教平和の会」の出発とは、ともにこの流れの中での顕著なできごとという意味をもつものと考えられます。しかも戦後の二五年というのは、赤岩さんの提起した問題をめぐっても、あるいは「キリスト者平和の会」というわれわれが関係してきた会をめぐっても、それ自身の歴史的な経過と変遷とをもっております」とある。 赤岩の問題については「戦争中のマルクス主義者たちのありかたにひきかえて、自分たちのキリスト教はどうであったかという反省から、マルクス主義に対してコンプレックスを強くもつ人々が、すくなからず出てきた。この人々にとってマルクス主義が自分たちの信仰との関係でどのようにうけとられたかが、赤岩さんをめぐってあらわになる事柄だといえましょう」「共産党入党の決意表明というこの赤岩さんの衝撃的な行動の原因には、むろん赤岩さんの個性もありますが、われわれにとっていっそう重要なことに、その根底に戦後の日本とキリスト教界のありさまの問題があったと考えなければなりません。その問題性に対する自覚こそが、近年の日キ教団のもろもろの動きを促す原点というべきで、改めて戦争責任が告白されたことの意義もそこにあると思います」というものである。 松木治三郎関西学院大学神学部長だった松本治三郎の『イエスと新約聖書の教会』(日本基督教団出版局・1972)も赤岩、田川建三の提起した問題に触れた六章からなる著作である。「序」によれば「第一論文は、故赤岩栄の『キリスト教脱出記』の提起した問題をめぐって、私の把握しているイエスの事柄を、自由に論述したものである」、「第二論文でも、田川建三氏の、画期的な研究成果である『原始キリスト教史の一断面』における、マルコによる福音書の史的状況把握とそのガリラヤのイエスの生把握からなされるエルサレムの、また原始キリスト教のケリギュマ(注・ギリシャ語で宣教や告知を意味する)的キリスト論批判の一点に限って、批判的に論及している」「赤岩=田川の線で提起している問題は、学問的にも実践的にも重大である」と書いている。二つの論文で約100頁を費やしている。 カール・バルト批判田川が師的存在であった赤岩を余り評価しない理由は、前回触れたような、雑誌『指』を継承するにあたって田川があげた赤岩への批判があったが、他にスイスの神学者カール・バルトに対する考え方の違いもあるようだ。田川が2004年に刊行した『キリスト教思想への招待』(勁草書房)の第一章「人間は被造物」で次のように書いている。 「神学者(注・近代ドイツのプロテスタントの聖書学者)が特にこの(「使徒行伝」)十四・十五章と十七章の創造神話の個所を目の敵にするのは、二十世紀前半から1970年ぐらいまでの強固な、むしろ頑固なと言う方がいいかもしれないが、バルト神学の流行が背景にある。御存じスイスの有名なキリスト教教義家カール・バルトである。もっとも、創造信仰に関するこの偏見は、バルトの影響というよりは、バルトを含めたこの時代のヨーロッパ神学全体の流行、と言った方がいいだろうけれども、その象徴的な位置にバルトが居た。」「バルトはキリスト教絶対主義者であった。キリスト教はキリスト教の専売特許でないといけない。神の子キリストを信じなくても可能な神信仰なんぞを許容したら、キリスト教以外の諸宗教、諸思想でもかまわないことになり、キリスト教の外でも本当の神様を信じることができるようになってしまう。だからバルトは、何が何でも「自然神学」を排斥しようとした」と。 聖書の書誌学的研究ならともかく、神学的な問題はここまで来ると私などには理解が及ばない。本稿の目的は主流ではない傍流の意見を発表できる雑誌文化を考えることである。 全共闘運動終息後20年以上を経過した1992年7・8月合併号の『情況』に田川は「自然世界と終末論」を寄稿している。特集が「世界は破滅する!?」であった。エイズや地球温暖化、遺伝子操作などバイオテクノロジーの問題が人類の差し迫ったテーマとなり始めたころであろう。田川の論考は特集目次のトップに置かれている。田川は冒頭、「われわれ人間は被造物である。神によって造られた。このことは、神が存在しないとしても、事実である。存在しない神が我々を造った。いや、我々だけでなく、自然に存在する万物が、存在しない神によって造られた。被造物であるということは、とりもなおさず、自分が自分の生命の主宰者ではない、ということである。」「キリスト教は、その長い歴史を通じて、特にその支配の歴史を通じて、さまざまな害悪を人類にもたらした。しかし、他方で、非常に多くの点で人類に貢献もしている。その中でも重要なものの一つが、創造神話である」と書いている。 樽見博 |
|
Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |