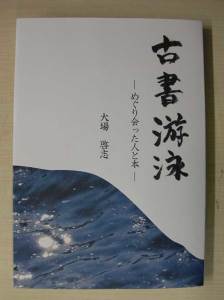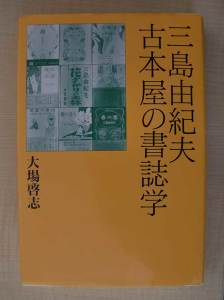変っていく古書店のかたち2樽見博(日本古書通信編集長) |
| 昨年末全営業を止めた龍生書林大場啓志さんの『古書遊泳』は、「日本古書通信」に5年間(平成19年9月~23年12月)にわたって連載されたものを加筆訂正してまとめた本だが、発行部数75部で希望しても入手は難しいだろう。巻末に添えた書名の由来となった「古書遊泳」は、自らの古本屋人生を回顧、1冊にまとめるに際し書き下ろされたものだ。興味のある方は「日本古書通信」でご覧頂きたい。近代文学稀覯本をめぐるドラマとしても楽しく読めるし、貴重な記録である。 大場さんは、その「古書遊泳」の最後に次のように書いている。 「今振り返ると何もかもが一瞬の夢のようだ。バブルに踊り、不相応な買い物もした。失敗も多くあるが、住まいは確保されている。今残されている在庫は夢の名残。そう慾を掻くべきでは無いであろう。」 その上で、「好きな戦後文学は、一通りは扱えたが、残念なのは」として、ついに扱えなかった、島尾敏雄『幼年期』(昭和18年・こをろ発行所)と山本周五郎『無明絵巻』(昭和15年・大阪泰光堂)の2冊を上げている。龍生書林と言えば、三島由紀夫本を連想するほどその収集に力を入れられた。その成果は『『三島由紀夫 古本屋の書誌学』(ワイズ出版・1998)にまとめられている。 人が古書店という仕事を選ぶ理由は様々だが、大場さんは「古書遊泳」の中でこうも書いている。 「昭和56年7月、五反田展同人のあきつ書店白鳥恭輔氏、芳雅堂書店出久根達郎氏らと目標としていた自家目録の第一号を発行することでスーパーから手を引くことが出来た。自家目録は古書展と違い、自分の世界を表す事が出来る。古本屋という魅力的な仕事に、やっと向き合う事が出来始めたと言える」 古本屋として自分の世界を表す手段が自家目録だと言っているのだ。これは、東京の業者に限って言えば、大場さんや、前記のあきつ書店や出久根さん(芳雅堂書店)、あるいは扶桑書房など現在70歳代を迎えている世代から、えびな書店、稲垣書店、石神井書林、けやき書店など専門店志向の強い現在60歳代の古書業者に顕著な考え方だ。勿論、もっと若い世代、例えば風船舎さんや、股旅堂さんなど、自家目録の発行に全精力を投入している古書店主もいるが、全体に若い世代は、店舗志向が強く、店こそが自己表現の場と捉える方が多いように思う。 これは、インターネット販売の普及で専門書の探求が客にとって楽になると同時に、古書相場の下落を招いていることが背景にある。特色のある自家目録を出すには多くの時間と費用が必要であり、希少本を長くストックしている間も相場が上昇していけば問題はないが、現在のように相場が下落したのでは商いとして難しい。 最近読んだ詩人浅山泰美の著書『木精の書翰』(思潮社・2000年)に「静かな店」という京都の老舗喫茶店を回想したエッセイがあった。「再会」「夜の窓」「クローバー」「フタバヤ」「北国」「白鳥」「フランソワ」「ソワレ」「築地」「イノダ」といった喫茶店の魅力と佇まいを取り上げているが、最後に「静かな店で、静かなひとりの時間を過ごしていると、ひとの世の出逢いや訣れが波のように寄せては返し寄せては返しし、小卓の向こうに、今は誰もいないことを奇妙にも思い、安らぎとも感じる。」と書いている。これは理想的な古書店の姿そのものである。若い店舗志向の古書店主たちも基本はそのような店を目指しているのではないか。私も過去にそのような雰囲気の古書店の魅力を満喫したことがある。しかし、私が満喫した店は殆どが知的な老齢の店主が、街の片隅でひっそり開いている店で、旧知の客と何やら楽しそうに話しあっているそんな店だった。ともかくも時間が止まったように静かな店だ。意識してできた雰囲気ではなく店主の人柄と店の歴史がそのまま佇まいに反映している。あの方、あの古書店と思い出すと、多くの店主が亡くなり、店も閉店している。ただ、今若い人が目指す「静かな古書店」も、基本は変わらいと思うが、それは自然に形作られたのではなく、意識して作られている点で違う気がする。私にとって古書店は静かなことが理想のように思えるのに、新刊書店は本を求めるお客の熱気が湧きたっている方が好もしく思えるのは何故だろう。高校生だった昭和40年代半、本を求める客で店が埋まっていた夕方の新刊書店が、当時の平台で輝いていた杉浦康平装丁の本たちと共に懐かしい。古書即売会も客が多いほうが購買欲をそそるのと同じ心理かもしれない。 現実の古書店の仕事は、いわゆる3Kに近い。店に持ち込まれる古本、宅買いで仕入れて来る本も、そのまま店の商品になるものは少ないし、宅買いが大量でも、相場の下落で運送費用や経費との厳しい計算を考慮しなくてはならない。トラック数台分のただ古いだけの蔵書があったとして、それを買ってくれと頼まれた時どう判断するか。市場での入札も相場が下がったとはいえ、良質の本は相変わらず競争が激しく、思い通りの仕入れができるわけでもない。安定した収入を確保するには勢い仕入れの量を増やしていくか、意には添わないが売れ筋に頼ることになる。利益第一で古書店を選んだのであれば問題はないが、もし理想の古書店を目指していたなら、現実とのギャップに苦しむか、割り切るしかない。あくせくしないで、「静かな古書店」を継続することなど、果たして可能なのだろうか。 「日本古書通信」で古本屋兼カメラマンの古賀大郎さんが「21世紀古書店の肖像」を連載して80回を超えた。『全国古本屋地図』を出していた頃には存在しない、若い古書店主を中心に素敵な店が多いのだが、各店とも理想を追えば追うほど継続には相当な困難を経験しているのではと想像している。(つづく) |
|
Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |