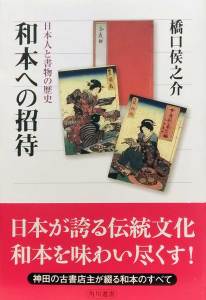江戸から伝わる古書用語 2 本の市場橋口 侯之介(誠心堂書店) |
| 競り市場というのは、一つのアイテムを複数の買い手が競争することで一定の値が付くことにある。これを相場といい、次回以降の取引に参照される。この関係は江戸時代には早くから金銀や米の取引で確立されており、きわめて現実的な価格形成が為されてきた。大坂の堂島では18世紀初頭の宝永・正徳頃に米の先物取引が始まったとされ、それが全国に影響を与えた。金銀銅貨の交換も取引所があって大坂では毎日レートが発表されていた。 この方法を本屋たちも早速取り入れている。享保の頃には(1720年代)には京都で本と板木の市が立ったことが確かめられているのだ。当初は私的な市場だったが、その重要性が認められて公的な仕組みが必要だと考えられるようになった。京都の宝暦12年(1762)の記録に市屋の株と仕法を定めたとあり、市場を開く権利を本屋仲間が認めた業者(本屋にかぎる)に株を与え、その規定を定めたという。後にさらに唐本を扱う唐本市にも同じ仕組みを設けた。 以来、本の市場(当時は本市といった)が定期的に開かれ、その取引はかなり盛んだった。18世紀中頃の本屋の日記を見ると(風月庄左衛門の『日暦』)、当主だけでなく番頭や手代を参加させてかなりの量を仕入れたという。そこで集めた書籍を各地の藩などにまとめて納入している。 この仕組みはすぐに大坂も導入し「世利分(せりわけ)市」と称した。江戸も同様で、その結果、三都の間を自由に古書が売買され、セドリ(世利子ともいった)のような業者が往来した。世利子は本屋仲間の店で登録され、その人別帳を市に登録するので、京・大坂・江戸のどの市にも参加できた。 つまり江戸緒時代の中期には、そのような流通形態が確立していたことがわかる。蔵書家の本が売りに出ると売り立てが行われ、例えば曲亭馬琴の蔵書は市で250両になったとか、大坂では大塩平八郎の本が600両で売られたという記録がある。 市場の株を持った者は、広い会場を用意し、そこが仲間成員の交流場所にもなっていた。 ここでおもしろいのは市の売り手が支払う手数料(歩金)が5分だったことだ。市の株を持った会主はそこから2分を仲間に納入した。当時の本市が東京の中央市会や東京古典会に相当し、東京組合が本屋仲間だと考えるなら、現在に至るまで変わらない制度なのだ。
|
|
Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |