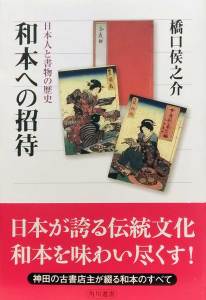江戸から伝わる古書用語5 江戸時代の本屋の取引橋口 侯之介(誠心堂書店) |
| 京都の本屋・風月庄左衛門の日記からもう少し紹介しよう。これは業界用語そのまま書かれたいわば業務日誌である。 例えばこんな表現がある。「万歳講丸源、若州買物出ス」というのは丸屋源兵衛方で行われた万歳講に、若狭からの買い物品を出した、ということである。本屋仲間公式の市場のほかに私的な市もあった。そのひとつである万歳講の場で若狭方面から仕入れた一口物を出品したのだ。「買物」といえば仕入れのことだと古本屋ならすぐわかるが、一般の人にはピンとこないだろう。 ある日の一文にこういうのもある。「松岡本ニフ帖打蔵へ入ル」というのだが、わかるだろうか? 松岡某氏から仕入れた本に「フ帖」、すなわち「符丁」を書いてお蔵にしまった、ということである。つい最近まで古本屋は仕入れた本の後ろに仕入れ値を記号で書いていた。今ならコンピュータにデータを打って所定の場所にしまうようなものだ。「ふちょう」といわれて古本屋ならわかる。 この貴重な日記を読み込んで書かれた論文というのがまだない。研究者には用語がわかりにくいからだろうか。ぜひ、使ってほしい。 この日記をはじめ当時の史料から本屋間の取引を調べると、案外、今とかわらないことが知られる。 たとえば、市場の取引では基本的に売り方から5分手数料を徴収する。それを歩銀(ぶきん)といった。当時、本は銀貨で売買されたのでこう書く。これをもっと高くしてほしいと市場運営者から要望がたびたび出たが、入れられることはなく、何と現代まで歩金は5%(税引き)なのである。 新刊本を他店に卸すのを売価(建値)の8掛にするのが通常の取引である。それを「仕切る」といった。なぜか今も取次から新刊書店への価格は似たようなレベルだ。 古本を各店に譲るときの値段は「一ワリ引ケ」といって10%引きだ。今も決まりはないが概ねそのように取引されている。こういう慣習は変わりにくいのだろう。 この本屋間での売買に利用された仕組みに「本替(ほんがえ)」というのがあった。細かい取引が錯綜し、その支払いも複雑になってしまう。それを避ける智恵がこの方法で、支払いを現金にするのでなく、実物の本で行う。 江戸時代の本屋が出版から問屋、販売、古本をすべて一軒でまかなっていたからできたことで、請求のあった分を、それに相当する額の自店の在庫品で支払うのである。本のやりとりだけで現金の動きを簡素化する方法だ。17世紀末の元禄頃の記録に京都と大坂の本屋間で行われたとあるので、古い慣習だ。同一市内だけでなく、遠隔地間でも盛んで、風月の日記にも「須茂本替渡シ、本一櫃(ぴつ)に致シ、大廻シニ出ス」とあり、江戸の須原屋茂兵衛向けの本替分を一箱に荷造りして大廻シ(海路)の便で出したという。その時の帳面を「本替帳」といったのだそうだ。前回も述べたように江戸時代の本屋は在庫管理といい、取引勘定といいきめ細かい仕事をしていたのに感心する。
|
|
Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |