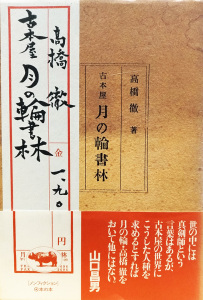古書目録「堀紫山伝」のこと(二)
|
| 表紙につかおうと心に決めている一枚の写真がある。 その写真は、今から百十二年前、明治39年7月22日、芝公園の浄運院というお寺の前庭で撮影された。 堀紫山が人物の名をすべて裏書きしてくれているので、とても助かる。集合写真には、名前の分からない人が必ず何人か出て来るからだ。 集まりの名は、「陶友会」。 メンバーは、堀紫山を含めて15名。 主だった人物をあげる。 堀 紫山(二六新報記者/42歳) 堀 今子(堀紫山の妻) 加藤眠柳(新聞記者) 堺 為子(堺利彦の妻/34歳) 堀 保子(堀紫山の妹/23歳) 深尾 韶(社会主義者/25歳) 上司小剣(読売新聞記者/31歳) 大杉 栄(社会主義者/21歳) 一目みて、社会主義者の集まりだと思った。 皆、不敵な面構えをしている。 この中に堺利彦の姿がないのが、ちょっと不思議な気がしたが、主義者の結社で陶友会とは、初耳。これは新発見ではないかと内心小躍りした。 明治の社会主義者は、自分自身をさほど危険人物と思っていなかったのか、あるいは明治という時代がおおらかで牧歌的だったのか、皆身なりをととのえ写真館におもむき、堂々と入獄記念写真や出獄記念写真をのこしている。 陶友会を撮影したのは、筒井年峰で、月岡芳年門下の明治の浮世絵師だ。堀紫山と年峰は共に大阪にいた明治26年、堺利彦や加藤眠柳らの文学仲間の結社「落葉社」で一緒に青春を謳歌した仲だ。 それはさて、この写真は、見れば見るほどホロ苦くも味わい深い。 堀保子をめぐって、恋のさやあてをくりひろげた二人、大杉栄と深尾韶が仲良く並んでうつっているからだ。 陶友会から2週間後の8月6日、堀保子は、深尾韶とその妹・けんと共に富士山に登った。下山の後、静岡にとどまった保子は、深尾韶の両親に結婚相手として紹介されたらしい。その折に深尾韶と一緒に地元の写真館でとった記念写真が、『大逆事件の周辺 平民社地方同志のの人びと』(論創社/昭和55年)に掲載されている。 堀保子の表情はとてもおだやかで、二人は仲の良い恋人同志に見える。 日付は、8月16日。それなのに、その一週間後、堀保子は、深尾韶ではなく、大杉栄と結婚した。 静岡の深尾韶研究者・市原正恵は、「大杉栄は自分の着ている浴衣の裾に火をつけて口説き、保子を妻としてしまった」(『日本アナキズム運動人名辞典』ぱる出版)と記している。 深尾韶は、その翌年、社会主義運動から離れ静岡に帰郷、日本ボーイスカウト運動の先駆者の一人として活躍していくことになる。 さて、主義者の結社、陶友会だが、同じ日に撮影された別の写真がひょっこり出て来た。写真の中央で陶器をあつかう老人を取り囲み、なごやかに見つめる紫山や大杉栄たち。陶友会とは、その字の通り、陶器を愛する者たちの同好会だったようだ。 しかし、そう頭では分かっても、国家転覆をもくろむ革命家の集まりにしかどうしても見えない。 写真にただよう不穏な空気を強く感じさせるのは、写真師・筒井年峰の研鑽をつみ重ねた技術のなせる技なのだろう。 写真の後方で背筋を伸ばし、すっくと立つ堀紫山。写真中央、カンカン帽をかぶり、髭をたくわえ、伏目勝ちだが眼光するどく大物感ただようまだ21歳の大杉栄。二人が滅法かっこういいのだ。 古書目録は、表紙という顔で全てが決まる。表紙につかいたいゆえんだ。
高橋 徹(たかはしとおる)
|
|
Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |