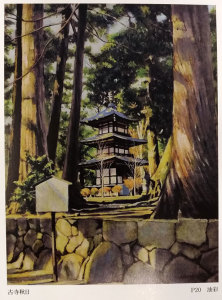古書組合の役割と古書業界の仕組み その2高橋秀行 (前 東京古書組合事務局長) |
| 前回のお話で市場(交換会)は組合が経営していると解説しながら、実際の運営は組合員の中で専門分野を同じくする古書店が同人組織を作り、日々市会を運営していると説明したため、話が分かりにくくなったと思いますので、少し整理して説明させていただきます。
組合という組織を運営するには役員と職員が必要なことは、どこの組合も同じですが、古書組合の場合は他業種組合と状況が少し違います。その最も大きな理由は取引前の古書の仕分けと価値(値段や値打ち)が専門外の人にはよく判別できないことです。交換会は組合の市場なので当然職員は運営実務に従事していますが、その仕事は古書の取引に関する伝票類の作成や取引後の会計事務及び清算事務、交換会の設備、什器備品の補充や落札品の管理等になります。例えば、青果市場や魚市場も競りで商品を落札しますが、野菜はキャベツやキュウリ、ナス等の商品の等級が仕分けできます。魚もマグロやブリやサンマと仕分けられますが、古書の場合は違います。 商品の古書は全国から東京へ送られてきますし、市会当日の持ち込みもあります。今日の交換会のほとんどは入札方式で取引していますが、古書は高価な貴重本以外一冊ずつ取引することはあまり無く、物量のこともあり、大方括りでまとめて取引します。 経営委員という名称は組合内の役職名で、前述したようにこの方たちは組合員ですが、開札作業や運営実務を担当し、自店の専門分野の本を勉強するための場として交換会のお手伝いをしています。ですから、若手の業者や二世の方、業界に入ってまだ日が浅い方が多く務めています。二十年ほど前までは、本部交換会の経営委員になるには支部からの推薦や本部市会からの引き立てが無ければ就けない役職で狭き門でした。このように交換会は売買取引の場であると共に、若い業者を育てる場でもあるわけです。 東京の本部会館は神田小川町にあります。その外堀を埋めるように十年ほど前までは地区会館が東西南北に四つありました。現在では東部会館が廃止され、三地区会館になっています。それらの地区会館でも市場(交換会)と古書即売展(西部会館と南部会館のみ)が開催されているのですが、本部会館は専門書市、支部の地区会館は一般書市という漠然とした区分けがあって、取引される本も異なる傾向です。 地区交換会の市場も入札と競りが採用されていますが、振り市では、振り手を中心に車座になった組合員が落札希望値を発声し落札するという競り方式で、見ていても醍醐味があります。振り手には名人もいて、途中で絶妙なジョークや合いの手、落札価を決定する間合いや本を傷めずに落札者まで放り投げる技は一朝一夕にはできません。この振り手ももちろん組合員です。 このように、古書業者は自店の営業が最も大切ではありますが、交換会を通じて本に関わる様々な勉強や情報と交流、組合事業等の多岐にわたる活動を行っていることをメルマガ読者の皆様に知って頂ければとても嬉しく存じます。 |
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |