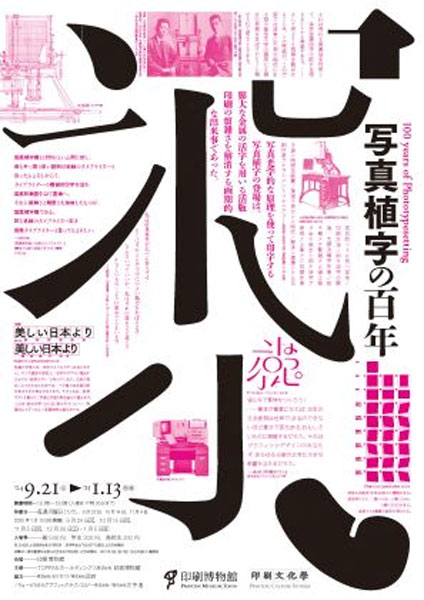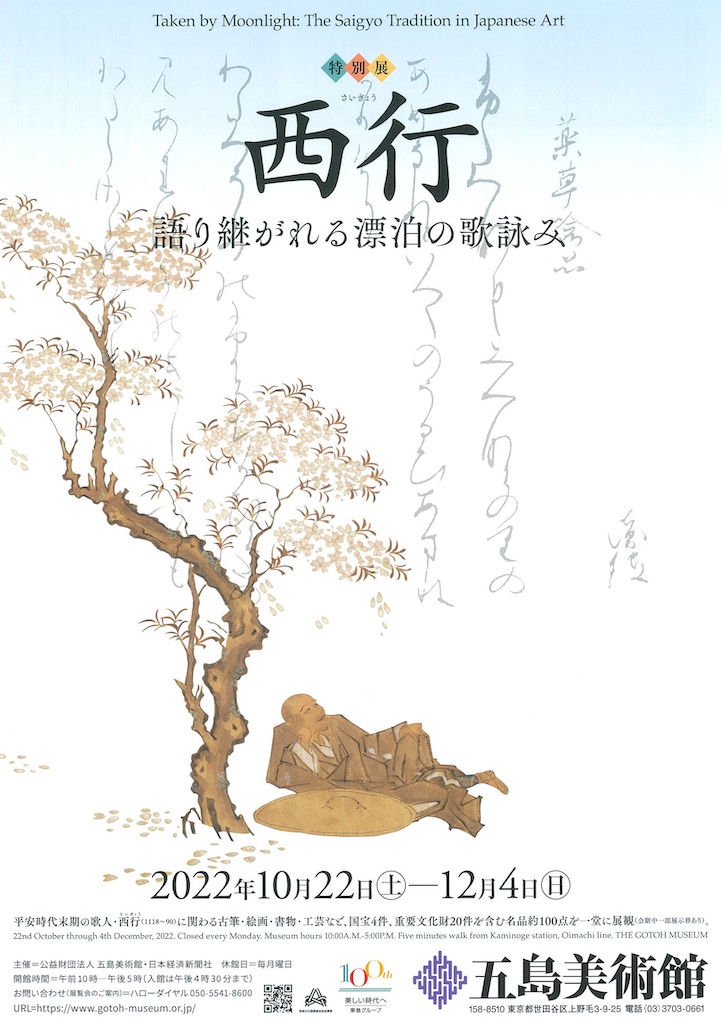『大宅壮一と古本収集』平澤 昇(公益財団法人 大宅壮一文庫) |
| 大宅壮一文庫は評論家・大宅壮一(1900~1970年)の収集した蔵書を引き継いで作られた日本で最初の雑誌専門図書館です。 「集めた資料を多くの人が共有して利用できるものにしたい」という遺志に基づき、現在も雑誌の収集と雑誌記事索引の作成を継続し、今年の5月17日で創立50周年を迎えます。 大宅壮一は戦後日本を代表する評論家で新語づくりの名人でもあり、大宅の生み出した“一億総白痴化”“口コミ”は現在でも日常用語として使われています。 大宅の古本収集には数々のエピソードが残されています。 古本屋側から見た大宅の古本収集に関する記録は少ないのですが『大宅文庫ニュース63号』に掲載された出久根達郎氏の随筆「おおやさん」には月島の店員時代に聞いた大宅の古本購入の様子について書かかれています。三人連れで月島の古本屋を訪れると2時間ほど本を漁り、下町の古本屋ならではの豊富な実話雑誌、カストリ雑誌、芸能誌を見て宝の山だと喜び、持ち帰れない量の古本を大量購入し、自動車便で送ってもらったそうです。 このようにして膨大な資料を集めたのは『実録・天皇記』『炎は流れる』の執筆資料として利用するためでした。収集した17万冊の雑誌を全て読むことは当然不可能です。大宅は「本は読むものではなく引くものだ」という発想で雑誌記事の分類を開始します。 「僕は珍本や稀覯本を集める趣味はないよ。僕の場合、一冊の本は百科事典の一項目に相当するのでね。それを引く可能性があるかないかでその本の価値が決まる。十円の本でも一万円の本でも、差別しないね。何万冊あっても、全体で一冊の本になるわけだ。」と大宅は述べています。 雑誌記事をひとつひとつデータ化するために常4~5人の助手を雇い、人物情報の「人名索引」と事項別の「件名索引」に分類しました。 「大宅式分類」の世相を反映した項目立ては、図書館の十進分類法にはないおもしろさがあり、分類の最上位項目にあたる33の大項目を見ても[奇人変人][おんな][趣味・レジャー]などがあります。検索キーワードは常に更新され、最近話題の[ウーバーイーツ]で検索すると48件、[新型コロナウィルス感染症]は4,406件、[芸能界と新型コロナウィルス]では124件の雑誌記事タイトルが検索できます。 [古本屋][古書、珍書][インターネット古書店]なども分類されており、例えば[古書、珍書]の雑誌記事データで最も古いものは「大震災と古書の保存」(『中央史談』1924年3月号,宮地直一著)になります。この記事中には関東大震災後の神田の古本屋に関する記述があり「震災当時には誰しも再起を予期しなかった神田に軒を連ねた古本屋が、八部通りまではバラック建てに復奮せられて(後略)」と書かれ、当時の神田復興にかける古本屋の意気込みを知る貴重な資料といえます。 [インターネット古書店]で検索すると、最も古いものは「パソコンで古書情報を。江東区の古本屋が始めた「古書ネット」。※高森古書」(『自由時間』1992年10月1日号)になり、分類の便宜上この記事はインターネット古書店に分類されていますが、インターネット普及以前のパソコン通信によるネット古書店の状況について知ることができます。 設立時は蔵書20万冊、索引データ30万件から始まった大宅壮一文庫ですが、設立50年を迎え蔵書80万冊、索引データ700万件にまで成長することができました。出版各社をはじめ多くの利用者の皆様、そして大宅の集書にご協力いただいた古本屋の皆様のお力添えのおかげと心から感謝しております。 最後に宣伝をさせていただきますが、電子書籍が席巻する令和の時代にあっても、大宅壮一文庫は紙媒体の出版物へのこだわりを持ち続けています。 『大宅壮一文庫 雑誌記事人物索引』シリーズを日外アソシエーツからオンデマンド出版で毎年刊行しています。各年版を見れば単なる人物索引ではなく毎年のキーマンを通して社会文化を読み通せる索引目録です。 『大宅壮一文庫所蔵総目録』を今年5月に刊行いたします。皓星社のご協力により実に38年ぶりの所蔵目録の刊行となります。大宅壮一文庫の蔵書リストとしてだけではなく、日本の一般大衆誌の出版状況を俯瞰できる資料となっています。 ※大宅壮一が他界して50年以上が過ぎ、当時の大宅を知る方も少なくなってきました。古本屋側の皆様から見た大宅の思い出やエピソードをご存知の方がいらっしゃいましたら是非お教え下さい。kengaku@oya-bunko.or.jp 宛にメールをお送りいただければ幸いです。 「雑誌の図書館 大宅壮一文庫 開館50周年を迎えて」 |
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |